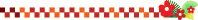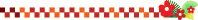
僕は山道をひとり歩いていた。
その日は快晴で、冬の冷たい風も爽やかに感じられた。揺れる白い息も楽しげに踊っているようだ。
僕は浮かれていた。
そして気がつかなかった。
すぐそこまで迫っている黒い影に
*
「ええ天気やなぁ。」
縁側で寛ぎ、空を見上げていた。澄みきった青は、まぶしいくらいに鮮やかだ。
久しぶりの静かな朝。今日は騒がしいのがいないからだ。それだけでなんて世界は明るいことか!
こんな綺麗な空をゆったりと見ていられる。贅沢な時間だ。
ここで暮らしていると、長く忘れていた感覚がよみがえってくる気がする。それは乱菊に出会ってから、あいつに出会うまでの短い一時に見つけた感覚だ。自然を感じる―いや、こう言ってしまうとありきたりな表現に聞こえてしまうか。そうだ、景色が色を持つのだ。ひとつひとつが自ら“色”という光を放っている。そんな風に、見えるようになった。
被った仮面も、心にかけた鍵も、ここにいると鮮やかな光の中に溶けてしまう。徐々に、徐々に、自分でも気づかないくらいのゆっくりとしたスピードで。
「なんやボクも老け込んだなぁ。」
自分でも笑えてしまう。こんなにも短い間にずいぶんと変わってしまった。
今は乱菊の為に生きている。昔のような独りよがりでは無く、乱菊を愛し乱菊に愛され、ボクは生きている。
さて…
「あいつらも居らんことやし、ゆっくり昼寝しよ。」
瞼を閉じた。最近幸せな夢を見ることが多い。
今日はどんな夢を見れるだろうか。
ボクは眠りの世界に落ちていった
緩やかに
緩やかに―
*
ハッ…ハッ…ハッ…
息が苦しい。
僕の肺はパニックを起こしたように呼吸を乱していた。足は絡まり、なんどもつまづきながら転がるように走っていた。
逃げていたのだ。
化け物から。
「ギャハハハハ!おいおいぼうず。もうしまいか?」
狂ったような笑い声はすぐそばで聞こえた。上だ。反射的に見上げれば、木の枝にその化け物はいた。
虚―
町の人に聞いたことがある。この辺りには滅多に現れないが、それでも時々、忽然と人は消えていた。それをみなは虚の仕業だと話していた。
僕もそんな風に消されるのだろうか。酸欠で変に冷静になった脳は、片隅でそんなことを思っていた。
「あ〜あ、飽きちまったなぁ!」
今度は右から。
「もう少し張り合いのあるやつがよかっぜ!」
今度は左から。
「なぁ…ぼうず?」
そして最後は耳元で囁くような声が聞こえた。
もうダメだ…
そう思ってしまった瞬間僕の体は力を無くし、よろよろと地面に倒れた。
「いよいよしまいかぁ!チッ。つまんねぇなぁ!まぁひさびさにありつけたんだ。贅沢は言うまいよ。」
「あ…」
化け物の声が聞こえたが僕の意識はもうそいつには向けられていなかった。
一点
道端に転がった御守りだけを見つめていた。
「おいおいなんだ?」
僕は無意識のうちに地面を這っていた。死ぬ間際に何をしているんだとまた冷静な脳は言っているが、これはもう意識外の行動で、どうすることも出来なかった。腕を伸ばしてそれを胸に抱く。よかった…。
「ん?…それ、見たことあんなぁ。」
どういう意味だ。なぜこいつが…
「あぁそうだ思い出した!」
“何年か前に喰ったガキがつけていたやつだ”
やけに大きく聞こえたその声は、僕の心臓を止めた。
「どういう…ことだ…。」
「なんだお前喋れるのか。口がきけねぇのかと思ってたぜ…」
「どういうことだと聞いている!!!!」
相手が一瞬怯むのを感じたが僕には関係が無い。今あるのは疑問だけだ。
「な、なんだその目は…。」
「答えろ!!」
「…あぁそうか。てめぇはあのガキの仲間か。」
「………。」
「そうかそうかあのガキの…ククク最高だなぁ!あいつはよかったぜ?存分に楽しませてくれた!お前と違ってなぁ!!?」
「許さない…。」
僕の奥ふかくに、赤い光が灯るのを感じた。
「あ?」
「僕はお前を許さないと言ったんだ!!」
「てめぇ…!生意気なんだよ!!!死ね!そして俺の腹ん中で感動の再会でもするんだな!!!」
飛びかかってくる虚を、僕はただ睨んでいた。焼けるような炎が、やつさえも燃やし尽くしてくれればいいのにと、ぼんやりと思っていた。
「破道の一、衝」
光が、走った。
次の瞬間化け物の叫び声が森中に響いた。
「て、てめぇ…!死神か!」
死神…?
そんなのどこにいるんだ。そこに立っているのは…
「ギンさん!」
ギンさんはこちらをチラリと見ると、すぐに視線を化け物に移した。初めて見る冷たい表情に僕の体には冷たい汗が流れた。
「死神がなんでこんなとこに…!それに死魄装は…刀はどうした!」
「質問ばっかりやなぁ。ボクは死魄装も刀も持っとらんただの流魂街の人間や。」
「じゃあなんで鬼道を使える…!」
「そやなぁ、昔ちょっとかじってたんよ。」
「昔…?元死神ということか。」
「まぁどうとでも受け取って。」
「…ク、クハハハハハハ!!さ、最高じゃねぇか!死神か、うまそうな響きだ!運が悪かったなぁ!刀さえあれば勝てたかも知れねぇのによ!!」
「う〜ん、どやろ?」
「あぁ?あっても勝てねぇってか!ギャハハハハ!実力をはかる力だけはあるんだな!」
「キミはその力無いみたいやね。」
「なんだと?」
「斬魄刀なんて無うても勝てる言うとるんよ。」
ビリビリと空気が震えている。僕は逃げることも忘れて唖然としていた。
再び光が放たれたと思うと、爆音と悲鳴とが混ざりあったものが耳をつんざいた。
「お、お前!なんで鬼道だけで…!!」
「ごめんな?ボク、これでも昔はけっこう偉いとこにいたんやで?」
「まさか、てめぇ…!三番隊の…」
「おっと、お喋りが過ぎる子はあかんなぁ。」
“大人しく、死に”
ギンさんの眼が冷たく光った。その一瞬の残酷で冷酷な美しさをたたえた光に、僕の心臓は一瞬動くことを忘れた。
気づいた時には、
化け物は消えていた。
*
あいつの夢を見ていた。
夢の中であいつはいつものように嘘臭い薄ら笑いを浮かべてこちらを見ていた。
体が熱い。自分が憎しみに支配された蛇に変わっていくのが分かった。苦しい。苦しい…
そこで目が覚めた。
額に浮かんだ汗はひんやりと冷たくなっていた。
「水でも飲も…。」
喉が張り付いてうまく声が出ない。頭痛もする。重い体をなんとか動かして立ち上がると嫌な臭いがした。
初めはあの悪夢の続きかと思った。だが違う。忘れた振りをしていてもそれは肌に馴染みすぎていた。紛れもなく虚の霊圧だ。
「最悪や…。なんでこないなところまで…。」
だいぶ距離もあるようだ。ボクは無視して家の中へ入ろうと踵を返した。しかし、ハッと体が硬直した。
「まさか…」
ボクは走り出した。
これは間違いなく、きらの霊圧だ―
*
「おい。」
焦点の合わない目でぼーっと戦いのあとをみていた僕は、ギンさんの声で我に返った。
「……。」
頭が働かず、言葉も出てこない。
「ひどい顔やなぁ。」
そんな僕を見て、ギンさんしゃがんで、涙と唾液と汗と鼻水でぐちゃぐちゃに汚れたボクの顔を手拭いでごしごしと擦った。
「ギン…さん…」
手が触れると、その温かさに視界が霞んだ。
「ギンさん…!ギンさん!」
一粒流れてしまえば、堰を切ったように涙が溢れた。泣きじゃくるボクをギンさんはあやすように抱き締めてくれた。
「あーぁ、せっかく拭いたったのに…。しかもボクの服まで鼻水だらけや。」
「ギンさん!ギンさん!」
「何回呼ぶねん。大丈夫や。ここにいる。」
「落ち着いたか?」
どれくらいの時間が経っただろう。何時間もそうしていたような気もする。なんとかこくんと頷くと僕はやっとギンさんの顔を見ることが出来た。何も読み取れないような先ほどまでの冷たい表情では無い。いつものように飄々と笑っていた。
「あ…あの…」
お礼を言わなくちゃ。しかし掠れた声ではうまく喋れない。それでもなんとか絞りだそうとする僕をギンさんは遮った。
「さ、帰るで。」
腰が抜けて、立つことすら出来ない僕を「しゃーないなぁ」と呆れながらギンさんは背負ってくれた。歩く度に揺れる背中は温かくて、僕は徐々に震えが収まるのを感じた。
いつもの縁側に座らされて待っていると、水と薬箱を持ってギンさんはやってきた。
「これ飲み。」
僕は夢中で水を飲み干した。体が生き返るのを感じる。
ゴクッゴクッ
脈打つように血が巡っていくのが分かる。
ギンさんはしゃがんで足に出来た傷を手当てしてくれている。何も言わずに、淡々と。
“この人は、一体何者なんだ…?”
落ち着いてくると疑問ばかりが浮かんでくる。
虚はギンさんを元死神だと言った。どういう事だ。ギンさんは流魂街の人間じゃ…
高い位にいたのなら、なぜ瀞霊廷ではなくこんなところに暮らして…
「ボクが何者か気になる?」
「え…」
思わず口を押さえる。知らぬ間に声に出していただろうか。
「なに考えてるかくらいはだいたい分かるわ。」
ギンさんは笑って言った。
「実はボクな、大罪人なんよ。」
その声はあまりに優しくて、僕は一瞬言葉の意味が分からなかった。
「ひとりの死神を殺す為だけに100年の間、数えきれんくらいの人間を殺したわ。そして最後は尸魂界自体も裏切った。」
手当てをしながらギンさんは話を続けた。顔は見えない。
「乱菊を捨てて、自分を捨てた。」
ギンさんはそこで初めて僕の目をみつめた。
「復讐の為にな。」
あの一瞬に感じた憎しみの炎の事を言っているのだろうとすぐに分かった。
「大事なもんなんやろ?もうこない強く握ったらあかんで。」
ギンさんは僕の右手にぶら下がる御守りを触った。
あの虚と対峙した時、憎しみに我を忘れ、気づかぬうちに潰れるほど握っていたらしい。
「僕の…」
「ん?」
「僕の幼なじみなんです…。しゅーへいくんやれんじくんに出会うずっと前から兄弟みたいに育った…大事な大事な仲間だったんです…。それを…それを!」
ポタリポタリと手のひらに涙が落ちる。悔しくてたまらない。なんであんなやつに。なんで彼が…。
「あほ。」
ギンさんの強い声が降ってきた。
「お前はあんな顔せんでえぇ。」
「……。」
「せんで…えぇねん…。」
西日が差してギンさんの顔は影になっていた。どんな表情を浮かべていたのか、それは分からない。ただその声は寂しい色を含んでいるようで、僕の胸はぎゅっと痛んだ。
「…はい。」
「ええ子や。」
わずかに光に照らされて見えた顔は、優しかった。
「おーい!きらー!どこいってたんだよ!」
「ずいぶん探したんだぜ…ってどうしたんだその傷!?」
「あ…えっと…」
帰りはギンさんが送ってくれた。町へ着くと、しゅーへいくん達が目を丸くして迎えてくれた。
「こいつほんまどんくさいなぁ。家の前で盛大に転びよったんよ。」
「そ、そうか…だいじょぶか?」
「え…うん!えへへ、大丈夫大丈夫。ちょっと擦りむいただけ!」
「ならいいけどよ…。もう晩飯の時間だ!早く帰んねーと食いそびれるぞ。」
「そうだな。じゃあギン!明日は行くからなー。」
「来んでいい、来んでいい。」
「素直じゃねーなぁ。じゃ!ほら行くぜ。」
「あ、待って…。」
後を追おうとして呼び止められた。
「きら。」
「ギンさん…今日は…」
「今日の喋ったこと、今日起こったこと。全部ボクらだけの秘密や。」
「ひみつ…。」
「ええな?男の約束や。」
「……はい。」
「それから…」
「?」
「笑って暮らせよ。」
「…はいっ!」
ギンさんの過去は何も知らない。あの話が本当なのかも分からない。だけど僕は知っている。ここで乱菊さんと笑い合って暮らす優しい笑顔のギンさんを。
憎しみの炎に焼かれそうな僕を救ってくれた。
この未だ燻る炎と傷とは、ずっと向き合っていくことになるだろう。
でもきっと大丈夫だ。
そう思うでしょ?
そっと手の中の御守り語りかけた。
僕は
最高の仲間と
乱菊さんと
ギンさんと
そして君に守られている
.
- 13 -