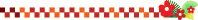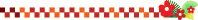
私は思い出していた。
「ギン!ギン!―」
一護が藍染と共に消えた後、私は何度も叫んだ。声が枯れてもまだ、名前を呼び続けた。
「ギン!ギン…ギン……。」
人形のように力無く垂れ下がる頭を胸に抱き、泣いていた。何も考えられない。何も分からない。でもそこにはどんどん冷たくなるギンの体がある。
愛した人が死のうというのに、私はただ、赤子のように泣くしか…それしか出来なかった。
―ら…
え?
耳には私の泣く声がうるさく響いているのに、小さな小さな声が聞こえた気がした。
いや、確かに聞いた。頭が、心が、体がその声がを覚えている。
「ギ…ン……?」
見るとギンが、微笑んでこちらを見ていた。
―らんぎく。
「あ…あ…。」
無様にも言葉を失い、意味の無い声を発する私を、ギンは笑ってみていた。
その時、違和感を感じた。
重さが、無い。
ああそうか、消えるのだ。
―乱菊、泣かんで?
愛してるから。
周りにはキラキラとした粒子が舞っている。ギンの体は、まるで砂時計の砂が落ちるようにその粒子になって消えていった。
―ほら、泣かんでって。
ギンは笑って残った左手で私の溢れる涙を拭った。
その手は温かかった。
―落ち着いた?
温かい光に包まれて、いつのか私の涙は止まっていた。頭がぼーっとする。ただその美しさに見とれていた。
―乱菊。最後にな、ボクの我が儘聞いて?
真っ白なギンの肌は透き通っていて、まるで…
雪のようだった。
―キス、してもええ?
もうほとんど消えかけていた。光が強くなる。
―乱菊。ええ?
頭は働かないのに、私は頷いていた。
―ありがとう。
近づいてくるギンを感じながら、瞼を閉じた。唇は、光よりも、先ほど涙を拭ってくれた手よりも…今までの人生で触れたどんなものよりも優しく温かかった。
目を開けると、触れあった唇から溶けるように消えていくギンの顔があった。
―ごちそうさん。
気づいた時には、ギンは完全に光になっていた。
(待って…。)
声は、喉の奥が張り付いて、うまく出てこなかった。
光の粒は舞い上がり、寒空に消えていった。
「なにぼーっとしとんの。」
「え?」
「せやから、約束したやろ?って。」
“約束”?
私は思い出していた。
光を唖然と見送っていると、どこからか声がした。
それは近くからのようにも、遠くからのようにも感じられた。
乱菊
約束や…
「現世で会お。」
そうだ。
ギンはそう言ったのだ。
「思い出した?」
目の前にはギンが立っていた。
白い雪の世界の中に、
現世の服を纏ったギンが―
「ほら、また泣いてる。」
手が頬に触れると、今まで閉じ込めていた記憶が溢れだした。初めて出会った日の空、闇に消えていく背中、ギンの最後の光…あらゆる記憶が駆けめぐる脳内に反して、私の心は静かだった。言われて、初めて自分の涙に気づいた。
「どう…して…。」
「何回言わせんねん、約束したからや。」
「でも…だって…。」
ギンは私の事をぽすっと胸に納めると、「はいはい。やっと30年振りに会えたんやから今は再会の感動に浸っとくもんや。」と笑って言った。
「うん。」
匂いも心臓の音も確かにギンのもので、いつの間にか私まで笑っていた。
「乱菊。」
「ん?」
「また、キスしてもええ?」
「…いいよ。」
私たちはキスをした。
2回目のキス。
「会いたかった。」
「ボクも。」
雪はキラキラと輝やいていた。
金色と銀色を写して。
それはその瞬間、世界で一番綺麗な光だった。
.
- 30 -