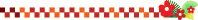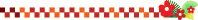
「松本君、ようこそ虚圏へ。」
「………。」
「まぁそんなに逆毛を立てないでおくれよ。まずは我が同胞たちを紹介していこうか。こちらはスターク…」
「さて…この二人について説明は要らないかな。要と…」
ギンだ。
乱菊は目を反らす。
「そんなに怖い顔をしては美しい顔が台無しだよ。」
藍染は顎に触れ、顔を上げさせる。
噛みつかんばかりに睨む眼を見て、笑みを深くする。
「さぁ、笑って。華はいつも笑っていなくては。」
手は顎から頬へ流れるように移動していく。
「藍染さん、ボクは他人のを見る趣味は無いですよ。やるんやったら、部屋でにしてくれませんか?」
「ああ、悪かったねギン。」
「……市丸っ!」
「あらら、十番副隊長さんいきなり市丸って。まぁ他に呼びようないかも知れんけど。」
「……。」
「織姫は…!織姫はどうしたの!?」
「大丈夫だ。彼女はこのウルキオラが世話してくれているよ。もう我らの同胞だ、身も心もね。」
「…!」
「それに彼女はね、松本君。君がここにいることは知らない。心配しなくていいよ。」
「…そう。」
「手荒な真似をして悪かったね。今これを外させよう。」
藍染が合図をすると、手下のものが乱菊の手枷をシュルッと外した。
見ると、赤い痣がついていた。
手首を押さえ視線を上げると、ギンと目があった。
にやついて、表情からは何も感じ取れなくなっていた。
寒気がした。
もう、ここにいるのはギンではなく、ギンの殻を被った違うものなのではないか。
怖い。
脂汗が滲み出る。
「おや、松本君はギンがお気に入りかな?じゃあ松本君の事はギンにまかせることにしようか。」
「そんな面倒な事、ボク嫌ですわ…。」
ギンは頭を掻く。
「ハリベルとかええんとちゃいます?女同士のがやりやすいんやないですか?」
「私は、御免だ。娼婦の世話をする義理は無い。」
「そんな言い方はよくないね、ハリベル。…だ、そうだよ。ギン、キミに頼むことにする。じゃあみんな、解散しようか。」
ため息をつくギンに、すれ違いざま、東仙はつぶやく。
「ギン…分かっているだろうな。藍染様が手を出すまでは…」
「あぁ分かってますよ、東仙さん。心得てますって。」
広い部屋には二人だけが取り残された。
「しゃーないなぁー…。藍染さんにも困ったもんや。 松本さん、立てる?」
「…ギン、あんた…!」
「なんや市丸から下の名前で呼び捨てなんて、ずいぶんと親近感持ってくれとるみたいやね、嬉しいわ〜。」
「…ねぇあんた!どうしてっ…」
「さ、行こ。松本さん。ボクはキミに部屋を用意したりせなあかんの。それに、はよ湯を浴びな、いつ藍染さんのお呼びがかかるか分からんしな。」
「………。」
「ついておいで。」
ギンは背を向けると、歩き出してしまった。
その背中に無意識のうちに恐怖を感じ、気付くと足が、一歩前に出ていた。
「ここ。まぁそれなりに綺麗やろ?入り。」
部屋は簡素で、無機質。
人工的な臭いがした。
壁に触れれば、やはり冷たい。
「あんた…藍染に何を吹き込まれたの?藍染に…」
「おっと。あんまりあの人の悪口言うたらあかんよ?たいていの所は藍染さんの監視下にあるから。気を付けたほうがええで。」
「あんた…どうして…。」
ぼろぼろと涙を流す乱菊を、入り口に寄りかかり愉快そうに眺めている。
「ほら、そこ使い。疲れとるやろ?ゆっくり浸かったらええ。ボクはしばらくしたらまたくるわ。じゃあな。」
「待って…!」
ギンはひらひらと手を振って、扉の向こうに消えてしまった。
はっとして飛び出した時には、その姿はどこにも無かった。
乱菊は力なくその場にへたりこむ。
「ギン、どうして…。」
パタリ
後ろ手でドアを閉めた。
ああ
何も考えられない。
思考を止めろ。
笑え
笑え
笑え
笑え
湯船の中で、乱菊はただただ泣いていた。
「よう似合うとるよ。」
与えられた服は死魄装ではなく、虚圏の服―
同胞の証だった。
乱菊にはとても似つかわしくないものだった。
「嘘。」
苦々しげに服を睨む。
「そんなこと無いよ。」
「あんたはずいぶん似合っているのね。」
「……。」
「さぁ、行こか。藍染様のお呼びや。」
ここで見たどの部屋よりも大きく、気持ち悪ほくなるほど広い場所だった。
遠近感が狂っている。
これを“部屋”と呼んでいいのかすら分からなかった。
「趣味の悪い部屋…。」
「これは辛辣な意見だな。私は気に入っているよ。」
「藍染…!」
「藍染さん、ちゃんと連れてきましたよ。じゃあ後は、ごゆっくり。」
「ああ、ありがとう。すまないね、ツラかっただろう。」
「何がです?」
「いや、何でもないよ。」
「ギン!待って!!」
後を追おうとする乱菊の腕を藍染が掴んだ。
「止めて!離して!」
決して強く握られているわけではないのに、力を込めても込めても、ピクリとも動かない。
「まぁお茶でも飲まないか?」
知りたくないかい?
ギンがここにいる理由を。
「君はギンと同期だったか。」
「……。」
「いや、それだけじゃないね。幼い頃から共に暮らした仲だ。」
「なんで、それを…!」
「あぁ、そうだ、そこからか。君は知らなかったね。どうして君たちは出会えたのか。」
「え?」
「私のおかげ…いや、せい、かな?」
「…………」
乱菊は茫然として、何も考えられなかった。
言葉も出ない。
「どうして泣いているんだい?」
藍染の指が乱菊の涙を拭った。
乱菊は初めて泣いている事に気付いたが、もう頬を伝う涙の温かさも、触れる手への嫌悪感も感じなくなっていた。
「君が気に病む事じゃない。運命のいたずらというやつだ。」
藍染は立ち上がると、乱菊の首もとへ口を寄せ呟いた。
さぁ、行こうか。
ギン…
ギン…
ギン…
「ギン。」
声をしたほうへ目を向けると、乱菊が立っていた。
「なんで…ここに…。」
「藍染が教えてくれたの。」
目を腫らしてこちらを見つめる乱菊に、ギンの心はざわめきたつ。
パリッ…パリッ…
と、破面の面が割れていくように、ギンの仮面にヒビが入るのが聞こえた。
「らん、ぎく…。」
自然とこぼれ落ちるそれをギンは止める事が出来なかった。
久しく口に出してはいないこの名は、二人しかいない部屋に響いた。
「よかった。ギンだ…。」
乱菊は心から安心したように笑った。
「ひどいわね…ここ。」
部屋は至るところに傷があり、家具もめちゃめちゃになっていた。
ギンの髪は乱れ、その肌には傷が刻まれ、汗が滲んでいた。
乱菊の指が傷に触れる。
ギンの目は見開かれたままだ。
仮面がボロボロと崩れ始める。
「…さわ、らんで。」
「え?」
「…触らんで。」
ギンが後ずさる。
「ギ…」
「触らんで!近付かんで!!ボクの名を…呼ばんで…。」
「何故?」
「ええから出てって…出てって!!!」
乱菊は後ずさるギンに迫り、その頭を胸に抱く。
「らん…ぎく…?」
「はぁ…。ギンの匂いだぁ。」
胸いっぱいに空気を吸い込んだ。
「子供の時に嗅いだ匂いなんて、未だに覚えているものなのね。」
「らんぎ…く?らんぎく…?」
「ほら、私の匂い、する?」
甘ったるい悪趣味な香水の香りの下に、血生臭い香りがあった。
そしてその奥の奥に、ギンの守りたかったものがあった。
「ギン、泣いてる。」
1度も流したことの無いそれを止める術を、ギンは知らなかった。
「よしよし、よしよし。」
サラサラと鳴る髪を鋤き、ぎゅっと頭を頭を抱いた。
ずっとそうしていた。
乱菊がギンを抱き
ギンが乱菊を抱いた。
ただ何もせず、抱き合っていた。
「ねぇ、ギン?」
「…ん?」
もう、終わりにしようか。
「うん。」
刀を、貸して。
「うん。」
すぐ、行くから。
「うん。」
愛してる。
「ボクも。」
刀を持った二人の影はひとつになる。
倒れる影を支える影は、
いとおしそうに髪を撫で、静かに笑うと、その影に重なった。
動かぬ影がひとつの塊のように隙間なく抱き合い、延びていった。
それを照らすのは青空の光。
窓から差し込むそれは愉快そうに揺れていた。
.
- 19 -