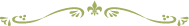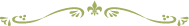
駅から少し離れた路地にひっそりと佇む小さな喫茶店。
老若男女問わず、それなりに人が入っている。
今日もまた、新たな客が来店した。
「いらっしゃいませ」
一人の女性がゆっくりと店内へ入ってきた。
白髪のマスターが笑顔を向ける。
馴染み深い木目調の床をコツコツと鳴らし、木のテーブルと椅子の触り心地の良さを指で確かめている。
窓からの日差しが店内を明るく照らすなか、彼女はテーブルに置かれているラミネート加工したシンプルなメニュー表に目を通す。
しばらくして、きょろきょろと店員を探す仕草をした。
それに気づいた青年がオーダー用紙を持って注文を受けに行く。
「お決まりですか?」
「えっと、……これお願いします」
細い指が差したのは昔ながらのオムライス。
以上で、と言葉を締めたので、一礼してそのままバックヤードへ注文を流しに行く。
「椿くん、オムライスひとつ」
「はい」
最年少の椿がせっせと準備に取り掛かる。
ここの喫茶店の従業員は、最年少で調理担当の久条椿。
マスターになるために勉強中の都築准。
アルバイトの片桐悠と茅野瑠衣。そして、彼らをまとめるマスターの五人だ。
たまに、二人の青年が手伝いに来てくれる。
「椿ちゃん、チョコパフェ」
瑠衣がオーダー用紙をひらひらと振りながら厨房へやってきた。しかし、オムライスに取り掛かっているのを見て、悠に視線を移す。
「悠ちゃん、チョコパフェ」
「瑠衣くんも作れるだろ。まぁ、いいけどさ」
よろしく~、と笑顔で用紙を置いていく。
瑠衣は明るく、喫茶店での太陽のような存在である。そんな彼がフロアに出たほうがいいだろう。
椿の隣でパフェの調理を始めた。
「椿くん、ナポリタンお願いします」
悠が厨房を後にしてすぐ、准が注文を伝えに来た。
そのままオーダー用紙を整理する。
瑠衣はただ置いていくだけなので、椿が注文の順番を覚えなくてはいけない。
彼の負担を減らすため、准や悠が用紙を並べるのだ。
瑠衣に言っても忘れてしまうので、最近はなにも言っていない。
「はい。准さん、これ四番さんにお願い」
「うん、わかった」
オムライスをトレイに乗せて、この分のオーダー用紙をボックスへ入れる。
後で整理をするために、一時的に保管するのだ。
先ほど来店した女性客へオムライスを運び、テーブルへ置いた。
一礼してカウンターへ戻る。
マスターは常連客と話をしている。中年男性の一方的な女房の愚痴だが。
今日は天気がいいせいか、客足がいつもより多い気がする。
「都築さん、今日は多いですね」
「そうだね。嬉しい限りだね」
そっと声を掛ける悠も、准と同じ表情をしていた。
やはり、自分が働いている喫茶店が繁盛しているのは嬉しいものだ。
自分たちの働き方が間違いではないことの証だから。
「あ、悠ちゃん。あの人」
いつの間にか隣にいた瑠衣が、悠の肩をぽんぽんと叩く。
彼の視線の先には、先ほどオムライスを注文した女性が席を立っていた。
真っ直ぐに、ある扉に向かっている。
来店したときとは別人のように、足取りはしっかりしている。
そのままパタンと扉が静かに閉まった。
「…………」
「なんだろね」
「瑠衣くん、俺たちはあっちには関わらないよ」
「わかってるって。けど、気になるじゃん」
「…………そりゃあ」
彼女が入っていった扉を見つめる二人の肩をぽんと准が軽く叩いた。
意識を喫茶店に向けるためだ。
「まだお客さんいるよ。僕はレジに入るから、後はお願いね」
「あ、はい」
准にそう言われ、慌てて仕事に戻る二人。
店の片隅にひっそりとある扉に気付くのは、見つけたいモノがある人だけ。
そんな不思議な扉の先には、ここのオーナーと二人の青年がいる。
そこは、なくしたモノを見つける失せ物屋。
ポツポツと点在している頼りない灯りが僅かに階段を照らしている。
踏み外さないように慎重に足を進めた先に、扉があった。
迷わずにそれを開いた。
扉の先には大きな空間。
紅い絨毯の上に漆塗りのテーブルと椅子。
向こう側の椅子には着物姿の青年が座っていた。
闇よりも深い黒髪を一つにまとめて、シンプルな簪で留めている。
男性なのに、とてもよく似合っている。
「いらっしゃいませ。失せ物屋へようこそ」
「失せ物屋……」
「見つけたいモノがあるのでしょう?」
「……はい」
彼女は決心したように足を踏み出し、椅子に腰掛ける。
膝の上でぎゅっと拳を作り、体を強張らせる。
「私はここの建物のオーナーの柊桃麻です」
「オーナー?」
「上も私のお店です」
「そう、ですか……」
随分と雰囲気の異なる二つのお店だと、きょろきょろと周りを見渡した。
ピアノのBGMがあった喫茶店に対して、地下の失せ物屋は無音だ。あるとするならば、お香の匂い。
「あの、父を探して欲しいんです」
「お父様?」
「はい」
鞄から取り出したのは、小さな子供を抱き抱える男性の写真と腕時計とボイスレコーダー。
ボイスレコーダーには、幼女の舌ったらずな声と嬉しそうな女性と男性の声が入っていた。
彼女の両親の声だそうだ。
「ずっと、母から父は死んだと聞いていたんです。けど、先日母が亡くなる前に、生きていると伝えられました」
親戚を訪ね回ったり、聞き込みをしたりと情報を集めた。この街にいる、ということがわかった。
一人で探すには限度があり、とうとう限界を迎えてしまった。
「お願いします。父を探してください」
「……わかりました。この依頼、お受けします」
「ありがとうございます。お願いします」
深く頭を下げた彼女の声は、震えていた。
やっと頼れる場所を見つけた安堵からだろう。
連絡先をきき、契約書にサインをもらう。
そのまま、彼女は扉から喫茶店へ戻って行った。
「オーナー、引き受けて良かったのか?」
奥から二人の青年が姿を現す。
長身の青年ーーー村雨陽介が椅子の背もたれに片腕を乗せて上から尋ねる。
もう一人の青年ーーー芦屋蒼は黙って様子を見ていた。
「大丈夫です。段取りはしておきますよ」
「いや、そこじゃねえし」
「では、陽介はなにを心配しているのですか?」
「あの人が自分の父親を殺すんじゃないかってこと」
ああ、それですか。と気に留める様子もなく、桃麻は微笑を浮かべる。
彼女が置いていった三つの物を手に、奥へ移動する。
「そうなったとしても、俺たちには関係のないことです」
「なっ!?」
彼の言葉に、二人は息を呑む。
ここに来る者の願いは、何かを見つけたいということ。
見つけた後のことを心配するのは願いに含まれていない。逆に、それは拒まれていることのほうが多い。
「君たちもそうでしょう?」
肩越しに向けられた眼差しが、全てを見透かすようなそれに感じた。
思わず目を逸らす。
その反応こそが答えなのだ。
「みんな同じですよ」
にこっと笑う。
そんな彼が、時々恐ろしい。
桃麻は不思議な力を持っている。
魔法と言ったり、魔術と言ったり、超能力という表現もできる。言葉を並べるのは簡単だ。
そしてそれはどれでもいい。
自分がしっくりくる言葉を選べばいいと彼は言う。
「少し時間をもらいます。その間、blossomを手伝ってあげてください。今日は忙しくなりますから」
あと五分後に上に行くこと、と条件を出された。
彼の言う通り、時間を見計って上にあがった。
扉を開けると、太陽の光りが目に差し込んできた。
下から上に出るとき、いつもこの光りが眩しくて動きが一瞬止まる。
「夜ならまだ良いんだけどな」
「行こう」
カウンターのマスターが彼らに気付き、微笑みを向けた。
彼らも会釈で返す。
そのままバックヤードへ足を進めた。
「あ、村雨くん、芦屋くん」
准が笑顔で彼らを呼ぶ。
それにつられて他の従業員たちも二人に意識を向ける。
「手伝いに来た。忙しくなるとオーナーが」
「本当?助かるよ、今まさにって感じなんだ」
二人は準備をして、准から今の現状をきく。
満席になっており店の外で待っている客もいる。
一斉に注文が入ったため、マスター以外の従業員が厨房にいるのでフロアが回らないとのこと。
二人はフロアへ向かう。そもそも、調理はできない。
「すみません」
早速若い女性客に声を掛けられた。
蒼が対応に行く。
「さっき頼んだカルボナーラ、まだですか?」
「すみません。ただ今調理をしておりますので、少々お待ちください」
丁寧に礼をすれば、彼女はわかりましたと椅子に深く座り直す。
こちらの波長が静かであれば、相手も自然と静かになる。
悪い例が、今対応をしている陽介だ。
マスターが間に入り、宥めている。
相手の男性客も、マスターに免じて許すと言っている。
なにをしたんだ、あの人は。
バックヤードからトレイに皿を乗せた悠と瑠衣が出てきた。
テーブルに皿を並べ、空いた席を片付けてから戻り、陽介と蒼が待っていた客を案内する。
ほとんど五人でフロアを回して、二時間後に一段落した。
「ふぅ~」
バックヤードで陽介が椅子に座り込む。
たまにblossomを手伝うが、その度に自分は向いていないと痛感する。
「お疲れ様、村雨くん。助かったよ」
「准さん、今日の分ちゃんと出る?」
「出るよ。もちろん」
「いつもよりも増しでお願い」
「うーん、それは難しいかなぁ」
苦笑を浮かべながら洗い物をする准を、手伝ったほうが良いんだろうなとは思うが、行動する気力が沸かない。
彼も陽介の状態を見て、無理にお願いはしないだろう。
「村雨さん、オーナーが呼んでる」
「げっ、もう?」
もう少し体を休めたい。
甘い物でも食べたい。
「あ、准さん。チョコある?」
「ん?あるけど、どうするんだい?」
「糖分補給。アイツの奢りで」
「誰がお前なんかに奢るかよっ」
オーダー用紙を持ってきた瑠衣が眉を吊り上げながらつらつらと陽介への文句を並べる。
当の陽介は右から左へと聞き流していた。
「あ、蒼くん。ありがとうね」
「悠さん。いや、オーナーに頼まれたから」
「これから仕事?」
「あぁ、まぁ」
「えっと……、気を付けて」
「大丈夫だよ」
心配そうに見つめる悠に、蒼は精一杯の笑顔で返す。
表情の変化が少ない彼の珍しい一面に、他の従業員が驚きを隠せずに見つめた。
視線に気づいた蒼は、照れ臭そうに俯いてしまった。
「村雨さん、行こう」
「ああ。じゃあな、今度奢れよ」
わしゃわしゃと犬のように頭を撫でる彼の手を振りほどき、「奢らねーよ!」と叫ぶ。陽介はひらひらと片手を挙げて地下への扉へ消えていった。
変化のない扉を見つめたまま、小さく「しかたねーな」と呟いた瑠衣の言葉は、静かに空気に溶けた。
.
- 1 -