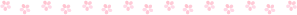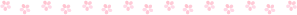
そんな感傷に浸りながら、病室の窓から外の赤や黄に染まる紅葉を眺めていた。
名前を呼ばれ振り返ると、若く溌剌とした看護婦さんが
「もう夕暮れで冷えて来ましたから、窓を閉めましょうか」
と言った。
確かに信州の秋は肌寒く短い。
素直に看護婦の指示に従い、言われた通りに窓を閉めると、私は自分の病床へ戻った。チラッと隣の空いている病床へ目をやる。一昨日は向かい側の病床の患者が亡くなった。昨日は隣の病床の患者が亡くなった。今日も誰かが亡くなるのかもしれない。明日は我が身かも知れない。ここでは誰かしら亡くなるのが日常だ。朝に顔を洗い歯を磨くのと同じ様に人が亡くなってゆく。
私は日記帳代わりにしている、初任給で購入をした本革の手帳を取り出し、やはり初任給で購入をした万年筆で、日課にしている日記を書き始めた。特に書く物がある訳ではない。ただ惰性で続けている行為に何の意味があるのか。あるとすれば、遺された家族がこれを読む時だけであろう。
「・朝食……梅干し入りのお粥・林檎
・昼食……味噌汁・雑穀米・納豆・冷や奴・野沢菜の漬け物
・夕食……月見蕎麦
微熱と咳が続く。」
これを読めば
「何だ、これは。喰う物ばかりではないか」
家族はゲラゲラと笑うであろう。
私は短い日記を書き終えると手帳を仕舞った。
窓へと目をやった。あの空に続く所にある銀行は平日の今日は営業をしているのだろう。岩手の田舎で商業高校を卒業した私は、株で成功した東京にある親戚の家で下宿をし、やはり親戚のツテで東京の銀行へ就職をした。
初めて血を吐いたのは、雪がしんしんと降り積もる日だった。勤めを終え道へ出た瞬間に喀血し、地面の白と血の朱がコントラストを描いた光景が、クッキリと脳裏に焼き付いている。上役のツテで富士見のサナトリウムへ入院をした。
最近は微熱が続くようになった。咳も続いている。
そして夕食までの仮眠を取ろうと毛布にくるまった。
半年後に富士見駅に私は立っていた。
「いやぁ!驚きの回復力ですなぁ!!」
感嘆の声を挙げた主治医の言葉が、まだ耳の底に残っている。どうやら私は病魔に打ち勝ったらしい。珍しい生還組といった所であろうか。
紅葉は瑞々しい新緑に姿を変えていた。それでも美しい景色は時に人を傷付ける。
汽笛の音がし、私は改札口を入ると汽車へ乗った。家族の待つ家へ帰る為に。――結――
- 3 -