
灯り
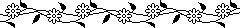
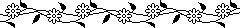
父に単衣を縫うと決めたのは、九十日と九日前。結は百日で仕立てると宣言して、母からお針をいちから習っていた。
「あと一日……」
期限を切ったのは結の勝手で、そもそも父には内緒で作っているのだから何日か先伸ばししても良いのである。しかし、結の性根はそれを許さなかった。百日と言ったら百日なのである。十二の娘にしては、かなりの強情。
「さて、と」
父は後家人で、先ほどお城に勤めに出ていったばかりだ。結は縫いかけの単衣とお針箱を引っ張り出すと、かけはりに掛けて、衿(えり)をくけはじめた。母なら、針は生地の中に隠れて見えず、そのまま布と布の間をうねって進むのだが、結はひと針毎に布を掬って針を引っ張りだし、糸をしごく。時がかかって、なかなか前に進まない。焦れったさに唇を噛み締めるが、指は動くようにしか動かない。
「結、お華ちゃんがみえましたよ」
「あっ、忘れてた!今日は、お華ちゃんと約束していたんだった」
「まあ、ではこれはどうするのです?」
母の眉間が曇って、お針箱と結を見比べるが、結はさっと立ち上がると、
「じきに戻りますから、それはそのままにしておいてください!」と言って、お勝手で待っていた友人をつかまえると、外に飛び出して行った。
「ほんとに、もう…」
母はため息をつきながら、単衣から針を抜いて畳んだ。
お華は呉服屋の娘で結よりもひとつ年がうえだ。
先日のお茶のお稽古の帰りに、相談したいことがあると言われ、今日はその約束の日だった。結は父の単衣のことが気になりながら、お華の相談事がややこしい事だったら嫌だなぁと思った。しかし、横を歩くお華の思い詰めたような頬をみて、そんな事を考えた自分の心に腹をたてた。ふたりは、これから暑くなりそうな通りを無言でぬけて、川縁まで来た。土手の草を踏みしめて座った。お華は薄紅梅色に撫子が染め抜かれた絽を着ていたので、草の汁がつかないか結はヒヤリとしたが、本人は気にしていないようだ。結は紺瑠璃に白い縞が入った綿紬で、こうしてみるとどちらが武家で町人なのか。
「結ちゃん、どうやら私、恋をしてしまったみたい」
「えっ、誰に?」
お稽古事の悩みかと思いきや、まったくの予想外に結は目を剥いた。
「どこの誰かは、わからないの…でも、お侍さんよ?」
「お侍…」
一週間ほど前、お花の稽古の帰り道。夕立がきそうで帰りを急いでいたところ、焦って小石に躓き持っていた桔梗を落とし、撒き散らしてしまったという。そこに現れた侍が拾って、紙に包み直してくれたそうだ。一目惚れである。
まだ恋に無関心の結には、何の言葉も出ない。
「どこのお侍さんかしら…結ちゃんのお父上なら、ご存じかしら?」
「うーん、どうかなぁ、わかるかなぁ…」
と言ってみたが、お城には何千もの人が勤めているし、結の父は大奥の世話係りである添番だ。多くの侍と顔を合わせるとも思えない。
「どんな人だったの?」
「私、どぎまぎしちゃって、ちゃんと見れなかったのよ。柳鼠の紬を着流して、すらっとしたお方だった。あ、でも少しお髭が伸びていたわ。とても静かな雰囲気だった」
「お髭って!いくつくらいの人だったの?」
「きっと、ひとまわりより年上だと思うの…」
恋の「こ」の字も想像できない結には、もう何の相談にも乗れそうもない。ましてや、お相手が親の年齢の方に近いとなれば、なおさらだ。
体にかかる草をむしりながら、結はお華の片思い話を延々と聞かされるはめになった。その間も、縫いかけの単衣が思い浮かび、しなければいけない作業の行程をなんども頭で繰り返した。
お天道が真上を過ぎ、暑さが川風に勝ってきた。もう昼九ツか。ふたりは、立ち上がってお互いの草を払うと、それぞれの家に帰った。
「遅いですよ」
母にたしなめられながら、簡単な昼餉をとると、結が洗い物をした。ようやく縫い物をしようと、腰を落ち着けられたのは、昼八ツも大分過ぎていた。
「急がなきゃ」
なんとか衿はできた。あとは両袖をつけるだけだ。少しほっとしたが、男物の着物には、みやつ口がないから、身頃と袖がぴったりはまらなければならない。そして、脇はきっちりと強く糸を結び絞めなければならない。思いの外苦戦して片袖が付いたころには、もう夜五ツだった。すっかり夕餉も忘れている。
夏で日が長いとはいえ、これでは明るいうちに完成することはできないだろう。それに、子は早く寝るもの。と、母は夜なべを許してくれないだろう。
「父上は、今夜はお役目でいらっしゃらないから、夜のうちにこしらえて、明けたら父上に渡せるのに…」
気持ちが沈んでいくのが自分でもわかった。
するりと、襖が開いて、母が入ってきた。手に持っているのは、置行灯。と、握り飯。
「さあ、この灯りでおやりなさいな。決めた事は、最後までやりとおすのでしょう」
母がにんまり笑うので、結もにんまり返した。
「ありがとうございます、母上」
次の袖は、先ほどよりは快調に縫えた。左右で手つきが逆になるところもあり、何度かどきりとしたが、なんとか完成した。師走の大晦日でもないのに、こんなに夜更かしをしたのははじめてだ。あと少し、全体に鏝をかけてシワをのばし、きせをかけて整えるのだ。
台所の竈から、種火を小さい火鉢に移し、鏝を温める。そして、桶に水を張った物も用意した。鏝は鉄の塊で、熱しすぎると着物に焦げ穴をあけてしまう。桶の水にじゅうと浸けて、温度を確認し調整するのだ。眠気でぼんやりしそうだが、一番神経を遣うところだ。じゅう、じゅうと暑い湯気が部屋を満たす。途中、何度も母が覗きに来ては、縁側へつづく障子を開けて風を入れてくれたのだが、結は全く気づかなかった。
全体が綺麗にのされた単衣は、行灯の灯りで、まるで黄金色のようだった。
戻る

