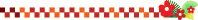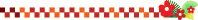
灯る灯る、今年も灯る―
秋の景色の中に、ひときは鮮やかな色が灯る―
****
「ギーン!」
「今日はなんや…。」
騒がしい毎日の中で、ギンの心は穏やかだった。表には決して出さないが、そこにはささやかだが、“幸福”が確かにあった。
ギン自身気づいていないのかも知れない。
ただ、過ぎる日々は閉ざした彼の心を静かに、ゆっくりと、溶かしつつあった。
「ちょっと出てこいよ!見せてーもんがあんだ。」
「しゃーないな…。」
のそのそと外に出れば、そこには見知った3つの顔。
黒いのと
赤いのと
黄色いの
うるさいのと
うるさいのと
気弱なの
(いいトリオやな。)
戸を開けた先に待っていた3人の姿を見て、ギンはふとそう思った。
「どうした、ギン…。なに笑ってんだ?」
「え?…何でも無いわ。」
自分は、笑っていたのか…。
気づかぬうちに笑っていた事に(特にこいつらの事で)、軽くショックを受け、ギンは少々いらついた。
「どこ連れてく気や。はよ行くで。」
「なんだよ、こんどは急に怒りだして…。」
「ギンって時々変だよなぁ。」
「…そうだね。でも楽しそうだよね、最近のギンさん!」
「「そうかぁ??」」
「なにしてんねん、はよしろ!置いてくでー。」
「あ、はーい!待ってくださーい!」
「置いてくって…俺らが案内すんだろ。」
「あいつ馬鹿か…?」
一行は山道ですら無いような、道なき道を進んでいく。
「まったく、どこまで行くねん…。」
「なんだよバテてんのか?」
「ギンも歳だな…。可哀想に。」
「お前ら…。」
「も、もうすぐ着きますから!」
「ここだ!」
(あぁ…。)
ギンは、心がわずかに揺れるのを感じた。
「どーだ!すげーだろ。」
胸を張る3人の弾む声が、ずいぶんと遠くに聞こえた気がした。
****
「隊長の好物は、干し柿でいいですよね?」
「なんや…急に。」
「瀞霊廷通信ですよ!こないだ言ったじゃないですか。全隊長、副隊長のプロフィールを掲載するんです。隊長がいつまでたっても書かないから僕がこうして…。」
「まためんどい事考えるなぁ、編集部は。ええでそれで。干し柿て書いといて。」
「はい。」
三番隊には、大きな柿の木がある。どれも渋柿だ。干し柿が並ぶ軒先は、もはや秋の風物詩と言われるまでになっていた。
「そういえば、乱菊さんと一緒ですね。」
「そうなんか?」
ざわつく心を隠し、ボクは平静を装う。もう慣れたものだ。
「みたいですよ?だけど…。」
「なんや。」
「好物だと聞いて、こないだ今年出来たものを持っていったのですが、何故か断られてしまいました…。なんでだろ。」
「……さぁな。買ったもんのほうがええんちゃうの?」
乱菊は三番隊で作られたものは食べない。以前にもそういった話を聞いたことがある。
(当てつけか…。)
ボクは自嘲する。
いや、ある意味ボクも“当てつけ”なのかも知れないな。
この時期が、ツラい。
道を歩けば鮮やかなオレンジ色が嫌でも目に入る。それは固く閉じ込めたはずの“過去”を、力ずくでこじ開けてはボクの心を荒らしていく。
やめ…てくれ。
ボクを苦しめるのがそんなに楽しいか。
それでも木を植え、思い出の欠片を作ってしまうのは、想いを主張せずにはいられないボクのエゴでしかない。
甘えだ。
弱さだ。
“こんなにも、愛しているのに”
伝えられない言葉を飲み込んで、ボクは自ら傷跡ををえぐる真似をする。
ただの自傷行為。
だがそんな愚かなもがきは、痛みだけでなく快感も与えてくれるんだ。
自惚れ
愛の為に生きる自分への自惚れ―
キミの為に命を捧げるボクの事を、誰かに観ていて欲しい…。
*****
…ン!ギン!
「ギン!」
「あぁ…。」
「どうされたんですか…?」
「何でもないわ。」
目の前にそびえる柿の木を見上げて、ギンは呟いた。
「何でも、ない…。」
3人はいつもと違うものを感じ取って、不安に顔を見合わせた。
「そうか…?大丈夫なんだな?」
「当たり前やろ。なに心配してんねん。」
「し、心配なんてしてねーよ!!」
「何があったのかは知らねーけど、まぁあれだ!これでも食って元気出せよ!」
投げられたのは、重みのあるいびつな球体―
柿だ。
はち切れそうなほど膨らんだ実は、皮に光を反射させて宝石のように輝いていた。
「うまそーだろ。」
「いいかー?抜け駆け厳禁なー。一斉に食うぞ!」
「「「せーのっ!」」」
シャリッ
「げぇぇ!」
「お゛えっ…」
「うわぁあ!」
「……………。」
「まっず!これ渋柿じゃねーか!」
「なんだよ〜。騙された…。」
「ペッペッペッ!うぅ…見た目はこんなに美味しそうなのに…。」
顔を歪めて口に含んでしまったものを懸命に地面に吐き出す姿に、ギンは笑ってしまった。
「くそっ!なんだよギン。おめーは平気なのかよ。」
「んな訳あるかい。渋くてたまらんわ。嵌められて、お前ら恨んでしまいそうやで。」
「僕らはそんなつもりじゃ…。ただギンさんに喜んでほしくて…。」
「バッ!俺をお前と一緒にすんじゃねーよ!」
騒ぎだした彼らの声を聞きながら、ギンはまた木を見上げた。
(ボクは一生、こいつの呪縛から逃れられないんやろうな。出会いも罪も、こいつと共にあった。つくづくおかしな人生や。)
風が山をなでていった。その風はギンの心まで揺らしていったようだ。痛みを伴いながらさわさわと鳴る心の音をどこか冷静に…他人事のように聞いていた。
「まーた自分の世界に入っちゃったぜ…。」
「今日は特にへんだな。」
「誰が変やって?」
「お、おう…。聞いてたのか。おかえり、ギン。」
「…どこにも行っとらんわアホ。」
「あの!ギンさん聞いてください!次の計画!」
「計画?」
干し柿、作りませんか?
(こいつらは…。)
ギンは笑った。
(どこまでもお見通しなんやな。)
初めて会った時、彼らは自分の名を“ヘンな名前”だと言った。それは昔昔―幼い日の思い出のひと欠片を呼び覚まさせた。
本当はあの日々の事は何一つ忘れなんかいなかった。その時流れていた雲、その時漂っていた匂い…すべての瞬間の記憶はずっとギンの中にあった。
その思い出たちに鍵をかけたときに感じた苦しみ、痛みはあまりにツラくて、無意識のうちにその存在すら、奥の奥―もう二度と浮き上がれないほど深い暗闇に沈めていたのだ。
パカリ
それを意図も簡単に開けてしまったのは思えば彼らだった。
「な!いいだろ?今ギンが自分の世界に行ってる間に相談してたんだ。」
「こんなにいっぱいあるんだ、街で売ってもいい。そしたら乱菊さんにまたなんか買ってやれるぜ?」
「………。」
「ギンは乱菊さんの名前をを持ち出すと簡単に操れるな。単純〜。」
「うるさいわ。」
「こないだは勝手に梅酒を売ってしまいましたしね…。何か埋め合わせをしないと…。」
「あれは!ギンの為だっただろ!?なんで俺がこいつの為に…ちくしょう…ちくしょう…」
「まぁまぁしゅーへい。涙を拭けって。」
「うっせーよ!とっとと取るぞ!」
・
・
・
*****
「ギン…これ。」
夜、食事の後乱菊は桐の箱をギンの前に差し出した。
「なに?開けるで?」
「うん。」
開けてみると、そこには綺麗に並べられた干し柿があった。
「なんや、買ってきたん?実は今日な…
「吉良がね?くれたの。」
「え…?」
久しく聞いていなかったその名前に、ギンの心臓はどくんと鳴った。
「“旦那さんに”って。」
「乱菊…。吉良に喋ったんか…?」
「ううん。ただ“旦那さんにあげてください”って。」
「そうか…。」
「うん。」
瀞霊廷では、反逆者であるギンの残した柿の木などすぐに斬り倒そうという声があがった。しかしそれに反発したのは三番隊の隊員達だった。彼らは静かにそれを拒み続けた。干し柿を作るのもやめなかった。黙々と、いつもと同じように作り上げた。
「あいつら、まだこんな事しとったんやな。」
「ローズ隊長なんて、ビックリしてたわよ?“いつの間にこんな風習が出来たんだ”って。」
「新隊長の下、ちゃんと働かなあかんやろ、アホやなぁ。」
「あんたが育てた隊なんだから当たり前でしょ?」
「…そうやね。」
ローズ…100年前、自分達が虚化の実験の為に殺そうとした死神か。それが今、吉良の上に立っている。運命とはなんとも不思議なものだ。
「…食べてみたら?」
「うん。」
優しい味がした。
「うまい。」
「そっか。」
「うん。」
しばらくの沈黙のあと、乱菊は「あんた達が作ったの、出来るの楽しみにしてるから!」と言った。
「なんで知ってんの…。」
「そこに渋柿あったでしょ?」
「渋柿やって分かったん?」
「…さっき美味しそうだと思ってかじっちゃったから……。」
「ぷっ。」
「な、なによぅ…。仕方ないでしょ!」
「ぷくくくく…くはははは!はー、ヤバい!息出来へん!」
ギンは笑った。
涙が浮かぶほど笑った。
赤くなって膨れる乱菊も、馬鹿馬鹿しい運命も、懐かしい三番隊の香りも…全てがおかしかった。
「笑うな〜!」
乱菊はギンに飛びかかると、力任せに髪をくしゃくしゃにした。
「ちょ、やめぇ!」
しばらくして笑いが収まっても、そのまま乱菊を胸に抱き締めていた。
「…ねぇ、ギン?」
「ん?」
「今年は…あんたが作る干し柿、食べてあげるから。」
「………そうか。そら頑張らんといかんな。」
「うん!」
ギンは心の音を聞いた。
さわさわとなる音は相変わらず痛いけど、よく耳を澄ませば、軽やかなリズムが聞こえた気がした。
安らぎは痛みを忘れる事では手にはいらない。
ギンの心は、“思い出”と“今”に包まれて、ゆっくりと溶けていく。
「ありがとう。」
「ん〜?なにが?」
「なんでもないよ。」
ギンは抱く腕にきゅっと力を込めて呟いた。
「愛してる。」
「うん。知ってる。」
今年は、
いいものが出来そうだ。
.
- 12 -