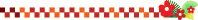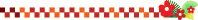
冬がすぐそばまでやって来ている。
寒さと闇は、まるで音を吸い取ってしまったかのように、一面を静けさで埋めていた。
乱菊は窓を開け、外を見ていた。暗さに慣れた目には、ほのかに白く浮かび上がる景色が映っていた。綺麗だと思った。昼間見慣れたものも神秘的な雰囲気を漂わせている。
まるで―
「乱菊。」
思っていた人の声がした。
「いらっしゃい。」
後ろを振り返ると、ギンが立っていた。音も立てずに入ってくるのはいつものこと。乱菊も驚く事は無い。
「寒いなぁ。それに真っ暗や。これじゃ外と変わらん。」
「待って、今火を入れるから。」
立ち上がると窓を閉め、火鉢を点した。ギンはと言えば、炬燵に入り、「寒い寒い」とひとりごちている。
「暖房もつけんと何してたん?」
「冬を…見ていたのよ。」
「なんやそれ。」
「いいでしょ、別に。それよりあんた夕飯は?」
「食べてきた。」
「そ。」
乱菊はのそのそとギンの側に寄ると、狭い炬燵に体を無理やりねじ込んだ。
「狭いんやけど?」
「寒いのよ。あっためて。」
ギンは「しゃーないなぁ」と、呆れたように、でも嬉しそうに場所を開けた。
徐々に温まる室内。力が抜け、今まで無意識のうちに寒さで体が緊張していたのだと知る。
ギンの胸にもたれ掛かりながら、心臓の音を聞いていた。規則正しいリズムは心地よく乱菊の心を溶かしていた。
「乱菊。」
呼ばれて顔を見上げれば、すぐ側にギンの瞳があった。
(ああ…。)
声、水色の奧に灯った熱。
乱菊はギンが自分を求めているのだと察した。
「ギン。」
乱菊は自分から腕を回し、唇を触れ合わせた。
ギンはすぐに体を反転させて、口づけを深くしていく。
舌は絡み合い、口の端からはどちらのものともとれない唾液が厭らしく光っていた。
ギンの手が髪に触れる度、クシャクシャと音が鳴り、乱菊の耳をくすぐる。ギンの息がかかる度、それは脳内をゾワリと駆けていく。
「やだ…。」
「なにが?」
ギンは分かっていて耳を攻める。甘噛みし舐め上げ、息を吹きかける。
反応を十分に楽しむと、首から肩口、胸へと舌を降下させていく。指が茂みの奧に到達する頃になると、唇はまた耳元へ。
余裕の無くなっていく声を乱菊に聞かせる。
こうしてお互いの熱を伝えあっている間にも、火は部屋を温めつづけ、ふたりをさらに高めさせる。
窓は曇っていた。
乱菊はギンを受け入れると、高く鳴いた。
慌てて口を押さえても声は静かな部屋に響いた。
体を打ち付け合う音、水音、こぼれる熱い息と睦事…音が性感帯を刺激していくようだ。
「声、抑えんで?」
「だって…。」
「聞きたいんや。ボクを…もっと感じさせて。」
そう荒い息とともに耳元で囁かれて、乱菊の背には電流が走った。
「あ…。」
もうダメだ。今まで自制心でせき止めていた本能がその一言で溢れ出した。
働かない頭で耳に届く自分の声を聞いて感じている。
早まる音がさらにふたりを高まらせ…
「あぁ…っ!」
叫びとともに二人は果てた。
甘い余韻に浸りながら、ギンはまた髪を弄んでいる。
「乱菊。今日も可愛かった。」
耳にチュッと音をたててキスをする。
「馬鹿。」
汗ばむ肌を合わせながら、乱菊はまた心臓の音を聞く。
先程よりも早く鳴るのがいとおしくて、少し笑った。
冬は嫌いだ。
初めて血に染まるギンの姿を見たから。
私を残して去っていった事を思い出すから。
だから、今だけでもこの音を刻み込みたい。
あなたと愛し合った音を。
.
- 2 -