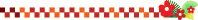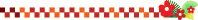
この男の事を私は何も知らない。
「藍染さんどないします、これ?」
「そうだな。適当に始末してくれ。」
「始末言うても、この量ですよ?簡単や無いですって。」
「こんなに盛大にやったのは君だろう。」
「命令したのは藍染さんです。」
「冗談さ。ここは手腕の見せどころだ。頼んだよ、ギン。」
「はいはい。しゃーないなぁ。なんとかしますよ。」
この男はなんの躊躇いも無く人を殺せる。
「ほんま人使い荒いで。なぁ東仙さん。」
この男はいつも声に笑いを含んでいる。
殺しへの高揚感も感じられない。
ただ、迷いなく人を殺す。
「…我々は藍染様の指示に従うまでだ。」
この男は何のためにこの方の元についているのか…
私は何も知らない。
「まったく、東仙さんの藍染さんへの盲信っぷりには敬服しますわ。」
「ギン。君は違うのかい?」
「いえいえ、そんな事無いですよ?崇めてます。現に藍染さんの為にこうして働いてるやないですか。」
「ははは。君に崇拝されるとは。得意の嘘でも嬉しいよ。」
藍染様はこの男について、どう考えているのだろうか。
殺戮をしたいわけでも、己の“正義”を貫きたい為でもないだろう。
それでもこの方の歩くところについていくのは何故なのか。
「なんや心外やな〜。まるでボクがいつも嘘をついているみたいな言い方やないですか。」
「違うのかい?」
「ちゃいますよ。ボクは正直者なんです。」
「嘘はつかないという嘘だろう?」
「なに言うても信頼されないなんて、ツラいわぁ。」
蛇が這うような話し方…そんな表現があるのかは分からないが、この男はまさにそんな話し方をする。
核心に迫りそうになるとするりとかわす。
時には相手の首をじわりじわりと締め付けるように追い込む事もある。
「仕事に関しては絶大な信頼をよせているさ。さて、行こうか要。ここはギンに任せよう。」
「…はい。藍染様。」
初めて対面した時の事をよく覚えている。
***
「この子はギン。私たちの新しい仲間だよ。」
その時まで、藍染様が“仲間”と呼ぶのは私しかいなかった。
「挨拶をしなさい。」
「市丸ギン言います。よろしゅうお願いします。」
「ああ…。私は東仙要だ。」
その声はまだ子供のもので、私はいささか驚いた。
感じる気配から大人では無いことは分かっていたが、藍染様から聞いていた話とは簡単に結び付かなかった。
以前藍染様はこう仰った
―いい人材を見つけたよ。彼は私の隊の三席を一瞬で殺した。彼は天才だ。霊術院を一年で卒業した程だ。―
藍染様の声はいつになく興奮気味だった。
こんな声は初めて聞いた。
そしてこうも言った。
―要。私は嬉しいよ。偶然撒かれた種が予想よりはるかに大きく花開いたようだ。―
―撒いていた種?―
―どんな風に私をおびやかしてくれるのか、実に楽しみだ。―
―藍染様…?―
―あぁ何でも無いよ。こちらの話さ。―
この少年を目前にして、彼から発せられる不気味な気配に、私の背筋には脂汗が流れた。
“こいつは危険だ”身体中の感覚が警鐘を鳴らす。
「藍染様、この男…市丸ギンは…」
「何だい?」
「…いえ、なんでもありません…。」
「要の目には、どんな風に映っているんだろうね。」
光の無いこの目には、感覚という絵の具が世界を教えてくれる。
そこには笑った蛇がいた。
燃えるように赤い目をした蛇が、藍染様を見つめていた。
****
藍染様に従いその場を後にする。
ふと振り返ると、そこにはあの時と変わらぬ姿の蛇が一面の屍の中にたたずんでいた。
その目は、やはり一点を見つめている。
藍染は愉快そうに笑っていた。
この男の事を、
私は何も知らない。
.
- 25 -