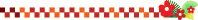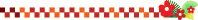
今、遊女と向かい合っているのは、かの護廷十三隊隊長、市丸ギンである。
「あー…めんど…。」
市丸は頭を掻いた。
ここは瀞霊廷の端の端。
それなりに栄えた町である。
ギンは三番隊の隊士数名を引き連れて、流魂街での調査に来ていた。
仕事が少し長引き、帰路へ着こうという頃には日も落ちかけ、ぽつりぽつりと星も出始めていた。
そこで今日は、この町に一泊していこうという事になったのだ。
ギンに用意されたのは、豪華では無いが、趣のある、風の良く通る二階の部屋だった。
食事も終わり、そろそろ酒が出されるだろうという時に、女はやってきた。
「失礼いたします。」
襖を開けて手をついているのは、艶やかな着物に身を包み、色気のある笑みをたたえた女であった。
酒を持ってきてはいるが、明らかにこの宿の仲居とは違う。
迷い無く隣に座り、酒を注ごうとする女に、ギンは警戒心を強める。
「…なんなん、キミ。」
ギンは嫌な予感がした。
「あら…。お客様のご指名じゃなかったの。」
女はさして残念そうな様子も、驚いた様子も見せなかった。
「アイツらか…。」
だいたいの予想はつく。
ギンに媚びを売ろうと、部下が要らぬ気を使ったのだろう。
「隊長直々にって話だったから、気合い入れてきたんですよ?」
彼女はクスッと笑ってみせた。
「あー…。そういう事やから、悪いけど今日は帰って。ボク、間に合うてるから。」
「え?」
「そういう気分やないねん。」
女はしばし考え込むと、「嫌ですよ。」とハッキリ言い放った。
「いや、そやから間に合うてるって。」
「嫌です。今帰ったら、仲間に何を言われるか。これでも私、この街で一番人気なんですからね?」
食い下がる女に、市丸は顔を渋らせた。
「顔に泥を塗るおつもりですか?」
その声色は、ほんの少しだけ、怒気を含んでいる。
(あー……。めんどい事になってきたわ。)
しかし「金はちゃんと払うから」というと、「あら。」とすぐに顔色を変えた。
(なんや現金やなぁー。)
事が上手く片付いた、と酒に手をかけようとすると、女はさっと徳利を取り、お酌をしようとする。
「そやから「でも。」
女は強い口調でギンの言葉を遮る。
「お酒のお相手ぐらいはさせて頂きます。」
女にっこりと見上げてくる。
それは先ほどまでの誘うような笑みではなく、さばさばとした、気のいい女の笑みだった。
「ただでお金を頂く訳にはいきません。言ったでしょう?この街一番の売れっ子だって。売れっ子は、それ相応の仕事をしなければお代金は頂きませんわ。」
悪戯っぽく笑う女に、ギンもつられて笑ってしまった。
「…そやなぁ。そんな売れっ子をただで帰して恥をかかす訳にいかんな。いい頃合いになるまで、しばらく酒につきおうてもらおか。」
女は
艶やかな黒髪に黒い瞳、白い肌に赤い紅。
着物から装飾品にいたるまで、計算されつくされたようにそれぞれの魅力を引き立たせている。
決して嫌みなほど派手すぎず、男の好みを全てわきまえている、といった風だ。
やはり美女と飲む酒は無条件に美味いものだ。
しばし酒と肴を楽しむ。
なかなかいい酒を出す宿だ。
酌をしながら、
「彼女、ですか?」
と、女は好奇心旺盛な子供のように聞いてきた。
「んー…。」
「ずいぶんやきもち焼きの彼女さんなんですね。大変。健全な男子に、こんなお遊びまで許さないなんて。」
女はクスクスと笑う。
「んー。そういう訳やないんやけどな…。別に他の女にしたい夜も無いことはないし。せやけどなぁ。なんや、他にはたいして興味湧かへんようになったんよ。」
まるで他人ごとのような口振りだ。
「へー。惚れてらっしゃるんですね。」
「キミ、面白がり過ぎ。」
「ふふ。だって天下の隊長さまの色恋沙汰なんて滅多に聞けるものじゃありませんもの。 いつから?」
二人の関係は誰も知らない。
しかし、何故だか彼女には、誘い出されるように話してしまいそうになる。
「あ。大丈夫ですよ?漏らしたりなんかいたしません。この職について長いですから。心得ております。それに、こんな女に話したところで何も変わりはしないでしょう?恥をかかせた分の料金です。」
女は相変わらず楽しそうだ。
不思議な力だ。
すっと心の内に入ってきて、警戒心を解かせてしまう。
ギンもどうでも良い事のような気がしてきた。
確かに今この女になにを話したところで、何も変わらないだろう。
「それもそやな。」
「で、いつから?」
「んー…。うんと昔やね。餓鬼ん時からの付き合い。」
「へぇー。意外!」
女は心底驚いた顔をした。
彼女からすれば、護廷十三隊の隊長など、女をとっかえひっかえしているのだと思っていたのだろう。
「純愛なんですね。」
「…客をからかいなや。」
「あら。誉めたんですよ?」
女に促されて、酒も進む。
夏の風に揺れて、軒下の風鈴が鳴っている。
「どんな…方なんですか?」
女はごく自然に聞いてくる。
しつこく詮索するようでも無く、ただ、話の先を誘うようだ。
「…拾ったんよ。」
「拾った?」
「そう拾った。」
ギンはさも可笑しそうに笑った。
「そやなぁー…」
そしてゆっくりと、話し始めた。
―道端で、生き倒れていた女の子を拾った。
やせ細ってボロボロだったけれど、ギンはとても美しいと思った。
灰色の世界の中でそこだけ色がついているようだった。
金色で水色で春色で…世界中の色を全部詰め込んだような色だった。
気付くと、ギンは吸い込まれるように手を差し伸べていた。―
女は笑うこともせず、静かに紡がれる昔話を聴いている。
―そこから一緒に暮らし始めるようになった。
もともと住んでいたボロ小屋に帰ってきただけなのに、そこはまったく違う景色のように見えた。
彼女は最初まったく心を開かなかった。
何を聞いても、素っ気ない答えしか返ってこない。
ある時、誕生日は?と聞いた事があった。
知らないと答えた彼女はいつもより寂しそうだったから、ボクと出会った日を誕生日にしようと言った。
ほんの思いつきでしか無かったが、大きく見開かれた彼女の瞳があまりに綺麗で、ボクはその思いつきに感謝した。
彼女が通った道、指差すところ。少しずつ、色は灯り、広がっていく。
灰色の世界は彼女によって、ほんの少しだけ色味を帯びた。
初めて会った時から、ボクは彼女に捕らわれているのだろう。
彼女が幸せであるのなら…。
自分を見失うほどに強く強く思うのだ。
ほんのりと色づいたこの世界はある時、見たこともないほど鮮やかな色を見ることになる。
赤。
血の赤。
復讐の赤。
その色はボクを狂わせる。
そう、ボクの全て…。
生きる意味。
そして死ぬ意味。
―
ギンは笑っていた。
女は、静かに、語られるその話を聴いていた。
それはあまりに現実離れしているように感じられ、おとぎ話のようにも聞こえた。
物語の余韻が2人の間に沈黙を作る。
「…素敵な、お話ですね。」
「んー。そやね、素敵なお話や。」
愛の物語なのか狂気の物語なのか…。
女にはこれが真実なのかすら知る術が無かった。
ただ、
少なくともそれを語るこの男のその表情や、声は、とても優しかった。
「愛してらっしゃるんですね…。」
「そやね…愛しとる。」
この風の先、どこかにいる彼女を思って、ギンは呟くように言った。
「あーあっ!ご馳走さまでした!」
女は沈黙を破った。
「だからちゃかすなて。」
「だってラブラブ過ぎてお腹いっぱいですよ。こんな一介の花街の女には胃もたれしちゃうくらいです。」
いつの間にかだいぶ時間も過ぎていた。
「そろそろええやろ。」
「そうですね、いい時間です。」
「喋り過ぎたわ。仲間には適当にゆうとって。」
「“凄かった”と言っておきます。」
女はニッと笑うと
「では失礼いたします。」と手をついてお辞儀をして、去ろうとした。
だが、襖のにかけかけた手を止めると、振り返り、最後にひとつだけ、と言った。
「最後にひとつだけ。お名前は…?」
「ん?」
「彼女のお名前。しぶってもダメですよ?これくらい料金に含まれますから。」
ギンはふっと笑うと答えた。
「乱菊や。…松本、乱菊。」
「らんぎく、さん…。」
「いいお話が聞けました。楽しかったです。」
「ボクも、なんや楽しかったわ。」
彼女は笑うと、「では今度こそ失礼します。」と襖を閉めた。
ギンは静かになった部屋で、ひとり酒を飲んでいた。
(流石売れっ子やね。聞き上手、喋らせ上手やわ。)
あれだけ秘密裏にしていた事を、随分と簡単に喋ってしまった。
しかも、自分でも口にしたことも無いような事まで。
後悔とも恥ずかしさともとれない気持ちになって、それが何だか可笑しくてギンはひとりで笑った。
こんなにも自然に話してしまったのは、彼女が乱菊に少し似ていたからかも知れない。
見た目こそ違えど、今思えば、醸し出す雰囲気がどことなく似ていた気がする。
階段を下りながら、女は乱菊の事を思った。
(十三隊の隊長さまにあれだけ愛されるなんてどんな人かしら。)
所詮遊女の身である自分には、到底手の届かない世界だ。
羨ましいとは思わない。私には私の暮らしがある。
明日はまた別の男との夜があるだろう。
(まぁ関係無い世界ね。あなたは幸せ者だわ乱菊さん。)
(顔も知らないのに、わたし、ちょっとあなたが好きになった。)
彼女はクスッと笑って最後の段を下りた。
世界の色が、少しだけ鮮やかになった気がした。
- 1 -