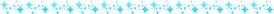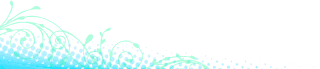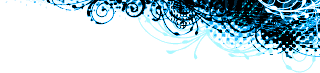
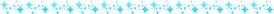
「すっごい新曲だね!まさかアルトがジズと組むなんて予想つかなかったよ」
「でも何でウイルスなの?幽霊引退?それとも現代社会に乗り出す為の第一歩?」
パーティの司会を務めるミミとニャミは、異色のコラボを見せたアルトと白い幽霊に駆け寄り質問責めにした。コンピューターアイドル・アルトは、今までの柔らかな雰囲気と一変したサイバー式の衣装を着てニッコリ微笑みかける。
「ミミさんニャミさん、どうもアリガトウ御座いマス!私トッテモ嬉しいデス」
対してネーヴェは不機嫌に息を吐き、有らぬ誤解を聞く司会者達を軽く睨んだ。
「…無駄口叩くと貴女達も感染させマスよ?」
それを聞いたアルトの表情が一変した。
「ジズさんそれ、駄目デス!」
衣装や身体から電子の粒子の様なものを散らすアルトは手を上げて彼等の間に割って入った。
「イキナリ私のプログラムに侵入してウイルスを撒き散らした上、ニャミさん達にマデ攻撃するナンテ…許しませんヨ!」
危害を加える発言にアルトは真剣に注意した。
「別に良いデショ。私のお陰でこの楽曲完成したんデスから…感謝して欲しいくらいデス」
いつも軽い気持ちで人を貶すネーヴェはアルトの忠告をあっさり流し彼女の画面を人差し指で小突いた。
今回の楽曲はネーヴェの悪戯から始まった。
つい最近性能をバージョンアップしたアルトはポップンパーティに参加する為新しい曲作りを次々と熟していたのだが、夜中に突然制作途中のデータが異常を起こし破損。目が醒めると不思議な衣装に包まれていて身動きが取れない中、別のデータが勝手に取り込まれ仮面の紳士、ネーヴェが現れた。彼は「新しい刺激が欲しくありマセンか?」とだけ言いアルトを抱き起こすと歌いはじめた。
怪訝な顔をするアルトだが、何故か口が勝手に動き知らない歌を口遊んだ。始めは何が起きたのか分からなくて恐怖とシャットダウンしたい気持ちで一杯だった。
インプットされた曲を歌い終えると満足げな顔のネーヴェは愉快に全てを明かした。
「今度のポップンパーティは私と出演しまショウ」
奇妙な衣装は彼が作ったもので、データを破損し曲を書き換えたのも彼の仕業。全てが乗っ取られてしまうかと思ったアルトは寿命が縮んだ気分を味わった。
「次カラは私と相談して曲を作りマシょう。良いデスね?」
頭のアンテナをぴょこぴょこ弄くるネーヴェに再び説教する風に言う。すると今度は愛でるような眼差しで彼は笑った。
彼等の新曲披露を終えた所で、会場にいるチューンストリートのメンバーがそれぞれ準備をし始める。
「よーし、それじゃ次はポップン19の同窓会始めるよー!」
来月には第20回目のポップンパーティが開催される。それに伴い第19回目のパーティをもう一度振り返ろうというのが今夜の本来の目的だ。楽器や衣装の確認を済ませ、ステージの横でマイクを持ったミミとニャミが順々に名前を呼んでいく。
「あれ?そういえばロキの姿が見えないけど…」
「ホントだ、まだ来てないのかな?」
しおんとアリシアの間に一人分のスペースが空いているのを見て気付いた2人は会場を見回した。招待状はちゃんと出した筈だ。
キョロキョロする司会者に、ネーヴェは観客席から声を掛けた。
「あの小生意気な魔女ならもうすぐ来マスよ」
隣に座っていたアルトは首を傾げた。
「一緒に来なカッタんデスか?」
「ホホホ、彼女寝坊助ナンで置いて来マシタ!」
そこへ黒い塊がネーヴェの頭に猛スピードでぶつかって来た。テーブルに荒々しく着地すると一度だけ大きく地団駄を踏んでそれは声を張り上げた。
「貴様、起こせと言っただろうッ!」
東西南北を問わず様々なジャンルの楽曲が緩やかに奏でられ会場を彩り、楽しくダンスも踊って大いに盛り上がった。それから皆で食事や会話の時間がやってきた。
「ロキ〜」
やって来るのが遅かったヴェレーノは空腹感を黙らせる為ひたすらパスタを頬張っていた。
「今日は来てくれて有り難う!やっぱあのルーン語って不思議だね」
骨付き肉を持ったニャミとミミが挨拶に来た。
自分の歌の感想を言われてヴェレーノは誇らしげに胸を張りふふんと笑った。
「当たり前じゃ。あれは古代から受け継がれてきた神秘の呪いの一つ。他の奴とは比べものにならないほど凄かったであろう?」
口の周りに付いたパスタのソースを拭きながら語る。
今まで誰も触れたことの無い要素を取り込んだこの一風変わった歌には自信たっぷりだった。決して容易く真似など出来ぬ魔術の篭った特別な歌を…。
「でもさ」
そこで突然背後から意地悪そうな声がこう言った。
「皆にとっちゃ意味良く分かんねえし。いまちいピンと来なかったけどまあ取り敢えず凄いんだろ?」
その時、ヴェレーノは雑音よりも嫌な音を聞いた。口の中に残るソースの味も泥水のように一気に不味く感じ、全身がカッと熱くなる。
猫と兎はヴェレーノの不快感に気付かずしおんの所へ挨拶に行き、残された魔女はジロリと背後を見た。悪口を言った愚か者に呪いの言葉ても投げ付けてやろうかとじっと睨み付けた…が、彼女の後ろに立つ者はいなかった。高い誇りを持つ自分の歌を「良く分からん」と無礼な一言で纏められたことに強い怒りを感じた。
食事をする気も失せ沈黙を続ける中、一方で呑気に会話をするニャミ達の声が耳に入って来る。
「そういえばしおんの曲はユビートにも入ったってショルキーから聞いたよ。おめでとう!」
白葡萄のジュースを飲んでいた雪女のしおんは雪の様に白い頬を赤く染めて「有り難う」と小さく言った。
この様に人気の高い曲が別の音楽界へ採用されるのは珍しいことでは無い。第15回のパーティに初参加した鹿ノ子の楽曲はしおん以上に有名になり彼方此方で採用されていると聞く。
然しヴェレーノにとって俗世からのこういった評価など気にはならなかった。この時は。
同窓会を終えてから、ネーヴェが夜の散歩に付き合わなくなった。毎日あの日の変な服を着て何処かへ出掛けてしまうのだ。屋敷にいるのは早朝、それ以外は外出。何をしているのか気になったヴェレーノは別の日こっそり跡をつけることにした。
昼頃、ビルが建ち並ぶ都会にあるポップンテレビ局に辿り着きそこで彼がアルトと合流するのを目にした。
(アヤツ…?)
同窓会の会場に飛び込んだ際、見慣れない服を着ていた箱頭娘を思い出した。一体2人で何をしに来たのか知りたかったが、警備がいる建物に―然も人間社会に積極的に乗り出していない無名の魔女―ヴェレーノが中に入れる訳も無くあっさり追い返され、木々の全く無い環境が息苦しく渋々屋敷に戻ることにした。彼は自分の知らない所で何をしているのだろう。
「あ、星」
夕方近くネーヴェの屋敷に着くとブラウン管テレビを担いだ星のひとが大広間にいた。
「何じゃ。また電子が欲しいのか?」
時たま彼は故障した古いテレビを直しに此処へ訪れる。星のひとのテレビはヴェレーノの青い電子と相性が良いらしく、一度小さな雷を落とすだけで砂嵐がころっと直る程だ。
少し休んでからテレビに電子を送ると彼はお礼に番組を見せてあげると言った。
「ひょあああああっ」
可笑しな掛け声で箱型受像機が動き出した。適当にチャンネルを回して行くと聞き覚えのある歌が聞こえてきてそこで止めると、独特の帽子に白い服を着た人物が映っていた。
「ん?ネーヴェではないか。アヤツめ、何をしているかと思えば…」
そのすぐ隣に、似たような服を着た者がいる。あの箱頭娘だった。
2人は宙を舞い時折寄り添い、丸で舞踏会へ来た紳士淑女の様なロマンティック溢れる姿をしていた。
『愛が故に…貴女を』
聞き覚えのある歌の正体はネーヴェの作った楽曲の一つだった。何故彼の曲が今更テレビで披露されているのだろう。発表されたのは随分前の筈だ。それに何故あの箱頭娘が一緒にいるのだ。彼女は関係無い筈だ…。
だが能く能く聞くとそれは純粋なQuietではない、自分が知らない曲だった。本当は誰の歌なのか?
『その美しい声を…』
迫る2人の顔にヴェレーノはそわそわし始めた。何がどうなってああなったのか。他人にあんなに積極的にする彼など今まで見たことが無い。嘔吐が出る…。
次の言葉に、ヴェレーノは強く気圧される。
『我が手に!』
それは全身が震える恐怖だった。
歌にはそれぞれ意味があり力がある。情熱的で、悲愴を奏でる時だってある。熱く大切な事を訴える為や、心の叫びを伝える為。
ではネーヴェは、何故自分の歌以外にあの言葉を入れたのか。誰の為に向けた言葉なのか…。
「一緒にいるのはだ〜れだ?」
突如背後から聞こえたのはあの夜自分の歌にぞんざいな口を利いた忌ま忌ましい声と同じものだった。
「誰じゃ!」
振り返るも矢張り人はいない。テレビを支える星のひとはいきなり声を上げたヴェレーノに驚いて肩をビクリと震わせた。
「歌ってのは想いが篭ってるよなあ。あの2人の歌は最高だよなあ」
(…2人の、曲)
―あの2人のための曲。
呆然としている内に番組は終わってしまった。
あの腹立たしい声の主を突き止められぬまま幾日も経った。矢張りネーヴェは屋敷にいる時間が少ない。お陰で構ってもらう暇も無く、彼の部屋を覗いても作業机に向かって人形作りをする姿は段々見られなくなった。話をしようにも朝早く出てしまうのでどうしても起きられない。仕方なくこの間行った街に出掛け、ネーヴェが建物の中から出て来るのを待つことにした。
色々な物を売る賑やかな商店街を暇潰しに回っていると、大きな窓硝子を貼った店の中に星のひとが持っているのとは少し違う受像機が映す映像に屯する人々がいた。上手く隙間に入り込んで見てみると、インタビューを受けているアルトが画面の中にいた。
「2人は今後も一緒に活動を続ける予定ですか?」
マイクを向けるマスコミにアルトは愛らしい笑顔で頷いた。
「ハイ、機会がアレバ是非!」
するとカメラは隣の人物を枠の中に映した。
(まただ…)
また2人は一緒にいた。繰り返すカメラのフラッシュにうんざりするネーヴェは口を開かなかった。
周囲の人々の会話と画面に流れる文字を見て漸くヴェレーノは理解する。彼等は新しく音楽活動を始めたのだ。2人で。
「あの2人は人気出るぜ。お前なんかよりもっと有名になるさ」
赤子の泣き声の様に耳障りな周囲の声に混ざって今度は耳元であの声がした。目の前にはあの2人、耳元ではあの嫌な声。見たくも聞きたくもないものばかりの空間にヴェレーノは苛々してきた。
―こんな世界など、知らぬ。
あれからネーヴェとアルトは様々な番組に出演、特別企画などで新曲を作りその新感覚な雰囲気と2人の組み合わせが反響を呼びあちこちに引っ張り凧になった。これを機にイベントや商品開発など盛んに行われ驚異的な人気を誇った。その結果、ネーヴェとアルトは揃って仕事に招かれるのが通例となった。
(退屈だのう……)
ひとり残されたヴェレーノは毎日屋敷でボーッと過ごすようになった。ソファの上で寝転んだまま何をする事も無く時間だけが過ぎてゆき、夜の散歩も回数が減っていた。
変わった事と言えば星のひとがよく訪れるようになったくらい、彼は元気の無くしたヴェレーノが心配で様子を見に来るのだ。だが会話をする日は無く、ただお互いそこに居るだけで静寂の日々は続いた。