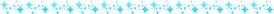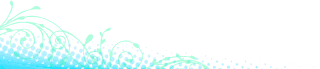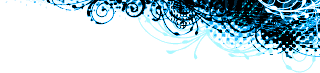
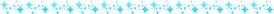
緑色の瞳は邪悪な者の証だとか、紅い化粧は野蛮だなどと囁かれていた。時々、街にやって来ては屋根の上を飛び回り、夜中には不気味な歌を歌い出し住人達を狂わせ、最近では街の明かりを守る機械人形と一緒に居るのを目撃されている。人々は、あの少女がこの街で最も大切にしている明かりを奪うのではないかと日々怯え、追い払う良い方法がないか試行錯誤を重ねていた。
だが勿論その少女にそんな気は毛頭なかった。少女は遊んでいるだけなのだ。屋根の上を飛ぶのは高い所が好きなだけで、自分の呪縛から解放感を得たいが為に大声で歌っている。頭が電球の機械人形と一緒にいるのは、唯一の友達だからだった…。
フードの付いた白い服を着ているその少女は魔女族の女王となる子で、闇の世界の頂点に立つ者として生まれながら不老不死を約束されていた。幼きながらも魔力は絶大で、一族の誰もが敬いそして恐れた。故に家族以外親しい者など居ないのは言うまでもない無く、女王の名を背負ったお陰で友人も出来ずに育った。
そこから生まれた虚無感や孤独感、普段抑え込んでいる感情を放って思うが儘に歌を歌っていた。そこへあの機械人形がやって来たのだ。
「……………」
初めて機械の巨人を見た少女は矢張り無表情の儘だった。カタリカタリと巨人の歯車が廻る音に耳を傾け、白く美しく光る電球をジッと観察した。巨人は長い腕を伸ばしてガラクタで作られた固い手を差し出し、只管電球を煌々と輝かせた。
『…歌っテ…』
声は無い。少女の心に直接語りかけているようだった。
『…モっと、歌ッて…』
優しく温かな光を降り注ぎ、少女を自分の手に乗せて再び言った。
機械人形はとても大きかった。少女の父親よりも高く、下を見ると屋根で踊る時より興奮した。巨人の胴体は熱したガラスを伸ばした細長い球体で、中には月と太陽の歯車が星を散らし乍ら噛み合って廻り、昼でも夜でもない真新しい空を作っている。間近で見ている少女は興味津々で、透き通ったガラスをつんつん突いたり星が生まれる音に耳を欹ててすっかり夢中になった。
そして歌った。一族の歌、呪いの歌、即興の歌。これまでで1番楽しい時間を過ごした。私の歌を欲するやつ、私の声を愛するやつ。巨人の手の上で飛び跳ね、肩に乗った。初めて笑った。巨人は喜ぶ様に軽快に歯車を廻した。
頭の大きな電球も突いてみる。キン、と透き通った音を出して光の欠片を零した。欠片は服に落ちて消えたり風に乗って旅立った。他の者には真似出来ない不思議な仕組み。だがそれでも魔女は歌以外言葉を発することを決してしなかった。
魔女もあの絡繰り人形の様に何か面白い事が出来るようになりたかった。闇の魔法で目映い光は作れない。時を告げる太陽も月も、身を寄せて踊らせるのは無理だった。森の中で考えを廻らせ、思うように浮かばず悩んでいると雨が降り出してきた。フードを被って木陰へ駆け込み身を丸める。こんな時、誰か一緒に居てくれたらちょっと心強い。
雨脚が激しくなってきて空が唸り出した。雷が来る…。
―嗚呼どうしよう、この儘では街の灯が奪われてしまう。
―相手は子供だよ?
―だから心配なんだ。子供は何でも欲しがる我が儘な生き物だ。
―それにあの子は普通じゃない。毎晩叫び廻る様に歌う歌だって身の毛が弥立つったらありゃしない。若しかしたら悪魔なんじゃ…。
街の大人達は心底焦っていた。街全体の灯の調子が悪くなっていたからだ。
―キリコだって自分から街の外へ出てあの子供に会いに行くんだよ?
―はっ、絡繰り人形の癖に悪魔に魅了されたってか?
人々の気は治まらなかった。何としても生活の明かりを取り戻さなければ、この街は暗闇に覆われた穢らわしい世界に成り果ててしまう。
空が晴れた。少女の目は少し腫れ、目許の化粧が落ちて顔を汚している。少女は激しい雷鳴と光を特に嫌っており、落ちる予兆からもう体が震え出し泣きじゃくってしまう。大きな音が鳴る度に小さな心臓が飛び跳ね、只管フードを深く被って耳を塞ごうと必死になる。
雨で湿った木の根本から離れ水溜まりを避けながら帰路に向かう中、嵐に倒された草花を見て少女は止まった。それから濡れた頬を拭って顔を綻ばせ、自分の素敵な閃きに喜び空中で踊った。そうだ、友が居ないのなら造れば良いんだ。
梟が鳴く夜更け。民家の扉は厳重に鎖され部屋の窓帷も締め切られている。馬車の轍が残る道に等間隔で立っている街灯はチカチカと点滅を繰り返し、蝋燭より儚いその光を嘲笑うかの様に夜風が吹いた。屋根を伝う少女の足音は無い。
キリコは街を出た。遠くの方であの歌声が聞こえてくるのだ。
『綺麗だネ…素敵ナ声だね』
得意げに歌う少女はキリコがやって来ると片足を軸に廻り、魔法を掛けて動けるようにした草花と踊り出した。
彼女の素敵な閃き、それは自分の魔力で新たな命を吹き込み不思議な友を作る事だった。ヘンテコな形をした植物に紫色の大きなキノコ、これらは魔女のお供、兼森の住民として誕生した。
巨人にそれをお披露目すると髪をパタパタ動かして燥ぎ回り、ぴょんとキリコの肩に飛び乗った。そして彼に一輪の花を渡した。
お前も私の友の一人だ、そう込めて花を置くと蔓が伸びてキリコの右肩から腕まで巻き付き強く根付いた。柘榴石の様に美しい花が自分の身体の一部となった人形は電球の光を強くして喜んだ。
『コの花も、綺麗ダね』
次の日。キリコの肩から生えている植物を見て住人達は驚きを隠せなかった。鉄の塊の人形に花が咲くなど前代未聞である。
―何であんな姿に…。
―あの子供だ。呪いを掛けたんだ!
―厭だよ気味の悪い!それじゃアタシらこれからどうするってんだい。
暗くもないのに街灯は太陽の様に目映い光を放って人々の目をチカチカさせた。愈々キリコが悪魔によって壊された、そうに違いない。住人達はこの異常現象を例の少女が原因だと断定した。否定を唱える者など誰も居ない。
―もう我慢ならん。彼奴を取っ捕まえてやる。
―でも下手に手を出したら…。
―纏めてかかれば大丈夫だろうよ。大暴れ出来るほど強い悪魔とは思えない。
夕方。巨人の姿が気になった少女は夜が来る前に街へ来た。初めて誰かにプレゼントを贈り、然もあんなに喜んでくれたから余計に彼の事が気になって仕方が無かったのだ。ちょっぴりドキドキしながら街に入ると、突然頭上から何かが振って来た。
「…ッ!」
それは鉄製の網だった。小さな体は鎖の重みで難無く倒れ地面に押さえつけられた。脱出しようと藻掻く少女から鉄の網は体力を奪い、建物の影から迫り来る大人達に捕まえる時間を与えた。
何が起きているのか分からない少女は睨んでくる大人の目を戸惑い乍ら見回した。どの顔も憤りの色をして冷たい視線を送って来た。
―赦さないよ、この悪魔!
―二度と此処に来れないよう崖の下に落としてやる!
怒り狂った大人達の大きな手が競り合う様に少女に迫って来た。頭を押さえ付けられ、腕は捻り上げられ、到頭網に包まれてしまった。彼等の怒号と吐き出される侮辱の言葉に遂に腹を立てた少女は子供とは思えぬ恐ろしい形相で、鼓膜を破く程の叫び声を上げた。
悪足掻きだ、耳を塞いで大人達は構いもしなかった。街の裏にある崖に捨てればこんなもの、軽い軽い。
然し、崖まで歩く道が突然揺れ、少女の叫び声に共鳴する様に地響きがして街全体が大きく震え出すと流石に無視は出来なくなった。立つ事さえ許されない強い地震に大人達は驚愕し、広場で遊んでいた子供は転んで泣いた。激しさを増す揺れは建物を崩し大地に亀裂を生み街灯の硝子を割った。
予期せぬ地震に魔女を捕らえた網を手放してしまった彼等は舌打ちして地面に手を着いた。
―い、一体どうなってるんだ!?
耳障りな金切り声が地震を呼び起こしている様に思えた。うっかり落とした魔女に目をやると激しく肩を上下に動かして息切れしていた。男は叫び疲れた魔女に再び手を伸ばしたが、今度は大きなガラクタの手が振り下ろされて遮られた。
―キリコ!!
絡繰り人形は少女を守る様に男の前に壁を作った。
『傷付けたら、ダメ』
電球の明かりを何度も点滅させて男に警告し、少女から網を取り払うと優しく抱き上げた。怒りで興奮し切っている少女に人形は悲しげな光を放った。
『争いハ、嫌い…』
途切れ途切れ光り乍ら伝わって来る切々たる声に少女はやっとキリコに意識を向けた。友の証として贈った花が凛として人形の肩に咲いているのを、はっきりと小さな眼に映した少女は今度こそ正気づいた。
一方、魔女を庇ったキリコに不信感を抱いた街の住人は敵意を露に憤慨した。
―おい、そいつをこっちへ寄越せ!悪魔を生かしておく訳にはいかないんだ!!
男が脚を蹴った。然しキリコは決して魔女を放そうとしなかった。
女が石を投げた。硝子の胴に傷が出来るも懸命に少女を守り続ける。
そんな事が繰り返される内に、太陽と月の歯車の音に乱れが表れ始めキリコの電球の光が徐々に小さくなっていった。大きな背の盾に守られている少女はそれを見て慌てて飛んだ。
殺意が篭った目の住人達の前に下りて両腕を精一杯広げた。その姿はキリコを守っている様に見えるが、大人達は気付こうともせず無防備な彼女に襲い掛かった。彼等は口々に「疫病神」と喚き立てる。少女は目を見開いて一言だけ叫んだ。
目が覚めたのは深夜である。酷い頭痛に苛まれ、起き上がれば眩暈がしてまた倒れてしまう。こんなにも具合が悪いのは魔法で自分と巨人を街から森の方へ転送した事による。2人分、然もキリコのような大きなものを転送させるにはかなりの負担が掛かってしまうのだ。揚げ句、彼女の小さな身体では無茶があった。
ズキズキ痛む頭に手を当てて同じ様に倒れているキリコの許へよろよろと歩み寄った。明かりは…。
『大、丈夫…?』
ひ弱な光が覗き込む少女の顔を照らし、夜の世界に頼りない明かりを燈した。肩の花は閉ざしてぐったりしている。少女は心配そうに頭の電球を撫で乍ら柘榴石の花を見つめた。
その花にはお呪いを掛けてあった。彼の灯がより強く、奇麗に輝くように…。
「…ご、……」
自分が善かれと思ってした事が裏目に出て彼を傷付ける結果になってしまった。
「ご…め、…」
何がいけなかったのか、何をすれば良かったのか、何故彼が壊されるような目に遭わなければならなかったのか。
「ごめん…な」
歌や叫び以外に初めて発した言葉は、悲しくて辛い気持ちで一杯だった。
皹の入った胴に手を当てて穴の深さを知る。尖った硝子で指から血が出るも撫で続け、溢れ出す泪でその溝を満たした。
『アリガトウ…もう森へオ帰り』
魔女の泪が硝子の様に固まって―多少の凹凸はあるが―キリコの体を修復し、彼は優しい魔女に感謝の言葉を贈る。…そして森を差す。
『平気ダよ、独リでも。ずっと待ってるかラ』
少女は人形の言葉に従った。途中、何度も彼を振り返り明かりが消えていないか確かめ森へ全速力で走って行った。
嗚呼、自分が傍に居ると彼は不幸になる。もう二度と彼の光を見る事は許されないだろう。小さな声でごめんと繰り返した。
翌日から街の住人の数が減り始めた。みな別の場所に移動を決意したのだ。ある者は都へ、ある者は大陸まで越え、4日目の朝には誰もいなくなってしまった。
閑散とした街にひとり残された巨大な絡繰り人形は魔女に直してもらった体でカタカタと歯車を廻し、夜には誰も居ない広場に明かりを燈す毎日を繰り返した。いつか此処へ訪れる旅人を、そして嘗ての友が会いに来るのを、ずっと待っているのだ。