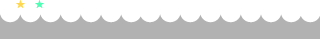「お先っス」
「おつかれさん」
コンビニのバイトが終わり、挨拶して外に出る。時刻は夜の10時で、東京でも片田舎に入るこの地では少しの星が見えていた。
「センパイ」
空を見上げていた笠松は、呼ばれて少し驚きながら振り向く。すると案の定、そこには予想していなかった姿があった。
ガードレールに腰掛け、車のヘッドライトの照らされる様子は様になっていて、なるほどモデルだなと納得してしまう。笑って近づく黄瀬に、笠松は呆れた表情を向けた。
「今日も仕事だったんだろ?疲れてんなら家で休めよ」
「センパイの家の方が休めるっスもん」
「んなわけあるか。お前、明日学校だろ」
都心から時間がかかる笠松の家から学校に行くには、朝6時過ぎには家を出なければならない。今から笠松の家に来て寝るよりは家に帰る方が、絶対に楽なはずなのに。
それに。
「…疲れてんのは本当だろ」
歩いていた足を止め、手を延ばして黄瀬の頬を包む。陽の光がなくても顔色の悪さはわかった。
それだけじゃない、最近見せるようになった何かに憂いているような影も。
「……適わないっスね。だから、」
「え?」
幾ら人通りの少ない道に入っていたとはいえ、ふわり、と公道で抱き寄せられる。あまりに自然で優しい仕草に、笠松はつい抵抗を忘れた。
耳元で「だから会いたくなるんスよ」と囁かれ、体の熱が一気に上がる。ついいつも通り離せ、と言いかけて、でも続けて囁かれた「黙って」という声の低さと強さに言葉を無くした。
「黄瀬?」
どうした、と問いかけて、見上げた黄瀬の視線が一点に固定されている事に気付き、笠松もそちらに首を向ける。するとそこには一人でこちらを見ている女がいた。
「アンタ、俺より先にコンビニで待っててずっと後をつけてきてたけど、この人になんか用?それとも俺?」
絶対に笠松には向けられない、絶対零度の声音で聞かれた女は、ポケットに手を突っ込んで何かブツブツと言っている。
立つ場所が街灯の影になっているのも相まって、どこか尋常ではない様子に笠松は息を飲んだ。そしてまさか、と口からこぼれる。
「あの手紙、お前か?それに」
「手紙?」
途中で訝しげな黄瀬の声にハッとした。どういう事、と問われて笠松はしまったとバツが悪い表情を浮かべる。
「センパイ、手紙って何」
「それはだな、つーか今はそれどころじゃ」
ねぇだろ、までは言えなかった。遮ったのは、それまで無言だった女の声だ。
「離れてよ。黄瀬くんから離れてよ!」
始めは呟くような声だったのが、だんだん甲高い声になる。
「アンタなんか男のくせに綺麗でもなんでもないくせに!なに黄瀬くんと一緒にいるのよ!見てたらべたべたベタベタ…うざいのよ!しつこいのよ!迷惑してんのよ!!ふざけんじゃないわよ!!」
言いながら、スカートのポケットから出した手で掴んでいる物に、二人はグッと警戒した。その手には小さめのカッターナイフ。
親指でキリキリと刃の部分を出し、腕を上げて狙うのは笠松の顔。黄瀬は腕に抱いたままだった笠松を己の後ろに下げると、オイ!と抗議する体を強引に押さえる。
「どけ黄瀬!」
「バカな事言っちゃダメっスよ。おとなしくしてて」
「おとなしくって、出来るか!」
狙われているのは自分なのだから、巻き込むわけにはいかないだろ、と主張する笠松に黄瀬は心底からのため息を吐き出す。
どうしてこうも、この人は守るという事を許してくれないのか。
黄瀬だって好きな人を守れる男でありたいのに。自分が自分がって、必要以上に抱えて頑張ろうとするこの人だから守りたいと思うのに。
黄瀬の価値観に多大な影響を与えたわりには自分の評価が低い笠松だから、きっとこんな時でも自分より黄瀬に怪我をさせるわけにはいかないとか思っているんだろう。きっとその想像は正しいとわかるからこそ、笠松を矢面に立たせるわけにはいかなかった。
「黄瀬!!」
「怒鳴ったってダメっス。ここは譲れない」
「―――」
見つめる視線の強さに、笠松は息を飲む。黙らせた黄瀬はすぐに前を向き直ると、ますます表情を醜悪なものに変えて罵る女をにらみつけた。
「だから、男と抱き合う黄瀬くんなんか見たくないって言ってるでしょお…?だって言われたもの、その人が悪いんだって。黄瀬くんを自分の良い様にして、利用するような悪い人って言ってたもの。だから離れるようにしてあげたのに、なんで黄瀬くんが怒るのよ!!」
黄瀬と笠松からすれば自分勝手過ぎる内容を、当然のように語る女にこっちこそうんざりしたが、笠松は一つ引っかかっていた。
おそらく黄瀬の熱狂的なファンであるこの女に、笠松が悪いから排除すればいいと吹き込んだのは、黒子の言っていた『彼女達』ではないのか?
聞いてみようとしたが、その前に奇声を上げた女がカッターナイフを突くようにして、こちらへ向かってきていた。
「黄瀬!!」
思わずまた前に出ようとした笠松を制し、黄瀬は自分から女に向かって走り出す。まさかそう来ると思わなかったのか、女が動揺して腕を引いた隙に黄瀬はカッターを持った手首を掴み、女の足を蹴り上げるような形で掬って地面に転がした。
その際にカッターを取り上げておくのも忘れない。
ぎゃっ!と正面からアスファルトに転んだ女は、すぐには立てないようだった。一瞬の事に思わず固まっていた笠松は、その横に立って冷たく女を見下ろしている黄瀬の横に駆け寄る。
「センパイ、大丈夫?」
「バッ…!大丈夫って、お前のほうだろうが!怪我は…!」
「ないよ。見ての通り」
ほら、と両手のひらを見せる黄瀬に、笠松はホッと安堵の息を吐く。だがすぐに沸いた怒りに黄色い頭に拳を落とした。
「あたっ!もうなんスかー、………」
痛みに抗議しかけた黄瀬は、見上げる笠松の表情を見て口を閉ざす。きゅっと唇を結び、眉を寄せて。
怒りをたたえていたはずの瞳には、それよりも怖かったと、心配したのだという感情が映っていた。
「……センパイ」
「………」
自分が前に出た事は謝らないが、心配をかけたのはごめんね、と告げると笠松は瞳を緩ませたものの、すぐには許すつもりになれないのか引き寄せる腕に抗う。
そんな些細な抵抗にそれくらい想われているのだと実感して満足する黄瀬は、笠松には申し訳ないなと思いつつも、それでも先ほどの己の行動に後悔は微塵も無かった。
その時、
「―――離れて、離れてよぉっ!!」
「っ…!!」
二人が見詰め合っていると、突然女が叫びながら立ち上がり、笠松を突き飛ばそうとする。
だが、黄瀬が素早く動き――その手に握られた、刃をしまったカッターナイフを女の眼前に突きつけていた。
「…あ……」
けれど動きを止めてまた座り込んだ女が焦点を合わせているのは、カッターではなく黄瀬が自分を見据える瞳の方だった。
この人にこれ以上手を出すなら、殺す―――と言わんばかりの温度の無い色に、女はガクガクと震える体を止められない。
目の前にカッターを放られても、それを拾う気力ももはや女には無かった。
「誰かは知らないけど、アンタに色々余計な事吹き込んだヤツにも伝えてくれる?」
「―――」
立ち上がって高い位置から己を見下ろす黄瀬を、女はノロノロと見上げる。
「俺がこの人といるのは俺が望んでいるからで、他人のアンタらには一切関係ない。次にまたこの人に危害を加えようとしたなら――本気で潰す」
「――!!」
有無を言わさない口調と迫力に、女はガクガクと必死で首を縦に振ることしか出来なかった。
「さて、センパイ。手紙って何」
「う…」
やっぱそう来るよな…。
部屋に帰ってすぐ、笠松はソファに半ば押し倒される形で尋問されて気まずげに顔を逸らした。すると強い力で頬を掴まれ、強引に視線を合わせられる。
声は怒っているくせにその瞳には隠し事しないで、と懇願する色に溢れていた。笠松はそれ以上黙っていることが出来ず、手紙のことやそれ以外にもあった嫌がらせなど、洗いざらい吐かされることになり。
途中からその手段がだんだん妖しいものになってきて、最低限の事だけでいいかと思っていたのに、慣れた手つきで翻弄されて抵抗は全部無駄となった。
「…それで全部?」
「ぜ、んぶ…っ…アッ…き、せ…っ!」
「ふーん」
「…んっ、あ…なん、で…いった、のに…っ」
「まだだよ。じゃあ、そんな嫌がらせされてたのに、なんで俺に言わなかったの?」
それを言うまで寝かせてあげないから、と宣言されて笠松は青ざめる。普段からしつこいのに、これ以上されたら…!
「無理だって言うなら、早く言って幸さん」
「待っ…!!」
待て、という訴えを無視して攻めて来る黄瀬に笠松は半泣きになりながら、息も絶え絶えに話していく。
だが聞いておきながら、笠松が何を考えて言わなかったのかなんて黄瀬はすでに想像がついていた。
心配かけたくなかった、迷惑かけたくなかった、自分が我慢すればいいと思ってた。
言葉は違っても、おおよそ間違っていない内容に黄瀬はこっそりとため息をこぼす。どうしたらわかってくれるのかなー…と思いながら、だがこの時黄瀬の頭を占めていたのは、言わなかったお仕置きと称してまだまだイケるな、という薄悪い考えだった。
その裏側には頼られなくて悔しい、という八つ当たりめいた思考も混ざっているのだが、黄瀬は都合よく蓋をする。
結局、夜半を過ぎて明け方まで離されず、二人とも学校をサボる羽目になって笠松が頭を抱えることになるのは、昼を過ぎて起きてからの話だった。
- 8 -