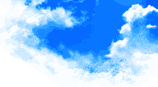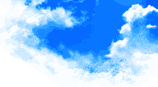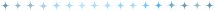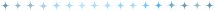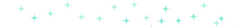嫌悪と恋慕の間に紙一重はあるか
(兵長が壊れています)
前々から、優しい人なんだなぁとは思っていた。
部下思いで知られる人徳者だ。訓練後の慰労の言葉や、食堂の入口で鉢合わせた際のレディファーストなど、こういう細やかな優しさも人望が厚い理由の一つなのだろう、と。
直接訓練を受ける班員になったとき、心配性な方なんだなぁと思った。
手に刺さった小さな刺を同期に見せていたら、腕を引きずられて医務室に強制連行されたり、立体起動装置の訓練中少しバランスを崩して私たちのグループにぶつかりそうになった後輩たちがこっぴどく怒られていた(罵倒されていた?)。
人類最強とも言われるほどの戦歴者だと、何があってもいいようにこれくらい色んなことに日々神経を張り巡らしていないといけないんだろうと、尊敬の念を感じた。
通称「リヴァイ班」に任命されてからは、もしかして兵長は私のことを好いているんじゃないかと周りから囁かれた。
壁外調査の際に私が担当しようとする巨人をことごとく兵長が削いでしまったり、食事に私の好物が出ると自分のものだけでなく部下のそれも取り上げ私に分け与えようとした。
いくら何でもそんな畏れ多いことは有り得ないし、これは好意というには遠回り過ぎ、またやり過ぎなのは間違いがなく、人並み外れた才能の持ち主は常人とは異なった少し…変はところがあるんだろうと自分を納得させた。(例えばハンジさんがいい例だ)
そして、謎の大抜擢で兵長補佐に任命されてから、私は身をもって理解した。
この人は、おかしいんだ、と。
「おい、name、てめえ、昨日一人で駐屯兵団支部へ書類を届けに行ったらしいな。」
「ええ、団長が急ぎだと仰っていたのでお預かりしました。」
「ふざけるな、お前は俺の補佐だろう。それに一人であんなむさ苦しいところに行って集団強姦にでも遭ったらどうする。そんなに犯されたいなら俺が抱」
「それ以上喋るとセクハラで即訴えます、次に会うのは審議所ですよ兵長。それに昨日は午後お休みを頂いておりましたので兵長には何もご迷惑はおかけしていないかと。」
私の身の心配をしながら、何故か腰に回されてきた腕を思い切り叩き落とすと、兵長はその手を憎々しげに摩りながら避難めいた視線を向けてくる。
「チッ。何故非番にエルヴィンの野郎のパシリなんぞやっている。大体午後に突然非番が入るのがおかしいだろうが。」
私が何故そんな視線を向けられなければならないのか。理解に苦しむがそもそもこの人を理解しようとすること自体が不可能なことを私はもう十分に知っている。
「お言葉ですが不要だという私に無理に非番を取らせたのはあなたです、兵長。たかが少し咳き込んだくらいで。お忘れのようなので念のためお伝えしておきますが。」
昨日、いつものように昼前に指定されている紅茶を淹れてこの執務室に持ってきた時、少し喉が引きつってわずかに咳き込んだ。それを聞くやいなや「風邪か」と、「どこか苦しいか」と、「今すぐ体を休めろ」と、聞く耳を持たずに無理やり休暇を取らされた私が被害者だ。
しかも私の個室に力ずくで引きずられたかと思いきや、寒いといけないからなどと言い出し一緒にベッドに潜り込もうとしたこの変…失礼、兵長の向脛を思い切り蹴り飛ばしたため、心なしか今日は兵長が脚を引きずっているように見えたが目の錯覚ということにしておく。そもそも今は夏だ、寒いわけがない。むしろ暑い。暑苦しい。
「そうだ、風邪はもういいのか。そんな遠っ走りをして悪化させたらどうする。」
そもそも風邪をひいていない。忘れたふりをしていたとしか思えない兵長にもはやいちいち反論するのも馬鹿らしく、私は無反応を決め込み、当人が手を動かさないため山積みになった手元の資料の仕分けに専念する。
度々感じることだが、私がここに居ない方が兵長の書類処理速度は格段に上がると思う。良く分からないが、この人は私にセクハラまがいの発言や行動や行き過ぎた心配をしていないと過ごせないらしい。
一度、自分が邪魔をしているような気がして団長に異動の直談判に行ったことがある。しかし、それは「そんなことはない、リヴァイの補佐は君が適任だ。」という穏やかな言葉に丸め込まれて終わってしまった。
「ああ、風邪は遷すと治るというからな、俺がその風邪をもらってやる。心配するな、俺はそんなにヤワじゃねえ、発症する前に滅菌できる。」
滅菌って。
こちらが真面目なことを考えているのに、鼻で笑いかけたところで顎を引き寄せられ、不意を突かれて目を見開いた目の前に兵長が居た。
「ちょ、なに、」
貞操の危機を感じ、不覚にもたじろいで後ずりながらデスクについた後ろ手が、デスク上のペーパーナイフに重なり鋭い熱さが走った。
「いっ…!」
「っ、おい、」
さすが人類最強と言おうか、気付いたときには私の指は兵長に絡め取られ、あろうことか兵長の舌が、舌がぷくりと丸く血が浮き出る指をちろりと、舐めていた。舐めていたのだ。(重要なので2回言いました)
「―っ!!!!」
かっと頭に血が昇った私に、兵長は上目遣いで見せつけるようにねっとりと更に舌を這わせる。
ぞわり、と、背中を何かが走った。拒絶からくる鳥肌だ、それ以外に有り得ない。でもぱくぱくと口を動かしても、言葉が出てこない。
私は反射的に、右膝を思い切り上に蹴り上げた。
それは、つまり、兵長の、何というか、申し訳ない箇所に見事命中し、そしていくら人類最強といえど身体の構造上悶絶を免れないようだった。
「―っ、い、医務室に行ってきます!」
その場に崩折れる兵長を思いやる余裕も反省の念もなく、執務室を飛び出した。顔と、そして切った指先がじんじん熱い。
怪我のせいだ。深めに切ってしまったせいだ。
私は、医務室の扉をこれでもかというくらい思い切り跳ね開けた。
体の熱が、その勢いと一緒に出ていってしまえばいいのに、と。
数分後、少し前屈みになりながら医務室に姿を現した兵長は、私に輸血が必要か、雑菌が傷に入っていないか検査はしたかなどと意味の分からないことをいつものあの無表情で並べ立て、医療兵を困惑させ私を憔悴させるのだった。
嫌悪と恋慕の間に紙一重はあるか
(あの指の疼きは、痛みのせい。)
戻る