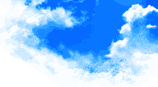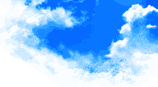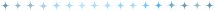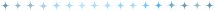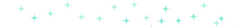おかえり。ただいま。
「…どうした。」
重い瞼をぼんやり開くと、ベッドに腰掛けて背中を向けていたリヴァイが振り向いて言った。
何がだろう、と思いながら視線を緩慢に落とすと、横たわった自分の右手が、リヴァイが裸の上半身にそのまま羽織ったシャツの裾を、きゅっと握っているのに気付いた。それで、ああ、と思い出す。
「…夢を、見てたんだ…。」
さっきまで、自分がそこにいたかのように感じていたその世界は、思い出そうとするともうぼんやりとした膜の向こうのように曖昧になる。
私は左手で、むき出しの肩を薄い掛け布団の中に埋めた。
「…そうか。」
リヴァイの指が、頬にかかった髪を優しく払って、そっと頬を撫でていく。
どんな、とは聞かない。聞かなくてもリヴァイはたぶん分かっている。
「甘ったるい、信じられないくらい、平和な夢。」
朝起きてから寝るまで、生死の危機なんてものが一切ない世界。
何となく生きていれば時が過ぎる、緩慢な空気。
同じような毎日。
起きて、会社に行って、飲みに行き、家に帰る。
目眩がするくらいの平和と幸せを、限られた世界で享受する日々。
「…それが、突然なくなる夢。」
その呟きに、リヴァイがすっと眼を細める。
「一人きりになる夢。」
そして、リヴァイの手はゆっくりゆっくり、宥めるように、髪を梳くように何度も頭を撫でる。
車の急ブレーキの音、視界を奪うヘッドライト、動かない脚、耳に響く心臓音、リヴァイが私の名前を叫ぶ声。
「name、」
頭の中の声と、少しどこか違うリヴァイの声が私を呼ぶ。
「残念ながら、ここは巨人どもが蔓延るクソみてえな最低な世界だ。おかえり。」
目覚めの悪い言葉を吐くリヴァイをぼんやり見て、寝転んだまま室内に視線をゆっくり回す。
さっきまで見えていたテレビも、キッチンも、エアコンも、ヒールの靴等もそこにはなくて、壁に掛けられたジャケットにくすんだ自由の翼。
「あは、…ただいま。」
吹き出して答える。
クソみたいな最低で、そして最高な世界。リヴァイがいる世界。リヴァイといる世界。
おかえり。ただいま。
そうだ、ここが、今私の生きている場所。
戻る