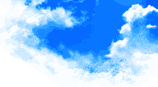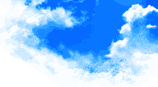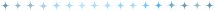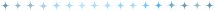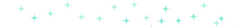ハッピーバースデーを聞かせて。
窓からの月明かりだけの暗い個室で、私はベッドに身を起こして、いつもは枕元に置いてある時計を手にそれを見ていた。
5、…4、…3、…2…
長針と短針がてっぺんに重なったその上を、秒針が通過していった。
「…。」
しばらくそのままじっと時計を見ていると、物音一つしなかったドアの向こうから静かなブーツの音して、私の部屋の前で止まった。
ドンドンドン、という深夜にしては荒っぽいノックが、静寂になれた耳に大きく響く。
「はー、」
「入るぞ。」
はーい、と言い切る前に、そのドアは不躾に開かれて、廊下のかがり火の柔らかい灯りが筋になって差し込んだ。
良いって言ってないし、そもそもこのはーいはノックに対する返事であって、入室の許可じゃないし。いや、そもそもそのはーいすら言い切れなかったし。
「鍵もかけてねえのかてめえは。無用心だな。」
「…あんたみたいに異性の私室にこんな強制的に乱入してくる奴がいるとは思ってないからね。」
そうかよ、と、その不法侵入者であるリヴァイは、全く気にもしていない様子で室内に一つだけ置かれたテーブルの上に、何やら瓶を叩きつけるように乱暴に置いた。
そして勝手に卓上のランプに火を点け、椅子にガタンと腰掛けた。
「ちょ、自分の部屋か。」
いつも鍵をかけていないのは本当だけど、今夜の乱入者の来訪は、予感してはいた。
「飲むぞ。グラスは。」
見れば、ランプに照らされた瓶には茜色の液体が綺麗に揺らめいていた。
「…どう見ても部屋着でベッドに入っている私は就寝直前の乙女だと思うんだけどね?」
「ごちゃごちゃうるせえな。こっちは今まで書類に埋もれていて酒でも飲まなきゃやってらんねえんだよ。」
握っていた時計を枕元に戻し、ため息を吐いてベッドから出た。抗っても無駄だ。
確かにリヴァイは兵服のままで、目元の隈がランプの影でより濃く見えた。まあ、それはいつもだが。
壁に備え付けた小さな食器棚から、グラスを二つ取り出した。
そしてリヴァイの向かい側に座ると、そのグラスに波波と茜色の液体が注がれた。酒は好きだ。悪くない。
つまみも何もないが、私もリヴァイもそれを特に必要としないから、気にしない。
グラスを少し掲げて合わせようとすると、リヴァイは少しだけ自分のそれを当て、ぐいっと一気に飲み干した。そして、また手酌で注ぎなおす。
私も、グラスを傾ける。
喉に流し込んだその酒はおいしくて、食道が熱くなるのが分かった。
2杯目もまるで水のように流し込むリヴァイを見ながら、ふと思いを馳せる。
3年前、訓練終わりに突然、リヴァイが「飲みに行くぞ。」と言ってきた。
二人だった。しかもおごってくれた。
頭の中が「?」でいっぱいだったけど、まあおごってくれるなら飲まない手はないか、と散々飲んでやった。
「…昨日、誕生日だったからってこと?」
帰り道、顔色の変わらないリヴァイの隣をフラフラと歩きながら問いかけた。
その前夜、つまり誕生日当日、同期が誕生日をささやかに祝ってくれて、その日その話をしているところにリヴァイも居た。
「…ああ、そうだったか。」
「…何、それ。」
何だかおかしくて、私は一人で笑った。
2年前、ある日何の前触れもなくリヴァイが無表情で言ってきた。
「お前、何か欲しいもんはねえのか。」
「は、何突然。」
「うるせえ。何かないのか。」
「…世界平和?」
「そういうんじゃねえよ。」
「えー?うーん……あ、そう言えばずっと使ってたペンが壊れて困ってたんだよねー。買いに行く暇もないし。」
そうか、とだけ言ってリヴァイは行ってしまったので、そんな意味の分からない会話はすぐに忘れた。
数日後の誕生日、前々から行きたいと話していた人気店を奇跡的にハンジが予約を抑えてくれて、二人で行った。
「あ、そういえばさー、出がけにリヴァイに会ったから誘ったんだけど、断られちゃったよ。しかも何か無意味に暴行されたし!」
「え、そうなの?リヴァイ、何か朝から飲みに行きたそうにしてたけど、ハンジと約束あるから無理って言っちゃったんだけど。人数増えても平気だったんだ?」
「ん?…ああ、一人くらいなら増えてもいけたと思うよ。……まあ、仕方ないね!」
「飲みたいなら来れば良かったのにね。変な奴。」
気の合うハンジとの時間は楽しくて、ご機嫌で帰ると部屋のドアに何かかけてあった。
小綺麗に包装された箱を開けると、ペンだった。送り主の名前は書いてなかった。
「これ、ありがとう。誕生日、覚えててくれたんだ。」
翌日、談話室の隅で書類を纏めているところにふらりとリヴァイがやってきたので、使っていたペンを見せてお礼を言った。
「…ああ、そうだったか。」
「…だから、何、それ。」
視線を逸らしながら言うリヴァイに、私はまた一人で笑った。
1年前、ある日何か欲しいものはないのか聞かれたのと一緒に、誕生日の予定を押さえられた。
当日は食事に行った。それだけ。
ちなみに、欲しいものはやっぱりすぐには浮かばなくて、手帳って言った。
「…これ、誕生日のお祝いだよね?」
向かい合ったテーブルの先から徐ろに手渡された包みに、問いかけた。
「…ああ、そうだったか。」
「…あは、もういいよ、それ。」
リヴァイは、また私を見ずに言った。
いつまでも笑う私に、リヴァイは少し不機嫌そうだった。
今年、何日か前にまた、何か欲しいものはないのか聞かれた。私は少し考えて、答えた。
それだけ。
お互い、何杯空けただろうか。
リヴァイが持ってきた酒瓶には、あとほんの少しを残すだけになっていた。
「いいよ、それ、リヴァイ飲んじゃって。」
テーブルに肘を付いた両手に顎を乗せ、ふんわりと心地よい酔いに浸りながら、リヴァイに言った。
が、リヴァイは空になった私のグラスを一瞥すると、残りを全部そこに注いだ。
「お前が飲め。」
リヴァイの目線が私の後ろに流れた。思わずその先を追うと、枕元の時計にぶつかった。
真夜中を過ぎて、相変わらず正確に、時計は刻々と時を刻んでいる。
「…さっき、誕生日になったんだけど。」
「…、」
「…。」
「……ああ、そうだな。」
そう言って、リヴァイは自分のグラスに残っていた僅かな酒をぐっと流し込んだ。
「…、」
「飲まねえのか。」
呆気に取られてリヴァイを見つめていると、睨まれた。
「あ、いや、いただきます。」
リヴァイの視線を感じながら、最後の茜色を飲み干した。
私がグラスをテーブルに置く音と、リヴァイが椅子を引く音が重なって聞こえて、すぐ近くに来たリヴァイにゆっくりと視線を上げた。
「name、お前が欲しいと言っていたものを、くれてやる。」
「リ、」
リヴァイ、と呟く声は、リヴァイの唇に押し戻された。いや、声ごと食われたと言った方がいいかもしれない。
食いつくように口付けられ、お互いの酒の匂いが更に酔いを深めてくるような気がした。思わずリヴァイのシャツを握り締めると、ぬるりと熱い舌が入り込んできて、びくりと体が跳ねたのが自分で分かった。
「何か欲しいものはねえのか。」
数日前、何だか恒例のようになってきたその問いに、私は少しその場で考え込んだ。
「…うーん…一生分の、リヴァイ、…とか?」
「…何だ、そりゃあ。」
「あはは。」
散々口内を荒らされて、ようやく解放されると、部屋の中には私の肺が酸素を求める息遣いだけがやけに響いた。
「…リヴァイが、誕生日プレゼント?」
「ああ、一生分のな。」
「あはは、それ、すごいね。」
首元に埋められた頭をやんわりと抱きしめると、指にリヴァイの柔らかな髪が触れて、リヴァイの清潔な匂いが肺を満たした。
食まれて、舐められる熱い感触に、深い溜息が漏れる。
「その代わり、お前も俺のものだ、name。」
「一生分の?」
「当然だ。」
「…じゃあ、お返しに。」
もう一度貪り合うような口付けをしながら、どちらからともなく縺れるようにしてベッドに倒れ込んだ。
「焦ったかったよ、毎年。」
どうしようもなく不器用すぎるあなたに、今年はもう一つおねだりしてもいいかな。
「ねえ、リヴァイ、」
今年は、あなたの口から。
ハッピーバースデーを聞かせて。
戻る