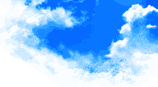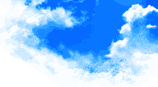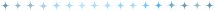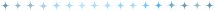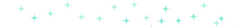何でこんなに、強くなれる気がするんだろう
(原作61話のところです)
少し前に落ち合えたハンジと共に合流した時、前にも増して眉間の皺が濃くなった気のするリヴァイが、ふっと小さく息を吐いたのに気付いた。
「リヴァイ、老けたね。」
「バカ言え、こんな短期間で老けてたまるか。」
「うそ、そんな短い時間だった?私もう何十年もリヴァイに会えなかったくらいの気分だよ、リヴァイ欠乏症だよ。」
「そうかよ。」
「あ、そう言えばリヴァイの手配書見た。何か似てた。ウケた。」
「似てねえ。ウケんな。」
次の行き先について道中ハンジから詳しく聞くことに決まり、出発の準備をするほんの僅かな時間、たぶんハンジが気を回してくれたんだろう、私とリヴァイは二人になった。
金属音を立てながら、暗がりで立体起動装置の整備をする隣のリヴァイ。
「また、いい部下に恵まれたね。」
「…しょんべんくせえクソガキばかりだがな。」
私は、壁外でのエレン奪還作戦後、エルヴィンから憲兵の動きを探る役割を任され、水面下で数人の部下と別行動をしていて、リヴァイと一緒にいることが出来なかった。
本当はリヴァイのそばを離れるのは嫌だったけど、ベテラン兵枠にしっかり入り込んでいる私がそんなわがままを言えないし、あのお兄さんも片腕無くなってかわいそうだったから言うことを聞いてあげた。
「新兵ばかりなのに、みんな顔つきが壁外調査の時と全然違う。」
「…随分修羅場ばかりくぐらせたからな。」
「ちゃんと、大人の覚悟をしてる顔だよ。彼らももう立派な兵士だ。」
「まだまだ不安だらけだ。」
「リヴァイがしっかり付いていてくれたおかげだね。エレンとヒストリアだけじゃなくて、彼らのことも考えてくれてた。」
「…死なせた奴らもいる。守り切れたわけじゃない。」
「私も同じ。でも、リヴァイは生きててくれた。」
「……、」
「―ありがとう、がんばったね、リヴァイ。」
私に着いてきてくれた部下も、みんな死なせてしまった。地獄のような自己嫌悪と罪悪感と喪失感だった。
でも、申し訳ないなんて思ったら、殴りますよ分隊長!って言われると思う。そういう子たちだった。
リヴァイは、エルヴィンも、ハンジも、ミケも、あの頃のリヴァイ班のみんなも、私も、誰もそばに居ない中で、これだけの若い命を携えて、どれだけの死線をくぐり抜けて、どれだけの死と相対したんだろう。
隣にしゃがむリヴァイをそっと抱き寄せると、素直に体重が預けられて、弱く右手が私の腕を掴んだ。
私やハンジが来たことで、リヴァイのずっと張り詰めていたものが少し緩んだ瞬間を、きっとハンジも気付いたはずだ。
私にはモブリットがいたからね、と、ハンジはさっき笑っていた。
リヴァイは人類最強だけど、完全無欠ではない。
「…お前もな、name。」
負け惜しみのようにぽつりと言うリヴァイは、今はまるで出会った頃のような、まだ初々しさのある新入りのゴロツキあがりの頃みたいだ。
「リヴァイが、生きていてよかった…よか、ったよーうえーん」
「…てめえ何てツラして泣いてやがる。」
安心したのは私も一緒で、気付けば寄り添っていたつもりの私が号泣するのを、リヴァイに叱咤されながらあやされることになってしまった。
残酷なこの世界をどれだけ飛んだって、大切な仲間をどれだけ無くしたって、勝ち目のない戦いをどれだけくぐり抜けたって、私たちは結局ただの人間で、それでも自由のために血を流し続ける。
どんなにこの心がズタズタになっても、リヴァイ、あなたがいるから私は進む。
離れていたって、あなたも飛び続けていると信じられるから、私も飛べる。
ぐずぐずと、抱きしめられたリヴァイの肩口に鼻水を付けてしまって、やべ、と焦る私を蹴飛ばしながら罵声を浴びせるリヴァイを見て笑い転げるハンジ。
気がひけるのか遠巻きに、でも興味深げに眺める新兵たち。
1日前は、少しも笑えなかったのに。
何でこんなに、強くなれる気がするんだろう
さあ、いこう。
緩んだ糸は、また、ピンと張り直すことができる。切れてはいないから。
一本じゃなくて、それが集まったら、もっと強くなれるはず。
戻る