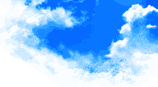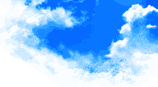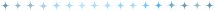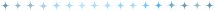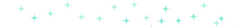不覚にも、あの瞬間に、私は堕ちた
「いやー、行きたくない。本当に行きたくないわ。」
夕暮れの街をかける馬車の中で、私は1週間前から言い続けているセリフをため息とともに吐き出した。
「もう諦めなって、name。適当に笑って適当に相槌打って適当に食べてればいいんだよ。」
同乗しているハンジは、普段からは想像もつかないほど綺麗に着飾られており、シンプルなドレス、ヘアースタイルながらとても兵士には見えない装いになっていた。
「ハンジはいいよね、もう慣れてるし、変人が知れ渡ってあんまり絡まれないんでしょ。」
「あははは、そういうこと!」
横目でじとっと睨むと、いつもの笑顔で軽い返事が返ってくる。
「大体分隊長になったら支援パーティーに出なきゃいけないなんて聞いてない。エルヴィンにハメられた。横暴。」
窓の外を流れていく王都の街並みに向かって、チッと舌打ちが出た。王都なんて興味がない。壁の外にしか興味はないのだ。
定期的に幹部が揃って王都に行っているのは知っていたが、こんなことだと分かっていれば分隊長昇進なんて受けなかった。
「君にはもっと前に分隊長になってもらっても構わなかったくらいだ。早速来週幹部の仕事があるが、頼りにしている。頼んだよ。」
あのエルヴィンの爽やかな笑顔を憎らしく思い出す。
これが初仕事って!貴族のじじいたち相手にご機嫌取りの資金調達パーティーなんて、想像するだけで反吐が出そうだ。
壁外で巨人とダンスでもしていたほうがまだマシだ。
「そもそも、兵士なんだから兵服でいいじゃない。なんでドレスなのよ、動きにくいし、似合わないし、化粧だってベタベタして気持ち悪い。」
「そんなことないよname、とってもよく似合ってる。すごく綺麗だよ。」
ハンジはさらっとそんなことを言う。面食らっていると、今すぐ抱きたいくらい、と鼻息荒く迫られたので、狭い車内で足蹴りを食らわせておいた。(ちゃんとヒールは脱いでやった。)
もっと豪華なドレスを、と担当の兵士に言われたけど、ふわふわひらひらのそれにドン引きした私は、ストンとしたネイビーのワンピースドレスでないと絶対に着ないとごね倒し、宥めにきたミケをも辟易とさせ、粘り勝った。
膝裏までスリットの入ったこれなら、動きやすいし、万が一にも備えられる。(万が一って?とハンジに聞かれたが、壁の中の中の中では何が起こるとも浮かばなかった。)
これくらい地味にしておけば、誰の目にも入らずに気配を絶ってやり過ごせるだろう。
「―リヴァイは遅刻らしいよ、珍しいね、時間にはシビアなのに。」
窓の外を見ながら、延々と話し続けるハンジの話を聞き流していた耳が、出てきたその名前をピクリと捉えた。
遅刻?リヴァイ?
「はあ?あのムッツリチビ、遅刻なの?有り得ない、私はこんなに嫌だってのに、ちゃんと向かってるっていうのに?兵士長のくせに?」
私の不機嫌に油を注いだと気づいたハンジは、「来たら3センチ身長縮めてやるわー。」とブツブツ言う私を見てケラケラ笑った。
「本当――――に、nameとリヴァイは似た者同士だよねえ。今回nameが来るって聞いた時のリヴァイの顔、見せたかったなあ。」
大いに想像が着く。さぞかし眉間に皺を寄せ、嫌悪感を顕にしていたに違いない。
私とリヴァイは、何かといえば突っかかり合う、いわば犬猿の仲というやつだった。
「心外。あんな鬼畜なコミュニケーション障害と一緒にされたくない。」
実力は認める。認めるが、あの態度が気に食わない。
いちいち人の言うことの揚げ足を取り、馬鹿にし、煽ってくる。私はそれに倍の勢いで言い返す。
「リヴァイがあんなに子供っぽい態度をとるのはnameくらいだよ。」とは、いつぞやのハンジの評だ。いい迷惑だ。
この格好で会いたくない、と思っていた私は、遅れるというリヴァイに少しほっとしたのと同時に強い怒りを感じた
私がこんなに嫌がってるっていうのに!あの野郎!
「ほら、着いたよ。」
そんな憤りを感じている間に、馬車は大層豪奢な邸宅前に到着していた。
もう腹を決めねばならない。name、気配だ。ひたすら、ひたすら気配を消すのだ。
外には既にエルヴィンがいて、降りるのをエスコートしてくれた。正装を纏う普段とは違う雰囲気に不覚にもどきりとするが、元凶はこの男であることを思い出しじろりと睨む。
しかし、そんなことは気にも留めないように、いつもの爽やかな笑顔が返ってきた。
「とても素敵だよ、name。見違えてしまった。いつもの勝気な君ではないみたいだ。…くれぐれも、来賓に失礼のないように頼むよ。」
耳元で囁かれた最後の一言に、私は引きつった笑顔を浮かべ言い捨てた。
「善処いたしますわ、エルヴィン団長。」
*
尽きた。精根尽き果てるとはこのことか。
私は人影のないバルコニーで、その柵に前のめりにもたれかかりぐったりとしていた。
気配を絶ってやり過ごす作戦は、早々に敗れた。
なぜなら、新幹部として紹介をするからと突然壇上に上がらされ、加えて挨拶をしろと迫られ(何も聞かされていなかったのはどう考えてもエルヴィンの仕業で、司会者よろしく隣に控える彼を思い切り睨みつけたものの、返ってきたのは結局いつもの笑みだった)、なんとかこなしてクタクタで壇上から下がれば、それを誠意と勘違いしているじじいたちがわらわらと挨拶を交わしに集まってきたからだ。
「挨拶も愛想笑いも完璧だったよ!」と、さっきすれ違ったハンジは親指を立ててきたが、それに突っ込む元気もなくようやく静かなところに逃げてこられた。
慣れないことに長時間晒された脳に、夜風が気持ちいい。
今何時なんだろう。中の賑やかさから察するに、まだすぐには終わりはやってきそうにない。
「良くやってるよ、皆…。」
幹部連中は、ただでさえその重圧と、調査の度の山のような仕事に追われているというのに、こんなことまでこなして兵団を守っていたのだ。
長い溜息を着くと、騒がしい談笑に重なって優雅な音楽が流れてきた。
「うわ…マジかー…。」
確か、パーティー中にはダンスの時間があり、これには必ず参加するように、と強く言われていて、この1週間は訓練後にみっちりダンスの個別レッスンを受けるという苦行を強いられてきた。
行きたくない。心底行きたくない。
しかしあの笑顔の団長の怒りに触れるのは得策ではないことを、私は兵団生活の中で身をもって知っていた。
「こんな所に居やがったか、グズ野郎。」
(うわーお。)
何ていうタイミング。神様は私の事がそんなにお嫌いなんでしょうか。
聞き慣れた暴言を吐くその声に、振り返る元気すら今はないのだ。いつものように言い争う余力ももちろん、ない。
「その耳は飾りか?この小煩い音楽が聴こえてねえのか、てめえには。エルヴィンの不機嫌をこれ以上煽るんじゃねえ。」
ああ、エルヴィンも、こんなパーティー中にはさぞストレスを感じているんだろう。あの笑顔の裏に隠された怒りを思うと、身の危険すら感じる。
行くしかない。分かっている。調査兵団のためにも、エルヴィンのためにも、自分のためにも、だ。
けど、背中で聞くコイツの言い回しはやっぱりムカつく。いつも通り、この非日常な場所でも変わらない。
「わーかってるよ!今行こうとしてたとこ。ていうか、遅刻してきたあんたに偉そうに言われたくないね。」
何度目かも分からない溜息とともに、振り向いた。
そこには、室内の柔らかな光を背にした、いつもの兵服とは違うタキシードを身に纏った声の主の、小柄なシルエットがあった。
そこからたっぷり、5秒の間、私たちは見つめ合っていたと思う。
間を、気持ちのいい夜風が吹き抜けて、二人の髪を揺らした。
5秒後、口を開いたのはリヴァイだった。
「俺の相手をしろ、name。面倒くせえ貴族の娘の相手なんざ御免なんでな。お前もじじい共と手を繋いで愛想笑いは本望じゃねえだろう。」
人類最強なんていう異名を持ったこの兵士長には、貴族内にもファンが多いと聞いたことがある。
今日も、姿を見せないその居所を尋ねるクネクネした娘の声を、何度か聞いた。
誰と踊れ、と言われているわけではない。要は、ダンスの間フロアで誰とでもいいから体を動かしていれば良いのだ。
「利害の一致ってやつ?」
「そういうことだ。」
光の中から差し出された右手に、そっと自分の右手を重ねると、あっという間に安息の地であったバルコニーから眩しく騒がしいフロアへ引っ張り出された。
既にフロアでは、くるくる回る色取り取りの男女で溢れていて、私たちは流れに合わせてその中へ紛れ込むように入っていった。
兵団本部では耳にもしないような音楽に合わせて、足はステップを踏む。1週間の付け焼刃にしては、上々じゃないだろうか。
流れに任せて踊り続けていると、やがて音楽はクライマックスを迎え、終息した。
男女は足を止め、演奏家や自分たちへ送る拍手喝采でフロアが満たされた。
踊り始めてから、いや、バルコニーで私が振り返った時から、
私たちはずっとお互いの視線から目を逸らすことなく、見つめ合い続けていた。
「リヴァイ、」
慣れない動きを続けた私は僅かに肩で息をしたまま、周りのざわめきの中で手を取り合ったままの目の前の人物に、ポツリと呟く。
周りの人の波は私たちを別の世界の存在のように避けていき、周りのざわめきは膜の外のようにぼんやりとしていた。
目の前のその男だけが、現実のように鮮やかに映る。
「私、堕ちたわ。」
視線が逸らせないまま呟いた言葉は、その声は、ぽとん、と磨き上げられた床に音を立てて落ちた気がした。
リヴァイはその形のいい口元を少し歪め、口角を上げた。その動きに、視線が持っていかれる。
「奇遇だな、俺もだ。」
リヴァイはそう言うと、私の腕を強く引いた。
人混みの間をまるで誰も居ないかのようにするすると早足にすり抜けていく。
周りの全てがスローモーションになる。
大きな木造りの重い入口の扉を押し開けて隙間に滑り込むと、廊下は薄暗く人の気配が全くしなかった。
その廊下を駆け、次の角を曲がると同時に、背中にヒンヤリと壁の冷たさを押し付けられた。
瞬間、待ち切れないように、どちらからともなく私たちは相手の唇を求め合った。
不覚にも、あの瞬間に、私は堕ちた
それは、今まで憎らしくて仕方なかった、あんたなんかに。
(一目惚れって、初対面で起きるもんじゃなかったの?)
戻る