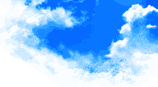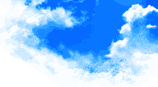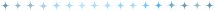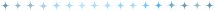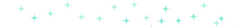強く生きる為に、弱くなる場所が要る
「こんばんはー。」
多忙を極める幹部たちさえ寝静まった深夜、本部の錆びたドアを開けた先の屋上で、冴えた月を、その光を浴びながらそいつは見上げていた。
軋んだドアの音に対して、振り返ることもなくそのままで、nameは不釣り合いに軽い挨拶を寄越した。
見上げているだけならまだ乙な風情もあるものだが、古びた木材をベンチ代わりにした奴の足元には、中身を抜かれた瓶が無造作に散らばっていて、思わず眉を潜めたのも仕方ないというものだ。
外気の下にいるにも関わらず、風に乗って流れてきたのは独特の刺激臭だった。それは、アルコールのものであって間違いない。
「このご時世に、一体何本煽ってやがる、nameよ。」
酒なんてものは、口に入れた瞬間焼かれるようなそこらに蔓延る悪酒を除けば、一般庶民が易々と手に入れられるような代物では最早なくなっている。調査兵団に於いても、いつ何時また壁が破られるか分からない現状のために摂取を規制しているという以前に、そもそも資金繰りの厳しい中でそんな道楽とも取られかねないものを市民の税金で表立って入手するわけにもいかない。それでも常に地獄をその目に見る調査兵たちの一時の逃避の手段として、悪酒まではいかないまでも安価な酒を辛うじて幹部の管理のもとに保管しているに限っていた。
一筋冷えた風が過ぎるのに混じって、小さな舌打ちが聞こえたのは空耳ではない。
「うるっさいなー、リヴァイ。小言言いに来たなら、帰ってもらえる?」
上を見上げ続けていた姿勢が揺らいだかと思えば、頷くように右手に握っていた瓶をぐいっと仰ぎ、また姿勢は月を見上げる。
「エルヴィンには許可を得てる。何度も言うけど、文句言われる筋合いないからね。」
何度も、には主観による違いがある。
こうやって酒を煽るnameに、name曰く小言を言いにやって来たのは確かに初めてではない。けれど、こいつは熟練兵に名を連ねながら酒乱という訳でもなければ、夜毎こうして瓶をまき散らしている訳でもない。
むしろ、この前はいつだったか、と、暫く見なかったこの姿にふと思いを馳せた。
初めてその場に居合わせたのは、偶然だ。あの時も、じっと月を見上げていた。
この時間と、この時間のための酒を奪われるのであれば、調査兵団を去る。
ハンジの野郎に聞いた話では、nameはエルヴィンにそう言い放って今なおここに居座っている。それはつまり、エルヴィンがそれを許したということだ。先ほど本人がそう言った通り。
けれど、こいつは熟練兵に名を連ねながら酒乱という訳でもなければ、夜毎こうして瓶をまき散らしている訳でもないことを、壁外に出る度に少しずつ減っていく熟練兵たちは知っていた。
この前は、いつだったか。
「俺が言ってるのは小言じゃねえ。一人で泣いてんじゃねえグズ野郎、ってことだ。」
相変わらず暗い夜空を見上げる背中に声を落とすと、暫くして小さく肩が震えた。
「うる、さいなぁ…、」
ひくりと肩が跳ねるのを、無理やり我慢するように強張る自分よりも細い身体をただ後ろから眺めた。
嗚咽を飲み込むのも、堪えきれない分が引きつるような音になって溢れた。
「うる、…さい、なぁ…っ、だからやなんだよ…!」
今日、一人の兵士が数人の仲間に看取られてこの世を去った。
nameの班員だったそいつは、長くこいつの片腕として壁外を飛び回り、一月前の壁外調査で致命傷を負ったところをnameが文字通り身を挺して救い出し、何とか息を永らえて、それでも意識は決して戻らぬまま、壁内に帰還した。
よく保った、と、医療兵は言った。
しかし、その体温を失っていく兵士の身体に、生の全てを絞り尽くすように泣き縋り付く同僚であり恋人である一人の兵士の姿を見た者は、何度同じような場面に立ち会っても決して慣れはしない抉るような痛みをその胸に負ったはずだ。
それは、nameも同じ。いや、それ以上に。
「…やめてよ…っ、入ってこないで…、」
ここにこうしてnameが居るのは、それは一人泣く為なのだと気付いたのは、いつだっただろうか。一人その痛みを、嚥下する作業のために、決して一人では上手くいかないそれを、それでも一人で行う為に、ここに居るのだと気付いたのは。
いつの間にか小さく抱えていた膝に伏せた頭にそっと手を乗せると、幼い子どもがむずがるように弱く頭を振る。
「…だから、やなんだ、このタイミングで、入ってくるやつ…っ、」
月夜に、嗚咽を耐える声がまるで手負いの獣の低く細い唸り声のように響くのが止むまで、緩く、壊れ物を触るようにそっと、俺の手はnameの髪を撫で続けた。
やがて、唸りは細く弱い泣き声に変わる。
それまで、普段巨人を屠るためのものであるのがまるで嘘のように、ただただ、静かに繰り返しこの手は目の前で小さく震えるnameを慈しむように撫で続けていた。
どれくらい経っただろうか。
いつの間にか震えが止んだ身体を尚更丸め、nameは深く、深く息を吐いた。気温を下げていく夜空に、僅かに白くなったそれがふわりと現れ、消える。
「…だから、やなんだ。」
今度の声は、震えてはいなかった。
頭にあった俺の手を、俯いたままnameはそっと外し、両手で包み込んで弱く頬を寄せた。普段にそぐわない、まるで、遠慮を見せるかのようなそれに、無意識に腰を落とした。
目線が合ったnameの目は、水分で揺れていた。いつもは目に映る全てが敵かのように荒んだその色が今は失せ、それを目の前から見据えられた動揺が更にその瞳を揺らしたかのようだった。
「…そんなの、リヴァイしか…いないんだけど、」
顰められた眉間は、苦し紛れの強がりしか表していなくて、気付けば握られていた手をそのまま頬に添えて引き寄せていた。一瞬強張ったnameの身体は、それでも素直に引き寄せられる。
触れた唇は、凍えていて少しかさついていた。それを潤すように丁寧に舐め上げるのを身じろぎして嫌がるのも、既に腕の中に捉えたnameでは大した抵抗でもなく、大した抵抗をしようとしているとも思えなかった。
強く生きる為に、弱くなる場所が要る
それが、nameがエルヴィンに突き出した条件だった。
何度折れても、また立ち上がる為の。
そして、その場に踏み込んだ俺を、nameはこうして受け入れる。
それが、俺にとって強く生きる為の場所なのだと、こいつは知る必要はない。
あとがき→
戻る