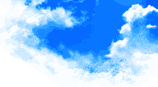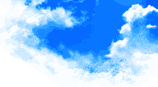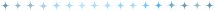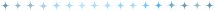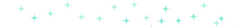目が覚めたらもう一度
「まずったなぁー。」
夕日が落ちていく地平線を眺めながら、拾ってくれる相手もいない呟きを落とした。
ああ、やっぱり壁外の空はどこまでも美しく、どこまでも自由だ。
巨大樹の太い枝に座り込み、幹に体を預ける。左腕に響く激痛に思わず顔をしかめた。流れる血がヌルヌルして不快だ。
壊滅状態に陥りかけた索敵班において、あれ以上班員たちの命を失わせるわけにはいかなかった。
錯乱仕掛けている部下を守りながら戦う余裕も、なかった。だから、自分だけで戦う判断をした。
「―エルド、走って!!」
班員の中で一人冷静さを保っていた彼に、生き残っている班員たちを任せた。エルドならきっとしっかり指揮をとって本隊に合流してくれたはずだ。
そして、エルヴィンなら、私に何があっても、情に流されず、正しい判断をしてくれるはずだ。
「ちょっと自信過剰だったかな。」
巨大樹の森の近くという立地で、巨人たちを削ぎ終わったあと、彼らを追う自信はあった。
しかし奇行種が混ざっていたことでペースを乱され、ガスが切れ、それでも最後の1体を仕留めたものの左腕を負傷した。
最後に巨大樹の上で戦いを終えたことも運が悪い。とてもじゃないがこの腕がまともでも降りられる高さではない。近くに15m級でも来てくれて降ろしてくれでもすればいいが、その前に確実に私は餌だ。
陽が落ちていく。
これから夜ということが、幸か不幸か巨人との遭遇をまぬがれ、こうして考えを巡らせる時間を作ってくれた。
「せめてお前だけでもみんなのところに帰らせてあげたいんだけどな。」
樹の根元では、愛馬のシャルが草原の上に寝そべり、垂れた頭を時折私の方へ向ける。
頭がいい子だから、状況は理解していると思う。そしてどこかで野営を張っている本隊の場所も察知できるはずだ。でも、本隊へ戻れと言っても、全く動こうとしない。
朝になれば巨人が現れるかもしれない。運良く遭遇しなくても、いつかは血が足りなくなるか、飢えて乾いて死ぬ。
降りられたとして、道中巨人と戦うことが出来るのか。
ふと気付くと、右手が無意識にブレードの残刃を数えていた。
「我ながらしぶとい奴...。」
自分に思わず苦笑する。
生への執着だ。絶望的な状況でも、どうしたら生き抜けるか。
「何があっても諦めるんじゃねえ、生きろ。」
リヴァイに教え込まれたことだ。上に立つようになり、私も班員たちにもずっと言い続けたことだ。
あなたは、どんな顔をするだろうか。私が戻らないことを知って。
情けねえと怒るだろうか。それとも、恋人を失うかもしれないことを嘆いたりするんだろうか。
調査兵団を支える身として、その優しさを、私への愛を、しっかり封じてるだろうか。
「思いっきり、矛盾してるな...。」
すっかり暗くなり、冷え込んだ体を右腕で抱え込む。
最後にリヴァイに抱きしめてもらったのは、出発の前夜だっただろうか。そのぬくもりの跡を探ってみても、今はどこにもない。
「俺はお前を守らない。自分で守れ。そして、ちゃんと帰って来い。」
いつも、壁外調査前に言われていたこと。
恋人にしては冷たすぎるんじゃないか、と、いつも拗ねていた私。こんな時に笑いが漏れる。
「そうだよね、リヴァイ。」
頬に流れた涙を、右腕で乱暴に拭った。
そこにどんなに深い愛が流れていたか、こんな時にふと気付いてしまう。
行こう。
ここで立ち止まって、行き着く先がどうせ死しかないのなら。私は誇りある調査兵団の一人として、生きるために足掻かないといけない。
手が届く細めの枝を降り、隊服のシャツの裾を裂いて、左腕に巻きつける。立体起動装置のワイヤーを座っていた巨枝に何度も巻いた。
私の身動きの気配で、シャルが小さく嘶いた。
月明かりはない。巨人たちは静かに眠っているだろうか。
「行くよ、シャル。」
私は帰らなければならない。あなたのところに。
どんな顔をしているのか、この目で確かめに行かなくては。
***
空が少し白んできたなあなんて、力の入らない体をシャルの首にもたれさせながら霞んだ視界で考えた。
体が動かない。
そもそもそんなに上手くいくはずもなくて、まず樹から降りるときに手を滑らせてかなりの高さから落下した。
しこたま全身を打ちつけたあと、夜の闇で動きの鈍くなった巨人に2体遭遇して、何とか回避したものの失血のせいでふらつく頭で縋り付くように乗っていた馬上から落馬もした。
そもそも血が足りないから、痛みを感じなくなったのは良かったことにしておこう。
あとはシャルを信じて、私は少しでも長く呼吸をすることだけに専念することにした。
今ならあのリヴァイの感情の読めない無愛想な顔も、いつも以上に愛しく素敵に見えるんだろうなあ、なんて、思う。
これが走馬灯じゃないことを祈りたい。
ぱかりぱかり...
シャルは私の体に負担にならないように、静かに歩いてくれている。
遠く耳にわずかに入ってきた聴き慣れた二つの声に、口角が上がった。
「...っと、待ちなよリヴァイ!あなたがここを離れてどうする?!」
「うるせえクソ眼鏡、エルヴィンには話をつけた。離せ。」
あの嘶きは、リヴァイの馬だなあ、なんて、規則的な揺れに身を任せて思った。
「落ち着きなよ!nameならきっと生きてる。信じて待とう!」
「黙らねえと削ぐぞ。もう十分待った、俺はー」
突然途切れた声を惜しく感じつつ、いつもどおりの言い合いだなあ、と安心する。
「...え、リヴァイ、あれ...」
(シャルー、帰ってきたねえ...)
ひどく重い右腕を少し動かして、シャルを撫でると、ブルルルと息を吐く振動に肺が揺れる。
ああ、私、生きてるんだな。
「name...!」
強い腕に抱えられて、次第に色んな声がして、温かい気持ちがじんわり溢れてくる。
何だか久しぶりに会ったような気がするリヴァイの何とも言えない表情に、私はあははと小さく笑ってしまった。
「ただいまー、リヴァイ。」
「黙ってろクソ野郎。」
ゆっくり伸ばした手でリヴァイの頬に触れて、私は体を満たす安心感に身を委ねて目を閉じた。
あなたからの説教も、その表情への感想も、壁の中へ戻ったらゆっくり時間を取ればいいから。そして少しは、褒めてもくれたり、改めてぎゅっと抱きしめてくれると嬉しいんだけど。
今は、その腕の中で少し眠ってもいいかな。
目が覚めたらもう一度
戻る