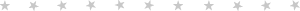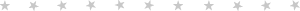
ヤコフ・フェルツマンは息を飲んだ。
世界を5年連続その手に納めた愛弟子が、何を思ったのか突然日本人スケーターのコーチを決めた。
勿論、止めた。
一度リンクを離れればどうなるか…。考えなかった訳ではないだろう。しかし、現実は残酷だ。
しかし、どう言葉をかけようが一度決めたら突き進む奴だ。
"それ"が己を高める長所のひとつといえばそうなのだけれど…。
コーチであるヤコフの言葉ですら一度も聞いたことはなかったのだ。
だが、そこには確かに見えぬ絆があった。"氷"に対する深い愛を知っていた。
だからこそ好きにさせてきた…
しかし…
忘れてはならない。
愛弟子は"祖国の象徴"なのだとういことを
『……○○だ。』
「ーーッ…!」
ヤコフは眉間に銃口を突き付けられた感覚に陥った。
人で溢れかえる空港で、況してや相手の手のひらがそのコートに収まっているにも関わらずだ。
しかし、何処か見覚えのある髪色とその瞳の色に、慌てるように我に返り、答えるように名乗った。
事の起こりは連盟上層部からの連絡だった。
愛弟子の行く末に温情を、暫しの自由を願い、頭を下げたその日。その条件として言い渡されたのが、"その身"を常に"祖国の目"に写して置くことだった。
ヤコフは首を傾げた。
言わんとすることは理解できていた。
本人の意に関係なく"その身"を守るボディガードをつけるということだろう。…しかし、"祖国の目"とはどういうことなのだろうか…
しかし、その疑問は○○を目にした瞬間一気に晴れた。
「…ヴィッ……ヴィーチャは手続きを終えラウンジで休んでいる。…我儘に付き合わせてすまない。ヴィーチをよろしく頼む。」
『……………。』
首を微かに縦に動かすのみで、○○はヤコフの横を通りすぎ、足を進めた。
歩く度に揺れる乱雑に結ばれたその金色の髪に目を奪われながら、ヤコフは理解した。
"あれ"は国の"影"だと。
そして改めて愛弟子の未来を案じた。
- 5 -