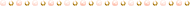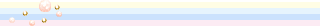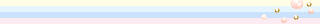
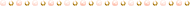
斎藤一は、とことん運が悪かった。斎藤家の一人娘として生を受けた彼女にまず降り掛かった災難は父親の死。物心つく前ではあったが両親が揃っていたこの頃がもしかしたら1番幸せだったのかもしれない。一の記憶にあるのはいつもピリピリとした様子で事ある毎に恐ろしい顔で自分を怒鳴りつけ殴る母の姿。そして小学4年の頃に、母は帰ってこなくなった。食べ物もない一人きりのアパートの一室に膝を抱え空腹に蹲っているところを、学校から連絡を受けた児童相談所の人が保護してくれた。後から聞けば栄養失調で危うく死ぬところだったそうだ。
母に捨てられた一は児童養護施設で暮らすこととなった。空腹に苦しむことも殴られる事もなかったが、母に捨てられたのだという悲しみと寂しさは消えなかった。
それでも何度か倒産やクビの憂き目に合いながらも働き夜間の高校を卒業した一も、一人の男性と知り合い男女の関係となった。男は優しく明るかったことから一緒にいて楽しかった。けれど一が妊娠したとしると男は「本当に俺の子なのか」というショックな言葉を最後に姿を消した。
残された一は膨らみ始めた己の腹を撫でながら、最早泣くことも出来ず呆然とするだけだった。もう、何で自分ばかりがと嘆くことも自棄になる気力さえなかったのだ。
それでも元気に生まれてきた二人の我が子に一は小さな幸せを味わった。兄である方を薫、妹の方を千鶴と名付けた一は、小さな安アパートで慣れない子育てを始めた。初めての子育て、しかも双子…慣れないことばかりで時には言う事を聞いてくれない我が子達に泣きそうになりながら、けして母のようにはなるまいと心に決め必死で育てて来た。
「まぁま、ないない」
「ん、ああ。全部食べれたのか、偉いな薫。」
小さな空になったご飯茶碗をスプーンを握り締め笑顔で見せてくる薫の頭を撫でれば、隣で千鶴がんくんくと頑張って残りのご飯を食べる。
「ちーも!ちーも、ないない」
「そうだな。千鶴も偉いな」
よしよしと千鶴の頭を撫でると、「さ、保育園の準備をしような。」と二人に言うと「むー、ほーくえん、ないないよ」と嫌々と首を横に振る。2歳になった二人は言葉も増えた代わりに、こうしてちょっとした事でいやいやとする事が多くなってしまった。
手が掛かって仕方ないが、これも成長の証なのだとイライラを我慢しつつ何とかならないものかと頭を悩ませていた。
「そうか。では、ママだけ理恵子先生に会いに行くが良いか?」
「「めー!まぁま、めー!」」
ふくりと頬を膨らます双子に、それじゃ保育園行くぞと声をかけるとようやく「「あーい」」と手を挙げてくれた。
next
- 1 -