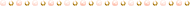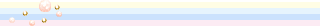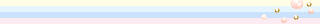
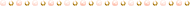
一は明石藩に仕える旗本の娘として産まれた。旗本といえど、身分はけっして高い方ではなく暮らしとて贅沢が出来る程のものではなかった。
しかし、両親も5つ上の兄も優しく何不自由ない穏やかな暮らしに一は感謝していたし幸せであった。
だが、ある日のこと明石藩の藩主と幕府の使者に呼び出された先で一は鬼の暮らす里、そこの当主に嫁ぐようにと命じられた。
まだ13になったばかりの幼い娘に下された無情な命令に父は震えながら何故娘なのか、まだ幼い故、嫁になどとても出せないと…逆らうこと等許されぬ状況で必死に取り縋った。
「…父上…母上…」
緑豊かな穏やかな土地を眺め、1人ちょこんと縁側に座っている一は嫁ぐ際に持たされたお守りを手に寂しそうに呟いた。
覚悟してきたはずではあったが、やはり家族と離れた寂しさが消えることはなかった。
それに何より一の心を痛ませているのは虚しさであった。嫁ぐ前に、幕府の使者からある程度の説明を受け、自分は人質なのだと幼くも賢い一は言われずとも理解することが出来た。それ故、嫁いでも歓迎されることはないだろうとも予測していた。けれど、実際に肌で敵意や憎しみを感じさせる冷たい視線に晒される事は辛く逃げ出してしまいたい程であった。
何より夫となった、ひどく美しい男も一を目に入れた途端にその顔を歪ませた。それが一にとっては悲しかった。歓迎されないことは覚悟していたとはいえ、一とて女子である。それなりに結婚に夢を見ていたとしてもおかしくはないだろう。好きな人と結婚し、子を産み…例え、会ったことはなくとも結婚してから、そんな風になれたならと、ほんの僅かに抱いていた期待が崩れさり、感じたのは悲しみしかなかった。
「……愚かな事を…私は、人質なのだから…その役目を果たせばいいだけ…」
悲しげに目を伏せ、自らに言い聞かせるようにお守りを握り締めた。
□□□□□□
「…ととしゃま、ととしゃま、およめしゃんは?」
「およめしゃん、およめしゃん」
歳三の膝に乗り、きらきらと丸く大きな瞳を輝かせて見つめてくる幼い双子の妹と弟に、歳三は溜め息を付くとポンッと丸っこい頭を撫でた。
「お前ら、何を期待してんだ?」
ぐりぐりと頭を撫でれば二人してきゃーと嬉しそうな歓声をあげるのだから、歳三の顔も緩むというものだ。
「あんねー」
「あのねー」
二人は顔を見合わせコテンと首を傾げると「「なーしょ」」と笑った。
「何だよ、狡いな二人して」
くすくすと楽しそうに笑う二人を見る歳三の眼差しは優しく細められている。
千鶴と薫は、歳三の年の離れた実の妹と弟だ。しかし、両親は幕府に攻め込まれた際に殺され、まだ物心付くかどうかだった二人は歳三を「ととさま」と呼び、歳三自身も兄というよりは父という感覚で二人を育てていた。
だからこそ、ふと妻となった一の事を思い出すと歳三の胸に苦いものが立ち込める。
いくら情を掛けないようにと思えど、もし千鶴が似たような事になればと思うと、やはり罪悪感が湧いてくる。
(困ったもんだ…)
溜め息をつき、ごろりと寝転がった歳三の上に、きゃっきゃとはしゃいだ千鶴と薫が乗っかってきた。
「…会いに行ってみるか」
ポツリと呟かれた言葉は、はしゃぐ幼子の声に簡単にかき消された。
next
- 2 -