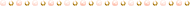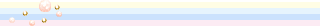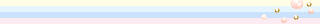
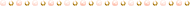
都内の繁華街の一角にあるビルの最上階。
ガラス張りで明るい窓際に立ち、書類を読みながらついつい癖で煙草を手に取った男は鋭く舌打ちをするとぐしゃりと煙草を握り潰した。
男の名を加々知鬼灯といい、まだ20代と思わしき容貌は目付きは鋭いながら所謂イケメンと呼ばれる部類に入るだろう。
「まったく、人のシマで勝手な事を…それもこれもあのボンクラがはっきりしないから舐めた真似をされるんです。」
忌々しげに部下からの報告書を見遣り、呟かれた言葉は暗い冷ややかなものだった。
「さて、最近うちのシマで勝手な事をしてる組がいるようですがお気づきですか。」
洒落たオフィス然とした部屋で聞くには少々違和感のある言葉に、その場にいた者達は真剣な面持ちで頷いたり、首を横に振り否定するなどの反応を見せた。席につくのは殆どが若い男女であるのもまた違和感に拍車を掛ける。
「この薬を見かけた事のある方は?」
そっとテーブルの上に置かれた一見するとただの粉薬のような物をそれぞれ見遣り首を捻る。
「…あ。」
「唐瓜さん、心当たりでも?」
鬼灯の言葉に唐瓜は「は、はい」っと上擦った声を上げ、戸惑いを見せつつも口を開いた。
「この前、集金にいった風俗店の従業員がコレと同じ薬を持っていました。」
「間違いなくコレですか」
「はい。同じく虎の透かし模様が入ってましたので間違いないと思います。」
「そうですか、ありがとうございます。」
生真面目に頷く唐瓜の横で茄子が薬を蛍光灯に照らし、目をキラキラさせて「おおー、ホントだー!すっごい、すごいよー!ね、唐瓜ー」とはしゃいでいる。
「それで鬼灯様。この薬は一体…」
頬に手を当ておっとりと首を傾げる華やかな着物姿のお香に、鬼灯は重々しく「違法ドラッグ」と告げた。
「え…マジですか」
「マジです。どうも新種っぽいので詳しくは調べてみないと分かりませんが、まごう事無く違法ドラッグですね。」
「え、でもウチは薬系ダメ絶対!だよね?シマ全体で徹底してるよねー?」
茄子ののんびりとした疑問に鬼灯も頷くと「人生を破滅させるだけと分かっていても手を出してしまう人もいるってことですね。」と溜息をついた。
「それは兎も角、何の断りもなく人のシマで商売なんざ、言語道断。許すことは出来ません。と、言う訳ですので、皆さん…キリキリ働いて下さいね。」
テキパキとそれぞれの役割を割り振ると、「それでは解散です。」と指示する。
「あの〜、ボスは…」
唐瓜がおずおずと本来ならこの場に居なくてはならない筈の人物について訪ねると、ぐっと眉間に皺を深くし今にも暗黒世界を呼び出しそうな顔で舌打ちをした鬼灯に、あちこちから「ひいぃぃ」と悲鳴が上がる。
「あのボンクラなら、急な腹痛で寝込んでいますよ。そもそもあのアホ上司が事ある毎になあなあで済まそうとするから舐められてシマに手を出されるんですよ。まったく…あのボケが…『えー、そうなの?困ったなぁ』で済むわけねぇだろうが。」
ピシャリピシャン
いつの間にか手にしていた鬼灯愛用お手軽お仕置き道具の一つである長定規を手の平で打ち鳴らす鬼灯に、さぁぁぁぁっと血の気の引いた唐瓜達は一斉に会議室を飛び出していった。
『そうですか、そちらでも出回り始めましたか』
電話口で溜め息混じりに寄越された回答に鬼灯は目を細め「ということは、警察では既にご存知でしたか。」と不機嫌さを含ませ返した。
『すみません、こちらも噂から漸く信憑性が出てきたレベルでしたので、まさかこんなに早くこちらにまで及ぶとは思っていませんでした…』
「そうですか。…今現在分かる範囲で構わないので情報をいただけますか。」
『分かりました。直ぐにデータをお送りします。それとこれは噂の域を出ませんが、バックにチャイニーズマフィアが絡んでいる可能性があります。』
「ちっ…そうですか。分かりました。」
面倒な事態に降り積もる苛立ちに持っていたスマホが粉々になって役目を終えた。
鬼灯の活動拠点であるビルから車で20分のところにある中華街の奥に目的の漢方薬局はある。
白を基調とした壁に、カウンター、奥には陳列された材料と作業台。そこで人の良さそうなふくよかな青年が漢方を煎じている。
「こんにちは、桃太郎さん。」
「あ、いらっしゃいませ、鬼灯さん。」
手を止めにこやかに出迎えてくれた昔話の英雄と同じ名前の彼は「閻魔さんの薬ですか?」と半ば動き出しながら聞いてきた。
「いえ、今日は白澤さんに用がありまして。二階、居ます?」
そういうと桃太郎は顔を引き締めると、ちらりと背後にやる棚を見遣り頷いた。鬼灯が二階に、わざわざ桃太郎に訪ねるというのは、あまり聞かせたくない仕事の事なのだと言われる前に理解した。
「すみませんが、私が帰るまで近付かないようお願いします。」
「分かりました。」
白澤の営む薬局には隠し扉があり、2階にいくには幾つかのルートがあり、どれもが巧妙なからくりが仕掛けられている。無表情にからくりを解除しながら2階への階段を昇る。
そして、中華風の彫刻が施された扉を開けると一気に日本ではなく中国に来たような感覚にさせられる。
調度品からそこにいる人までもが中華風なのだ。
「遅かったね」
寝台に寝転がり水タバコを吹かしながら、婉然と笑みを浮かべる白澤の姿に眉を寄せると溜息をついた。
「昼間だというのに、そうやってぐうたらしてると牛になりますよ。ああ、もう牛でしたか。それは失礼。」
「誰が牛だ!!ったく、機嫌悪いな。」
淡い水色の華服は襟元に繊細な刺繍を施され、着ている白澤自身の細さや容姿もあり、儚げにみせていた。あまり現代的ではない服装も、この男が着るといたく自然で似合っているのだから、それなら性格ももう少しマシであれば良いのにと思う。
「遅かったねと言ったからには、私が此処に来た理由に心当たりがあるんですね。」
ゆるりと起き上がった白澤は、つまらなそうに片耳に付けている朱い耳飾りを指で弄りながら「まぁね」と肩を竦めた。
「お前が聞きたいのは、この薬のことだろう?」
白く男にしては細い指に摘まれているのは確かに例の薬で、鬼灯の顔が正に鬼のように吊り上がる。
「まさか、貴方が作ったんですか。」
「僕が、こんな薬を作ると?」
余裕たっぷりに口元を上げ笑うのが気にくわない。
「関わりはないと?」
冷たく問う鬼灯にふふっと笑うと、ふわふわとした足取りで近づいてきた。そして、ゆるりと鬼灯の首元に腕を巻き付け抱きつくと、耳元で「お前がいるのに、そんな事するわけないだろう」と囁いた。
「…はぁ…ならコレについて知ってる事を今すぐ吐きなさい。」
「ふふ…教えてあげてもいいよ。可愛いお前の為だもの。でも…タダではあげない。」
きゅぅっと目を細め舌で赤い唇をぺろりと舐める白澤に鬼灯は「この色魔が」と舌打ちした。
「この薬はね、服用すると強い快楽と催淫を引き起こし、人をただの獣のようにしてしまう。狂ったように只只sexを続けるのさ。そして薬が切れ始めると今度は幻覚や幻聴…人は苦痛から逃れるためにまた薬を飲む、その繰り返し。」
気だるげに煙草を吸う鬼灯の胸元に頬をすり寄せながら、白澤は例の薬について語る。布団から白い肩が覗き、ついついそこに視線がいってしまうのを意識的に避ける。しかし白澤は、まるで興味がなさそうに振舞う鬼灯が気にくわないのか、構えとばかりに誘ってくる。
「…それで、何故貴方がこの薬を持っていたんですか?」
「ああ、それはね…貢ぎ物。」
すぅっと細められた目が冷たい光を帯びる。普段はふわふわと頼りなさげな印象のこの男だが、こういう表情を見ると確かに中国裏社会のトップなのだと思わせる。
「アレはあわよくば僕ごと乗っ取るきだったんだろうねぇ。ふふ…殊更、僕に勧めてきたよ。」
「おやまぁ…」
薬の知識においてもトップクラスのこの人にそんな真似をするとは、愚かとしか言えない。
「あそこのボスは僕、嫌い。」
つんっと子供っぽく唇を尖らし「イヤらしい目で見てくるし」と言う白澤を見遣り鬼灯は無言のまま眉を上げる。
その男は特別に念入りにボコろ…いや、挨拶をしようと心に決める。
「…協力してあげようか。」
「そもそも貴方のとこの不始末なんですから、協力も何もないでしょうが…まぁ、それなりに働いてもらいましょうか。」
「ふふ…なら、もう一回しよ?」
にこりと笑う男に鬼灯は深く溜息をつくと、その赤い唇を塞いだ。
挫折。
- 23 -