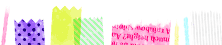室町時代パロ⑩
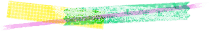 #室町時代設定のなんちゃってパロディです。
#室町時代設定のなんちゃってパロディです。
テツの朝は早い。
生臭坊主が幅をきかせ、己が利を増やすことや欲を満たすことに一生懸命になっている中で、テツはただ真っ直ぐに仏の道を生きているような男だ。
日も昇り切らぬうちに起きて沐浴を済ませ朝の修行を行うと、毎日町に出掛けていく。そして日がてっぺんに差し掛かる頃に帰ってくる。
たいていは黄瀬が用心棒と自称して着いていくが、黄瀬が赤司に用事を頼まれたりすれば別の奴がついていく。俺か、火神か。
長く続く戦乱で、千年の都と謳われた町は今や見る影もない。
絶えず何処かから煙があがり、道には物乞いが行き倒れ、追い剥ぎや夜盗が我が物顔で高笑いをしている。
それが、俺たちが暮らすこの国の中心、京の都の現状だ。
誰もが目を背けたくなる状況に、それでも、テツは目を逸らすことなく毎日、毎日飽きることなく町に通っている。
死した者に手を合わせて念仏を唱えて川原に葬り、その川原で行き倒れたもののために薄い、ほとんど水のような粥を炊いて配る。赤司に頼めば、テツが頼めば、莫大な援助をえられるだろうに。テツは首を左右に振り、商家や武家の家々を回っては施しを貰い、それを炊きだしている。
「熱いですから、ゆっくり食べてくださいね」
そう言いながらボロ雑巾のような物乞いが差し出した欠けた茶碗に丁寧に粥を注いでやるのを、河原の岩に座りながらぼんやりと眺める。
こんなことをする理由が、俺にはやっぱり分からない。
都周辺で始まった世継ぎ問題を発端にした戦乱は、時間を経て沈静化するどころか泥沼化。そして時とともに地方へと飛び火していき、今や戦乱の火が及んでいない国を探すほうが難しい。日の本には60の国があると赤司は言っていたが、その全ての国で同じように毎日物乞いや行き倒れが生まれているのだ。
家を焼かれ、田畑を荒らされ、家族を殺されて…。
「…くん。青峰くん。…青峰くん?どうしたんです?終わりましたよ」
「っ?!あ、あぁ……わり」
いつの間にかあんなに集まっていた物乞いたちは居なくなっていて、疲れた表情のテツが不思議そうにこちらを見ていた。
最近、気を抜くとこうして物思いに耽ってしまう。物を考えるのはどちらかと言えば不得手なのに、それなら剣を握っていたほうがずっと好きなはずなのに。絡め取られるように深みにはまる思考は底無し沼のようで落ち着かない…自分が立っている場所すら、曖昧になる。
「行きましょう。途中で赤司くんに頼まれたものを買わないと」
こちらのことに気付いているのか、いないのか。
いつものように無表情に言うテツの声からは、それが分からなかった。
「おい、テツ……まだ買うのか?」
「はい、おつかいです」
赤司が注文していた履き物の受け取り、書状に使う上等の紙の巻物、替えの硯、おまけに味噌と塩…こんなもの、店に届けさせればいいのに、何を考えているのか赤司の命でその全てが俺の肩をずっしりと虐めている。
「次はあそこですね」
手に持った紙を見ながらテツが指差したのは酒と書かれた看板…これは何の虐めだよ?赤司のやつ、俺に恨みでも……一昨日、赤司の分の菓子を食ったの…まだ根に持ってんのか、あいつ。
酒屋へとスタスタ歩いていくテツの姿に、肩への更なる重さを想像してげっそりしていた、その時だった。
路地の向こう、破れた土塀の向こうから悲鳴が聞こえた。
「…青峰くん」
「止めとけよ。どうせ客取りの女だろ、下手にかかわったらこっちが危な……おいっ!こら、テツ!」
断続的に聞こえる声に面倒くさいとばかりに返すが、気付いた時にはテツが駆け出し破れた土塀をくぐっていた。
ったく、あの溢れんばかりの正義感はどこからくるんだよ?!
「おいっ!テツ、お前なぁ…っ?!」
テツの弱さをしっている手前、放っておくことも出来ず慌てて後を追いかける。荷物がつっかえて土塀を潜るのに苦労しながら何とか向こうへ行くと、予想以上の光景に息を飲む。
テツは殴られでもしたのか、口の端から血を流しながら地面に転がっていた。
「おいっ、大丈夫か?テツっ!」
「あ、ぉ…みねく…」
急いで駆け寄ると腹を押さえ呻きながらも、それ以外は無事らしい。
荷物をテツの傍に降ろすとゆっくり立ち上がる。俺の睨んだ、その向こうは…地獄だった。
そこは元は多少は名のある貴族の屋敷だったのか、赤司の屋敷には負けるが風情ある佇まいをしていた。
だが、打ち棄てられ、踏み荒らされ、荒れ果てていた。
既に板戸も障子もない、むき出しの座敷には、20人近い若い女たちが一塊に身を寄せ合って震えていた。声を殺しながら泣いている奴もいる。
それを足軽崩れのような格好の男たちが5人、下衆な笑みを浮かべながら取り囲んでいる。そこから少し離れた場所には、男たちよりは少しだけ身綺麗な恰幅のいい坊主頭の男がニタニタとした笑みを浮かべてこちらを見ていた。
--人攫いか。
ゆっくり腰を落として、腰のものに手をかける。
身体は怒りで燃えるように熱いのに、頭の芯はまるで冬の日の朝のように凍っている。
怒りというのは極限まで高まると頭を凍らせるのだと、初めて知った。
音が、遠い。と思った。
坊主野郎が何か叫んだが、何も聞こえなかった。
刀の血を払い、鞘に納める。
あれだけ怒りに身体が震えていたのに、一人も殺していないなんて…自分ですら信じられなかった。
「……青峰くん。腱を切ったんですね。よく、殺しませんでしたね」
よろけながらも立ち上がったテツに言われ、刀を握っていた手を思わず見つめる。ゆっくり顔を上げるが、このわけのわからない怒りも、気持ちも、思考も、何も言葉にはならなかった。
「取り敢えず、屋敷に戻りましょう。この人たちの仲間が来たりしたら大変ですから」
どこかぼんやりしている俺の背中をポンと叩いてから、テツは唖然としている女性たちに優しく声をかけた。
「みなさん、早く逃げてください。この人たちの仲間が来るかもしれません、注意して出来るだけ人が多い…ッ!」
そこで、テツの身体が横に吹っ飛ぶのを、俺は目を見開きながら見ていた。
丁寧に話していたテツの声は、最後まで聞かれることなく途切れ、突然飛び掛かってきた敵…ではなくて、女たちの中の一人に飛び付かれ、尻切れ状態になってしまった。
「怖かったー!助けてくれてありがとう!本当に、もうダメだと思った!もう、どこかに売られるんだと思って、私…」
高い声を張り上げながら、ぎゅうぎゅうに抱き付く力にテツは落ちる寸前になっていた。
「あ、ゴラッ!てめえ、何すんだよ!テツが死ぬっつーの!」
「あんたには用はないの!私は彼にお礼を…」
無理矢理引き剥がそうとするが、女は馬鹿力を発揮して更に抱き付く腕に力を込めた。本気でテツが失神しかけてきたことに気付き、力任せに引き剥がす。
きゃっ!なんてわざとらしくもしおらしい声を出して女が離れた時、手が当たったのか髪飾りが外れ女の長い髪がハラハラと背中に降りた。
嗅いだことのある、何だか懐かしい匂いがした。
何の匂いだっけと考えようと思った俺の頬を、女が振り下ろした掌がバチンッと音をたてた。
「いったいわね!女は大切に扱いなさいよ!全く……え、あれ?あなた、もしかして…大ちゃん?!」
意識を取り戻したテツが、女の声に驚いている。
そうだろうな、俺だって驚いてんだから。
俺の桃色の髪が、暮れゆく夕風にふわりと舞った。
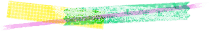
テツの朝は早い。
生臭坊主が幅をきかせ、己が利を増やすことや欲を満たすことに一生懸命になっている中で、テツはただ真っ直ぐに仏の道を生きているような男だ。
日も昇り切らぬうちに起きて沐浴を済ませ朝の修行を行うと、毎日町に出掛けていく。そして日がてっぺんに差し掛かる頃に帰ってくる。
たいていは黄瀬が用心棒と自称して着いていくが、黄瀬が赤司に用事を頼まれたりすれば別の奴がついていく。俺か、火神か。
長く続く戦乱で、千年の都と謳われた町は今や見る影もない。
絶えず何処かから煙があがり、道には物乞いが行き倒れ、追い剥ぎや夜盗が我が物顔で高笑いをしている。
それが、俺たちが暮らすこの国の中心、京の都の現状だ。
誰もが目を背けたくなる状況に、それでも、テツは目を逸らすことなく毎日、毎日飽きることなく町に通っている。
死した者に手を合わせて念仏を唱えて川原に葬り、その川原で行き倒れたもののために薄い、ほとんど水のような粥を炊いて配る。赤司に頼めば、テツが頼めば、莫大な援助をえられるだろうに。テツは首を左右に振り、商家や武家の家々を回っては施しを貰い、それを炊きだしている。
「熱いですから、ゆっくり食べてくださいね」
そう言いながらボロ雑巾のような物乞いが差し出した欠けた茶碗に丁寧に粥を注いでやるのを、河原の岩に座りながらぼんやりと眺める。
こんなことをする理由が、俺にはやっぱり分からない。
都周辺で始まった世継ぎ問題を発端にした戦乱は、時間を経て沈静化するどころか泥沼化。そして時とともに地方へと飛び火していき、今や戦乱の火が及んでいない国を探すほうが難しい。日の本には60の国があると赤司は言っていたが、その全ての国で同じように毎日物乞いや行き倒れが生まれているのだ。
家を焼かれ、田畑を荒らされ、家族を殺されて…。
「…くん。青峰くん。…青峰くん?どうしたんです?終わりましたよ」
「っ?!あ、あぁ……わり」
いつの間にかあんなに集まっていた物乞いたちは居なくなっていて、疲れた表情のテツが不思議そうにこちらを見ていた。
最近、気を抜くとこうして物思いに耽ってしまう。物を考えるのはどちらかと言えば不得手なのに、それなら剣を握っていたほうがずっと好きなはずなのに。絡め取られるように深みにはまる思考は底無し沼のようで落ち着かない…自分が立っている場所すら、曖昧になる。
「行きましょう。途中で赤司くんに頼まれたものを買わないと」
こちらのことに気付いているのか、いないのか。
いつものように無表情に言うテツの声からは、それが分からなかった。
「おい、テツ……まだ買うのか?」
「はい、おつかいです」
赤司が注文していた履き物の受け取り、書状に使う上等の紙の巻物、替えの硯、おまけに味噌と塩…こんなもの、店に届けさせればいいのに、何を考えているのか赤司の命でその全てが俺の肩をずっしりと虐めている。
「次はあそこですね」
手に持った紙を見ながらテツが指差したのは酒と書かれた看板…これは何の虐めだよ?赤司のやつ、俺に恨みでも……一昨日、赤司の分の菓子を食ったの…まだ根に持ってんのか、あいつ。
酒屋へとスタスタ歩いていくテツの姿に、肩への更なる重さを想像してげっそりしていた、その時だった。
路地の向こう、破れた土塀の向こうから悲鳴が聞こえた。
「…青峰くん」
「止めとけよ。どうせ客取りの女だろ、下手にかかわったらこっちが危な……おいっ!こら、テツ!」
断続的に聞こえる声に面倒くさいとばかりに返すが、気付いた時にはテツが駆け出し破れた土塀をくぐっていた。
ったく、あの溢れんばかりの正義感はどこからくるんだよ?!
「おいっ!テツ、お前なぁ…っ?!」
テツの弱さをしっている手前、放っておくことも出来ず慌てて後を追いかける。荷物がつっかえて土塀を潜るのに苦労しながら何とか向こうへ行くと、予想以上の光景に息を飲む。
テツは殴られでもしたのか、口の端から血を流しながら地面に転がっていた。
「おいっ、大丈夫か?テツっ!」
「あ、ぉ…みねく…」
急いで駆け寄ると腹を押さえ呻きながらも、それ以外は無事らしい。
荷物をテツの傍に降ろすとゆっくり立ち上がる。俺の睨んだ、その向こうは…地獄だった。
そこは元は多少は名のある貴族の屋敷だったのか、赤司の屋敷には負けるが風情ある佇まいをしていた。
だが、打ち棄てられ、踏み荒らされ、荒れ果てていた。
既に板戸も障子もない、むき出しの座敷には、20人近い若い女たちが一塊に身を寄せ合って震えていた。声を殺しながら泣いている奴もいる。
それを足軽崩れのような格好の男たちが5人、下衆な笑みを浮かべながら取り囲んでいる。そこから少し離れた場所には、男たちよりは少しだけ身綺麗な恰幅のいい坊主頭の男がニタニタとした笑みを浮かべてこちらを見ていた。
--人攫いか。
ゆっくり腰を落として、腰のものに手をかける。
身体は怒りで燃えるように熱いのに、頭の芯はまるで冬の日の朝のように凍っている。
怒りというのは極限まで高まると頭を凍らせるのだと、初めて知った。
音が、遠い。と思った。
坊主野郎が何か叫んだが、何も聞こえなかった。
刀の血を払い、鞘に納める。
あれだけ怒りに身体が震えていたのに、一人も殺していないなんて…自分ですら信じられなかった。
「……青峰くん。腱を切ったんですね。よく、殺しませんでしたね」
よろけながらも立ち上がったテツに言われ、刀を握っていた手を思わず見つめる。ゆっくり顔を上げるが、このわけのわからない怒りも、気持ちも、思考も、何も言葉にはならなかった。
「取り敢えず、屋敷に戻りましょう。この人たちの仲間が来たりしたら大変ですから」
どこかぼんやりしている俺の背中をポンと叩いてから、テツは唖然としている女性たちに優しく声をかけた。
「みなさん、早く逃げてください。この人たちの仲間が来るかもしれません、注意して出来るだけ人が多い…ッ!」
そこで、テツの身体が横に吹っ飛ぶのを、俺は目を見開きながら見ていた。
丁寧に話していたテツの声は、最後まで聞かれることなく途切れ、突然飛び掛かってきた敵…ではなくて、女たちの中の一人に飛び付かれ、尻切れ状態になってしまった。
「怖かったー!助けてくれてありがとう!本当に、もうダメだと思った!もう、どこかに売られるんだと思って、私…」
高い声を張り上げながら、ぎゅうぎゅうに抱き付く力にテツは落ちる寸前になっていた。
「あ、ゴラッ!てめえ、何すんだよ!テツが死ぬっつーの!」
「あんたには用はないの!私は彼にお礼を…」
無理矢理引き剥がそうとするが、女は馬鹿力を発揮して更に抱き付く腕に力を込めた。本気でテツが失神しかけてきたことに気付き、力任せに引き剥がす。
きゃっ!なんてわざとらしくもしおらしい声を出して女が離れた時、手が当たったのか髪飾りが外れ女の長い髪がハラハラと背中に降りた。
嗅いだことのある、何だか懐かしい匂いがした。
何の匂いだっけと考えようと思った俺の頬を、女が振り下ろした掌がバチンッと音をたてた。
「いったいわね!女は大切に扱いなさいよ!全く……え、あれ?あなた、もしかして…大ちゃん?!」
意識を取り戻したテツが、女の声に驚いている。
そうだろうな、俺だって驚いてんだから。
俺の桃色の髪が、暮れゆく夕風にふわりと舞った。
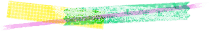
戻る