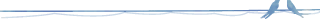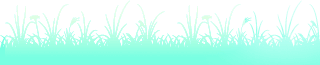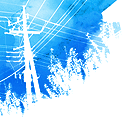
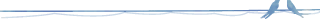
#お世話になっている
夢路あき さんに捧げます。
#リクエスト
「甘美の大人デザート」
そんなことを、今改めて実感するなんて最低だな。
自分で自分を笑ってしまう。
「……ごめんなさい。気持ちは、嬉しいっスけど」
「でもさ、お前らしょっちゅう喧嘩してんじゃん。青峰だってあんなだし…」
「うん…」
そうだよね、最近は…っていうか、付き合い始めてから普通の時よりも喧嘩してる時間のほうが長い気がする。まだ片想いの頃は、あんなに毎日一緒に笑い合っていたのにな。
「気付いてねーかもしんないけど…今もお前、ひでー顔してんぞ?そんなの、見てらんねーよ」
「火神っち……ごめん。それでも俺、青峰っちが好きなんス。どうしようもないくらい、大好きなんスよ。だから…火神っちとは、付き合えないっス」
出来るだけ笑顔になるように唇の端を上げる。
大丈夫、ちゃんと好きだよ。青峰っちが好きだよ。喧嘩ばかりでも、口が悪くても、なかなか会えなくても。声が聞けただけで、たった一言名前を呼んでもらえるだけで、その手が肌に触れただけで、やっぱり好きだって思うんだ。
火神っちはまだ納得してなさそうだったけど、最後にはくしゃくしゃと髪を撫でて「わかった」と言ってくれた。
はずだったんだけど。
まさか、今でも俺を好きだなんて。あれからもう3年近くたつのに…。
青峰っちが大学のチームの遠征で不在の週末。
黒子っちがてきぱきとまとめてしまった待ち合わせに従い、俺と火神っちは"お試しデート"をすることになってしまった。
デートの前の晩に眠れなかったなんて、いつぶりだろう。
日付が変わる頃には布団に入ったのに、妙にドキドキして眠れなかった。気付けば何度も無意味にスマホの履歴をチェックしてしまう…遠い地にいる青峰っちは、こんなことになってるなんて知るよしもないのに。俺は、何を期待してるんだろう。
悶々とした夜を過ごしていたはずなのに、ハッと気付いた時には完全に寝坊していた。すでに時計は待ち合わせの30分前を指していて、移動時間20分を除けばあと10分しかない危機的な状況だった。
今日の天気を見て服を決めようと思って、目覚まし時計を早めにセットしたのが完全に裏目に出てしまった。
いつもは素直な髪が何故か寝癖が取れない!
仕方なく頭からシャワーを浴びて適当に乾かし、天気も、最近の寒暖の差が激しい気温も無視してクローゼットの服を漁る。時計に急き立てられながら、この前撮影で着て買い取った全身トータルコーディネートの服を急いで着込む。
あぁ、もう!このスキニーパンツ!細身すぎて履くのに苦労する!
合う鞄を選ぶ余裕もなく、適当なトートバッグに必要なものを突っ込む。髪のセットの時間もない、これは帽子を被るしかないな。
ダッシュで走ったのに、予定よりも10分も遅れてしまい、乗り込んだ電車の中で深いため息が漏れる。せっかくのデートなのに…ずっと俺を好きでいてくれた火神っちとの、せっかくのデートなのに。
こんなの、火神っちを幻滅させちゃうかな。
「火神っち!ごめん、俺…ね、寝坊して…」
待ち合わせの駅前には既に火神っちがいて、慌てて駆け寄ると緊張していた顔をホッとした笑顔に変えた。
「時間ぴったりじゃん、そんな謝ることじゃねーだろ」
「あ、うん…そっスよね」
「おう。……えっと、どうする?行きたいところとかあるか?一応さ、その…デートプランつーの?考えてきたんだけど…」
ちらりと見れば、火神っちの目の下にはくっきりと隈が出来てしまっていた。
「デートプラン……そんなの俺、初めてっス…」
「えっ?!そ、そうなのか?いや、あの…」
俺の言葉に火神っちはわたわたと慌て始めた。自分が変なことを言ったと勘違いしたのかな。
「違うっス!初めてだから、嬉しいっス。それでいこ?今日は火神っちのデートプランで!」
俺のために寝ないで考えてくれたんだろうか、なんだか胸がくすぐったい。思わずふわりと笑うと、火神っちは音がしそうなほど真っ赤になった顔を隠すように歩き始めたから、俺は慌てて追い掛けた。
映画を見て、近くのカフェに入ってお茶をしながら感想を言い合った。
火神っちは派手目なハリウッド映画が好きだって前に言ってたけど、これを見ようと誘われたのは俺が見たいと思っていた史実を素にして描かれた有名なファッションデザイナーの一生を丁寧に描いたフランス映画だった。デザイナーが魂を込めたデザイン画、丁寧に作られるパターン、一針ずつ想いが込められた仕立て、そしてそれを纏う誇らしさ。華やかな本場のショーと、それと引き換えに魂を売り渡したデザイナーの苦悩と孤独。
この前仕事で一緒になったライターさんが試写会で見て絶賛していたから見てみたかったけど、見て正解だったと素直に思える素晴らしい映画だった。
そんな興奮冷めやらない俺のハイテンションな言葉を、珈琲を飲みながら火神っちは時々相槌を打ちながら聞いてくれた。これが青峰っちなら、うるせーとか、いつまで言ってんだとか、そのシーンの話は3回目じゃねーかとか、絶対言う。そんでまた喧嘩になる…俺は、青峰っちだからこそ聞いて欲しいのに。青峰っちがデザイナーにもファッションショーにも興味がないことなんか分かってる、それでも…好きな人にこそ、自分の好きなものの話を聞いて欲しいと思う。
そんなことが頭を過ってしまい、興奮気味に話していた俺の口はしおしおと力なく萎んでしまった。
「ん?黄瀬、どうした?」
「えっ…ううん、何でもないっス。ねぇ!次はどうする?」
そんな俺の変化に気付き心配そうに声をかけてくれた火神っちに、笑顔を向ける。かなり無理矢理笑ったけど、火神っちはくしゃりと髪を撫でてくれた。
「少しぶらぶらしようぜ?俺、見たいショップがあってさ」
「ん、いいっスよ」
また無理矢理笑顔を作る。表情を作るのなんか慣れっこだから何とも思わないけど…そういえば、デート中に表情を作るなんて随分久しぶりだな。いつも、青峰っちといると喧嘩ばっかりで、取り繕ったり無理に笑ったりしないし、表情なんか作らない剥きだしの、そのまんまの俺だから。
慣れているはずの"笑顔"の頬が、少しだけ引きつった気がした。
火神っちが行きたいと言ったショップは最近出来たらしくて、火神っちも俺も初めてだったけどセンスがいい服と雑貨が並んでいたし、店員さんも気さくで話しやすくてとてもいいお店だった。綺麗なカラーのストールが目に止まり、つい手が伸びてしまった。どれも手触りがいいし柄もシンプルで着回しに持って来い。うわぁ、迷うなぁ…何枚もある中から散々迷って2枚にまで絞ったけど、どちらにするか決められなくて。ずっと隣で火神っちが待っててくれるのも申し訳なくて余計にソワソワしてしまい、もういっそ買うのを止めようかとさえ思った。その時、火神っちがするりと片方を取ってレジへと向かってしまった。
「えっ、火神っち?」
「迷ってんだろ?こっちは俺が買うよ、まぁ、その…今日の記念?的な、プレゼント」
「っ…あ、ありがと」
思わぬことに、頬が熱くなった。
くそ、火神っちってば彼氏力すごいなぁ。青峰っちなら絶対こんなことしないし、そもそも俺が迷ってるのを待っててくれない。いつも俺にどこに行きたいか聞く癖に、見て回りたいお店に入ると10分もしないうちに暇そうに欠伸をしだす。終いには、長過ぎるから適当にブラついてくる、終わったら電話しろ。とか言って行ってしまうのだ。せっかくのデートなんだから、どっちが似合う?とか、俺だってやりたいのに。……まぁ、待ってられても"待たせてる"っていうのが申し訳なくて仕方なくて、買い物に身が入らなくなっちゃうんだけど。
同じ袋を2つ手に提げて、店を出る。向かった先は火神っちが調べてくれた、住宅街の片隅にある静かな雰囲気の創作イタリアンのお店だった。ランチ時を過ごす過ぎていることもあって、店内は思ったより空いていた。
「うわ、美味しそうっスね!」
「良かった。俺、こういう店とか分かんねーからさ。この店、雑誌とかメディアを一切断ってるから穴場なんだって。うちのサークルのマネージャーに聞いたんだ」
おすすめだというランチプレートは大きな四角いお皿に3種類のパスタにサラダ、マリネ、チキンの香草焼が少しずつ盛り付けられた可愛らしくて目に楽しいものだった。オーガニックだという野菜はどれも味が濃くて美味しい。パスタも、量がすくないけど色んな味を味わえて楽しいし。このお店はリピート決定だなぁと優しい味のマリネを頬張りながら思った。でも、飲み込んだ瞬間に思い出したのは、この前青峰っちと一緒に行った色が禿げた丸椅子が並ぶ、青峰っちの大学の先輩がバイトしている中華料理屋さんで食べた濃い味付けのザーサイサラダを思い出していた。床が染み付いた油でベタベタする狭くて古いお店は混んでいたし、出された中華丼は味が濃いし量も多かった。でも何故か、この優しい味付けのマリネよりも手が伸びてしまって、あんなに大盛りだったのをペロリと食べてしまっていた。先輩って人がおまけで出してくれた餃子も、昔ながらの少し焦げたもので…デートのはずなのに美味いぞと餃子を勧める青峰っちに呆れたけど、少し小さめで何個でも食べられる不思議な美味しさだった。
いつもは撮影とか体型を気にしてドカ食いを我慢してるし、野菜をたくさん食べたり味の濃いのを避けたりしてるから。あんな食事は青峰っちと食べに行くときばかり…だからかな、あの濃い味付けが頭から離れない。餃子を食べて美味しいと言った時の青峰っちの得意げな顔も一緒に…。
お皿が下げられて、代わりにテーブルに運ばれてきたのは、ランチプレートとセットになっていたデザートプレートとエスプレッソだった。俺たちの前にはティラミスがたくさんの果物と一緒に綺麗に盛り付けられている皿が置かれた。
パクッと一口頬張れば、本格的なマルカルポーネの味とほろ苦いカカオパウダーの味が口いっぱいに広がった。
甘いものが苦手なのだと言った火神っちと一緒に、本格的な味のティラミスを味わう。舌に残る仄かな苦味が癖になる味で美味しいけど…こんな味、青峰っちは苦手だろうな。苦いの、大嫌いだから。
ふと目を向けた先。
俺の隣の椅子には、さっきのお店で買った袋が2つ仲良く鎮座している。
片方には火神っちが買ってくれた、ワインレッド色の地に白とネープルスイエローの細いストライプ柄。もう片方には俺が買った鮮やかなレモンイエローとサファイアブルーの千鳥模様柄のストールがそれぞれ入っている。俺は、このストライプのストールを見る度に今日のことを思い出すのかな……どこにいても、何をしていても、何を食べても、青峰っちのことを思い出すみたいに。
「……黄瀬」
「ごめ…火神っち…」
パタッと小さな音がして、真っ白なテーブルクロスに涙が染み込んでいく。
黒子っち、この試みは失敗だよ。
どこにいても、何をしていても、何を食べても、俺の中には青峰っちがいる。息をするみたいな、瞬きをするみたいな自然さで、青峰っちを想ってしまう。
「……わかってた、最初から。だってお前、あいつの話してる時…すげー恋してるって顔してっからさ」
「ごめ…っ、火神っち」
「いいんだよ、俺は今日楽しかったから。ほら、食おうぜ?」
そう言って優しく笑う火神っちは、本当に大人だ。このティラミスみたいに。
火神っちとのデートは、まるで極上のデザートみたいだった。
甘い甘い、優しいデート。
ふわふわとした、優しいデート。
それはまるで、パティシエが作る極上のデザートみたいだ。
トロけるように甘くて、傷付いた心を癒してくれる。
ふんわりと心を満たしてくれる、優しい味。
嫌なことも、イライラも全てギュッと握り込んで噛み締めて、絶対にこの場には持ち込まない。だって、せっかくの甘い味が台無しになってしまうから。
to be continue.....
- 15 -