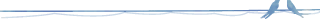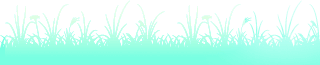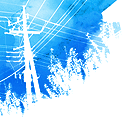
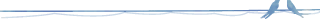
玲央の誘いにイエスと答えると、全くの予想外だったのか酷く驚いた顔をされた。
初めて名前を聞いた日から2週間後、僕は東京駅のホームにいた。
玲央が何気なく言った、どう?見に行ってみない?という言葉に、そうだね。と答えた結果だ。
取材名目で交通費その他は編集部が持つらしい。
僕の横には、まだ驚いた顔をしている玲央がいる。
「そんなに意外かい?」
「当たり前じゃない、征ちゃんが執筆に必要なこと以外に興味を持つだなんて…今日の秋田は雪でも降るんじゃないかしら」
心からの疑問を口にしながらまじまじと僕の顔を見つめる玲央に小さく肩をすくませただけにして、秋田行きの新幹線こまち7号に乗り込む。この電車なら、昼には秋田に着くだろう。
グリーン車の広めの座席に座り、パソコンを立ち上げるとまだ何か言いたげな玲央はもう話しかけてこなかった。
玲央と組んで仕事をするよいになって、もうすぐ2年。編集部内で鬼作家さま、天才作家さまなどと呼ばれているらしい僕の相手を、デビューした時から変わらず担当してくれている彼は、さすがに僕の扱いに慣れている。
でも、今回のこの小旅行は、さすがに驚いたらしい。当たり前だ、自分でも驚いているのだから。
初めての秋田は、どこまでも晴れ渡り心地よい風が吹き抜ける落ち着いた街だった。
天井の高い駅のエントランスも、そこを歩く人たちのゆったりした足取りも、僕が住む人ばかりが多い街とは違っていて、まるで違う世界に降り立ったような錯覚を覚えた。
すぐにお店へ行っても、平日の今日は昼休みの会社員で混雑しているだろう。そんな中お邪魔するわけにはいかないと、先に昼食を済ませてからゆっくりと店に向かう。他に目的がないから日帰りで十分だと言ったが、僕の予想外の発言が嬉しかった玲央が無理矢理一泊の予定を組んでしまった。目的の店を見学し、あわよくば担当者と話をする以外はすることがないのに…。
昼食を食べた和食レストランから店へ歩く途中、ふと玲央が持っている紙袋に目を止めた。
仕事の関係先に行くのだから菓子折りくらい持参するのは分かるが…如何せん数が多い。
「玲央、ちょっといいか。どうしてそんなに菓子折りを持っているんだ?」
「あぁ、コレ?小太郎に教わったのよ」
そもそも、あの奇妙なランキングに最初に気付いたのは、洛山出版社でこのエリアの営業を担当している玲央の同期だった。
今回の小旅行にも行きたがっていたようだがスケジュールがどうしても合わず、代わりにホテルの手配からオススメのレストランまで張り切ったらしい。
その中で出た話が、この菓子折りだというのだ。
「陽泉書房に行く時は、新商品や話題のお菓子を出来るだけたくさん持っていく。コレ、このエリアを担当している出版業界人には有名な話らしいわ」
「……いったい、どういうことなんだ?」
「さぁ…小太郎に聞いても行けば分かると一点張りで…」
首をひねるばかりの玲央と一緒に駅前を歩き、デパートに入りエスカレーターで上を目指す。
陽泉書房 中央店
フロアの半分もの面積を使う、広い売り場は清潔感がありながら落ち着いた色合いで統一されていた。
平日の昼過ぎ。昼休みのサラリーマンは会社に戻り、学生が現れるまではまだ時間がある。
店内は時間の拘束がない人たちが、のんびりと本を選ぶ穏やかな空気に満たされていた。
「征ちゃん、どうする?小太郎が取ってくれたアポまで少し時間あるけど…店内を見て回る?」
「そうだね、どんなお店なのか見てみようか」
「そうね。私も一回りしてくるわ」
じゃあね。と言って玲央は離れて行った。僕が文芸コーナーから見るのを知っていて、玲央は料理本のコーナーへと紙袋をさげたまま軽い足取りで歩いていく。それを見送ってから、ゆっくりと棚の間へ足を進めた。
落ち着いた店だ。
店の雰囲気もそうだが、なによりもそう思う理由は、並んでいる本にある。
どの本も、とても大切にされているのが分かる。選び方、並べ方、見せ方…。無数にある発行済み書籍の中から、売りたい本を選び、並べ、見せる。その一つ一つが丁寧で真摯だ。
でも、優しいだけじゃない。随所に強いほどの個性で読ませたい本が棚の片隅に鎮座している。
なるほどな、確かに面白い店だ。
「ね?紫原っち!この本は絶対にお薦めっス!」
棚の奥から、落ち着いた店内に似合わない騒がしい声が聞こえてきた。内容から察すれば、どこかの出版社か。
「えー、どうしようかなー」
妙に緩い話し方だ…余りに営業がしつこくて、暗に断っているのか。
棚の死角になっていて姿は見えないが、何故だか営業の方の姿が金色の毛並みをした大型犬とダブって想像出来てしまうのがおかしい。
「絶対にお薦め!前作と一緒に、今度キャンペーンを打つことにしたんスよ!表紙が綺麗だから、並べて展開すると素敵っス!」
「あー、確かにそうかもー。ん、わかったー。最初のを30冊、続編を50冊で注文入れといてー」
注文をした?断りきれなくて困っていたんじゃないのか…それにしては、冊数を言う声に迷いはなかったな…。
そんなことをぼんやり考えていたら、女性店員と一緒に玲央がやってきた。
「もう、征ちゃん!約束の時間よ?全然来ないから心配しちゃった」
「…あぁ、すまない」
女性店員に軽く挨拶して、文芸コーナーの担当者の所に案内してもらう。
店の奥へと進むと、先ほどから聞こえていた騒がしい声が近付いてきた。
「紫原さーん。洛山出版社の方がいらっしゃいましたよ?」
「んー?」
しゃがみこんで、ストッカーを覗き込んでいた二人が立ち上がる。
驚いた。
この身長なら、何かプロのスポーツ選手の方が向いてそうだな。
長身の分類に入るはずの隣に立つ玲央まで、二人に驚いている。
そこから素早く立ち直り、玲央は微笑みながら名刺を二枚取り出して不思議そうにこちらを見ている二人に渡した。
「こんにちは。洛山出版社で編集をやっております、実渕といいます」
「あ、はじめまして!俺、海常出版の黄瀬涼太です」
黄色い髪の男が慌てた様子で名刺を取り出した。
「洛山出版社ってことは…このエリアの担当者、葉山さんから変わったんスか?」
「あぁ、違うのよ。ちょっと用があって、今回は営業じゃなくて見学。ここの担当は小太郎よ」
玲央が営業スマイルで黄瀬となのった出版社の営業と話すのをぼんやりと見ていると、ふと視線を感じた。気付けば、先ほど女性店員に紫原と呼ばれていた男が、じっとこちらを見ていた。
穏やかな目だ。
静かで穏やかで、でも自己主張もしっかりと持っている目だ。
一目で、あの文芸コーナーの棚を作ったのがこの男だとわかった。
それが、僕と彼との出会いだった。
真っ直ぐにこちらを見ていた紫色の瞳は、すっと僅かに細められてから玲央へと逸らされた。
「あー、それ新発売のやつだしー」
目ざとく玲央が持っていた紙袋に目を止めたらしい。
黄瀬と名乗った男と話していた玲央がパッと笑顔になる。
「えぇ、テレビでも話題になってるみたい。これ、みなさんでどうぞ?」
ニコリと笑い、たくさんの紙袋をガサガサと全て紫原へと差し出す。
いや、明らかに数がおかしい。差し入れとか、そういうレベルじゃない。でも、紫原は分かりやすく表情を和らげて何の疑問も持たずに紙袋を全て受け取った。
「うわー、ありがとー」
「良かったっスねー、紫原っち!今日は千客万来で、お菓子食べ放題っスね!」
ニコリと黄瀬が笑う…どうなら、この状況はこのエリアの営業担当には日常らしい。あの、山のようなお菓子が…。
「じゃあ、俺はそろそろ失礼するっス!貰った注文と在庫の補充は、ちゃんと発注しておくっス!」
僕たちに遠慮したのか黄瀬は笑顔で鞄を肩に駆け直し、失礼します!と元気に言いながら去って行った。
「うん、またねー」
とやはり緩い口調で紫原は言うが、その目は完全に玲央が渡した紙袋の中身を物色することに夢中になっていた。
残された僕と玲央は、あれこれとお菓子を手に取っている紫原に完全に面食らってしまった。
「……えーと。紫原、さん?こちらのお店の文芸コーナーの担当者の方なのよね?」
「うん、そうだよー」
お菓子に意識を奪われたまま、のんびりした口調で答える。それを聞きながら玲央が心配そうにこちらをチラチラと見てくる。
僕が、彼にキレるのを心配しているんだろう。
迅速果断を座右の銘にする僕は、会話が滞ったり言い淀むような人間が何より嫌いだった。そういう人間と話すことは時間の無駄だとすら思っている。だから、僕のことは編集部ではまるで腫れ物扱いらしいのだが。
それなのに、不思議とこの男には苛立ちを感じない。
理由は簡単だ。緩く、間延びした口調で話しているが、決して言葉に詰まったり言い淀んだりしないからだ。むしろ、頭の回転の速ささえ伺える。
「小太郎からお話がいってるとは思うんだけど…こちら、赤司征十郎先生。こちらのお店で、とてもたくさん先生の著作を売ってくださってるみたいで。今日は先生と一緒に見学に来たの」
僕の反応を心配しながらも、玲央は今日の目的を笑顔とともに説明した。
そこで初めて、紫原はお菓子から目を上げてこちらに視線を向けてきた。
穏やかで、奥深くに強い自我を秘めた瞳が、僕を映した。
その時だ。
普段は僕が一人になった時にしか決して表に出てこないもう一人のオレが、コポリと音を立てたと思ったら前に出てきた。
初めてのことに、慌てて短く息を吸うと、あっという間にオレは心の奥へと再び潜っていった。
それは、僅か2、3秒の出来事だった。
それなのに。
じっとこちらを見ていた紫原は、表情一つ変えずにぽつりと呟いた。
「あのさー、あんたって赤司先生だけじゃなくて、アイオライト先生もだよねー?」
心の奥から、大きな泡がゴポッと溢れた。
「っ?!ち、ちょっと!何言ってるの?!そんなこと…」
「だってー、同じだしー。小説読んだ時から分かってたけどー」
「そ、そんなこと…」
玲央が真っ青になりながら口をパクパクしている。
驚きの余り、言葉が出ないんだろう。
こんなことが、あるんだろうか。
小説を読んだ時から、分かっていた?
僕がアイオライトだと、赤司征十郎がオレだと。気付く人間がいるなんて。
「せ、征ちゃん…」
あまりにきっぱり言う紫原に、オロオロしながら玲央が躊躇いがちに僕と紫原を交互に見ている。
だけど、僕は不思議なほど、気持ちがスッキリしていた。
そうか。オレは誰かに、気付いて欲しかったんだな。ここに、いる。確かにここに存在しているのだと。
静かに目を閉じて、ゆっくりと開く。左右の色が違うオッドアイだった瞳が、2つとも赤く染まる。
「紫原、ずっと会いたかったよ」
オレの言葉に、紫原は嬉しそうな笑顔で頷いた。
end.....
→正直に言います。
結末に迷いました。ものすごい迷いました…何だか不完全燃焼。
オレ司さまのペンネーム「アイオライト」は、赤ちんの誕生石から取りました。それを持っているとその人の能力を引き出す力があるらしいです。
得られる効果は「希望の光を得る。二人の愛を導く」らしいです。素敵っ。
- 7 -