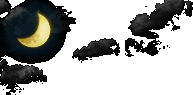
「随分たくさん貰ったね。」
バレンタインデーの帰り道、チョコらしきものが詰まった紙袋を下げて歩く幼なじみを見つけた。
「ああ、いつの間にかロッカーやら机やらに入ってたんだ。」
「ふーん。
ちょっとちょうだいよ。」
「だめだ。」
「え〜、けちっ。
そんなにあるのに独り占めする気?」
「義理でもなんでも、俺のためにくれたんだから、ちゃんと食べるのが礼儀ってもんだろ。」
仏頂面で言い放たれた言葉は、生真面目な堂上らしいもので、思わず吹き出してしまった。
「なんだ。
笑うとこか。
お前だってせっかくやったチョコを、違う奴が食べたら嫌だろ。」
眉間に皺を寄せて拗ねる堂上。
「そんなの言わなきゃわかんないけど、そういうバカ正直なとこ、堂上らしいよね。」
「バカは余分だ。」
いつものようにじゃれ合いながら、今日1日出したり引っ込めたりしていたものを、この勢いで渡してしまおうかと思ったその時、後ろから声が掛かった。
「堂上くん、ちょっと話があるの。」
振り返るとそこには学校一の美少女が立っていた。
「なんだ。」
相変わらず仏頂面の堂上にはにかみながらも、さりげなく棘のある視線を私に向ける美少女。
「……あっ、私先帰るねっ!」
私は何か言いたげな堂上に背を向け走り出した。
一刻も早くこの場を立ち去りたかった。
しばらく走って家の近くの公園に来ていた。
今頃、あの美少女と一緒にいるのかな。
あんな子に告白されて断る男なんていないよね。
あぁ〜あ、さっさと渡しておけば、とりあえず食べてはもらえたのにな。
もう必要ないから食べちゃおうかな。
昨夜、苦心の末完成した、自分のキャラには似合わない可愛らしいラッピングを解いて、初めて作ったチョコを見つめた。
少し歪なチョコを一つつまんで口に放り込んだ。
「おい、誰のチョコ食ってんだ?」
聞き覚えのある不機嫌な声に慌てて振り返る。
「ど、堂上?
なんでここに…。」
「…さすがにこんなに食べきれないから、お前に分けてやろうかと思って…探してたんだ。」
なぜか照れたように顔を背ける堂上に、私も頬が熱くなるのを感じて、慌てて言葉を探す。
「あ、あの子に告白されたんじゃないの?」
「ああ、されたな。」
「じゃ、じゃあなんで…?」
「何がだ。」
「なんで帰って来ちゃったの?
まさか断ったわけじゃないでしょ?」
堂上は私が驚いている意味がわからないのか、不思議そうな顔をしている。
「断ったに決まってるだろ。
それより、お前が食ってるそのチョコはなんだ。」
「こ、これは…。
お父さんにあげようと思って作ったら、ちょっと失敗しちゃったから、あ、あんたにあげようかなっと…思って…。」
我ながら苦しい言い訳に声が小さくなる。
「で、なんでお前が食ってるんだ。」
至極当然の質問に、私は益々どぎまぎする。
「そ、そんなに一杯もらってる奴に、これ以上あげなくてもいいかなって…。」
堂上が近付いてくる。
「いいから寄越せ。」
堂上が私の手の中のチョコをラッピングごと取り上げる。
「な、なんでよっ。
そんなにあるんだから私のなんていらないでしょ!」
堂上の顔がみるみる赤く染まっていく。
「お前のだからほしいんだろっ!阿呆!」
「はぁ?!
わけわかんなっ」
私の反論は遮られた。
堂上に抱き締められたことによって。
「ど、堂上?!」
「いい加減大人しくしろ。阿呆。」
いつもより低い声に毒気を抜かれて、私は堂上に体を預けた。
「俺が本当に欲しいのは、お前のチョコだけだ。」
「う…そ…。」
ずっと片思いだと思ってた。
勇気を出して作ったチョコをなんとか渡せたとしても、素直な想いを彼に届けることはできないと思ってた。
ましてや堂上がこんなこと言うなんて、夢にも思わなかった。
だから、ずっとこのままだと…。
「信じないなら…。」
ゆっくりと堂上の顔が近付いてきて、唇に柔らかいものが触れた。
「これで信じられるか。
俺が好きなのは絵里奈だけだ。」
うん、おいしい。
あの頃より上手になったチョコ。
あいつは喜んでくれるかな。
「ただいま。」
「おかえり。
はい、これ。」
「ありがとな。」
包みを受け取ると、堂上は絵里奈の腰を引き寄せ、深く口付けた。
「あの時と同じ…お前の唇は甘いな。」
end
- 118 -
戻る
