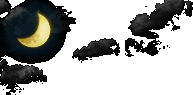
『運命』とはこういうことを言うんだろう。
隣で机に突っ伏している恋人をぼんやり見つめながら、私はそんなことを考えていた。
目の前では一人の女の子が、自らを救った王子様について熱く語っていた。
面接官達は皆笑いをかみ殺していた。
私は一人笑うことも、聞き流すこともできずに途方に暮れた。
あれから数ヶ月。
私はさらに途方に暮れることになった。
「笠原、腕下げんな!」
「笠原!!」
「笠原っ!」
彼が呼ぶ彼女の名前、何度聞いただろう。
「あのクソ教官っ、絶対あたしのこと目の敵にしてるって!」
あんなに彼に目をかけてもらってるのに、彼女は不満だらけのようだった。
彼に対する新人達の批評に苛立った。
彼のこと、何も知らないくせに……。
「村上?
先に来てたのか。」
食堂で私を見つけた彼と小牧くんが、同じテーブルにトレイを置き、彼は迷うことなく私の隣に座った。
「なんかあったか?」
どうやら彼は後ろのテーブルの新人達の話は聞いていなかったらしい。
「ん?なにが?」
「すごくこわーい顔してたよ。
鬼教官がもう一人いるかと思った。」
小牧くんは眉間に皺を寄せてみせて吹き出した。
「あぁ、ちょっと頭痛くて…。」
私の言い訳に彼が険しい顔になった。
「それなら午後からの訓練は休め。」
本当にこの人は心配症だ。
いつも私を最大限に気遣ってくれる。
いつも…そうだった。
これからもそうだろうか……。
「おい、絵里奈聞いてるか?」
「聞いてるよ。
でも、本当に大丈夫だよ。
だいたい私達は監督するだけでしょ。
堂上くんたら心配しすぎっ。」
「…だが、本当に無理するなよ。
辛くなったら俺に言うんだぞ。」
とことん心配症な彼に、私はまだ『思われている』という実感を噛み締めることができた。
午後からも相変わらず彼は彼女にかかりきりだ。
そんな2人を見ているのは辛かった。
堂上くん…私、辛い。
言えばきっとすごく心配してくれるよね。
でも、そうやって私は、2人が赤い糸を手繰り寄せるのを、邪魔してるだけなんだよね。
2人の再会が必然なら…これが運命なら、どんなに邪魔したって変わらない。
無駄な足掻きは虚しいばかり……。
それでも私は……たとえ虚しくても、見苦しくても、足掻き続けたい。
彼の傍にいたい。
ずっと……。
- 83 -
戻る
