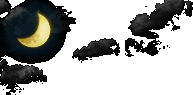
本当の気持ちをうやむやにしたまま、義理チョコを装った本命チョコを渡したのは何度目か。
今年も他の隊員達に買い出しを押し付けられた彼が、私へのお返しを渡してくれるのだろう。
義理だとわかっていても、少しでも私のことを考えて選んでくれるのなら、それだけで嬉しい。
でも、今年はそうもいかないと思うと溜め息が零れた。
「笠原っ!
お前は何度言ったらわかる!」
また始まった。
ホワイトデーのほんの少しの間だけでも、私のことだけを考えてくれているかもしれないというわずかな喜びを、この新人は見事に奪ってくれた。
きっと彼女の徳用チョコのお返しを考えるのに必死で、私のことなんて思考の外に追いやられているに違いない。
もう諦めなきゃ…。
大半の隊員が帰路につき、彼と彼女の言い合いがヒートアップするのをよそに、私はそそくさと帰り支度を済ませ、逃げるように事務室をあとにした。
外に出ると、もう3月だというのに、小雪が花びらのように舞い落ちていた。
そっと手に取ると、あっという間に溶けてしまった。
その儚さに自分の独りよがりな想いを重ねて、泣きたくなった。
「…寒い。
帰ろ。」
一人呟いて歩き出そうしたその時、ふわりと柔らかな感触を感じて立ち止まる。
「ちょうどよかったな。」
振り返ると、慌てて出てきたのか、上着も着ずに彼が立っていた。
そして、私の肩には桜色のストールが掛けられていた。
「堂上くん、これ…?」
彼は照れくさそうに頭をかきながら、ぶっきらぼうに答える。
「ホワイトデーのやつを頼まれて色々見に行ったら、それがお前に似合いそうな色だったからな。
で、これがみんなから。」
洋菓子のお店の紙袋を差し出す彼の耳が、ストールの色と同じ桜色で、私は思わず頬が緩むのを止められずにいた。
「ガラでもないと思ってるだろ。」
彼はふてくされたようにそっぽを向いた。
「確かに、堂上くんがこんなかわいいストールを選んでる姿は想像しにくいかも。
見る度に思い出し笑いしちゃいそう。
でも、嬉しい。ありがと。」
「ああ、ありがたく受け取っとけ。」
彼ははにかんだように微笑んでから、軽く片手を上げて庁舎に向かって歩き出した。
しばらくその後ろ姿を見送っていると、不意に彼が振り返った。
「それ、義理じゃないからな。」
end
- 128 -
戻る
