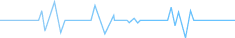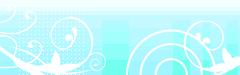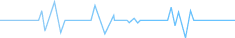
・・・・・・・・・・・・・・・・・
ぼくの頭の中は、まっしろになっていた。
目の前をながれている人のなみは、行ったりきたりせわしなくて、たぶん、止まることはずっとない。
ぼくは、その中に、ただ一人でとり残されてしまった。
そして、そのながれにさからうことも、泳いでわたることもできないで、た立ちつくしている。
どうしよう。
お母さまとはぐれてしまった。
しかも、初めてきた見知らぬばしょで。
波をつくっている道ゆく人たちはみんな自分たちの商いに夢中で、小さいぼくのことなんて見向きもしない。
助けてくれる人なんて、だれもいない。
ぼくは、ただじっと、泣くもんかと涙をこらえているしかできなかった。
今まで、お屋敷の中しか知らなかったぼくにとってのせかいは、こんなにもぼくに冷たい。
そんな、ただ、広いせかいの中で、ぼくは、ただひたすらひとりぼっちだった。
外のせかいが、こんなにこわくて冷たいところだったなんて。こんなところだと知っていたら、外に出たいだなんて思わなかった。
外に出たい、だなんて、おかしなおねがいなんてしてしまった、あのときの自分をしかってやりたい。
ただ、男子たるもの人前でなみだを見せてはいけません、という言いつけをまもらなければお母さまにしかられてしまうから、がんばってそれだけは守ろうと、ぼくは必死だった。
やっぱり、いつだってお母さまは正しかった。
外はこわいところだから、あなたを行かせるわけにはいかないのですよ、と、お母さまはぼくが外に行くことにずうっと反対していたけど、ぜったいに言いつけは守るから、と説得をして、ようやくつれてきてもらったのに。
あのとき、お母さまのいうことをよく聞いて、わがままなんていわなければこんなことにはならなかったのに。
自分のおろかさと、みじめさがゆるせない。
こんなんじゃ、鍾家の人間としてしっかくだ。
もしかしたら、こんなじぶんはもう、鍾家にはいらないのかもしれなかった。
だから、だれも助けに来てくれないし、それがとうぜんなのかもしれなかった。
ぼくが悪い子だったから・・・。
「どうしたんだ?」
うつむいたぼくの頭のうえで、声がした。
その声は、この人の波のなかでゆいいつ、ぼくにだけむけられたものだった。
声にうながされるようにして、そっと顔をあげると、そこにお星さまがいた。
そう、見えた。
でも、ほんとうにそこに立っていたのは、ひょろりと細くて、背がたかくて、黒いぼさぼさのかみのけをした、男の子だった。
からだも大きいし、すごく大人っぽいから、きっとぼくよりお兄ちゃんだろうと思った。
その子の着物は、すその部分がかわいそうなくらいぼろぼろになっていて、全部が黒くよごれていて、すごく汚いかっこうをしていた。背中には、やっぱりぼろぼろの、重そうなかごをせおっている。
でも、どろだらけの顔についている目の中は、天の川みたいにきらきらと輝いていて、ぼくはまぶしくって、そのお兄ちゃんの目をじっと見れなかった。
ぼくの目は、いつだって雨もようのくもり空だもの。
「君のような子供がこんな場所に一人か?見たところ、なにかを売りにきたようにも見えないが・・・」
お兄ちゃんは、ぼくのことを下から上までゆっくりと見て、ぼくののどのあたりで目をとめた。
「ひどいな」
ぼくは、ちょっとだけなんのことかわからなくて、でも、すぐに思い出して、首のところをあわてて服でかくした。
この、のどについた赤いわっかの跡は、誰にも見られてはいけませんよ、と、お母さまにきつく言われていたのに。
ぼくはもう、体の震えが止まらなかった。
見られてしまった。
見られてはいけません、といわれていたものを、しかも、知らないお兄ちゃんに。
こんなことがしられたら、ほんとうにお母さまを怒らせてしまう。
「どうした?寒いのか」
お兄ちゃんが、ぼくのあたまの上に手を置いた。
ぼくは、いつものとおりに。
「ごめんなさい、ぼくは悪い子です。ぼくのなかの悪い子をおいだすために、たくさん叩いてください」
「・・・なに?」
あたまを手に置かれるのは、これからたたきますよ、というあいずだ。
これをされたら、ぼくは懺悔の言葉をいって、だまってあたまをさしださなければならない。
きっと、このお兄ちゃんは、言いつけを守らなかったぼくをしかるために、お空からやってきたのに違いなかった。
そして、お兄ちゃんはこれから、ぼくに徹底的なばつを与えるんだ。
そう思ったぼくの予想は、けれど、おもいもしなかった形でうらぎられた。
「自分に、そんなことはできない」
お兄ちゃんはそう言って、ぼくを強くぎゅうっと抱きしめた。
ぼくよりずっとおおきなお兄ちゃんのからだはすごく温かくて、土のにおいがした。
ぼくは、もうわけがわからなくなってしまって、お兄ちゃんのするがまま、ぎゅうっと抱かれていた。
あたたかくなったからか、いつのまにか、さっきまでのふるえは止まっていた。
「ずいぶん、怖い思いをしたんだな。もう大丈夫だ」
「こわい・・・?」
「違うのか?」
よく、わからなかった。
お母さまはぼくを叩く。
悪いことをしたから、ちゃんと目を見てお話しないから、とくに、勉強でわからないところがあると、つよく叩かれる。
でも、書物を全部暗記しおわったときや、大人との議論で一番になったときは、すごくほめてくれる。
「あなたより優秀な子はいないわ、士季さま。あなたは、偉くなるために生まれた、選ばれた人間なのよ」
ぼくは、そんなお母さまが大好きで。
こわいことなんかなにもない。
そう、ぼくはお母さまが大好きなんだ。
そんなお母さまといつでもいっしょのぼくには、こわいこともなにもないはずなのに。
それでも、ぼくの目からは、いつのまにかなみだがずっと止まらなくなっていた。
必死に止めようとしたんだけどやっぱりだめで、たぶん、ぼくはこのままからだじゅうの水がなくなって、ひからびて死んじゃうんだと思った。
いつの間にか、ぼくたちの周りには人だかりができていた。
みなりの違う男の子ふたりが人ごみの中でぎゅうっとしていて、めだってしまったんだろう。
それでも、ぼくはかまわずに泣き続けていた。
どれくらい、そうしていたんだろうか。
人ごみをかきわけるようにして、鬼のような顔をした女の人が、ぼくたちの前にあわられた。
お母さまだった。
ぼくは、悲鳴にも似たお母さまのさけび声とともに、すごいいきおいでお兄ちゃんと引きはがされて、すぐに屋敷に連れ帰られた。
お母さまは、泣きながら、ぼくのからだを何度も、何度も、洗った。
お兄ちゃんを、たくさんのひどい言葉でののしりながら。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
妙な夢を見た。
夢というよりは、確かに体験した過去の記憶。だが、数十年経った今ではそれもすっかりかすんでしまって、現実ではないような気もしてくる。
こんな夢を見てしまうあたり、自分は疲れているのだろう。
かといって、しっかり身を休めに寝台に行くのもおっくうで、幕舎の机にけだるげにつっぷして、鍾会はまた目を閉じた。
もうすぐ戦が始まるというのに、こんな調子ではだめだということは分かってはいるのに。
うとうとと、幸せな怠惰に身をゆだねながら、鍾会はゆっくりと眠りに落ちていった。
ふわりと、背中になにか温かいものがかけられたことについては、気がつかないふりをして。
思い出すのは、あの土の香り。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マザコン鍾会が書きたかったのですが、
成人だと非常に気持ち悪かったのでショタに。
作業BGMはポップンのアンセムトランスこと
votum stellaumで。
- 6 -