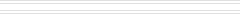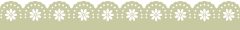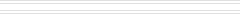
閣下が冷たいです注意
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最近、遠くに出かけることが多くなった。
これまでも、視察や貴族との会談などで外出する機会がなかったわけではないが、ここのところは目に見えて多い。落ち着いて部屋のベッドで休んだ記憶が、遠い昔のこととなりつつあるほどには。
団長自らの頻繁な遠出は一部から批判的な反応もあるが、それも、私の計画が新しい段階に進んだ証と思えば苦ではなかった。
新しい魔導器の実験を、監視の目が多い帝都で行うわけにはいかないのだから。
そして、そんな私の現状に、不審な目を向けるでもなく、一人傍観者のような顔をしている男が一人いた。
「また、お出かけですか」
「今日は戻らん。留守は任せる」
淡々と仕度をする私の後ろに立っているシュヴァーンは、声さえしなければそこに存在しているのかもわからないほどに、不気味に気配を殺していた。
ちらりと振り返ると、光の無い目でただじっとこちらを見つめている。それがまた不快感を増す。
今取り組んでいる魔導器実験は一日二日で終わるものではない。
結果を元に、現地の技師たちと検討を重ね、よりよい成果があがるものを作り上げるには、半月でも短いほどだった。
評議会を牽制するために丸一日留守にすることは少ないものの、昼間は実験地に身を置き、夜に帰還し執務をこなして朝にはまた戻る。そんなサイクルがここのところずっと続いていた。
団長はいつ寝ているのですか、と言われ、答えられずにいたら若い団員から「せめて夜間は休息を取られてください」と苦言を呈されてしまったが、実際、寝ていられないのだから仕方ない。
そんな私の留守中、帝都ににらみをきかせるのはこの男の仕事だ。
隊長首席、という身分もそうだが、なんだかんだで、この男が一番信用が置ける。
彼にはとうに思考というものが散逸している。命令を与えておけば、忠実に任務をこなし、自身で勝手に判断し勝手な行動を起こさないというだけで、ずいぶんと彼は優秀な道具だった。
全ての身支度を整え、私は身を翻した。
「では、行ってくる」
「アレクセイ様」
そっと、シュヴァーンが私の右腕をとった。
なにかとそちらを見ると、彼がなにやら私の腕に太い紐のようなものを巻きつけている。
その中心には魔導器のようなものがついていて、見ようによっては洒落た武装魔導器のように見えなくはない。
「なんだ、これは」
「無事の祈願、だとお思いください」
「まじない、か?女々しいな」
「私には、このくらいしかできませんから」
いそいそと紐を巻いていくシュヴァーンは、なにか甲斐甲斐しさすら見せる。
今まで、死んだ魚のような目をして何を考えているのかすら分からないほどに感情を見せることがなかった彼に、情緒と呼べるものが残っていたのは喜ばしくもあり、そして忌々しくもあった。
この男は、いつでも遅すぎる。
後手後手に回って、そしてようやく事態に追いついたときには、物事は全て決着を見ている。しかも極めて最低な形で。
私の腕にすっかり紐を巻きつけ終わると、彼はうやうやしく礼をした。
「どうぞ、道中お気を付けて」
実験地に着いて、私はシュヴァーンのことをすぐに忘れた。
今日初めて本格的に稼働させた新型が、予想以上に成果をあげた。
今回の魔導器の開発は特に簡単にいくものではないと覚悟はしていたが、当初の想像よりも極めてスムーズに事が進んでいくのはやはり気持ちがいい。
実験がすべて終了する頃には、辺りがほぼ壊滅的な状況になっていた。
立派に建っていた建築物も、草木も、ほとんど跡形もない。
これほどの破壊力があれば、私の夢がより近づく。
惜しむべくはその耐久性と連射力だが、それはこれから調整していくとしよう。
周囲になにもなくなった廃村は、どことなくすっきりとしていて私の高ぶる気分を落ち着かせた。
成果に満足して、まっさらになった大地に沈みかけている夕日をちらりと横目で見やった、その瞬間、激痛が走った。
最初は、どこが痛むのかすらわからないほどの強烈な、ほとんど衝撃に近いような痛み。
思わずうずくまってからようやく、右腕に血が溜まっていっているのを恐ろしいほどはっきりと感じた。
心配して近寄ってくる部下たちを制し、気分がすぐれないので少し休むとだけ告げて、実験用に建てられた小屋に駆け込んだ。
しっかりと設営された本部は別にあったが、そこまで行く力は残っていなかった。
喉の奥から、いや、体の奥から空気が漏れ、それが喉を震わせる。
右腕を締め付ける力は、どんどん強くなっていく一方だった。
みるみるうちに末端から血が失せていき、指から感覚が消えていく。
肘から上がそのまま心臓になってしまったかのように、血管が大きく鼓動するのが気持ち悪い。
なんなのだ、これは。
私はすぐに、ある可能性に思い当たった。
そして、あの時の自分のうかつさを激しく後悔した。
「至急帝都に戻る。あとは任せた」
よろよろとした足取りで外に出て、必死で叫び出しそうになる声を抑え、私は馬に飛び乗った。
鎧の音ががしゃがしゃと鳴る。
兵士が後ろで敬礼をしたようだが、私はそれすら目に入らなかった。
「シュヴァーン」
城にたどり着き、私は何にも目をくれずにシュヴァーンの部屋のドアを開けた。
どういうつもりだ、と尋ねる先にいるシュヴァーンは、なぜかなにも身につけておらず、寝台に気だるげに寝そべっていた。
彼には私がどうしてこんな夜中にここに来たのか、当然のように全て分かりきっているようであり、その顔には薄ら笑いすら浮かべているように見えた。
不思議なことに、いや、必然か、シュヴァーンの顔を見た瞬間に、腕の痛みは驚くべき早さで引いていき、もう痛みも何もない。
指先はしびれているものの、まだ動く。それだけが救いだった。
「それ、時間によって収縮するようになってるんです。日の入りから夜中にかけて、特に強く締め付けるようになっています。あとちょっと到着が遅かったら、腕は完全に壊死してたと思います」
「どういうつもりだね・・・」
「勘違いなさらないでください。別に私はあなたの身体を壊したいわけじゃありません」
「こんなもの・・」
「ああ、それ、外そうとすると爆発するようになっています。改造をお願いした技師はどうしてこんな機能をつけるのかと不思議がってました」
どうしてこんなことを、と語気を荒らげる前に、体がぐらりと傾いた。
服の端を強く引っ張られ、私はそのまま寝台に引き倒された。
シュヴァーンの体が近い。
離れようにも、肩を抑えられ、思うように身動きが取れないのが不覚だった。
「ここにお戻りになって、私を抱かれる時には外しますから。それとも、ここで私がこれを外して、一緒に木っ端微塵になりますか?」
「お前と心中だと?ごめんこうむる」
彼は惚けた顔で息をついて、私の青くうっ血した私の頬にそっとくちづけた。
その様子に虫酸が走り、感覚が戻ったばかりの右手で強く頬を張ると、彼は実に気持ちよさそうに嘆笑した。
「私は、心中でもよかったんですけどね」
- 34 -