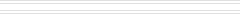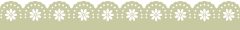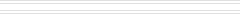
集団×シュヴァという描写があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「気をつけろ、前方に段差だ」
言うと、即座にぴたりと足が止まる。
しかし半歩ほど前に出ていた右足に重心を取られたのか、シュヴァーンの体がふらりとよろめいた。
手を引くと、以前より痩せた体はなんの抵抗もなくすんなりと腕の中におさまる。
「ありがとうございます」
頬を色づかせてかすかに息を上げているシュヴァーンの手をとって先導しながら、私は、無意識に足を急がせていた。
彼の顔を、極力見ないようにしながら。
以前命じた騎士団本部の改修工事は、ようやく終わったばかりだ。
朽化に伴う改装、というのが名目の大改装によって建物の中の段差がほとんどなくなって歩きやすくはなったものの、まだ一人にさせるには危なっかしい。
それに、段差を全てなくすというのは建物の構造上不可能だった。
団長権限を最大限使っても、限界はある。
そう言うと、愛しいこの部下は「大将が気にすることではありません」と、淡く微笑んだのだった。
その目にはなにも映していないはずなのに、お前の顔は目はじつに多方を向く。
一体どこを見ているのだ。
しかし実際に問い掛けることはない。
答えを聞くのが怖いだなど、思ってしまう私はどうにかしているのだ。
兆しは、あった。
二人で城内の廊下を歩いていると、若い団員とすれ違う。
団員は私達に敬礼し、去っていこうとする。
私は団員にねぎらいの言葉を一言かけ、シュヴァーンは私の隣でにこりと微笑む。
とたん、団員がぎょっとしたような顔をして慌てて去っていく。
そんなことが数度。
団員の顔は毎回違ったが、皆が同じような反応をする。
知り合いか?と尋ねると、シュヴァーンは、いいえ、と短く答えたあと、
「大将に気圧されてしまったのではないですか?」
と、楽しそうに言っていた。
団長がいきなり向こうから歩いてきたら、緊張くらいしますよ。大将は、そのあたりの自覚を持ったほうがいいです。
的を射た忠告に、私も思わず「そうか」と反省し、今後は若い団員に対しての接し方をもう少し考えるか、と、そんなのんきなことを思っていた。
天地が決定的に逆転してしまったのは、数日前のことだ。
信じられない、という絶望、私の中にあったのはただそれだけだった。
そうだったと、思いたい。
それは、まるで死肉にたかる魔物の群れのようだった。
何人もの人間がなにかに群がり、それは実に奇妙に複雑にうねうねと動く。
実に奇妙な光景。
「おい、早くこっちに回せ」
下品な声と粘液の擦れる音に混じって、甲高い声を上げていたのは、私がよく知る、いや、知りすぎている男だった。
「ったく、首席隊長サマがこんな名器だったなんてな」
「まったくだ。団長閣下とのうわさは、本当だったってことか」
いっそう激しく揺さぶられ、シュヴァーンが鋭い悲鳴を上げた。
持ち上げられた足が、これみよがしにびくびくと痙攣する。
果てたのだ、と知ったとき、私は剣を抜いた。
瞬間的に目の前が真っ白になっていて、自分がそのときなにをしたのかも鮮明には記憶していない。
気付いたときには、私は全身血まみれで、蹂躙者たちの赤に塗れながら、彼の眼を潰していた。
彼は全く抵抗しなかった。
むしろ、私の指が埋まっていくにしたがって、くつくつと笑い声のようなものを上げる様が実に気持ちが悪くて、私のほうが心が折れそうになった。
いったい何が楽しいというのだろうか、この状況で。
その違和感に甘え、そこでやめておけばよかったのかもしれない。
だが、私はそうしなかった。
彼は、こんな汚れきった自分の体など、見たくは無いに決まっている。
私は彼を救うのだ。
指が眼球に食い込むその瞬間に流れた涙は、悲しさのためではなかったように思う。
自分にもよくわからないのだ。今もなお。
完全に事が済んでから、
「見えない、見えない」
と壊れてしまったように繰り返すシュヴァーンは、実に気味が悪かった。
目を潰してから、彼は今まで以上に従順に、そして無邪気になった。
なにをなすにもままならない彼の介助が、私の恒常的な仕事の一部として加わった。
書類上では、私の魔導器実験に巻き込まれて光を失った、ということになっているので、監督責任をとるという形で私はシュヴァーンをいつもそばにおいておくことにしたのだ。
こうすれば、二度と彼が悲しい目に合うことは無い。
身の回りの世話、と、それ以上にそんな意味を多分に含んでいた。
いつでも私に手を引かれて歩くシュヴァーンはまるで子犬のようで、
「大将の手、握っていると安心するんです」
とうれしいことまで言ってくれる。
しばしば私は小動物でも飼っているような、そんな気分に陥った。
その日、私は会議が長引き、いつもより遅い時間に執務室を出た。
評議会連中の陰湿さにイライラしながらも、早くシュヴァーンの顔を見るために自然に足が速まる。
早く戻って安心させてやりたいのか、それとも、所有物を確認して自分が安心したいのか。
本当に、ペットでも飼っているかのようだ。
環境の変化にデリケートで、寂しいとすぐに死んでしまう、かわいらしいうさぎのような。
シュヴァーンの待つ自室のドアをあけると、部屋が明るかった。
早めに戻るつもりだったので、確かに、部屋を出るときに照明は消したはずだったのだが。
そのせいで、それははっきりと目の前に現れた。
あの日の続きが、そこにあった。
一人の男に抱きかかえられ、上の口で別の男のものを咥えているシュヴァーンは、実に楽しそうに腰を揺らし高らかに喘いでいた。
その手は二本とも横にいる男たちの男根をつかみ、それらを実に器用にしごいている。
ときおり、なにか懇願するように彼の口が動くのを、私はまるでガラス越しの部屋の出来事のようにただ見ていた。
「なにを、している」
ようやく絞り出した声は、小さく、かすれていた。
それでも、目の前で狂宴に熱中していた連中をこちらの世界へ引き戻すには、十分すぎた。
「だ、団長!これは・・」
今まで私の存在にも気づかずシュヴァーンを組み敷いていた者たちがあわただしく身なりを正し、シュヴァーンから離れて形式じみた礼をする。その姿はひどく滑稽だ。
それを無視して、私は裸体のまま放置されたシュヴァーンを抱き起こした。
シュヴァーンの体は下半身から髪の毛まで白い液体で汚れ、今までどのような仕打ちを受けていたのかが一目瞭然だった。
「シュヴァーン、どういうことだ?」
「・・・私が、大将の帰りを待っていたら、誰かが入ってきた気配がしました。誰だと尋ねると、急にのしかかられて・・」
とたん、どよめきが走る。
「違います、団長!誘ってきたのは、隊長で・・・。」
「なに?」
「その・・・巡回していたら、団長の部屋から叫び声のようなものが聞こえたのであわてて部屋に飛び込みました。鍵は開いておりませんでした。そうしたら、なにも身にまとっていないシュヴァーン隊長が、その、いきなり抱きついてきて・・・」
「どうか、お許しを、わたしたちは・・・」
ほとんど衝動的に剣を振り、言い訳を続けようとした騎士の首を飛ばした。
血しぶきが数滴シュヴァーンの頬にかかって、そこだけが映える。
情けない悲鳴を上げて逃げようとした残りも同じく首を刎ね、あたりにはむっとした臭いが立ち込めた。
こんな光景を、以前どこかで見た。
・・・ああ、そうだ、戦場だ。
「・・・みんな殺してしまったのですね」
感情が無い声で、まるで独り言のようにつぶやくシュヴァーンの首に剣先を突きつけながら、私は必死に震えを抑えて言った。
「シュヴァーン。この件に関して、真実を言え」
「・・私には、真実を捉える目がありません」
その声には、よどみも震えも無い。
これだけのど元の近くに突きつけられた剣にも、彼は一切おびえることはない。
見えないのだから、なにもかも。
私と間違えて他の騎士を誘うような真似をしたのも、
そのままやつらを受け入れたのも、
あんな痴態を演じることができたのも。
そう、すべては見えないせいなのだ。
私は手の力を全て抜いた。
じゅうたんの敷き詰められた柔らかな床に、剣がなんの音も立てずに落下する。
「私のせいか・・・?シュヴァーン」
私がお前の光を奪った。良かれと思って。それがお前のためになると信じて。
シュヴァーンが、そっと私の方に手を伸ばした。
手探りで私の体をあちこち触り、最終的にたどり着いた私の頬をそっとなでる。
その腕が絡みつくたびに、私の体が血糊でべたべたに汚れていく。
まとわりついた人間の臭いが、不快だった。
それでも、シュヴァーンは行為をやめることは無い。
自分が今どうなっているのか、わからないのだから。
「あなたは何も間違っていません」
だって、あなたは私の全部なんですよ。
あなたが間違ってしまったら、私はいったいどうしたらいいんですか?
「シュヴァーン・・・」
「大将、だいすきです」
大すき、だい好き、ダイスキ
一言一言、そのたびに私は縛られていく。
呪いのようにつぶやかれるその言葉に。
私もだ、私も、愛しているよ。
そう、愛しているんだ。
なにかを確かめるように絶叫して、私は彼の体を強く抱く。
シュヴァーンは、私に抱かれながら幸せそうに声を上げて笑っていた。
その左手は、すでに私の股間にそえられていた。
シュヴァーン、これだけは教えてくれないか。
私は、一体どこまで
お前を信じればいいのだ。
- 22 -