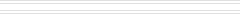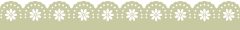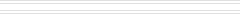
決して覗いてはいけないよ
覗いてしまったら、
傷つくのはあなたなんだからね。
その日、ユーリは神妙な面持ちでレイヴンの泊まっている部屋の前まで足を運んだ。
今日の宿は個室のため、いつもの大部屋なら聞こえてくるみんなの楽しそうな話し声はなく、辺りはしんと静まり返っていた。
レイヴンの様子が、前々からどうもおかしい。
そう初めて思ったのは、ザウデが崩壊して大きな災厄が世界を飲み込もうとし始めてしばらく経ってからのことだった。
気付いた最初は気分でも悪いのかと思って(このおっさんはとんでもない持病もちなので)しばらく観察していたが、どうやら顔色もよくそういうわけでもないらしい。
ユーリがが問いただすと、
「うんにゃ、なんにもないよー」
と、なんとも楽しそうな返事が返ってくるばかりだ。
なんにもない?
そんな馬鹿な、とユーリは思う。
どう見ても、そんな風ではなかった。
いくら彼の行動がいちいちおちゃらけているからといって、なにもない宙を見上げながら薄笑いを浮かべているなんて、どう見てもおかしい。
それが、このところ頻繁だ。
宿に着いてみんなと別れ、自由行動になってからも、彼の足取りはいつもよりやけにふらふらしていて頼りない。
まるで、なにかに操られて、自分の意思とは関係なしに歩いているみたいだ。
「疲れたからこのまま寝るわ。あ、最近寝付き悪いから部屋入らないでね」
と言い残して、そのまま彼は一直線に部屋に向かったきり、夕飯にも顔を見せなかった。
・・・やはりあいつのことだろうか、とユーリは思う。
かつての騎士団長にして、彼を道具のように扱ってきたあの男。
きっぱり決別したと本人が言っているとはいえ、あんな死に様を目の前で見て、さすがにこたえているのかもしれない。
もしそうなら、なんのために俺たちがいるんだよ、とやるせない気持ちが、ユーリをここまで連れてきたようなものだ。
もう夜も遅い。
訪ねるなら今のうちにしないと、寝つきの悪いおっさんがまたブツブツ文句を言ってくるに違いない。
ふう、と小さく息を吐き、ドアノブにそっと手をかけたそのとき、ユーリは背中に突然悪寒が走るのを感じた。
なにやら嫌な予感がする。
自分のこういう予感は妙によく当たるから、なおさら不安な気持ちになる。
らしくない、とは思いながらも、この気持ちを無視するわけにはいかなかった。
本当は、扉をすぐにでもドアを大きく開けて中に入りたかったのだが、それがなんとなく出来ない。
ユーリは、少しだけドアを開けた。
開かれた扉の隙間から、ほんのり淡い明かりが漏れた。
かすかだが、妙な臭いも漂ってくる。
一体何だ・・?
好奇心に駆られ、ユーリはその隙間からそっと中を覗き見た。
そこには何かが、横たわっているのだか座っているのだか分からない姿勢で、ベッドにあった。
光が少なすぎてよくわからないが、おぼろげながら人影であろうとわかる。
もっとよく見ようと目を細めた、その瞬間、ユーリはすさまじい吐き気に襲われた。
火明かりに浮かび上がったそれ。
寝台で、不自然にだらりと首を下に折り曲げている「モノ」
あれは、ザウデで自分が殺した・・
間違いない、あれは確かに「アレクセイ」だ。
だが、それはもはや人間の形を半分失っていた。
アレクセイと分かったのは、あの特徴的な鎧姿と、かろうじて顔面の形状が元のままをとどめていたから。
不自然なくらいにやつれきって、まるで骸骨のような体になっているそれの皮膚は変色し、黒ずんで、なにやら白くなった表面が不気味に波打っている。
波打っている・・・?
と不思議に思い、その正体が無数の蛆だと分かった時、さすがのユーリもめまいで倒れそうになった。
あまりに数が増えすぎて居場所から追い出されたそれらが、ぼたぼたと下へこぼれ落ちているのが遠目にも分かる。
その姿はまるで、地獄の底からむりやり引っ張り出してきたようだった。
しかし、そんな地獄からよみがえったようなアレクセイの姿すらどうでもよく思えるような光景が、そこにはあった。
その、アレクセイの下にはもう一人いた。
気色の悪いものに組み敷かれてなお反抗しているようすも見せず、むしろうっとりとした様子で受け入れている人は・・・。
「お、っさん・・・」
無意識に、ユーリは声に出していた。
それは、あまりに汚濁にまみれて、そして淫靡な光景だった。
彼は、死人に抱かれていた。
アレクセイの腐った体は、二人が動きあうたびに、いちいち、ぐちゅり、と音を立てる。
それと合わさって、粘液と粘液が擦れあうひどく不快な音が、荒い息遣いが、耳の奥でわんわんと響く。
自分の耳が、目が、信じられない。
コレは間違いだ、と思いたい。
いや、そうでなくてなんだというんだ。
「おっさん!?おい、なにやってんだよ!」
ドアを開け、絡み合う二人へ駆け寄った。
だが、ユーリの声は、レイヴンの笑い声とも泣き声ともつかないものにかき消された。
おびただしい数の蛆と血にまみれながら、
レイヴンは楽しそうな声を上げて笑っていた。
声は、突然淫らな喘ぎ声になり、悲鳴になり、歓声になった。
それにあわせるように、上のアレクセイの体が大きく揺れた。
レイヴンの体もべったりとした赤にまみれ、まるで彼自身が血を流しているかのようだ。
それ以上、見ても聞いていられなかった。
こんなもの、この世のものではない。
・・・腐臭が強い。
強い。
「おっさん!」
ユーリの必死の呼びかけに、レイヴンはたったいまその存在に気づいたようにこちらを見た。
「せいねん・・?なんだ。いたんだ」
レイヴンは、にやりと笑った。
「すごいだろ、うそみたいだよな。でも、ほんとなんだよ、これ。」
そう言って、愛おしそうに自分の上に乗っているものの頬をなでるようにすると、すぐにドロドロとしたものがそこから溢れ、レイヴンの顔を汚した。
レイヴンは、恍惚の表情を浮かべ、そっと
自分の前を開いて見せた。
この状態で、なおも生々しいそれが、彼の上で脈打っている。
中途半端に挿入されたアレクセイのものは、深く入れ物を求めて根元がびくびくとふるえていた。
「ごめんねえ、おれ、せいねんも、だいすきだけど、やっぱりこのひとじゃなきゃあ・・・」
それ以上は、言葉になっていなかった。
アレクセイが結合を深くしたのだろう、レイヴンの体が反動で大きくしなる。
「ひっ、あ、あれくせいさまぁ、ごめんなさ・・っ、わたしにはあなただけ、あなただけですから・・・!」
粘液を直に犯されたレイヴンが、甲高い悲鳴を上げた。
これは、これは一体、どういうことだ?
ザウデで死んだはずのアレクセイがドロドロになって蘇っておっさんを犯して俺に見せ付けてこうしておっさんをよがらせて俺に見せ付けて・・・。
一体、何の冗談なんだ!
『私の道具は、返してもらったよ、ローウェルくん』
聞こえないはずのアレクセイの声が、言葉が、頭の中で炸裂した。
ユーリはそのまま、意識を失った。
目覚めた時、ユーリは自分の部屋のベッドの上にいた。
わけも分からず突然現実に引き戻されたユーリの眼に飛び込んできたのは、
心配そうに、というよりはからかうような顔でこちらを見つめているレイヴンだった。
「どうした、青年。妙な声出してうめいちゃって
「お、おっさん・・・?」
「おたく、俺の部屋の前で気を失ってたのよ。」
なんか怖いもんでも見たの?といつもの調子で言うレイヴンに、ユーリはいささか拍子抜けした。
「おっさん・・」
「なんだよ?」
「いや、なんでもねえ」
そうじゃなきゃ、耐えられるかよ。
そう一人心の中でつぶやいて強引に抱き寄せたレイヴンの体からは、かすかに自分の知らない臭いがした。
- 8 -