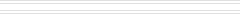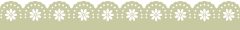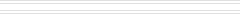
こういう雰囲気は、ついついぼんやりしてしまう。
窓からぼうっと夜空を眺めていたレイヴンは、ふっと一言こう言った。
「今日は星が綺麗だねえ」
一瞬の沈黙が周囲を支配した。
そして、すぐにくすくすという笑い声が低く響く。
その笑い声の元を、レイヴンは不服気ににらみつけた。
「なんかおっさん、おかしいこと言った?」
「いや、なんか似合わねえな、と思って」
あー、おかしい、とわざとらしく言う青年・ユーリの顔は、意地悪い笑いを浮かべていた。
レイヴンは、小さくため息をついた。
そこまで大げさにすることは無いでしょうよ。
たしかに少し、らしくはなかったけどね・・。
そう思いながらも、ユーリの遠慮ない笑い声を聞いているうちに、レイヴンもどんどん顔が熱くなっていくのを感じた。
「そんなに笑わなくたっていいじゃないの」
「いやー、悪い、止まらなくてさ」
ユーリはようやく笑いの波から開放されたのか、窓辺の自分の横にひょいと身を置いてきた。
だが、顔はまだにやけている。
「おっさん、そんなに星が似合わないって?」
「違うよ。むくれんな、おっさん」
いや、絶対図星だ。
なんだか癪に障って、困ったように微笑むユーリの顔を無視して、顔をそらし、もう一度窓の方を向いてみる。
空の星は、自分たちのいざこざなんて関係ないといわんばかりに自分たちの光をそれぞれ存分に誇って光り輝いていた。
その様子が、なんだかうらやましくもある。
「どーせ、俺様には星なんて似合いませんよ」
「そんなことないって。星が好きって、いい趣味じゃねえか。・・それにさ」
ぐい、と無理やり体を反転させられた。
「俺も、こんなに綺麗な星をいつも愛でてるわけだしな」
しばしそのまま見つめあい、二人は同時に噴き出して笑った。
「うわ、青年、寒っ」
「んだよ、おっさんがらしくねえからだろ」
「なに、おっさんのせいにするわけ?」
「それに俺、本当のこと言っただけだしな」
・・・俺は星か。
レイヴンは小さな声でつぶやいた。
太陽のような人が、よく言うよね。
- 7 -