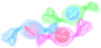二足の靴下が、並んでちょこんと置いてある。
その中には、「サンタさんへ」と書かれた手書きの手紙がきちんとたたまれて入れてあった。
確か一週間ほど前、二人で仲良さそうにわいわい言いながらなにやら書いていたっけ。
と、そこまでならほほえましい光景だが、その手紙の内容を読んだその家のサンタさんは、凍りついた。
『KKを』『スモークおじちゃんを』
【ください】
「・・・靴下に入んねえだろ」
はあ、と深いため息をついて、サンタさん・・・KKは手紙を閉じた。
どうしろと言うんだろう、こいつらは。
こんな欲望丸出しなお願い事、本物のサンタさんも引きつり笑いで逃げ出すだろう。
そして、そのプレゼントを一体どうするというんだろう・・。
そこまで思って、KKは考えることをやめた。
恐ろしい想像図しか出てこない。
「あんなこと言わなきゃよかったな」
今年は給料がよかったから、今年くらいはなんでもサンタさんにお願いしたら叶えてくれるかもな。
なんて、ファンシーなこと言ったのが間違いだったのかもしれない。
ガラに合わないことはするもんじゃないな、と反省したってもう遅いが。
とりあえずスモークはムリだ。
今ここにいないし、多分、言ったとしたっておとなしくプレゼントになってはくれない。
KKは自分の部屋に戻って、ざっとこんな内容の手紙を書いた。
【スモークおじちゃんは部屋から出てこない人なので、サンタさんも連れてくることができません】
その手紙を手に寝室に戻り、なおも寝息を立てている二人の枕もとの、片方にそれを入れる。
とりあえず納得してくれることを祈って。
「さて。」
もう一つ、どうしようか。
別に知らん顔してしまっても。「サンタさんに人間をお願いするな」くらい言ってやってもいいんだけど。
なんとなくそんなことはしたくない。一つくらいは。
こんなこと、らしくないのかもしれないけど。
今日が、神様の誕生日、という名目の日だからかもしれない。
KKは、そっと二人の寝ている布団にもぐりこんだ。
二人の体温が、やわらかい温かさがじんわりと伝わってきて、ふわりと眠気が全身を包む。
「・・・これでカンベンな」
朝起きたら、どんな顔をするのだろう。
そんなことを想像してちょっと楽しくなりながら、KKは優しい睡魔に身を任せた。
- 22 -