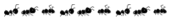パーティーデビュー
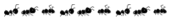
「そろそろ末の弟君もパーティーに連れてきたらどうだ?」
「ご冗談を。末弟はまだ子供ですよ」
とあるパーティー会場でスコットはシャンパングラスを片手に隣の紳士に微笑んだ。
今日は父親の会社代表として財界のパーティーに出席している。隣の紳士は父親と旧知の仲であり、スコットのことも末っ子のアランのことも知っていた。
「幾つになる?」
「14歳です」
「それで子供扱いか。君が14歳の頃はパーティー会場で大人顔負けに振る舞っていたじゃないか」
紳士は楽しげに低い声で笑う。
言われてみればスコットが14歳の頃は父親に連れられ色々な会場に顔を出していた。それを思い出すとスコットは困ったようにシャンパンを飲み干した。
今までもペネロープが主催するようなパーティーにはアランも参加したことがある。ただそれは兄弟全員参加であり、今日のような場はまだ早いのではと思ってしまうのだ。
「子供子供と思っていても本人はしっかりしているものだぞ。ジェフの息子なら特にな」
紳士はスコットの肩を叩くと、その場を離れる。
「考えておきます」
スコットが紳士の背中に声をかければ、軽く手を挙げて紳士が応えた。
いつかはアランも1人でパーティーに参加するだろうが、それはまだまだ先の話だと思っていた。しかし客観的にはそうでは無いらしい。今日の紳士との会話は家に帰ってからもスコットの頭の片隅に引っかかっていた。
(一緒に連れていくべきか?)
明るく社交的で愛され型のアランならパーティー会場でも物怖じしないで溶け込むだろう。スコットが一緒なら変な輩も近づいて来ない。ただ、
(縁談を持ち込まれそうなんだよな…)
トレーシー家の末っ子で家柄、見た目、立ち振舞い、社交性、将来性も申し分ないとくれば近い年齢の娘をもつ親が近づいてくること間違いない。アランがついウッカリ「喜んで」と言おうものなら大変なことになるだろう。あの無邪気な末っ子なら場の空気に圧されて言いかねないなと思う。
その点ゴードンはあしらい方が絶妙で心配はしてないのだが。
スコットがジャケットを脱ぎならがラウンジに戻ると、そこには噂のアランが大きなモニターでシューティングゲームに興じている真っ最中だった。
「スコット、おかえり!早かったね」
チラリと視線をスコットに向けると直ぐにモニターに集中する。最終面なのだろう。縦横無尽に飛んでくるミサイルをアランは見事に避けていた。
流石に兄弟の中でも特出した動体視力の持ち主だ。それを使うのがシューティングゲームというのに苦笑いしながらもスコットは後ろからアランの操作を眺めた。
「早いか?いつもこんな感じだろ」
「ゴードンが朝になるんじゃないかって言ってたから。お持ち帰りがどうとか。お持ち帰りってピザでも買ってきたの?」
アランは期待に満ちた目でスコットを一瞬だけ振り返るが、スコットが手ぶらなのを見ると残念そうに視線を戻した。スコットは僅かに頬をひきつらせる。本当にあの弟は余計なことしか言わないな、と思いながら。
「アラン、それが終わったら僕の部屋に来てくれ」
スコットの意外な言葉にアランはゲームを止めると体ごとスコットを振り返った。部屋に呼び出されるなんて滅多にない。アランは不安そうに視線を揺らした。
「えー…僕何か怒られることした?」
「心当たりがあるのか?」
「でもアレはゴードンがやったのを見てただけだよ!」
「おい、何の話だ」
「だからスコットのデスクにおばあちゃんのクッキーを入れた話………あ!勝手に生ハム食べた方?それともバスルーム…」
思いがけない話が次々と出てくることにスコットは頭を抱えた。デスクにおばあちゃんのクッキー?最近部屋で異臭がすると思っていたのだ。それだけは早急に片付けないと。バスルームとは?
アランをパーティーに連れていく以前に解決しないといけないことが山積みでスコットは「続きは部屋で聞く」と立ち上がった。
アランは叱られるのを嫌がる子犬のようにソワソワとスコットの後に続いた。
※※※※※
キラキラと彩られたパーティー会場に一歩入るとアランは圧倒されたように会場を見渡した。
豪華なシャンデリアに柔らかな絨毯、華やかなドレスに賑やかな談笑の声。白いテーブルクロスが掛けられたテーブルの上には豪華でお洒落な料理が並んでいる。
見える範囲では自分が最年少なことにアランは戸惑ったように隣のスコットを見上げた。
「僕が隣にいるから安心しろ」
真新しく着なれないスーツに身を包み、まるで捨てられた子犬のような瞳で見られたスコットは笑いを噛み殺してアランの背中を叩いた。
「やぁ、スコット」
後ろから掛けられた声に振り向けば先日の紳士が微笑みながら立っていた。
「早速連れて来たのかい?」
「紹介します。末弟のアランです」
スコットに促されるとアランの肩が緊張で微かに跳ねた。
「久しぶりだ。こんなに大きくなって」
紳士は感慨深そうにアランの手を握った。
「えーっと…お久しぶりです」
語尾にクエスチョンマークを付けながら言えば、「私が君に会った時は君は赤ん坊だったからな」と紳士は懐かしむように目を細めた。
「時が経つのは早いものだ。今日が君にとっていい思い出になるよう祈っているよ」
紳士が言えばアランも嬉しそうに「ありがとうございます!」と返した。
「優しい人だね」
パーティーも楽しいじゃないかとアランが思っているとスコットが「気を抜くな。ここからが大変だぞ」と周囲の視線を気にしながらアランにだけ聞こえるように囁いた。
「…疲れた。トイレ行ってくる」
「アラン、そんな顔をするな。常に見られてると思え」
紳士と別れてから始まった怒濤の時間。
トレーシー家の末っ子が来ていると噂はあっという間に広がり、スコットとアランは休む暇なく対応に追われていた。
「はじめまして。アラン・トレーシーです」
まるで壊れた人形のように何度同じセリフを口にしただろう。スコットが相手の紹介をしてくれるが、同じ話に同じ様な服装が続くと顔すら同じに見えてアランの頭を混乱させた。
「弟君には婚約者はいるのかね」
「うちの娘に会ってみないか」
「ホームパーティーに来て欲しい」
そんな質問も何度も飛び交い、その都度スコットが壁となりアランを守っていた。
ようやく僅かな隙間時間を見つけるとアランはパーティー会場を抜け出した。
しかし会場出口に行くまでにも先程挨拶した人々に呼び止められる。失礼にならないように疲れた顔を消して笑顔で対応するアランをスコットは心配と頼もしそうな気持ちが半々な視線で眺めていた。
トイレの個室に避難したアランは疲れきったようにしゃがみこんだ。
普段の島での生活では考えられない程の人と会い、話をした。愛想笑いで固まった頬を擦りながらアランは改めてスコットを尊敬する。あれだけの人数の顔と名前を一致させるだけでなく、前回話した内容までも覚えているのだ。自分がいるからだけでなく、人がスコットの周りに集まってくる理由が何となくわかった気がした。
「何時に終わるのかな…」
会場に戻れば質問攻めの続きが始まるだろう。目の前には美味しそうな料理が並んでいるにも関わらず、アランはまだ一口も食べられていなかった。
「お腹空いたなぁ…」
出掛けにゴードンが何か食べていった方がいいと言ったのを「パーティーだよ!ご馳走あるからお腹空かせていかないと!」と断ったのが悔やまれる。きっとゴードンはこうなることを予想していたのだろう。
そろそろ戻らないと心配される。
アランが個室から出るのと入れ違うように1人の男が隣の個室に入っていった。アランに気づくと男は慌てて顔を背け、手にしていたものをポケットに隠す。ほんの一瞬であったがアランはそれがナイフだと気づいた。
男が隣の個室の鍵を閉めるのを確認するとアランは足音を殺してトイレを飛び出した。
「スコット!」
アランはパーティー会場に戻ると見知らぬ夫妻と談笑するスコットの腕を引っ張ってスコットの耳に口を寄せた。
「アラン、不作法だぞ」
スコットは嗜めるが、アランが「緊張事態だ」と囁けばスコットは「わかった」と詳細を聞き返すことなく短く応えた。
「失礼。少し問題が起こりまして。続きはまた今度聞かせてください」
夫妻に穏やかに詫びるとスコットはアランを促してその場を離れる。
人がいないテラスで「どうした?」と尋ねればアランはトイレでの出来事を話した。アランがナイフを見たと言うのなら確かにナイフを持っていたのだろう。アランの動体視力を疑うことなくスコットが頷けばアランはホッとしたように息を吐いた。
「アラン、その男の顔は覚えているか?」
「もちろん」
一瞬ではあったが間違えることはない。
レスキュー中に見せるアランの1人前のiRの顔を頼もしく思い、スコットの顔に場違いな笑みが浮かんだ。
「行くぞ。その男を探すんだ」
「FAB!」
スコットとアランはテラスからパーティー会場へと戻った。
「スコット、いた!」
アランの緊迫した声にスコットが振り返れば、そこにはパーティー会場を早足で歩く男がいた。姿格好は招待客のように整っているが纏う雰囲気はパーティーを楽しむそれではない。男の行く手には恰幅のいい1人の男性がいる。それが男のターゲットだと直感したスコットは急いで恰幅のいい男性に向けて走った。しかし人が多く思うように距離が縮まらない。このままでは間に合わない。
(仕方ない…)
スコットは恰幅のいい男性の近くにあるテーブルのテーブルクロスを掴むと思い切り引っ張った。
テーブルクロスが乱暴に引かれ上に乗っていた料理や取り皿が音を立てて床に落ちる。
飛び散る料理に割れる食器。
どよめきと悲鳴と視線が一帯に集まった。
「アラン!誤魔化しといてくれ!」
「誤魔化……えぇ?!」
アランの上擦った声を無視してスコットは騒ぎのどさくさに紛れて逃げようとしていた不審な男の腕を掴んでいた。
男はスコットの手を振り払おうとするが、一流のレスキュー隊員であるスコットに敵うはずがない。周囲の招待客に気づかれないように会場の外まで連れ出すと警備員を呼ぶように会場スタッフに言った。
※※※※※
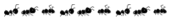 戻る
戻る

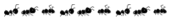
「そろそろ末の弟君もパーティーに連れてきたらどうだ?」
「ご冗談を。末弟はまだ子供ですよ」
とあるパーティー会場でスコットはシャンパングラスを片手に隣の紳士に微笑んだ。
今日は父親の会社代表として財界のパーティーに出席している。隣の紳士は父親と旧知の仲であり、スコットのことも末っ子のアランのことも知っていた。
「幾つになる?」
「14歳です」
「それで子供扱いか。君が14歳の頃はパーティー会場で大人顔負けに振る舞っていたじゃないか」
紳士は楽しげに低い声で笑う。
言われてみればスコットが14歳の頃は父親に連れられ色々な会場に顔を出していた。それを思い出すとスコットは困ったようにシャンパンを飲み干した。
今までもペネロープが主催するようなパーティーにはアランも参加したことがある。ただそれは兄弟全員参加であり、今日のような場はまだ早いのではと思ってしまうのだ。
「子供子供と思っていても本人はしっかりしているものだぞ。ジェフの息子なら特にな」
紳士はスコットの肩を叩くと、その場を離れる。
「考えておきます」
スコットが紳士の背中に声をかければ、軽く手を挙げて紳士が応えた。
いつかはアランも1人でパーティーに参加するだろうが、それはまだまだ先の話だと思っていた。しかし客観的にはそうでは無いらしい。今日の紳士との会話は家に帰ってからもスコットの頭の片隅に引っかかっていた。
(一緒に連れていくべきか?)
明るく社交的で愛され型のアランならパーティー会場でも物怖じしないで溶け込むだろう。スコットが一緒なら変な輩も近づいて来ない。ただ、
(縁談を持ち込まれそうなんだよな…)
トレーシー家の末っ子で家柄、見た目、立ち振舞い、社交性、将来性も申し分ないとくれば近い年齢の娘をもつ親が近づいてくること間違いない。アランがついウッカリ「喜んで」と言おうものなら大変なことになるだろう。あの無邪気な末っ子なら場の空気に圧されて言いかねないなと思う。
その点ゴードンはあしらい方が絶妙で心配はしてないのだが。
スコットがジャケットを脱ぎならがラウンジに戻ると、そこには噂のアランが大きなモニターでシューティングゲームに興じている真っ最中だった。
「スコット、おかえり!早かったね」
チラリと視線をスコットに向けると直ぐにモニターに集中する。最終面なのだろう。縦横無尽に飛んでくるミサイルをアランは見事に避けていた。
流石に兄弟の中でも特出した動体視力の持ち主だ。それを使うのがシューティングゲームというのに苦笑いしながらもスコットは後ろからアランの操作を眺めた。
「早いか?いつもこんな感じだろ」
「ゴードンが朝になるんじゃないかって言ってたから。お持ち帰りがどうとか。お持ち帰りってピザでも買ってきたの?」
アランは期待に満ちた目でスコットを一瞬だけ振り返るが、スコットが手ぶらなのを見ると残念そうに視線を戻した。スコットは僅かに頬をひきつらせる。本当にあの弟は余計なことしか言わないな、と思いながら。
「アラン、それが終わったら僕の部屋に来てくれ」
スコットの意外な言葉にアランはゲームを止めると体ごとスコットを振り返った。部屋に呼び出されるなんて滅多にない。アランは不安そうに視線を揺らした。
「えー…僕何か怒られることした?」
「心当たりがあるのか?」
「でもアレはゴードンがやったのを見てただけだよ!」
「おい、何の話だ」
「だからスコットのデスクにおばあちゃんのクッキーを入れた話………あ!勝手に生ハム食べた方?それともバスルーム…」
思いがけない話が次々と出てくることにスコットは頭を抱えた。デスクにおばあちゃんのクッキー?最近部屋で異臭がすると思っていたのだ。それだけは早急に片付けないと。バスルームとは?
アランをパーティーに連れていく以前に解決しないといけないことが山積みでスコットは「続きは部屋で聞く」と立ち上がった。
アランは叱られるのを嫌がる子犬のようにソワソワとスコットの後に続いた。
※※※※※
キラキラと彩られたパーティー会場に一歩入るとアランは圧倒されたように会場を見渡した。
豪華なシャンデリアに柔らかな絨毯、華やかなドレスに賑やかな談笑の声。白いテーブルクロスが掛けられたテーブルの上には豪華でお洒落な料理が並んでいる。
見える範囲では自分が最年少なことにアランは戸惑ったように隣のスコットを見上げた。
「僕が隣にいるから安心しろ」
真新しく着なれないスーツに身を包み、まるで捨てられた子犬のような瞳で見られたスコットは笑いを噛み殺してアランの背中を叩いた。
「やぁ、スコット」
後ろから掛けられた声に振り向けば先日の紳士が微笑みながら立っていた。
「早速連れて来たのかい?」
「紹介します。末弟のアランです」
スコットに促されるとアランの肩が緊張で微かに跳ねた。
「久しぶりだ。こんなに大きくなって」
紳士は感慨深そうにアランの手を握った。
「えーっと…お久しぶりです」
語尾にクエスチョンマークを付けながら言えば、「私が君に会った時は君は赤ん坊だったからな」と紳士は懐かしむように目を細めた。
「時が経つのは早いものだ。今日が君にとっていい思い出になるよう祈っているよ」
紳士が言えばアランも嬉しそうに「ありがとうございます!」と返した。
「優しい人だね」
パーティーも楽しいじゃないかとアランが思っているとスコットが「気を抜くな。ここからが大変だぞ」と周囲の視線を気にしながらアランにだけ聞こえるように囁いた。
「…疲れた。トイレ行ってくる」
「アラン、そんな顔をするな。常に見られてると思え」
紳士と別れてから始まった怒濤の時間。
トレーシー家の末っ子が来ていると噂はあっという間に広がり、スコットとアランは休む暇なく対応に追われていた。
「はじめまして。アラン・トレーシーです」
まるで壊れた人形のように何度同じセリフを口にしただろう。スコットが相手の紹介をしてくれるが、同じ話に同じ様な服装が続くと顔すら同じに見えてアランの頭を混乱させた。
「弟君には婚約者はいるのかね」
「うちの娘に会ってみないか」
「ホームパーティーに来て欲しい」
そんな質問も何度も飛び交い、その都度スコットが壁となりアランを守っていた。
ようやく僅かな隙間時間を見つけるとアランはパーティー会場を抜け出した。
しかし会場出口に行くまでにも先程挨拶した人々に呼び止められる。失礼にならないように疲れた顔を消して笑顔で対応するアランをスコットは心配と頼もしそうな気持ちが半々な視線で眺めていた。
トイレの個室に避難したアランは疲れきったようにしゃがみこんだ。
普段の島での生活では考えられない程の人と会い、話をした。愛想笑いで固まった頬を擦りながらアランは改めてスコットを尊敬する。あれだけの人数の顔と名前を一致させるだけでなく、前回話した内容までも覚えているのだ。自分がいるからだけでなく、人がスコットの周りに集まってくる理由が何となくわかった気がした。
「何時に終わるのかな…」
会場に戻れば質問攻めの続きが始まるだろう。目の前には美味しそうな料理が並んでいるにも関わらず、アランはまだ一口も食べられていなかった。
「お腹空いたなぁ…」
出掛けにゴードンが何か食べていった方がいいと言ったのを「パーティーだよ!ご馳走あるからお腹空かせていかないと!」と断ったのが悔やまれる。きっとゴードンはこうなることを予想していたのだろう。
そろそろ戻らないと心配される。
アランが個室から出るのと入れ違うように1人の男が隣の個室に入っていった。アランに気づくと男は慌てて顔を背け、手にしていたものをポケットに隠す。ほんの一瞬であったがアランはそれがナイフだと気づいた。
男が隣の個室の鍵を閉めるのを確認するとアランは足音を殺してトイレを飛び出した。
「スコット!」
アランはパーティー会場に戻ると見知らぬ夫妻と談笑するスコットの腕を引っ張ってスコットの耳に口を寄せた。
「アラン、不作法だぞ」
スコットは嗜めるが、アランが「緊張事態だ」と囁けばスコットは「わかった」と詳細を聞き返すことなく短く応えた。
「失礼。少し問題が起こりまして。続きはまた今度聞かせてください」
夫妻に穏やかに詫びるとスコットはアランを促してその場を離れる。
人がいないテラスで「どうした?」と尋ねればアランはトイレでの出来事を話した。アランがナイフを見たと言うのなら確かにナイフを持っていたのだろう。アランの動体視力を疑うことなくスコットが頷けばアランはホッとしたように息を吐いた。
「アラン、その男の顔は覚えているか?」
「もちろん」
一瞬ではあったが間違えることはない。
レスキュー中に見せるアランの1人前のiRの顔を頼もしく思い、スコットの顔に場違いな笑みが浮かんだ。
「行くぞ。その男を探すんだ」
「FAB!」
スコットとアランはテラスからパーティー会場へと戻った。
「スコット、いた!」
アランの緊迫した声にスコットが振り返れば、そこにはパーティー会場を早足で歩く男がいた。姿格好は招待客のように整っているが纏う雰囲気はパーティーを楽しむそれではない。男の行く手には恰幅のいい1人の男性がいる。それが男のターゲットだと直感したスコットは急いで恰幅のいい男性に向けて走った。しかし人が多く思うように距離が縮まらない。このままでは間に合わない。
(仕方ない…)
スコットは恰幅のいい男性の近くにあるテーブルのテーブルクロスを掴むと思い切り引っ張った。
テーブルクロスが乱暴に引かれ上に乗っていた料理や取り皿が音を立てて床に落ちる。
飛び散る料理に割れる食器。
どよめきと悲鳴と視線が一帯に集まった。
「アラン!誤魔化しといてくれ!」
「誤魔化……えぇ?!」
アランの上擦った声を無視してスコットは騒ぎのどさくさに紛れて逃げようとしていた不審な男の腕を掴んでいた。
男はスコットの手を振り払おうとするが、一流のレスキュー隊員であるスコットに敵うはずがない。周囲の招待客に気づかれないように会場の外まで連れ出すと警備員を呼ぶように会場スタッフに言った。
※※※※※
- 85 -