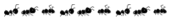不機嫌犬の取説
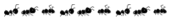
『スコットの機嫌が悪い』
ジョンからの申し送りにゴードンは面倒だなと思いつつも「FAB」と軽く答えた。
聞けばまたGDFのiR反対派と一悶着あったらしい。加えて父親の会社と取引のある会社が不正で摘発され、その火の粉が降りかかってきた。更に例のお騒がせ社長がまた何かやらかそうとして、それを阻止するのにもゴタゴタがあったのだという。
聞けば聞くほど気の毒になる。
それでよく『機嫌が悪い』で済むものだとゴードンは感心した。
時刻は午後11時。バージルもアランも部屋に戻っている時間だ。ジョンによるとスコットは後5分で家に着くという。一日が不愉快のまま終わるなんて、とゴードンはスコットを出迎えるべく立ち上がった。
「頼んだ。ゴードンが一番犬猫の扱いが上手いからな」
「さぞかし不機嫌な犬が帰って来るんだろうね」
「噛まれないように気をつけろよ」
「ジョンも降りて手伝っ……あ、切れた」
先程までジョンのホログラムが浮かんでいた空間にゴードンは軽く舌打ちすると急ぎ足でキッチンに向かった。
スコットが不機嫌に突っかかってくるのは迷惑ではない。さすがに毎日毎日突っかかってこられたら迷惑だが、全てを抱えて黙り込まれるより何倍もいいとゴードンは思っていた。
キッチンの電気を点けると手早くお湯を沸かす。格納庫に戻って着替えてキッチンに来るのはどれくらいだろう。安眠効果があるハーブティーを戸棚から取り出すとスコットのマグカップを用意した。ついでに自分のマグカップも。
スコットが美味しいと言っていたバームクーヘンもある。冷蔵庫にはフルーツタルトも入っている。果物ならリンゴとバナナがあったはずだ。
(いつでもどうぞ)
ゴードンは楽しむようにスコットがキッチンにやって来るのを待った。
「ゴードン、いつまで起きてるんだ!」
キッチンにいるゴードンを見つけたスコットから「ただいま」より先に険しい言葉が飛んでくる。これは随分ご機嫌斜め、且つお疲れだなとゴードンは思った。
いつもなら弟の姿を見たらそれだけで破顔する長男なのだ。それが今夜は眉間に皺を寄せていた。
「スコットの帰りを待ってたんだよ。お疲れ様」
スコットの不機嫌も気にせずいつもの笑顔を見せれば、スコットの勢いが少しだけ削がれた。
「僕の帰りなんて待たなくていい。それより早く寝ろ」
「えー?せっかくだから一杯飲もうよ」
飲むと言ってもアルコールではない。マグカップを見せるゴードンにスコットは返事の代わりに溜め息を吐いた。
「お疲れなスコットに気持ちを落ち着かせるハーブティーだよ」
「余計なお世話だ。それに飲むならコーヒーがいい」
「コーヒーは眠れなくなるからダメ」
「…そのハーブティー美味しくないんだよ」
「あ、そーだった?」
突っかかるスコットにゴードンはハーブティーを淹れながら浮かぶ笑みを噛み殺した。一昨日同じハーブティーを飲んだ時は美味しいと絶賛だったじゃないか、と。それを言えば火に油を注ぐことになるので黙っているが、まるで反抗期の少年のようなスコットにゴードンは微笑ましさを咳払いで誤魔化した。
「僕はこのハーブティー好きなんだよね。別なの用意した方がいい?」
甘えるような上目遣いでスコットのマグカップを差し出せば、スコットは「これでいい」と渋々といった様子で受け取った。
「お腹空いてる?フルーツタルトあるよ。リンゴもバームクーヘンも。あ、バームクーヘンにしようか。僕も食べたい」
スコットの視線がバームクーヘンに反応したのに目敏く気づいたゴードンはすかさずバームクーヘンを取り出す。それも準備万端に切ってフォークも添えてあるやつだ。もしスコットが食べないと言ったら2つとも自分で食べるつもりだった。
「夜空でも見ながら食べようよ」
「好きにしろ」
口調こそ吐き捨てるようにキツいが部屋に戻ろうとはしない。
「ありがとう。スコットと一緒で嬉しいよ」
あざとい位のとびきりの笑顔を見せれば、スコットの毒気が抜かれたように見えた。
「何があったの?」なんてゴードンは聞かない。話すことで思い出して不愉快になることもあるし、そもそも弟には聞かせたくないかもしれない。ジョンから聞いていることなど、おくびにも出さずゴードンはただ「おいしい!おいしい!」とバームクーヘンを口に運んだ。
スコットのハーブティーが無くなれば、すかさず「おかわりいる?」と尋ねる。「さっき『美味しくない』って言ったくせに」なんて微塵も感じさせないゴードンの自然な態度にスコットは大きく溜め息を吐いた。
「ゴードン、今日のレスキューだけど」
「うん」
「あれだけ危ないことをするなと」
「うん」
ゴードンは素直に聞いている。その姿にスコットは三度溜め息を吐くと「いや、何でもない」と話をやめた。それが八つ当たりに近い感情だと気づいたからだ。
「悪かったな。気を使わせて」
スコットがゴードンの頭に手を置けば、ゴードンは「なんのこと?」と素知らぬ振りで聞き返した。
「よくわからないけど疲れてるならバグでもする?30秒バグするとストレスが減るらしいよ」
ゴードンは椅子から立つとスコットに向けて両手を広げた。
「それって恋人同士の話じゃないのか?」
「愛情があればOKらしいよ。スコット、僕のこと好きでしょ?」
「…そうだな」
スコットは苦笑すると、カウンターの椅子に座ったままゴードンを抱き寄せた。抱きしめられれば服越しにスコットの体温が伝わってくる。ゴードンはスコットの背中に手をまわすと、自らスコットに抱きついた。
「……スコット」
「なんだ?」
「長い長い。30秒でOKだって。もう3分は経ってるから」
「まだ15秒位だろ」
「体内時計だいぶ狂ってるよ!」
暫くは大人しくしてたゴードンだが、流石に長過ぎると徐々に抵抗を始めた。しかしスコットの腕力には敵わない。暴れはじめてから更に2分程経った頃ようやくスコットの腕から解放された。
「気が楽になったよ」
「…それは良かった」
先程までの不機嫌な様子は影を潜め、スコットは満足そうに暴れ疲れてぐったりとしたゴードンの頭を撫でた。ワックスで固めてないゴードンの髪は柔らかく、おでこにかかる髪が幼い印象にしている。
「ありがとう。ゴードンは優しいな」
最後に軽くゴードンを抱きしめると、スコットは椅子から立ち上がった。空になったマグカップを片付けようとするのを遮って、ゴードンは「片付けとくからスコットは早く寝なよ」と言った。
「おやすみ」
ゴードンが背伸びをしてスコットの頬にキスをするとスコットも穏やかな表情でキスを返した。
「相変わらず手慣れてるな」
ゴードンが部屋に戻るとジョンから通信が入った。
「ちょっとは機嫌が直って良かったよ」
「お前が笑うとつられるからな。自分のペースに引き込むのは大した才能だよ」
「ジョンが褒めるなんて明日は雪かな」
ゴードンがおどけて窓に目をやれば、ジョンは「失礼なやつだな」と大袈裟に首を振った。
「ジョン、明日降りてきてよ」
とびきりの笑顔をジョンに向けるが、返事の前にジョンの通信が切られた。
「つられないじゃん!」
ジョンがいた空間に叫ぶが勿論聞こえるはずもない。
だが、通信機を挟んだ向こうとこっち側でジョンとゴードンは同時に笑うのだった。
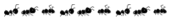 戻る
戻る

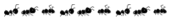
『スコットの機嫌が悪い』
ジョンからの申し送りにゴードンは面倒だなと思いつつも「FAB」と軽く答えた。
聞けばまたGDFのiR反対派と一悶着あったらしい。加えて父親の会社と取引のある会社が不正で摘発され、その火の粉が降りかかってきた。更に例のお騒がせ社長がまた何かやらかそうとして、それを阻止するのにもゴタゴタがあったのだという。
聞けば聞くほど気の毒になる。
それでよく『機嫌が悪い』で済むものだとゴードンは感心した。
時刻は午後11時。バージルもアランも部屋に戻っている時間だ。ジョンによるとスコットは後5分で家に着くという。一日が不愉快のまま終わるなんて、とゴードンはスコットを出迎えるべく立ち上がった。
「頼んだ。ゴードンが一番犬猫の扱いが上手いからな」
「さぞかし不機嫌な犬が帰って来るんだろうね」
「噛まれないように気をつけろよ」
「ジョンも降りて手伝っ……あ、切れた」
先程までジョンのホログラムが浮かんでいた空間にゴードンは軽く舌打ちすると急ぎ足でキッチンに向かった。
スコットが不機嫌に突っかかってくるのは迷惑ではない。さすがに毎日毎日突っかかってこられたら迷惑だが、全てを抱えて黙り込まれるより何倍もいいとゴードンは思っていた。
キッチンの電気を点けると手早くお湯を沸かす。格納庫に戻って着替えてキッチンに来るのはどれくらいだろう。安眠効果があるハーブティーを戸棚から取り出すとスコットのマグカップを用意した。ついでに自分のマグカップも。
スコットが美味しいと言っていたバームクーヘンもある。冷蔵庫にはフルーツタルトも入っている。果物ならリンゴとバナナがあったはずだ。
(いつでもどうぞ)
ゴードンは楽しむようにスコットがキッチンにやって来るのを待った。
「ゴードン、いつまで起きてるんだ!」
キッチンにいるゴードンを見つけたスコットから「ただいま」より先に険しい言葉が飛んでくる。これは随分ご機嫌斜め、且つお疲れだなとゴードンは思った。
いつもなら弟の姿を見たらそれだけで破顔する長男なのだ。それが今夜は眉間に皺を寄せていた。
「スコットの帰りを待ってたんだよ。お疲れ様」
スコットの不機嫌も気にせずいつもの笑顔を見せれば、スコットの勢いが少しだけ削がれた。
「僕の帰りなんて待たなくていい。それより早く寝ろ」
「えー?せっかくだから一杯飲もうよ」
飲むと言ってもアルコールではない。マグカップを見せるゴードンにスコットは返事の代わりに溜め息を吐いた。
「お疲れなスコットに気持ちを落ち着かせるハーブティーだよ」
「余計なお世話だ。それに飲むならコーヒーがいい」
「コーヒーは眠れなくなるからダメ」
「…そのハーブティー美味しくないんだよ」
「あ、そーだった?」
突っかかるスコットにゴードンはハーブティーを淹れながら浮かぶ笑みを噛み殺した。一昨日同じハーブティーを飲んだ時は美味しいと絶賛だったじゃないか、と。それを言えば火に油を注ぐことになるので黙っているが、まるで反抗期の少年のようなスコットにゴードンは微笑ましさを咳払いで誤魔化した。
「僕はこのハーブティー好きなんだよね。別なの用意した方がいい?」
甘えるような上目遣いでスコットのマグカップを差し出せば、スコットは「これでいい」と渋々といった様子で受け取った。
「お腹空いてる?フルーツタルトあるよ。リンゴもバームクーヘンも。あ、バームクーヘンにしようか。僕も食べたい」
スコットの視線がバームクーヘンに反応したのに目敏く気づいたゴードンはすかさずバームクーヘンを取り出す。それも準備万端に切ってフォークも添えてあるやつだ。もしスコットが食べないと言ったら2つとも自分で食べるつもりだった。
「夜空でも見ながら食べようよ」
「好きにしろ」
口調こそ吐き捨てるようにキツいが部屋に戻ろうとはしない。
「ありがとう。スコットと一緒で嬉しいよ」
あざとい位のとびきりの笑顔を見せれば、スコットの毒気が抜かれたように見えた。
「何があったの?」なんてゴードンは聞かない。話すことで思い出して不愉快になることもあるし、そもそも弟には聞かせたくないかもしれない。ジョンから聞いていることなど、おくびにも出さずゴードンはただ「おいしい!おいしい!」とバームクーヘンを口に運んだ。
スコットのハーブティーが無くなれば、すかさず「おかわりいる?」と尋ねる。「さっき『美味しくない』って言ったくせに」なんて微塵も感じさせないゴードンの自然な態度にスコットは大きく溜め息を吐いた。
「ゴードン、今日のレスキューだけど」
「うん」
「あれだけ危ないことをするなと」
「うん」
ゴードンは素直に聞いている。その姿にスコットは三度溜め息を吐くと「いや、何でもない」と話をやめた。それが八つ当たりに近い感情だと気づいたからだ。
「悪かったな。気を使わせて」
スコットがゴードンの頭に手を置けば、ゴードンは「なんのこと?」と素知らぬ振りで聞き返した。
「よくわからないけど疲れてるならバグでもする?30秒バグするとストレスが減るらしいよ」
ゴードンは椅子から立つとスコットに向けて両手を広げた。
「それって恋人同士の話じゃないのか?」
「愛情があればOKらしいよ。スコット、僕のこと好きでしょ?」
「…そうだな」
スコットは苦笑すると、カウンターの椅子に座ったままゴードンを抱き寄せた。抱きしめられれば服越しにスコットの体温が伝わってくる。ゴードンはスコットの背中に手をまわすと、自らスコットに抱きついた。
「……スコット」
「なんだ?」
「長い長い。30秒でOKだって。もう3分は経ってるから」
「まだ15秒位だろ」
「体内時計だいぶ狂ってるよ!」
暫くは大人しくしてたゴードンだが、流石に長過ぎると徐々に抵抗を始めた。しかしスコットの腕力には敵わない。暴れはじめてから更に2分程経った頃ようやくスコットの腕から解放された。
「気が楽になったよ」
「…それは良かった」
先程までの不機嫌な様子は影を潜め、スコットは満足そうに暴れ疲れてぐったりとしたゴードンの頭を撫でた。ワックスで固めてないゴードンの髪は柔らかく、おでこにかかる髪が幼い印象にしている。
「ありがとう。ゴードンは優しいな」
最後に軽くゴードンを抱きしめると、スコットは椅子から立ち上がった。空になったマグカップを片付けようとするのを遮って、ゴードンは「片付けとくからスコットは早く寝なよ」と言った。
「おやすみ」
ゴードンが背伸びをしてスコットの頬にキスをするとスコットも穏やかな表情でキスを返した。
「相変わらず手慣れてるな」
ゴードンが部屋に戻るとジョンから通信が入った。
「ちょっとは機嫌が直って良かったよ」
「お前が笑うとつられるからな。自分のペースに引き込むのは大した才能だよ」
「ジョンが褒めるなんて明日は雪かな」
ゴードンがおどけて窓に目をやれば、ジョンは「失礼なやつだな」と大袈裟に首を振った。
「ジョン、明日降りてきてよ」
とびきりの笑顔をジョンに向けるが、返事の前にジョンの通信が切られた。
「つられないじゃん!」
ジョンがいた空間に叫ぶが勿論聞こえるはずもない。
だが、通信機を挟んだ向こうとこっち側でジョンとゴードンは同時に笑うのだった。
- 110 -