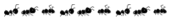プールとレスキュー案件
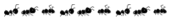
トレーシー・アイランドには大きなプールがある。大富豪の邸宅に相応しいプールは幅9レーンに深さ3メートル。プール端にはコースロープも備えられている本格的なプールだ。
もっともプールはカモフラージュであり、サンダーバード1号の発射口を隠す為のものだが。
そのプールを愛用しているのな言うまでもなく海の申し子ゴードンだ。レスキューが入っていない時には広いプールで悠々と泳ぐ姿が目撃されていた。
それからスコット。多忙な長男もいい気分転換になるのかプールで泳ぐことが多々あった。それも速さ重視なクロールでも豪快なバタフライでもなく、平泳ぎが好きだと言うのだから驚きだ。
他の兄弟もプールを使うことはあるが、やはりメインに使うのはゴードンとスコットだった。
ある日。
いつものようにゴードンが泳いでいると、そこに競泳水着に着替えたケーヨがやってきた。
「ゴードン、一緒していいかしら?」
ゴードンが泳ぎきったタイミングで声をかければ、ゴードンはゴーグルを外してケーヨを見上げると短く口笛を吹いた。
「最高だね!ケーヨの水着姿が拝めるなんて」
「はいはい。端のレーン借りるわよ」
軽くあしらうケーヨにゴードンは「つれないんだから」と笑いながらプールサイドに上がった。競泳水着のケーヨと違いゴードンは色鮮やかな黄色のサーフパンツだ。右下に赤いラインと黒字の『4』が入っていることからサンダーバード4号をイメージした水着なのだろう。手作りなのか特注なのかはわからないが。
スイマーの体型をしたゴードンはプールと水着がよく似合う。競泳水着ではなくサーフパンツなのは今日はゆっくり泳ぎたいということなのだろう。
「端じゃなくて隣で泳ごうよ。競争でもする?」
「あら、いいわね。何か賭ける?」
「夕飯の片付けなんてどう?」
「OK。準備をするから待ってて」
ケーヨが準備体操をする隣でゴードンは距離やハンデについて決めていく。普通に泳げばゴードンの方が間違いなく速い。それでは賭けにならないし、ゴードン自身も楽しくない。どちらが勝つかわからない鬩ぎ合いが一番面白いのだ。
「少し泳いでからでいい?」
「もちろん!急に泳ぐと危ないからね。僕は休憩してるからごゆっくり」
プールに入るケーヨに軽く手を振るとゴードンはデッキチェアに向かった。
降り注ぐ陽射しは強烈だ。
今日も暑くなりそうだとデッキチェアに横になっていると、不意に上から「何をしているんだ?」と声がかけられた。
「あ、スコットだ」
視線だけ上に向ければ、自分を覗き込んでいるスコットと目が合った。逆さから見るスコットの顔は明らかに疲労が溜まっていて、ゴードンは心配そうにデッキチェアから起き上がった。
「ケーヨ待ち」
「ケーヨ?」
スコットはプールで泳ぐケーヨに目をやった。
「競争するんだ。敗者は夕飯の片付け」
ゴードンが人差し指を立てて言えば、スコットは「楽しそうだな」と笑った。
「それよりスコットちゃんと寝てる?酷い顔だよ」
「言い方に気をつけてくれよ。こんなハンサムに酷い顔はないだろ」
「色男は自信家なんだから」
ゴードンは大袈裟に両手を広げて首を横に振った。スコットが茶化して返してくる時は大抵徹夜明けだ。気取られないように元気を装うが、兄弟達にはバレバレだった。
「今日は暑いから泳いだら気持ち良さそうだな」
「今スコットに必要なのは睡眠だと思うよ。ほら、早く戻った戻った」
まるで犬を追い返すような仕草にスコットは不満そうな顔で家に戻って行った。
それから数分後。
ケーヨが「お待たせ」とプールサイドに上がってきた。しなやかな筋肉はケーヨの持ち味だ。ゴードンは失礼にならない程度にケーヨの筋肉に目を走らせた。
「コースロープはどうする?」
「どちらでも」
「じゃ、無くていっか。真っ直ぐ泳げるもんね」
ゴードンとケーヨはゴーグルをしながらコースに立った。
「種目は自由形200メートル。ケーヨが泳ぎ始めてから…」
「ゴードン?どうかした?」
ルールを説明するゴードンが急に言葉を切って嫌そうな顔をする。視線はケーヨの向こう側で、ケーヨは不思議そうな顔でゴードンの視線の先を追うように振り返った。
「スコット」
「あのバカ長男…」
ケーヨに聞こえないように小声で悪態をつくとゴードンはスタート位置から離れた。スコットは競泳水着に着替えていて手にはゴーグルを持っている。競争に参加する気満々なスコットにゴードンは漠然と嫌な予感を抱いた。それはゴードンならではのイカセンサーかもしれなかった。
「僕も混ぜてくれないか?」
「えぇ、いいわよ」
「嫌だ」
「おい、ゴードン。ケーヨの前でワガママ言うな」
スコットはゴードンのワガママを嗜めるようにゴードンの肩を叩くが、それがゴードンの機嫌を更に悪くさせた。
「敗者は夕飯の片付けだって?」
「そうよ。自由形だからスコットは得意の平泳ぎでもいいけど」
「それは厳しい戦いになりそうだ」
スコットは上機嫌に笑うとゴードンの隣のレーンに立った。ゴードンを真ん中にケーヨとスコットが並ぶ形だ。
「スコット、いきなり泳ぐ気?」
「家の中で準備してきた」
やけにテンション高く感じるのは徹夜明けだからだろうか。こうなったスコットは誰にも止められない。ゴードンは渋々レーンの前に立った。
「もう一斉スタートでいいかな?」
スコットが乱入してきた時点で競争がどうなるかはわからない。ゴードンの提案にケーヨは「勿論」と微笑んだ。
「じゃあ、行くよ。Ready…」
太陽が照らす水面に3つの水飛沫が上がった。
勢いよく飛び出したのはゴードンだ。
ハンデ無しだからと言って手を抜くのは相手に失礼だ。ゴードンは真剣な表情で水の中を前へ前へと進んだ。そのゴードンに続くのはケーヨ、そして徹夜明けが響いているスコットがケーヨより更に遅れて続いた。
ターン地点に到達した時にはゴードンとスコットの距離はだいぶ開いている。無駄な動き無くターンを決めたゴードンが泳ぎを進めると不意に視界に異変を感じ、水を掻く手を緩めた。
(なんだ…?)
視線をプールの中に走らせる。
そして隣のレーン底に蹲るスコットを見つけると思わず悲鳴を上げた。もちろん水中での悲鳴は声になることなく、口から大量の空気が漏れだしただけだ。慌てて水面に顔を出すと苦しそうに咳き込みながらも反対側のレーンに向かって「ケーヨ!」と叫んだ。
そして直ぐに息を吸うとスコットの元へ潜水を始めた。
(スコット!どうしたの?!)
スコットの腕を引っ張れば、スコットはゴードンに向けて親指を立てた。口元は笑っているかのような余裕の表情だ。
(いやいや、沈んでて『問題ない』は通用しないから!)
スコットがいつから沈んでいるかはわからないが、スコットなら2〜3分息を止めていられる。ゴードンは呆れながらもスコットの腕を掴んで水面に引っ張り上げようとした。しかしスコットの体は不自然に力が入っていて素直に浮上してくれない。足を押さえるような仕草に(足つったな)とゴードンは冷めた目で長男を見た。だから徹夜明けでいきなり泳ぐことに反対したのだ。
そこに異変に気づいたケーヨも合流する。両脇から抱えるようにしてプールの底を思いきり蹴る。今となっては水深3メートルがこの上なく負担だった。
「スコット!」
「やぁ、ゴードン。ケーヨも見事なレスキューだった」
まるで訓練の出来を褒めるかのような口調にゴードンの眉はつり上がった。スコットは一見細身に見えるが筋肉質なので体重もそれなりにある。特に今は足が使えないので全体重がゴードンの肩にかかり、それを沈まないように支えるのは一苦労だった。
「とりあえずプールサイドに」
ケーヨが2人を誘導する。よりによって真ん中のレーンで泳いでいたのでプールサイドまでの距離がある。うんざりとするゴードンに対しスコットはケロッとしていて、ゴードンは思わず水中に置いていってしまおうかとスコットを睨んだ。
「……疲れた」
ゴードンはスコットをプールサイドに引っ張り上げることに成功すると、ゼーゼーと息を吐きながら疲れきったように膝をついた。自分より体の大きいレスキュー対象者は厄介だなと呼吸を整えながら頭の片隅で思う。ケーヨも「溺れるなんてビックリしたわ」と困惑げにスコットを見た。
「溺れるなんて人聞きが悪いな。泳ぐことが一時的に困難になったから水中で待機してただけだよ」
「泳ぐことが困難な状態を『溺れる』って言うんじゃないの?」
「捉え方の違いかな」
スコットが微笑めばケーヨは「呆れた」と視線をくるりと回した。
全く反省の色がないスコットにゴードンは不機嫌にタオルを投げつけた。
「ゴードン?」
「そんな状態で泳ぐなんてバカじゃないの!海を舐めるな!」
「いや、ここプール…」
スコットの反論も聞かずゴードンは乱暴な足取りでプールサイドを後にした。沈むスコットを見た時の衝撃と、イカセンサーが働いていたにも関わらずスコットを止められなかった自分に腹を立てながら。
「怒らせたみたいだ」
スコットが困ったように頭を掻くのをケーヨは隣で眺めていた。
「追わなくていいの?」
「追いたいのは山々なんだけど…」
スコットは足に力を入れようとするが、ピリピリとした痛みが残る。
「もう少ししたら行くよ」
ケーヨに気づかれないように穏やかに言うが、ケーヨは「足がつるのを予防するには毎日6時間以上の睡眠がいいらしいわよ」と全てを見透かしたように言う。
「まいったな…」
スコットは誤魔化すように空を見上げた。
そこにはどこまでも広がる青い空があった。
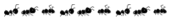 戻る
戻る

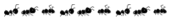
トレーシー・アイランドには大きなプールがある。大富豪の邸宅に相応しいプールは幅9レーンに深さ3メートル。プール端にはコースロープも備えられている本格的なプールだ。
もっともプールはカモフラージュであり、サンダーバード1号の発射口を隠す為のものだが。
そのプールを愛用しているのな言うまでもなく海の申し子ゴードンだ。レスキューが入っていない時には広いプールで悠々と泳ぐ姿が目撃されていた。
それからスコット。多忙な長男もいい気分転換になるのかプールで泳ぐことが多々あった。それも速さ重視なクロールでも豪快なバタフライでもなく、平泳ぎが好きだと言うのだから驚きだ。
他の兄弟もプールを使うことはあるが、やはりメインに使うのはゴードンとスコットだった。
ある日。
いつものようにゴードンが泳いでいると、そこに競泳水着に着替えたケーヨがやってきた。
「ゴードン、一緒していいかしら?」
ゴードンが泳ぎきったタイミングで声をかければ、ゴードンはゴーグルを外してケーヨを見上げると短く口笛を吹いた。
「最高だね!ケーヨの水着姿が拝めるなんて」
「はいはい。端のレーン借りるわよ」
軽くあしらうケーヨにゴードンは「つれないんだから」と笑いながらプールサイドに上がった。競泳水着のケーヨと違いゴードンは色鮮やかな黄色のサーフパンツだ。右下に赤いラインと黒字の『4』が入っていることからサンダーバード4号をイメージした水着なのだろう。手作りなのか特注なのかはわからないが。
スイマーの体型をしたゴードンはプールと水着がよく似合う。競泳水着ではなくサーフパンツなのは今日はゆっくり泳ぎたいということなのだろう。
「端じゃなくて隣で泳ごうよ。競争でもする?」
「あら、いいわね。何か賭ける?」
「夕飯の片付けなんてどう?」
「OK。準備をするから待ってて」
ケーヨが準備体操をする隣でゴードンは距離やハンデについて決めていく。普通に泳げばゴードンの方が間違いなく速い。それでは賭けにならないし、ゴードン自身も楽しくない。どちらが勝つかわからない鬩ぎ合いが一番面白いのだ。
「少し泳いでからでいい?」
「もちろん!急に泳ぐと危ないからね。僕は休憩してるからごゆっくり」
プールに入るケーヨに軽く手を振るとゴードンはデッキチェアに向かった。
降り注ぐ陽射しは強烈だ。
今日も暑くなりそうだとデッキチェアに横になっていると、不意に上から「何をしているんだ?」と声がかけられた。
「あ、スコットだ」
視線だけ上に向ければ、自分を覗き込んでいるスコットと目が合った。逆さから見るスコットの顔は明らかに疲労が溜まっていて、ゴードンは心配そうにデッキチェアから起き上がった。
「ケーヨ待ち」
「ケーヨ?」
スコットはプールで泳ぐケーヨに目をやった。
「競争するんだ。敗者は夕飯の片付け」
ゴードンが人差し指を立てて言えば、スコットは「楽しそうだな」と笑った。
「それよりスコットちゃんと寝てる?酷い顔だよ」
「言い方に気をつけてくれよ。こんなハンサムに酷い顔はないだろ」
「色男は自信家なんだから」
ゴードンは大袈裟に両手を広げて首を横に振った。スコットが茶化して返してくる時は大抵徹夜明けだ。気取られないように元気を装うが、兄弟達にはバレバレだった。
「今日は暑いから泳いだら気持ち良さそうだな」
「今スコットに必要なのは睡眠だと思うよ。ほら、早く戻った戻った」
まるで犬を追い返すような仕草にスコットは不満そうな顔で家に戻って行った。
それから数分後。
ケーヨが「お待たせ」とプールサイドに上がってきた。しなやかな筋肉はケーヨの持ち味だ。ゴードンは失礼にならない程度にケーヨの筋肉に目を走らせた。
「コースロープはどうする?」
「どちらでも」
「じゃ、無くていっか。真っ直ぐ泳げるもんね」
ゴードンとケーヨはゴーグルをしながらコースに立った。
「種目は自由形200メートル。ケーヨが泳ぎ始めてから…」
「ゴードン?どうかした?」
ルールを説明するゴードンが急に言葉を切って嫌そうな顔をする。視線はケーヨの向こう側で、ケーヨは不思議そうな顔でゴードンの視線の先を追うように振り返った。
「スコット」
「あのバカ長男…」
ケーヨに聞こえないように小声で悪態をつくとゴードンはスタート位置から離れた。スコットは競泳水着に着替えていて手にはゴーグルを持っている。競争に参加する気満々なスコットにゴードンは漠然と嫌な予感を抱いた。それはゴードンならではのイカセンサーかもしれなかった。
「僕も混ぜてくれないか?」
「えぇ、いいわよ」
「嫌だ」
「おい、ゴードン。ケーヨの前でワガママ言うな」
スコットはゴードンのワガママを嗜めるようにゴードンの肩を叩くが、それがゴードンの機嫌を更に悪くさせた。
「敗者は夕飯の片付けだって?」
「そうよ。自由形だからスコットは得意の平泳ぎでもいいけど」
「それは厳しい戦いになりそうだ」
スコットは上機嫌に笑うとゴードンの隣のレーンに立った。ゴードンを真ん中にケーヨとスコットが並ぶ形だ。
「スコット、いきなり泳ぐ気?」
「家の中で準備してきた」
やけにテンション高く感じるのは徹夜明けだからだろうか。こうなったスコットは誰にも止められない。ゴードンは渋々レーンの前に立った。
「もう一斉スタートでいいかな?」
スコットが乱入してきた時点で競争がどうなるかはわからない。ゴードンの提案にケーヨは「勿論」と微笑んだ。
「じゃあ、行くよ。Ready…」
太陽が照らす水面に3つの水飛沫が上がった。
勢いよく飛び出したのはゴードンだ。
ハンデ無しだからと言って手を抜くのは相手に失礼だ。ゴードンは真剣な表情で水の中を前へ前へと進んだ。そのゴードンに続くのはケーヨ、そして徹夜明けが響いているスコットがケーヨより更に遅れて続いた。
ターン地点に到達した時にはゴードンとスコットの距離はだいぶ開いている。無駄な動き無くターンを決めたゴードンが泳ぎを進めると不意に視界に異変を感じ、水を掻く手を緩めた。
(なんだ…?)
視線をプールの中に走らせる。
そして隣のレーン底に蹲るスコットを見つけると思わず悲鳴を上げた。もちろん水中での悲鳴は声になることなく、口から大量の空気が漏れだしただけだ。慌てて水面に顔を出すと苦しそうに咳き込みながらも反対側のレーンに向かって「ケーヨ!」と叫んだ。
そして直ぐに息を吸うとスコットの元へ潜水を始めた。
(スコット!どうしたの?!)
スコットの腕を引っ張れば、スコットはゴードンに向けて親指を立てた。口元は笑っているかのような余裕の表情だ。
(いやいや、沈んでて『問題ない』は通用しないから!)
スコットがいつから沈んでいるかはわからないが、スコットなら2〜3分息を止めていられる。ゴードンは呆れながらもスコットの腕を掴んで水面に引っ張り上げようとした。しかしスコットの体は不自然に力が入っていて素直に浮上してくれない。足を押さえるような仕草に(足つったな)とゴードンは冷めた目で長男を見た。だから徹夜明けでいきなり泳ぐことに反対したのだ。
そこに異変に気づいたケーヨも合流する。両脇から抱えるようにしてプールの底を思いきり蹴る。今となっては水深3メートルがこの上なく負担だった。
「スコット!」
「やぁ、ゴードン。ケーヨも見事なレスキューだった」
まるで訓練の出来を褒めるかのような口調にゴードンの眉はつり上がった。スコットは一見細身に見えるが筋肉質なので体重もそれなりにある。特に今は足が使えないので全体重がゴードンの肩にかかり、それを沈まないように支えるのは一苦労だった。
「とりあえずプールサイドに」
ケーヨが2人を誘導する。よりによって真ん中のレーンで泳いでいたのでプールサイドまでの距離がある。うんざりとするゴードンに対しスコットはケロッとしていて、ゴードンは思わず水中に置いていってしまおうかとスコットを睨んだ。
「……疲れた」
ゴードンはスコットをプールサイドに引っ張り上げることに成功すると、ゼーゼーと息を吐きながら疲れきったように膝をついた。自分より体の大きいレスキュー対象者は厄介だなと呼吸を整えながら頭の片隅で思う。ケーヨも「溺れるなんてビックリしたわ」と困惑げにスコットを見た。
「溺れるなんて人聞きが悪いな。泳ぐことが一時的に困難になったから水中で待機してただけだよ」
「泳ぐことが困難な状態を『溺れる』って言うんじゃないの?」
「捉え方の違いかな」
スコットが微笑めばケーヨは「呆れた」と視線をくるりと回した。
全く反省の色がないスコットにゴードンは不機嫌にタオルを投げつけた。
「ゴードン?」
「そんな状態で泳ぐなんてバカじゃないの!海を舐めるな!」
「いや、ここプール…」
スコットの反論も聞かずゴードンは乱暴な足取りでプールサイドを後にした。沈むスコットを見た時の衝撃と、イカセンサーが働いていたにも関わらずスコットを止められなかった自分に腹を立てながら。
「怒らせたみたいだ」
スコットが困ったように頭を掻くのをケーヨは隣で眺めていた。
「追わなくていいの?」
「追いたいのは山々なんだけど…」
スコットは足に力を入れようとするが、ピリピリとした痛みが残る。
「もう少ししたら行くよ」
ケーヨに気づかれないように穏やかに言うが、ケーヨは「足がつるのを予防するには毎日6時間以上の睡眠がいいらしいわよ」と全てを見透かしたように言う。
「まいったな…」
スコットは誤魔化すように空を見上げた。
そこにはどこまでも広がる青い空があった。
- 114 -