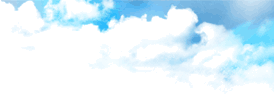
戻らない人がいる
戻ってほしい人なのに
戻らない人がいる
手を伸ばして触れると、その頬は氷のように冷たかった。
石田三成は沼の底を思わせるような真っ暗な瞳で、たった今触れた白い肌から自分の周りに視線を巡らせた。
布団を挟んだ向かい側、亡きがらの頭の横に、朱眼の大老前田利家が座っている。
利家は膝の上に握り拳を作り、小刻みに震えていた。
悲しみに堪えている。
三成は、この大老が自分より過酷で辛い人生を送ってきたことを知っている。
兄のように慕った魔王や父のように慕った鬼王…大事な人を沢山亡くして傷付いてきたことを知っている。
そして、この人はまた亡くしてしまったのだ。
三成は瞼を閉じた、が、その状態を長く続けることはしなかった。
部屋の隅から、遠い野原を低空飛行する蜻蛉の羽音のように小さな鳴咽が、ひっくひっくと響いてくるからだ。
三成は薄目を開けた。
暗がりで、がっちり長身で図体ばかりがでかい福島正則が男泣きしている。
三成は彼のことが以前よりあまり好きではなかったが、それでももらい泣きしそうになった。
首をぶんぶんと激しく振りたくったせいで後頭部で結んだ髪が大きく揺れたが、涙はなんとか堪えた。
三成は視線をそこから僅かにずらした。
いつもならば主の横に行こうとするあの狸は、随分後ろにいて控え目だった。
いや、狸ではない。
なんだ、あの髪は。
まるで昆虫の触角の様ではないか、賤しい…と、三成は内心毒づいた。
狸…徳川家康の小さな瞳の中に、利家の大きな背が揺れている。
三成はじっと家康を見ていた。
今更言うまでもないことだが、胡散臭いこの男を三成は好んでいない。
福島正則などまだ可愛らしいと感じるほどに、嫌いだ。
そんな負の感情を含んだ視線に気付いたのだろうか、家康が三成を見た。
真正面から見ても、家康の表情は読めない。
辛そうに眉を寄せているように見えないこともないが、三成にはその口元が緩んでいるような気がしてならない。
家康は三成に頷くように小さく頭を下げた。
三成も、同じようにした。
三成が顔を上げたのと殆ど同時に…もしかしたら家康の方がほんの少し早かったかもしれないが、家康も顔を上げていた。
しかしその狸のような小さい目はもう三成を見ておらず、元の“前田利家の背中”を映していた。
そういえば前田利家と徳川家康は若い頃から親しかったらしい。
織田家の時代、今川義元を討った約一年後に清洲同盟というものを織田家と徳川家で締結したが、国境まで家康を迎えに出たのが利家と今目の前の褥に横たわる主だったと、三成は聞き及んでいたのだが…。
三成は口元をきゅっと結んだ。
家康は危険だ…と、本能が訴えてくるのだ。
こめかみの皮が内側からきゅーっと引っ張られるような、何かよくわからないキリキリする感覚。
三成は一旦目をぎゅーっと閉じ、そしてまた開いた。
景色は変わらない。
薄暗い部屋。
悲しみに暮れる同僚や上司達。
上座には、誰も腰を据えていない。
こめかみがまだ少々キリキリする。
三成は利家越しに締め切られた障子を見た。
丁度、薄い紙に稲妻が走った。
三成はあまり視線を落としたくなかった。
黙って褥に横たわる、冷た過ぎる体を見たいと思わなかったから。
しかし稲妻など、不吉な物も見たくない。
仕方がなく、また室内に目を向ける。
同じ五奉行の前田玄以が音もなく部屋を出て行った。
何通かある遺書の中のひとつに、自分の骸の処理は前田玄以に一任する、とあったのだ。
そう、この骸は生前、遺書を書いた。
…いや、書かせた。
三成が立ち会った。
利家や家康などの五大老の面々もいた。
三成の主は、息子のことをくれぐれも頼む…と消え入りそうな震える声で懇願した。
利家、家康の手を順に取り、よしなによしなに…と、何度も懇願していた。
そのとき、三成は泣きそうになった。
結局泣かなかったのだが。
だが義理人情に厚い利家はボロボロと泣いていた。
三成は利家がそれなりに好きだった。
皆の前で主の為に泣ける男ほど好ましい男はいない。
家康も泣いた。
しかし三成は鼻を鳴らした。
家康はきっと嘘泣きなのだと思った。
胡散臭い狸だ。
いや、髪型が触角だから、昆虫だ。
そもそも方や本気泣き、方や嘘泣き。
隣同士で座っているのだ。
気付かない道理がない。
あの息が詰まりそうな会議の後、三成は同じ五奉行の増田長盛に家康の嘘泣きに気付いただろうと話に行った。
長盛はかなり慎重で、腹黒く姑息な算段を得意とする人物である。
周りをちらちら見渡して、しばし口ごもった。
しかし辺りに聞き耳を立てている怪しい人物がいないことをしっかり確かめると、まぁ利家様と同じ泣き方ではなかったかな、と言った。
そしてそそくさと去って行った。
三成は長盛のことを昆虫風情を恐れた腰抜けだと思ったのだが、後々長盛はまだマシな方だったのだということに気付くことになる。
福島正則らなどは、家康の化けの皮の中の本性に気付かず、家康様は慈悲深いお方だなどと寝言を言った。
三成は苛々した。
本当に慈悲深い利家様に迷惑な話だと思った。
狸より犬の方が忠実で心優しいではないか。
しかし正則達でさえ、ただの愚か者と罵ってしまえば済む。
一番酷いのは気付きながら知らんぷりを決め込む連中だ。
愚かである上に、弱虫。
この中にも沢山、そんな考えの奴らがいる…と辺りを見渡してから、三成はふと、自分の膝に乗る自分の手を見つめた。
男にしては細い指だ。
そういえば…と、目の前に横たわる主の言葉を思い出した。
よく食べろ、と言われたものだ。
お前は細いからと。
指もこんなに細いのだから、と。
あのひょうきんな笑顔で、猿の様に大きな耳をパタパタさせながら。
…しかし、死ぬる直前三成の頬に伸ばされた震える指は、三成のもの以上に痩せ細っていた。
あんなにもやつれてしまうなんて。
三成は、布団の上に乗る主の手を見た。
いつの間にかこんなに皺くちゃになっていた。
昔頭を撫でられたときは、多分もっと滑らかだった。
…三成は鼻の奥が痛くなって、喉の奥がカッカしてきた。
それをなんとか耐え抜く。
泣いてはいけないと誰かに言われているわけではない。
そもそも、三成が唯一命令を聞こうと思える人は、もう二度と動かないのだ。
だから、これは意地だ。
人前では決して泣かない…三成の意地だった。
三成は感情の高ぶりをごまかそうと、再びなんとなしに利家を見遣った。
相変わらず小刻みに震えている。
三成は、利家を見ることで死ぬる直前の主の様子を思い出していた。
最初のうちは、三成も名を呼ばれていた。
三成三成と、途切れ途切れに掠れ声が三成を呼んだ。
正則も呼ばれた。
加藤清正も呼ばれたが、清正は朝鮮に出兵中である。
三成は正則と同じくらい清正が気に入らなかったが、幼い時分から同じ生活をしてきたあの男を憐れに思った。
自分や正則が想うように、清正も主を父のように慕っていた筈だ。
最期の瞬間に立ち会えないなんて、なんと憐れなことだろう。
三成は主の折れそうな手を包み込みながら、そんなことを思ったものだった。
三成の主は、やがて三成や正則の名を呟かなくなった。
家康や淀やおねや利家…これらを呟くようになった。
淀以外は皆いた。
淀は息子の世話をしていた。
主はひとしきり息子の名を言いながら唸ると、急に目をカッと開いた。
恐怖の表情で虚空を睨み付け、涙とよだれを垂れ流しながら唸った。
皆腰を退いたが、三成と正則とおねと利家は寝具の方にますます近付いた。
主は、声の限りに…掠れて消え入りそうな声だったが、叫んでいた。
許して下さい信長様
許して下さい信長様
おれを許して下さい信長様
連れて行かないで下さい信長様
まだ行きたくない
許して下さい信長様
信長様
信長様
信長様…
三成は唇を噛み締めて、亡きがらを見つめている利家を更に強い眼差しで見た。
あの時の利家は、これ以上白くなれないくらい真っ白だった三成の主と同じくらい、蒼白だった。
多分、例の噂を思い出していたのだろう。
あれは三成のこの主の体調が優れないと囁かれ始めた頃。
疑わしい噂が立ち込めた。
実は太閤殿下が織田信長公を死に追いやったらしい。
明智日向守光秀を影で操っていたのは太閤殿下らしい。
…どれもナンセンスなものだ。
三成は鼻であしらっていたが、死に際のあの現場を見せられると正直まごついてしまう。
まさか“太閤殿下”は本当に…。
三成でさえ、ほんの少し疑念を抱いた。
死に際の主が口走った“謝罪”は、信長公亡き後に織田の血を利用するだけ利用して結局は自ら政権の座についたことに対する謝罪だったのか。
それとも…。
利家も疑念を抱いたに違いないのに、利家は主の死を本気で悲しんでくれている。
三成にとって、それはとても嬉しいことだった。
しかし、当然のことかもしれないとも思った。
利家は三成より、主との付き合いは長い。
それは家康も同じな筈だが…まさに月とすっぽんだな…と三成はまた家康を見遣った。
家康の表情は先程までと同じ、よくわからないものだった。
三成さえ読めない。
戻る
