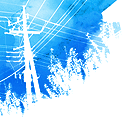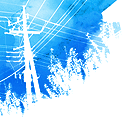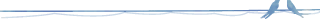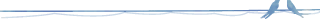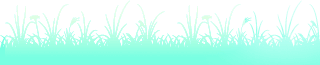『漂流者』10
言葉を無くした二人の前で、長針は更に一つ時間を進めた。針が進むたび、自分達の心臓の鼓動も大きくなる。そんな錯覚さえ覚え始めていた。
「さ、三時になりまする…!」
午前三時。それはつまり、寅の刻。
振り子時計が、古ぼけた音を三度響かせる。
そうか、昨日聞いたのはこの掛け軸の中の時計の音か。一人納得した真田が頷くと共に瞬きをすると、目を開けた瞬間には、男の姿は掛け軸の中から消えていた。
「旦那、あんた中々肝の据わったお方だねぇ。…それとも、まさかただのおバカさん?」
くつくつと笑う声。聞きなれぬ声音に慌てて顔を向ければ、昨夜見たあの男が…幽霊画の男が、己の隣に立っていた。
「二日連続でお会いしたヒトは、あんたが初めてだよ。」
やはり、夢でも幻でもなかった。
思わず立ち上がった真田は、近くなった男の顔をマジマジと正面から見つめた。
赤い髪。白い肌。だが、特別血色が悪いという気はしない。土汚れの付いた着物の裾からは二本の足が伸び、しっかりとフローリングの床を踏みしめている。
ふわりと香ったのは、草木や湿った土の、どこか懐かしい優しい匂い。
「お主は…幽霊、なのか?」
直球で投げた質問に、男は困ったような笑みを浮かべた。頬をかく指は、爪の先まで人間のそれと変わらない。
「幽霊、かもね。」
触れるかどうか試してみる?なんて冗談のように軽い口調で言われ、差し出された手に一瞬ためらう。
おずおずと手の平を重ねてみれば、そこにはしっかりとした手の感触があった。普通の人間と違うのは、ひんやりとした体温くらいだろうか。
幽霊なのか、ヒトなのか。それとも、もっと別の何かなのか。
困惑をあらわにして見つめても、目の前の男は笑顔を返すばかり。
「か、片倉殿…っ」
縋るような気持ちで先輩を振り向くが、残念ながら視線は交わらない。彼は常よりも一段と厳しい顔をして、なにか考えを巡らせている風だった。こちらの視線どころか呼びかけにさえ気付いていないようで、両目は掛け軸の男から逸れることがない。
思えば、彼が怪現象に出くわすのは今日が初めてだ。二日連続、更には会うことを望んでいた己とは違い、驚きも衝撃も大きいだろう。
ここは自分で乗り切るしかない。そう覚悟を決めて前を向くと、男は変わらず楽しげに笑っていた。
「ゆ、幽霊か否かはさておき…」
「うん?」
「貴殿のことを、某に教えて頂きたい。」
へ?と間抜けな声をあげた男は、目を大きく瞬かせた。崩れた表情も相まって、その姿は人間としか思えない。
重ねたままだった手の平を握手の形に変えて握りこみ、真田はもう一度「教えて欲しい」と繰り返した。
「なんでも良い。某は、貴殿のことが知りたい。」
ぽかんと口を開けた顔に、じわりと朱色がにじむ。
どこか初々しく映る表情は、掛け軸の中で見る憎悪の顔とは似ても似つかなかった。
掛け軸としての彼に、強く惹かれた。
けれど、今目の前にいる彼に、その比ではない程に惹かれている。
まるで恋のようだ。
そう自覚をすると、途端に顔が熱くなる。
照れ臭さに強く手を握りこむと、ぎゅっと、答えるように握り返された。
心なし、手が少しだけ温かくなった気がする。
「…俺様、大したこと知らないけど。それでもいーの?」
消え入りそうな小さな声に、真田は大きく頷いた。
- 10 -
戻る