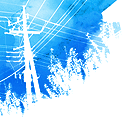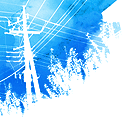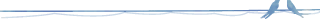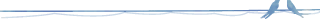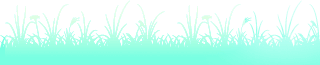19.言伝て
ヒデヨシとオチビさんが、家を出て行ってから数時間後。
彼らのいなくなった家に施錠をした女性は、その足で竹中の入院する病院へと向かった。
手にしたのは、一つの大きなカバンと大きな花束。花束は見舞いの品で、カバンは、今朝竹中が入院に備えて準備したものだ。
余計なものはいれないでくれ、との伝言に従って、中身には一切触れていない。
まだ青年と呼ぶに相応しいあの家の主は、親戚と呼ばれる面々に、あまり心を開いてはいなかった。
「まったく、可愛げのない…。」
思わず漏れた本音に、「なんであんな子供が、あの家に一人で住んでいるのよ」と、妬み混じりの悪態が続く。
聡い彼がそんな胸の内を見抜いていることなど、夢にも思っていないのだった。
病院の個室。真っ白なベッドに横たわった竹中は、部屋の扉が開く音に上体を起こした。
視界を遮断していたカーテンを開くと、予想通り、親戚の姿がそこにある。
ノックをするのが礼儀だろ、とは思ったところで口にはしない。今更注意してみても、更正されることはないだろう。
「いつもすみません。」
代わりに口に出したのは、事務的な挨拶の言葉。受け取ったカバンは、上部のチャックが少しばかり開いて見えた。
まさか、中身をいじくったのか?
疑問が生じるも、中身を確認するまでは不用意なことは言えない。もしかしたら、今朝、自分の締めが甘かっただけかもしれないからだ。
同時にカバンにヒデヨシ達の毛を見つけ、思わず溜め息を吐き出した。
突然の入院に、彼らには迷惑と心配をかけてしまっただろう。
特に気がかりなのは、オチビさん。以前一日体調を崩したときでさえ、彼はあんなにも悲しい顔をしていた。
それを再び具合の悪いところを見せてしまって、悔やんでも悔やみきれない失態だ。
(泣いていなければいいのだけど…。)
それとも、二回目だからと心の準備が出来ていただろうか。
(ヒデヨシが一緒だから、きっと大丈夫に決まっている。)
そうは思うのだけど、彼はまだ病み上がりの子猫。元来の性格もあってか、心配せずにはいられない。
ヒデヨシの後をついて歩き、大人びて振舞ってはいるが、実際にはまだまだ幼い子猫なのだ。
「おばさん。家に猫はいましたか?」
たまらず、隣に立つ女性へ声をかけた。
しかし、正直なところあまり答えを期待してはいない。この人は自分の前でこそ良い顔をしているが、その素顔は醜いものである。
自身が直接実害にあったことはないのだが、ヒデヨシの、彼女に対する態度を見ればすぐにわかることだ。それに、ヒデヨシを見る彼女の目も凍っている。
彼女はヒデヨシの前で吊り上げていた瞳を、今はわざとらしいくらいに細めて笑った。
「えぇ、もちろん。いつも通り、家から出して戸締りをしましたよ。自分から出て行って、賢い猫ちゃんだこと。」
「子猫はどうですか?」
子猫?と首を傾げる彼女に、やはり猫は好きではないのだと確信した。興味がないから、その姿が記憶に残っていないのだ。
宙をさ迷う視線は、機嫌を損ねないようにと、必死になって記憶の糸を探している。
「…あぁ、子猫!はいはい!お父さん猫が一緒にくわえて行きましたよ。仲が良いのねぇ!」
ふふふ、と笑う彼女に曖昧に笑みを返し、もはや用はないとばかりに退室をお願いした。もちろん、表面上あくまで物腰は柔らかく丁寧に、だ。
女性は少し不満げな顔をしたものの、「また来るから」と、大人しく病室を出て行った。
一人になった病室で、ようやくほっと息をつく。
「お父さん、か。」
きっと、本人にとってはとんでもなく不本意な言葉だろう。不機嫌なヒデヨシの顔を思い浮かべて、くすりと笑みが漏れる。
ヒデヨシは、彼女のことを嫌っている。
それは間違いない。それなのにわざわざ子猫と一緒に立ち去る姿をさらしたというのは、どうにも違和感がある。彼の、意思を感じる。
これはきっと、ヒデヨシなりのメッセージなのだろう。
どこへ行ったのか、どんな判断を下したのか。今は知る術はないけれど、何も問題はなさそうだ。
(本当、君って男はとても頼もしいよ。ヒデヨシ。)
大きな不安の種が取り除かれたところで、もう一つ。今朝自分で荷造りをしたカバンへと手を伸ばす。
彼女がなにか余計なことをしていないか、確認するためだ。
体の弱い自分のことを「心配している」などと口では言っているが、目に浮かんでいるのは紛れもない欲の色。
狙いが金か、あの家か、あるいはその両方かは知らないが、恩を売ろうとずいぶん必死なようだ。出来るだけ放っておいて欲しいのが本音だが、せっかくなので、こういう場合は遠慮なく利用させてもらっている。
(僕の性格の悪さなら、僕が誰よりも知っているさ。)
咳を一つして、中途半端に開いたチャックに手をかける。着替えの衣類を取り出すと、中から何かがポロリとこぼれ落ちた。
「?」
摘み上げたそれは、一本のねこじゃらし。
もっとも、まともな姿は保っていない。茎は途中で折れ曲がり、葉っぱは縦に引き裂かれ、種は所々落ちてしまっている。なんとも無残な姿である。
けれど、竹中はそのくたびれっぷりに見覚えがあった。
子猫が思いっきり遊んだ後は、たいていのねこじゃらしがコレと同じような有様になるのだ。(おかげで、庭に生えたねこじゃらしが、ずいぶんとその数を減らしていた。)
「…開いたチャックは、コレが原因か。」
よくよく見れば、金具の周りには猫の毛が集中的についている。
ボロボロのねこじゃらしを手の中で遊ばせれば、脳裏にいつもの光景が再生された。
草の揺れる裏庭。石の上で眠るヒデヨシ。元気にねこじゃらしを追いかけるオチビさん。
捕まえて、噛み付いて、蹴り上げて。ボロボロになったねこじゃらしを自分の元へ運んでくる、誇らしげな顔。
「二人とも、大丈夫みたいだね。」
ほっこりと温まった胸中に、知らず、安堵の笑みが浮かんだ。
猫にまで気を使われて、なんて情けない男だろうか。
(早く、元気にならないと。)
病室に置かれた立派な花瓶。そこに活けられた、豪華な花々。
その中で一際存在感を放つのは、ボロボロになったねこじゃらし。
場違いな姿の雑草は、なによりも彼の心を和ませるのだった。
- 20 -
戻る