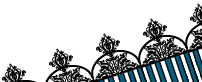「やあ、バーナビー君にロックバイソン君じゃないか。お疲れ、そしてお疲れ!」
爽やかな笑顔を振り撒きジャケットを脱いだキースは、それからも何事か喋っていたが、バーナビーはほとんど聞いていない。
三人の傍で終始笑顔の虎徹は普段と何ら変わった様子はなく、それが逆にバーナビーを不安にさせた。
◇◇◇
その日は、朝から雨が降っていた。
強くもなく弱くもないその雨は、シュテルンビルトの街全体を包みけぶらせている。
バーナビーはオフィスのブラインドから外の景色を眺めながら、背後で聞こえた生欠伸に眉間の皺を深くした。
サリバンは出先からの直帰らしく、今日はもうここには来ない。
だからだろうか、虎徹のだらけっぷりもいつにも増している。
「止まねぇな」
「ええ」
「梅雨かな」
「ツユ?」
「…何でもねぇ」
デスクに腕を組み、その上に顎を載せて無意味にハンチング帽の形を整えている。
横目でその様子を見ながら、バーナビーは窓から身を離した。
昨日は眠れましたか、と彼は頭の中で何度も復唱したが、ついぞその言葉は出てこない。
髪色と同じダークブラウンの太い睫毛は重そうに瞳に被り、ばらまいた書類には目もくれずに手元を動かしていた。
「虎徹さん」
「んー?」
「一度、実家に帰られたらどうです?」
ハンチング帽を弄る虎徹の手が止まる。
バーナビーは彼の方を向いた。
「最近のあなたは」
「もうほっていてくれよ」
バーナビーの言葉を遮る虎徹の声は、言葉の意味に反して力の抜けたようなものだった。
目を細め、一歩近づく彼に更に声が飛ぶ。
「確かにバニーちゃんは俺の…名実共にパートナーだし、頼りにもしてる」
でも、と掠れた低い声が空気をざらつかせた。
「俺は大丈夫だから。もう構わないでくれないか」
「虎徹さん…」
自分はずかずかと人の領域に入り込んでくるくせに、自分のことには一切触れさせようとしない虎徹に、バーナビーは舌打ちしたい気分になる。
後ろ姿しか見えない虎徹は、全身から拒絶オーラを出してバーナビーを牽制していた。
(こんなときばかり大人ぶって)
ずるい人だと、彼は寂しさを感じる。
同時にアントニオには話した不眠の事実を、虎徹の口から言ってもらえないこてにも不満を抱えていた。
共に過ごした年月の差は圧倒的だが、内容の濃さに関しては自分が勝ると自負していたバーナビーだけに、思うよりショックは大きい。
「分かりました」
素直に頷いて、頭を冷やそうとバーナビーはドアに向かって歩き出す。
今この雨に打たれれば、少しは気が紛れるだろうと思った。
そのとき。
バニー、と虎徹の声が聞こえた気がしてバーナビーが振り向くと、デスクからずるりと落下していく最中の体が見えた。
「え」
現実離れしたその光景はスローモーションに見え、虎徹が床に落ちきるまでの数秒がやけに長く感じる。
ガタン、とけたたましい椅子の転がる音に目が覚めたように瞼をしばたかせるバーナビーは、息を呑んで虎徹に近寄った。
「虎徹さん!」
危惧していたことが現実に起こってしまった。
バーナビーは焦りながら虎徹の傍まで行き、その上半身を抱える。
軽かった。こけた頬からも分かるが、彼はかなり痩せている。
手を伸ばし内線電話の受話器を取ると、受付の番号を手早く押して耳に押し当てた。
「虎徹さん…くそッ。ああ、バーナビーです! 今すぐ救急車を呼んでください!」
叫ぶようにして受話器に話しかけ、困惑している受付に事情を伝える。
虎徹の呼吸は浅く早く、触れている地肌の腕は平熱のように思えた。
電話の向こうでは焦るバーナビーの声に動揺している騒ぎが聞こえる。
「早く!」
『わ、わかりました!』
半ば怒鳴るように言って、バーナビーは受話器を投げ捨てた。力が余って電話機ごとデスクに転がるが、無視して虎徹の体を抱え上げる。
弛緩してずしりと重いが、先程感じた軽さは間違いないようだった。
虎徹さんと叫びながら部屋を横切り、ドアを蹴破る。蝶番ごと破損して廊下に散乱した破片を避けながら、バーナビーは必死に走った。
息をつく間もなく階段を駆け降りていく。
瞬間、見えた窓の外に救急車が来ている様子はない。
「まだ来てないのか!」
「あの」
「くそっ! 何やってるんだ」
「おい、バニー!」
「おじさんは黙ってて下さい!」
え、とバーナビーは自分の言った言葉に我に返った。
階段の踊り場で立ちすくみ、腕の中の重みに目線を移す。
「おじさん?」
「ああ。起きたよ…ジェットコースター並に揺れるから」
額を手の平で覆った虎徹は、バーナビーの肩をぽんぽんと軽く叩き乾いた笑みを漏らした。
「し、心配したんですよ! 急に、倒れるから!」
珍しくどもりながら言うバーナビーに、悪い悪いと言って腕の中でもがく虎徹は窓の外から聞こえてくる不穏な音に目を見張る。
町中を縫って雨をものともせずこちらに向かってくるその音は、やはり虎徹の危惧通りこのビルの下に止まった。
「あれ…もしかして」
「忘れてました。救急車を呼んだんです」
「はあ!? おま、軽はずみな行動は慎めよ!」
「その台詞、そっくりそのままあなたにお返しします。病院には行って頂きますよ」
ややイラついたように言って、バーナビーは踊り場から窓を覗き込む。
「虎徹さん、鍵を開けてください」
「え?」
「早く!」
バーナビーの気迫に圧され、虎徹はわたわたと手を伸ばして窓の鍵を開けた。
どうするん、まで言って最後の「だ」は空気に紛れて消える。
バーナビーは能力を発動させ、窓のサッシに足をかけた。無論、虎徹を抱えたまま。
「え、うわっ嘘だろ」
「少々派手ですがこれなら早く着けますから」
行きますよ、と言った時には、すでに飛び出していた。
少々ォ!? と律儀にツッコミを入れていた虎徹だが、突然の浮遊感と安定感のなさに思わずバーナビーの服をがしりと掴む。
「ぎゃあああああ」
これ以上ないほど、叫び声の手本とも言うべき大声を上げて落ちていく虎徹と涼しい顔のバーナビーの姿は、幸か不幸か雨に紛れて着地するまで気付かれなかった。
その後無事に救急車に乗せられた虎徹は、目を回しながら病院まで運ばれた。
◇◇◇
「あのなあ! バニー!」
「何ですか」
「確かにぶっ倒れたのは悪かったが、あれはねぇだろあれは!」
点滴の管をガチャガチャやりながら叫ぶ虎徹は、眉間に皺を寄せて立っているバーナビーを詰る。
「心配してくれんのは嬉しいし、救急車呼んでくれたのも…まあ俺だってそうするだろうけど!」
「けど、何ですか」
静かに聞き返すバーナビーに言葉を詰まらせる虎徹だが、頭をがしがしかいて自分の物言いを反芻するように目を伏せた。
「…ごめん」
ドアの外の喧騒が遠くなって、バーナビーにはその声がはっきり聞こえる。
「八つ当たりだ」
「虎徹さん」
「腫れ物に触るみたいに扱われんのが嫌で…ごめんな」
ふうと溜め息をついたバーナビーは、項垂れる虎徹の傍に行き丸椅子に座った。
必死で大人の対応をしているのが分かって、バーナビーは苦笑する。虎徹の独白は本心なのだろうが、納得しているようには見えなかった。
かさついた肌と目の下の隈から、この健康が取り柄の男がどれほど参っているかが窺えて、バーナビーは震える。
本当に、いなくなってしまいそうな気がして。
「どれくらい、眠れてないんですか」
「どれくらい…一週間くらいか」
「そんなに!?」
驚くバーナビーに虎徹はまあ、と前置きして続ける。
「うたた寝くらいはしてるんだけどよ。一時間もしねぇうちに目が覚めるんだ」
「病院にはかかったんですか」
「ああ。いくつか回ったけど…」
駄目だった、と力なく言った虎徹は、枕にばふんと頭を預けてふぅと長く息を吐いた。
バーナビーは自然に、その髪へ手を伸ばしていた。しなやかな黒髪はバーナビーの手の平にしっくり馴染み、すくほど柔らかくなっていく。
生え際をなぞると、虎徹はからからと笑った。
「おいおい、まだフッサフサだろォ。勘弁しろよ」
その疲れたような笑みに同じように苦笑して返すと、バーナビーは上半身を屈めて血色の悪い唇にキスをする。
僅かに身動ぎした体に連動するように、点滴のスタンドがかたりと音を立てた。
「な、バニー」
「何です…?」
「点滴終わったらさ」
――しようか。
何をとは、バーナビーも聞かない。
「はい」
雨は優しく街を濡らし、その表情を変えていた。
◇◇◇
「あ、あぁ、バニー」
「静かに。ばれてしまいますよ。ほら、僕の肩に寄りかかって」
「ん…」
ぽす、とバーナビーの左肩に顔を押し当てた虎徹は、腕を伸ばして背中の服を掴む。
狭い空間は逆に性欲を煽り、互いの怒張はすでに張りつめていた。
放置された点滴の管は、未だ病室で所在なげに立っているのだろう。
何せ二人が今いる場所は病棟にあった職員用のトイレの一番奥なのだから。
「ぅう、きもちいぃ」
「……っ」
耳元で低く甘い声が聞こえ、バーナビーは情欲が更に高まるのを感じた。
彼の右手は互いのものを同時に扱き、左手はみっしりと筋肉で覆われた尻を撫でている。
頭の中はひとつのことで占められていた。
繋がりたくて、感じ合いたくて、渇望は更なる渇きを生む。
「はやく、バニー、バーナビー」
「待って…久しぶりだからちゃんと解さないと」
「もう、欲しい。我慢できない」
ぎゅっとバーナビーの背中にしがみつき、虎徹は泣く。すぐ後ろに迫るドアがぎしぎしと軋むのも構わず、二人は性急に口付けを交わしあった。
「っは…はぁっ」
「入れて、バニーの…っ」
低く掠れた声は色に濡れて、今にも溶けてしまいそうだとバーナビーは思う。
抑えた吐息が漏れたのを彼は感じた。これほどまでに理性を抑えきれない衝動に侵されたのは初めてのように思った。
虎徹の体を反転させ、ドアに両手をつけさせる。
「痛かったら言って下さいね」
「う、く」
声を出さないようにと手に噛みつき、虎徹は来る衝撃に期待するようにぶるりと震えた。
「駄目ですよ。傷がつきます」
「ん…んぐ」
歯形のついた手を口から離し、バーナビーは自分の指を虎徹の舌に絡ませる。
ぬるりと湿って熱いそこは、バーナビーの指をつたなくしゃぶって端から漏れた唾液を垂らした。
「ふあ、ふぁにー、んや」
「可愛い…虎徹さん」
- 8 -
戻る