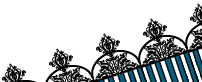「何にやけてるんです」
「だーって」
あのバニーが、俺にチャーハンを作ってくれてるなんてなぁ。
もう嬉しすぎて、おじさん死んじゃうかもしれない。
手狭なシステムキッチンも、こいつが立っているだけで上等な場所に見えてくるから不思議だ。
「楽しみだなぁ」
にやにやしながら、チャーハンが出来上がっていく行程を眺める。
中華鍋なんて本格的なもんはないが、深い底のフライパンでも十分なようだ。
手際よく具材をかき混ぜるバニーは、本当に絵になってカッコイイ。楓が見たら卒倒しそうだ。
「味は期待しないでくださいよ」
「うんうん。しないしない」
「…そう言われるのも何か癪ですね」
ガキみたいにびょんぴょん跳ねながらキッチン周りを回る。
俺とは少し違う味付けのチャーハンは、見た目も匂いも完璧でこれが美味くないわけがない。
「はい、完成」
「おおお! チャーハンだな!」
「当たり前です」
終始テンションの高い俺に冷静なツッコミを入れて、バニーは丁寧に盛り付けた。
それから、どこから出したのか、爪楊枝仕様のミニ国旗を立てる。可愛い奴め。
「食っていい?」
「ええ。机でお願いしますよ」
「おう。スプーンスプーン」
ガチャガチャやって食器棚からスプーンを取り出し、バニーの後をついていく。
ほかほかと湯気の出る皿を持つ後ろ姿なんか、これをブロマイドにしてばらまけばすげぇ儲かりそうな気さえする。
どうやってセットしてんのか、ふわふわした髪の毛に似合わないように見えるチャーハンも、豪華な料理に見えた。
「オハシで食べないんですか?」
「オハシ? ああ、箸か。チャーハンはスプーンだろ」
「ふぅん」
オハシの発音がかなり怪しいが、バニーは興味深そうに相槌を打つ。
「どうぞ。召し上がって下さい」
「ありがとな! いただきます」
机に置いたチャーハンを前に手を合わせ、じっとこっちを見るバニーにもう一度にやけ顔を拝ませてから、スプーンで掬って口に入れた。
「……」
「どうですか」
「うん、美味い!」
お世辞なしに美味い。何の技術か、卵と飯は絶妙に絡んでいるしベースに入れたらしい醤油が焦げて香ばしい匂いが口いっぱいに広がる。
具材の厚切り豚肉と野菜にもしっかり火が通って、まあ何というか、文句なしに美味かった。
「バニーも食う?」
「いえ、僕は結構です。散々食べましたから」
「なにお前、俺に内緒で食ったのかよぉ。寂しい奴だな」
「勘違いしないでください。僕が食べたのは自分で作った失敗作です」
うわ。
顔が一気に熱くなる。何なのこいつ、練習したの。
ああもう、可愛い可愛い。
あの広いキッチンで真剣にチャーハン作ってるバニーなんて、似合わなすぎて可愛い。
俺のためにたくさん失敗して、それ自分で食うなんて、もしかしなくても俺って愛されてる?
「全部口に出てますよ。虎徹さん」
「感動してんだよ」
「ただのチャーハンなのに」
照れたように口を尖らせて言うバニーに笑いかけて、ああ美味い美味いと一気に食った。
残ったのはあのミニ国旗と、綺麗になった皿とスプーンだけ。
腹をぼんぽんと撫でて手を合わせる。
「ごちそうさま。ありがとな! めっっっちゃ美味かったよ」
「いえいえ。あなたの口に合ったのならよかったです」
ものの十分も経たずになくなったチャーハンは、もっと惜しみながら食えばよかったなぁなんて思いながら座っていると、バニーが食器を持ち上げた。
「上げ膳下げ膳だなぁ。久しぶりの感覚。ハハハ」
「なんならこれからもしましょうか」
半分振り向いて言うバニーに、そりゃいいなぁと答える。
カチャ、と割と近場で食器の重なる音がして、そちらを見るとバニーが床に皿を置いていた。
どうした、と聞こうとすると真剣な顔をした奴が名前を呼ぶ。
「ん?」
「一緒に住みませんか」
「え?」
「僕と一緒に、暮らしませんか」
藪から棒。というわけでもなかった。
バニーとただならぬ関係になって、ほんのりと何度か打診されていた提案だった。
その度にうやむやにして誤魔化していたが、そろそろ潮時だろうか。
「この家でも、僕のマンションでもいいんです」
ずっとあなたといたい。
ストレートな言葉に、年甲斐もなく胸が高まる。嬉しすぎてどうにかなりそうだ。
――でも。
「多分、一緒に住んだら…ダメになると思う」
「え?」
「お前が嫌だとかそういうんじゃないからな! そうじゃなくて」
少なくとも俺は、バニーといた毎日毎日が発見の連続だった。
こんな表情もするのかとか、意外な食べ物が苦手だったりとか、慌ただしく過ぎる日々の中で見つけるそれらが、物凄く新鮮だったから。
バニーはぽつりぽつりと話す俺の言葉を静かに聞いていたが、ふと優しい表情になる。
「あなたらしいですね」
そう言うと、屈んで床に置いたままだった皿を持ち上げた。
「さっきまで、僕はあなたがチャーハンをオハシで食べると思ってました」
相変わらずオハシの発音はおかしかったが、バニーはやや困ったような微笑みを湛えている。
キッチンカウンターに皿を置いてまた戻ってきた奴は、俺の横に腰を下ろして前を見据えた。
「一年間虎徹さんを見てきたのに、あなたに関して僕は知らないことばかりです」
「バニー…」
「一緒に住んだらきっとそういうのももっと早く、たくさん分かるかもしれないと、僕は思ったんですけど」
食い下がるような物言いだが、バニーの顔は依然優しいままだ。
白い大きな手が伸びてきて睫毛に触れる。
自然に相手の同じ場所に視線がいき、長く金色に輝く睫毛を見た。
「あなたがそう言うなら、このままで我慢します」
「…ごめんな」
大人な対応で接してくれたバニーは、さっきまで可愛くて仕方なかった男とは別人のようだ。
同じソファに腰かけて、明るい部屋で話しているのが逆に何だか現実離れしている気がした。
「まあ、突然僕と虎徹さんが一緒に暮らし始めたら、周りの驚きが恐ろしいですね」
「まあな。お前のファンに殺されちまう」
「僕だってあなたのファンに殺されそうですよ」
「俺のファンねぇ」
ハハハ、と笑って目にかかる手を掴むと、呆気なく離れていく温度がすこし寂しい。
「チャーハン、また作ってな」
「ええ」
もちろん、と言ってくれたバニーは、ハンサムスマイルを惜しげもなくさらけ出して、こちらの肩に頭を預ける。
なんだ、男前の次は甘えたか?
兎の可愛いギャップにおじさんついていけない。
「色々したかったんです。キングサイズベッドを下見に行ったりもした」
「マジか。てかキングサイズって。ハハ」
「あなたと二人でカワノジに寝たかったんです」
「二人で川の字はちょっとできそうにねぇなぁ」
様々に間違っている日本語に苦笑しながら、肩に乗っかる重みを受ける。
今日は幸せな日だ。
バニーがチャーハンを作ってくれて、一緒に暮らそうと言ってくれて、俺の話を受け入れてくれて、今はこうして甘えてくれている。
友恵がいなくなってから、こんな充足感は感じたことがなかった。
いつもいつも自分だけが幸せになっていいのかと、小さな罪の意識に苛まれていた。
「虎の縫いぐるみとか、買ったりとか」
「んー、じゃあ兎のも買わないとな」
きっとバニーも同じ痛みに苦しんでいたからこそ、この空間があるんだと思うと、何だか感慨深かった。
「兎のはいりません。ブタの貯金箱を買うんです」
「お前、どっからその知識を仕入れてきてんの」
「折紙先輩から」
「あーなるほど」
俺が笑うと、バニーも笑う。
一人で居すぎて忘れてたしまっていたのかもしれない。
誰かと何かを共有することが、こんなにも幸せなんだと改めて気付かされた。
静かな部屋の真ん中、ソファに座ったデカい男が無意味に体をくっつけてただ喋る。
そんななんでもないありふれた時間が、本当は一番手に入りにくいんだろう。
だからこそ、今を大事にしたい。
「虎徹さんのチャーハンも食べたいです」
「おう、作ってやるよ」
「ピーマンは入れないで下さいね」
「えーバニーちゃん、ピーマン食えないのかよ」
だっせーと茶化すと、うるさいですと今まで通り冷静なツッコミが飛ぶ。
ああ、本当に今日は気分がいい。
ふわふわのバニーヘアを撫でながら、俺はふわあと欠伸をした。
おわり
デレおじ。
そんなおじさんが好きです←
- 6 -
戻る