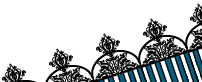「チョコレートフォンデュがしたいです」
「男二人で?」
「恋人二人でです」
二日間の休みをもらったのだと嬉しそうに喋るバーナビーが、何やら大きな段ボールを抱えて二階に上がってきたのが一時間前。
段ボールの中身を組み立て、見覚えのある形になったのが二十分前。
鞄から大量に板チョコを取り出し、虎徹の前に広げたのが五分前だ。
「つってもなぁ、今フルーツとかないし」
「今日売れ残ったお菓子を使いましょうよ」
「残念。売り切れご免だったよ」
すでに虎徹のものと化しているバーナビーの黒いセーターを着て、彼は手を振ってみせる。
少し袖が余ってしまっているが、手首が特に寒いと言う彼にはちょうどよいとのことだった。
逆に首回りは少し開きすぎているが、元々体温が高いらしく余り気にしていないようだ。
むうとふくれたバーナビーは、組み立て終わった機械を眺める。
小さいながらタワーのような構造になっているそれは、可愛らしいピンク色の装飾がされ天辺にはハートがついていた。
「今ウチには野菜とチャーハンの具しかねぇよ。まさかエビでやるわけにはいかないだろ」
「いや、頑張れば…」
「そもそもこんな可愛いの、どっから買ってきたんだ?」
「近所のおもちゃ屋で」
やっぱりな、と虎徹は苦笑した。結んだ髪の間から頭皮をポリポリと掻く。
幼い頃から大人びていたという彼は、その時抑圧されていた欲求の反動かよく子供の玩具を衝動買いしていた。
大概は電車や車、プラモデルを買っているようだったが、遊ぶわけでも並べて鑑賞するでもなく部屋に置いてあるため、少し前から施設などに送っているらしい。
別に迷惑をかけているわけでもないからと、虎徹は何も言わずに来たがまさかこんなものを買ってくるとは思わなかった。
「またの機会にしとこうぜ。チョコレートだけあっても意味ないし」
「…今日、やりたかったのに」
「うん。俺もしたかったけどな」
電源だけを無意味につけて稼働するチョコレートフォンデュの機械を見ながら、二人は板チョコをバリバリ食べる。
時刻はそろそろゴールデンタイムだ。夕食は虎徹がチャーハンを作る段取りで動いていたが、この分だと板チョコだけで腹を満たせそうだ。
「チャーハン食う?」
板チョコをぱきっと割って噛む虎徹が聞くと、バーナビーは拗ねた顔でこくりと頷いた。
よし、と掛け声を上げて立ち上がった虎徹は、椅子に座って稼働し続ける機械を睨みつけるバーナビーの頭をぽんぽんと撫でる。
すぐ傍のキッチンに立った彼はいつもしている黒いエプロンをして、早速冷蔵庫を開けた。
昼間出しておいた魚介がいい具合に溶けているのを確認し、シンクに取り出してから再び冷蔵庫に戻り、卵を四つ手に取った。
「今日はとっておきだぞ」
日本から個人輸入した炊飯器を開くと、白い水蒸気がもわりと立ち上る。
おお、いいねぇと思わず呟いた虎徹だったが、その体を突然羽交い締めにされ「おわっ」と声を上げてしまった。
「ちょっ、バニー! 危ないだろっ」
「虎徹さん…」
「おま、こらこらこら、尻に何を当ててんだ! キッチンではしねぇって言っただろ!」
「キッチンにいるあなたを見てるとムラムラしてくるんです」
む、ムラムラって…と顔を赤くした虎徹は緩まない力に諦めを強め、とりあえず炊飯器の蓋を閉めようと手を伸ばす。
だがそれも掴まれて、すでに拘束されている右手と共に片手の中に収まってしまった。
(お、おいおい…おっさんとはいえ男の腕を片手で…ちょっと落ち込むじゃねぇか)
炊飯器が開いたままなのが気になって仕方ない虎徹だが、バーナビーは力を緩めるどころか背後からぴたりとくっついてエプロン越しに股間を撫で擦ってくる。
腰には既に張り詰めたバーナビーのものがぐいぐいと押し付けられ、逃げようにも逃げられない態勢になっていた。
「バニーちゃん、ちょっとだけでいいから落ち着こう。な? べ、ベッド行、んあッ」
言い募ろうとした虎徹の耳を、バーナビーはねっとりと舌で愛撫した。
耳から熱が全身に広がっていくような感覚に、バーナビーの手を押し返す股間の力が強まった。
べちゃべちゃと犬のように虎徹の耳から首を舐め回すバーナビーは、その間も手を休めずに刺激を与えていく。
そのうち不埒な手はエプロンの中に滑り込み、部屋着のズボンの中に入った。
「虎徹さん、ん…あなたのここ、すごくあったかい」
「はず、かし、こと言うなっ」
「パンツが濡れてきましたよ」
徐々に現れてくる形に沿って指を動かされ、更に耳元で低く呟かれては虎徹ももう料理どころではない。
緩急をつけて撫でられるとどうにも堪らなくなっつしまう。かくかくと笑い出す膝を叱咤して何とか立つが、がっちりと掴まれて離れない腕で体重を支えられない分重心は簡単にふらついた。
「あっ、はぁ…っ、バニ、おいって」
「甘い匂いがしますね…たまらない」
すん、と肩口に鼻を押し当てるバーナビーにこれ以上ないほどに赤面する虎徹は、とうとう立っていられずに膝を折る。
やや背の低くなった虎徹を労るように優しく抱き上げ、キッチンの壁に腰を落ち着けたバーナビーはそのままズルズルと床に尻をつけた。
「ん、虎徹さん、熱い」
「ふぁ、もぉ…っ、ちゃんと触れよぉ」
「パンツの布と擦れて気持ちいいでしょう?」
「よく、ねぇよバカっ、あぁうっ」
叫んだ彼のペニスをぎゅっと握ると、驚いたように跳ねたら肌がいとおしい。バーナビーは一心に手を動かしながら虎徹の耳や首を舐め、唇を求める。
その間もずっと掴んだままの両手はぎゅっと拳を握り、エプロンの胸部分を掴んでいた。
「んんっ、ふぅ、う」
真っ白になった指先は震え、酸素の足りない頭はくらくらとぼやけてくる。
そこでようやく、先走りに濡れそぼつペニスにバーナビー自身の手が絡み付いた。
ああ、とあらもない声を上げて体を縮める虎徹は、膝を擦り合わせようと足を寄せる。
いつもならそこにいるはずの男は、今は後ろにいて手だけを懸命に動かしている事実に、虎徹はどうしようもない羞恥を感じて俯いた。
「虎徹さん?」
「はっ、はぁっ…あ」
「イきたいんですね。先走りがすごい量だ」
「……っ」
あからさまな言葉に耳を塞ぎたくなるが、両手共今はバーナビーに拘束されたまま。
浮いてくる爪先を咎めるものはどこにもなく、じゅぷっじゅぷっと嫌でも拾う不快な音まで虎徹を追い詰めた。
「はぁっ、うぁ、バニ、イくッ」
「ええ」
限界を訴える声に低く返して、バーナビーは再び耳の中に舌をぬるりと入れる。
「ああああっ、いや、だ」
抱きすくめた体は魚のように跳ねさせ、重い頭を後ろの肩に乗せた彼はチカチカと明滅する景色に意識をも手放しかけた。
ふ、と外れた手首の拘束は、滑るように虎徹の肌を撫で髪を結んでいたゴムを取る。
「はあっ、はっ、はっ」
「いつもよりオーガズムが長くなかったですか?」
「し、るか…はぁ、はぁっ」
くたりと弛緩した体をバーナビーに預けて目を瞑る虎徹は、再びごそごそしだした手にようよう瞼をこじ開けた。
「おい」
何してんだ、と言いかけたその瞬間。
今まで感じたことのない浮遊感に襲われて虎徹は、目を回した。
「わわっ」
「ソファに行きましょう」
「え、いやちょっ…バニーちゃん自分で歩けるからッ」
「ええ」
「す、炊飯器の蓋っ」
「あとで。お願いします」
そう言っておかしな態勢でひょこひょこと歩き出したバーナビーを下から見上げながら、彼の毛穴ひとつない滑らかな肌にぽーっと見とれてしまう。
これが世に言うお姫様抱っこというやつかなどと冷静に思う虎徹だったが、ソファまでの道のりでバーナビーの手がチョコレートを取ったことに驚愕の声を上げた。
「おい、それどうするつもりだよ!」
「大丈夫大丈夫」
「何が大丈夫だ! おろせ!」
「大丈夫大丈夫」
この夜虎徹が新しい扉を開けてしまったことは――言うまでもない。
おわり
- 36 -
戻る