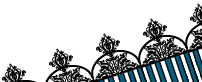甘いにおいの、する人だと思った。
sweeeeet!
「で、こっちがベルギー産のチョコレート。これはオランダ産のラズベリー」
「随分たくさん買いましたね」
「そりゃあ可愛い娘のバースデーケーキだからな」
キッチンにどさっと広げた材料の数々を見下ろして、虎徹は腕を組んでいた。その背後から何やら不満げな顔をして立っているバーナビーは、オランダ産というラズベリーを一粒手に取って口に運ぶ。
あっ、コラ食うなよという咎める声も無視して咀嚼すると、上質な甘酸っぱさがいやらしくなくふわりと広がった。
バーナビーはふうんとひとつ唸ると、材料を見分している髪を纏めた虎徹の首筋にちゅっと唇をつける。
「こらこらこら」
「美味しいですね。ちなみに僕は貴方を食べたいんですが」
「そういうことはもっと大人になってから言え」
更に腰を抱こうとしてくりバーナビーの腹にエルボーを決め、手の平で迫る顔を押し止めた。
「どうして今なんです? パーティーは明日の午後からでしょう」
「今夜のうちに作らねぇとだめなの。明日は家の飾り付けとかすんだから」
「だからって今からって時に…ひどいです」
「ティッシュ使いきっていいからトイレでしてきなさい」
「僕にオナニーをしろと? 嫌です。トップモデルはオナニーなんかしないんです」
「へー初耳だなそりゃ」
腰にまとわりつくバーナビーをいなして、虎徹は早速ケーキ作りに取り掛かった。
未だ虎徹さん虎徹さんとうるさいバーナビーだが、意図を持って触ることはしなくなる。
その様子に軽く微笑む虎徹は、いい子だなと呟いてチョコレートの欠片を口元まで持っていってやった。
――バーナビー・ブルックス・Jr.は、今やアメリカを代表するトップモデルの一人だ。
その折紙付きの美貌とスタイル、加えて有名大学を首席で卒業した頭脳。更には事故で命を落とした両親から受け継いだ莫大な遺産が、彼を一流セレブの仲間入りを果たすのに一役買った。
最早この国にその名を知らぬものはないだろうという程、将来を期待される若きカリスマ。
「見てるだけなら手伝ってよバニーちゃん」
「早く作り終われば一緒に寝てくれますか?」
「考えとく」
片やこちら、柔和な笑顔でケーキを作る男の名は鏑木虎徹。一目でアジア人と分かるそのオリエンタルな顔立ちは、年を重ねてはいるが未だ若々しい。
バーナビーのような華やかさはないものの、どこか見る者を安心させる不思議な魅力を持っていた。
彼のケーキを作る手際はかなりいい。それもそのはず、鏑木虎徹は小さな菓子専門店を営むオーナーパティシエなのだ。
日本人の繊細な手先から産み出される菓子は、作り手同様派手な装飾はないが食べやすさと美味しさを研究した可愛らしいもの。
主に焼き菓子を扱っているが、注文があれば何でも作るオールマイティーな職人だった。
「チョコレートケーキですか」
「うん。楓はチョコレートケーキが一番好きなんだ」
「知ってますよ。その次がエクレアで、次がチョコレートシフォンでしょう」
「娘はやらんぞ」
「何でそうなるんですか」
呆れたように言って、バーナビーはチョコレートを湯煎用の鍋に割って入れた。
その間虎徹はチョコレートに練り込む為にラズベリーを丁寧に解していく。
「チョコレートはいい。何たって美味いからな」
「ぷっ…子供みたいですね」
「いいんだよ。ホントのことなんだから」
午後十時、すこし前。
バーナビーはチョコレートとラズベリーの甘い香りに包まれながら、もう何度も思い出してはくすぐったくなるあの日を反芻した。
*
雨のひどい夕方だった。大規模な道路工事があるとかで電車で通勤したバーナビーだったが、余りの雨量に電車が運休になってしまった。
仕方なくタクシーで帰宅しようとしたのだが、考えることは皆同じ。待てど暮らせど通りかかるイエローは人を乗せて空車など一台も通りかからない。
ついてないなと思いながら役に立たない傘を畳み、通りにずらりと並ぶ店舗の軒下を少々拝借しようと歩みを進め。
――菓子屋? こんなところに。
そんな彼だが、甘い匂いに連れられて一軒の店が目に止まった。
元々辛党で甘味には強くない舌ではあるが、その店から漂う香りには何故か抗えずふらふらと店に入る。
外の雨音とは一変、スローテンポな曲が流れる店内は暖かかった。
昔はよく見た客を知らせるドアベルも、本来の意味を忠実に守りドアの上についてバーナビーの存在を知らせる。
一歩足を踏み入れると、甘い香りばかりではなく上質なコーヒーも香っていた。
――やあ、いらっしゃい。降られたみたいだなぁ。
やけにフランクな口調でバーナビーを出迎えた男は、薄い茶色の瞳を優しげに微笑ませて口元のカップをソーサーに置いた。
やや長めの黒髪を後ろで束ね、キッチンスタッフの装いにギャルソンエプロンをつけた彼は、履き込んだ革靴の音高らかにバーナビーに近付いてくる。
狭い店内にはよくあるショーウィンドウが置かれ、中には小さな菓子やケーキが並んでいた。設置されている席は三ヶ所のみで、どれも二人掛けだ。
――この天気で閑古鳥でさぁ。暇してたんだ。ちょうどよかった。
――店員なんですか?
――そうだよ。はいメニュー。
葉書より少し大きめにカットした羊皮紙が、椅子に座ったバーナビーの前に差し出される。
枠をキャメルの革で覆ってあり、皺がいい具合に出ていてそれだけで目を楽しませた。
バーナビーは店内に漂う甘い香りにどこか心を弾ませながら、メニューを開く。
――君みたいな若くてハンサムな子が一人でこんなところに来るってことは、雨宿りか?
――あ、気を悪くしないで下さいね。いい匂いがしたもので。
――謝るなよ。お陰で俺は助かった。
人懐こい笑顔を見せて、店員は再び靴音を響かせてバーナビーの傍から離れた。
絶妙のタイミングだな、とバーナビーはひっそり思う。このところ仕事で齷齪(あくせく)と動き回ってばかりいたから、丁度いい骨休めになるはずだ。
メニューには大方他店が取り扱っているものと同じものが並んでいるが、その価格は驚く程安い。
相場の半額程だ。
――随分安いんですね。
――あ? ああ。利益度外視ってやつだな。決まったか?
――ではこの…パウンドケーキとホットミルクを。
――はいよ。ちょっと待っててくれな。
奥から男の声が聞こえ、何やら食器を触る音がし始める。
バーナビーが手持ちぶさたに店内を見回すと、丁度スローテンポな曲が途切れ新たな曲がかかった。
一瞬だけ強い雨足の音が聞こえるが、すぐに掻き消される。
木目調の建材で統一された店内は温かみがあり、とても落ち着いた。
窓辺やちょっとしたデッドスペースには様々なスノードームが置かれていて、バーナビーはそのひとつを手にとって眺めてみる。
マフラーを巻いたテディベアが、小さな町の中で微笑んでいた。
――可愛いだろ。
――あ、すみません、勝手に。
中身を一心に覗き込んでいると、小脇に何かを抱えた男が立っている。
――いいよ。俺が奥さんと旅行先で買ってきたやつなんだ。それはイギリスに行ったときの。パディントンって知ってるか?
――ええ、絵本のキャラクターですよね。
バーナビーからスノードームを受け取った男は、球体を振って中の雪を舞い上がらせた。
今まで何度だって見てきたはずなのに、まして今は秋なのに、バーナビーはその美しさに見とれる。
雪が舞い終わるとどこか寂しくて、再び球体を揺らしていた子供の頃を思い出した。
スノードームをバーナビーの座る机に置いた男は、小脇に抱えていたランチョンマットを敷いてフォークをそっと据える。
ふと視線を外したバーナビーの耳に、つい先程始まった曲が聞こえてきた。
――雨に唄えばだ。
思わず口に出してしまってから、はっとして視線を戻す。
――へえ、若いのによく知ってるな。
――ゆ、有名な曲ですから。それに仕事で何回か聞いたこともありますし。
――映画関係?
――いえ。モデルを…少しだけ。
――モデル! 道理でハンサムなはずだ。
尻すぼみになった声。バーナビーは何故か羞恥を感じて顔を赤くした。
モデル、モデルかぁと俄にはしゃきだした男にも照れてしまう。一体何が、と思っていると、男が何か考えるように腕を組んで唸った。
――どうしました?
――ええっと…何てったかな。最近よく見るモデルがいんじゃん。娘がすげえファンなんだよ。君もし会えたらサインもらってくんない?
図々しい頼みではあるが、バーナビーには何故かそうは聞こえなかった。
むしろ叶えてあげたい、とも思っていた。
偶然入ったカフェで出会った赤の他人なのに。
――いいですよ。もし会えたならお願いしておきます。名前は何と言うんですか?
営業スマイルを何とか張り付けて羞恥心をごまかし問うと、男はまたもや唸って額を押さえた。
その手の指に光る指輪は、薬指に嵌まっている。
理由は分からないが、それを見た瞬間気分が落ち込んだ。
バーナビーは彼の長い指を見ながら、その手を自分が舐めている様子を思い浮かべる。
全くもって自分が信じられなかったが、一度浮かんだ妄想は消えない。
――ああ! 思い出した。バニービー・ブロッカス・Jr.だ! …あれ? なんか違うな。バニーリー? ん?
――もしかしてバーナビー・ブルックス・Jr.ですか?
――そうそうそう! あーよかった。すっきりしたー。
そう言って胸に手を当てた男に、バーナビーはゴクリと喉を鳴らしていた。
このスノードームのテディベアのように、自分だけの檻に囲ってしまいたい。
出会って二十分程しか経っていないのにすでにそんな心境を作り出している自分は、どこかおかしくなってしまったのだろうか。
この男が仮に女性ならば、あるいは説明はつくが。
どこからどう見ても一般的な成人男性、いやむしろ一般よりスペックは高いように見える。
長身で細身だが、袖を捲った腕は筋肉質で逞しい。
透き通る樹液のような甘い色をした瞳は、優しく垂れていて可愛らしさすらある。
バーナビーは自分の鞄から名刺入れを取り出して一枚を引き抜いた。
――?
きょとんとしている男に合わせ立ち上がり、名刺を差し出した。
――実は僕、こういう者でして。
名刺を見た彼の表情は、今でもバーナビーを満面の笑顔にさせてくれる。
*
「なにニヤニヤしてんだよ」
ケーキの生地を型に流し込んでいる最中、虎徹は自分を見ながらにやつく男に声をかけた。
卵を多めに入れた黄色い生地が全て流し込まれると、とろりとした液体かツヤツヤ輝く。
「いえ。あなたに出会った時の事を思い出していました」
「おいまたかよ。もういいだろあん時のことは」
「だって貴方、僕がバーナビーだって知った瞬間すごい勢いで謝ってきて…注文したパウンドケーキをタダにした上店のお菓子全部持ってけって言い出すから」
「ったく。人が悪いぜ」
顔を赤くする虎徹に尚も笑いながら、バーナビーは今この瞬間の幸せを噛み締めていた。
もし道路工事があの日ではなかったら。
もし電車が運休しなければ。
もしタクシーを捕まえていたら。
もし入った店があそこでなかったら。
度重なる偶然の連鎖によって、バーナビーは虎徹という人間に出会えたのだ。
彼は何度か虎徹にこの事の凄さを説明してみせるのだが、虎徹はまるで取り合おうとしない。
彼曰く出会うべくして出会ったのなら、他の場所ででもまみえていたはずだと。
それも中々の殺し文句なのだが、言った本人はそうと気付かない。
バーナビーはこうして恋人同士になれた喜びを、いつだって感じていたいのだ。
- 31 -
戻る