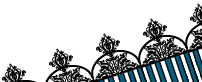あ、と思ったときには遅かった。バニーの不埒な手のひらが俺の腰を撫でて行くのを阻止できず、ひん、とへんな声が漏れてしまう。
インタビュアーが奇妙なものでも見るような目をこちらに向けるが、咄嗟にバニーが「ところで」と話題を振ったおかげで難を逃れた。
自分でピンチを作っておきながらそれを回避するなんざ、一体なにがしたいんだ。
「……」
いいや。なにがしたいかは分かってる。
奴は嫌がらせをしているんだ。一昨日した告白の、嫌がらせを。
◇◇◇
発端は二日前の午後だった。俺たちはアポロンメディアのオフィスで例によって書類仕事をしていた。
経理のおばちゃんは休みで不在、つまりは俺とバニーの二人だけが広い部屋に囲われていた。
『どうだ。一部の感覚は戻ったか』
『ええまあ。あなたは?』
他愛もない話をしながら、つい先日まで在籍していた二部ヒーロー達のことを考える。
マーベリック事件が終息し、なんやかんやで二部ヒーローとして活動していた俺達が一部に昇格したのは、つい二週間程前のこと。
たとえ頭を失っても、アポロンメディアはヤマタノオロチだ。マーベリックがいた頃となんら変わらない日常が、返り咲いた一部にはあった。
マーベリックもまた表の顔は資本主義の歯車だったのかと語りながらバニーと酒を呑んだのは記憶に新しい。
『…傷は』
『おい、大丈夫って言ったろ。もう半年以上前だぜ。後遺症もないし』
『ええ。でも心配なんです。本当に』
本気で不安そうな顔をしているバニーに笑いかけ、ほんの10ヶ月程前のことを思い出した。
俺は頬杖をついて横を向き、そのとき自覚した気持ちを反芻した。
好きなんだ。バニーが。心の底から。
何日も何日も考えて、悩んで、図太いと思っていたのに体重も落ちた。急性の胃炎とかいうのにもなった。
でもやっぱり答えは最初から見えていたのかもしれない。
あの日、死を覚悟したあの瞬間に、俺はもうとっくに認めていたんだ。
バニーの涙が胸に痛くて、今でもあの泣き顔は忘れられないのは、俺がこいつを、バニーを、好きだから。
『なぁバニー』
だからって何かアクションを起こすわけでもなく10ヶ月が過ぎて、それでも俺たちはここにいる。
なら、それでもういいじゃねぇか。
充分あった、いやありすぎた時間の中で俺はあるひとつの結論を出した。
卑下するわけじゃないが、俺なんかがバニーに好きだなんて言うのはコメディだ。
オジサンだし、既婚だし、娘もいる。
このままバディのタイガー&バーナビーでいようじゃないか。
四十路の恋は茨の道だ。
『俺、お前のこと好きだ』
なのに。
『え?』
『…あれ』
俺はどうゆうわけか、このままバディヒーローでいよう! と誓ったその瞬間に、バニーに好きだと言っていた。
『こて』
きっと「だからこれからもよろしく!」的なことを言えばよかったんだろうが、俺はまたしても墓穴を掘った。
散らかしていたデスクの上を更に散らかし、何故かバニーが出していたコインをひっつかみ、俺はその場を逃げ出したのだ。
◇◇◇
どういうつもりなんだこいつは。
どういうつもりなんだこいつは! ああ!?
俺はバニーの後ろをついていきながら、奴の後頭部を睨み付けていた。
相変わらず派手なアタマしやがって。なんだその髪型。重力無視すんな。
「レーザーでも出そうな勢いですね」
「あ!?」
「いえ。視線が刺さるもので」
睨んでいたことに気付いていたらしい。
後頭部に目でもついているんだろうか。
「頭に目なんかついてませんよ」
「!?」
「そんな顔してます。ほんと、考えていることがすぐ表情に出る人ですね」
「…お褒めに預かり光栄だよ」
「笑えません」
偏屈め。
俺は半眼になってバニーを見た。
フフン、と嫌味なセレブみたいに笑って何故かこっちに近付いてくる。
俺は慌てた。逃げよう、咄嗟に思う。
ここは廊下だが、数メートル後ろはアポロンメディアの二階ロビーだ。
そんなとこに俺が全速力で駆け込んでいったら職員が何事かと思う。
仕方ない、バニーを振り切って前に逃げよう。
そう思ってた足に力を入れた、その瞬間だった。バニーの背後、つまり俺の前から何やら歓談しながら歩いてくる男が二人見えた。
ちっ、と舌打ちをして辺りを見回す。ここは連絡通路で部屋もない。やばい。
「なにをキョロキョロしてるんです」
捕まった。手首をとられて、呆れたような目を向けられる。
「ああ、いや…」
「普通にしてないと、あの二人にばれてしまいますよ」
ばれるって何がだよ。
俺がお前のこと好きなのが、何であの二人にばれるんだ。
俺は自分が震えてくるのがわかった。
「それともばれてほしいんですか?」
バニーに掴まれている手首を、思いっきり振り払う。
びくっとして目を見開いた奴の横を通り抜けて、前から歩いてくる二人組に突進する勢いで通りすぎた。
危ねぇだろ、と叫び声が聞こえたが無視する。俺がワイルドタイガーだと気づかれただろうか。
――いや、どうだっていい。もうバニーの傍にはいられない。いたくない。
やめよう、アポロンメディアを出て、ネイサンのとこにでも就職しよう。
スーツなら前のを使えばいいさ。綺麗にとってあるんだ。
「虎徹さん!」
「来んな!」
お前みたいにカッコよくてスマートで、頭も切れてしかも若いし能力もある男に、恋した俺がバカだった。
◇◇◇
僕は必死に虎徹さんを追いかけていた。
それは、言いすぎた部分もあったかもしれないが、可愛いもんじゃないか。
でも、そう思っていたのも十秒前のことだ。
どこか甘えていた。虎徹さんなら、笑って許してくれると思っていた。
「……っ」
僕は虎徹さんの腕をようやく掴み、一瞬見えたドアを開けてそこに彼の体を引っ張り込む。
いたっ、と声が聞こえたが無視してドアをばたんと閉めた。
「ちょっと!」
まだ逃げようとする体をがしりと掴まえて、壁際に追いやる。荒く息をする虎徹さんのアイパッチはずれていて、大きな目から子供のようにポロポロ涙を溢していた。
ひ、ひ、と嗚咽を漏らし、自由な手で僕の胸やら顔やらを叩いてくる。
ただ、力はろくにこもっていなかった。
少しは冷静になって回りを気にすると、そこは非常階段の踊り場だった。誰かが通る気配はない。
ぽかぽかこちらを殴る右腕をとり、壁に押し付けて拘束すれば途端なおとなしくなる。
「バカ、ば、ばに、この兎…っ」
「あなたが逃げるからでしょうが!」
「るさぃ…大体」
まだしゃべろうとする口を塞いだ。
初めてのキスは夜景を見ながらムーディーにと決めていたのに、台無しだ。
でも、はっきりと感じた。虎徹さんのあたたかで、柔らかな唇を。
思っていたものとは全く違っていて、僕は状況も忘れてキスを深くする。
ずるずると落ちていきそうになる体を腰を抱えて支え、一度離してからまた、キスをした。
「ん、んゥ」
拒絶なのかすがっているのか、虎徹さんの手は僕の腕に力なく添えられている。
は、と口を離した。塩辛い唇を舐めると、彼の息を呑む声がする。
「お、お前、今なにしたか」
「ええ。分かってますよ。キスしました」
あわわ、とまるで漫画のような声を出して口を押さえた虎徹さんは、慌てたように唇を拭って、固まった。
それはそれでまた傷つくような。
「虎徹さ」
「そ、そんなにおかしいかよ」
「え?」
唇に手をやったまま、虎徹さんは低い声で言う。
光を受けて薄く輝く琥珀色の瞳は、悲しみを宿したようないろで僕を捉えていていたたまれない。
僕はわけが分からず彼の右手を解放した。
「そんなに俺がお前を好きなのがおかしいのかよ!」
「…は?」
「は、じゃねぇよ! な、なんっ、俺は…ッ」
また涙の膜がゆらゆら揺れ始めて、僕は慌てる。
あの小さな牽制すら、彼には通じないのだろうか。
だって仕方ないだろう。彼を手に入れて初めて気付いたんだ。ワイルドタイガーを見る周囲の目にこもる熱を。
もしかすればそんな目線にすら気付いていないのか?
まさか。
「虎徹さん、あの」
「うるさい! 聞きたくない!」
子供のように駄々を捏ねる虎徹さんは、耳を塞いで床に座り込んでしまった。
体を丸めるようにして座る彼の脇の下に手を入れ、何とか立たせようとするが「うるさい!」の一点張りで聞こうとしない。
ふうとため息をつけば、ビクリと跳ねる肩は怯えている。
どうしてだ? あなたからはこんなに僕が好きだということが伝わるのに、どうして僕からのアクションを嫌がる?
「考えて考えて…お前のことばっかで…頭へんになりそうなのに」
…熱烈な告白だ。
生唾を飲み込む音がした。まさかの僕からだ。
「お前の一挙一動に振り回されて、もう嫌だ」
「虎徹さん、僕は」
「何だよ…キスなんかしてよ…勘違いさせて喜んでんだろ」
さっきから感じていたが、この人の言葉がどうもおかしい気がする。
何だ? 何がおかしい?
「俺が嫌なくせにッ、ひぐ、気持ち悪いくせにッ」
「なっ」
「さっさと言えよ! あなたなんか嫌いですってよ! 得意だろ!」
…違和感の正体は、これだ。
◇◇◇
どうにか虎徹さんを落ち着かせ、僕達は誰もいないオフィスに戻った。
経理のおばさんはいない。今日は姪御さんのバレエ発表会があるとかで、前から楽しみにしていた。
オフィスには一昨日と同じく僕と虎徹さんの二人だけがいる。
ずっと下を向いている彼の顔は、よくよく見れば目は腫れているしアイパッチは濡れているし、ふて腐れたように唇を突き出しているしで、とてもヒーローとは思えない。
でも僕は、そんな人間くさい、子供のような彼が好きだった。
バディとしてでもなく、友人としてでもなく。
まして兄のようになんか、思えるはずがない。
『バニー』
彼の笑顔が脳裏を駆け巡る。
――好きなんだ。僕だって。
「ごめん」
虎徹さんが涙声で言った。膝に乗った拳がぶるぶる震えている。
「俺は」
「突然キスしたのは、謝ります」
「バニー、なぁ」
「あなたが言いたいことは、分かってます。言ったでしょう。あなた、すぐ顔に出るんですよ」
「……」
虎徹さんが項垂れた。
ハンチングがぽとんと落ちる。
僕はそれを拾い上げ虎徹さんのデスクに置いて、彼の顎に手を添えた。
薄く輝く琥珀色が、何かを図りかねて右往左往している。
ふ、と笑って前髪をかきあげた。
「好きですよ。虎徹さん」
元々丸かった目が、更にまんまるくなった。
あ、と虎徹さんが言って椅子ご後ろに下がろうとするから、肩を抱いて阻止する。
そのまま抱き寄せて、ずれていたアイパッチを剥がした。
「あなたが死ぬかもしれないと思ったとき、僕は一緒に死のうと考えました」
「なっ」
「でも生きてた。僕がどんなに嬉しかったか、分かりますか?」
出来るだけ優しい声で。
出来るだけ優しい目で。
あなたをこんなに愛していると伝える。
好きじゃ足りない。愛しくて、なのに遠く感じたり、解らなくなったり。
そんな悩みの種まで楽しい。あなたがいたから、僕は僕でいられる。
「じゃ、じゃあ何で嫌がらせなんか」
「だから、嫌がらせなんてしてませんてば。僕がベタベタとあなたにスキンシップを取っていれば、分かる人間には分かるんです。ワイルドタイガーが、誰のものか」
「…?」
「今は分からなくていいですよ。そのうちたっぷり教えてさしあげます」
もちろん体でね。
耳元で囁けば、虎徹さんはぼんっと爆発したように顔を赤くした。
僕を椅子ごと突飛ばし、ハンチングをぐしゃっと握って喚き始める。
お前はもいちょっと言葉を選べだの、気障は二十歳までだの、髪型を変えろだの、関係ないことまで。
- 27 -
戻る