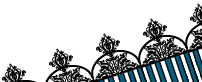「トシ」
近藤さんが小さく俺を呼んだから、目だけで先を促す。
まあ、言いたいことは大体わかった。
近藤さんは素っ裸で、俺はまだベストすら脱いじゃいないから。
ややオレンジがかった黄色い照明に照らされた部屋は、スペースをほぼ占領するベッドと小さな冷蔵庫があるくらいだ。
いつか入った性欲を掻き立てる下品な内装とは違い、いかにも雰囲気があって近藤さんが好みそうだ。
「なあ、きいてんのかよ」
「ん?」
「お前も脱げよな」
「いや。今日はあんたのことメロメロにさせようと思って」
な、そう言って口の端を上げれば、近藤さんは一気に顔を赤らめた。でかい図体を丸めて顔を手の平で覆い、まじありえねぇと女子高生のような口調で小さく言う。
「誕生日一緒にいられなかったから好きにしていいって言ったの、あんただろ」
「い、言ったけど」
「もう観念しな。ほら、手ェどけろよ」
手首を掴んで顔の外に追いやれば素直に従うから、誕生日作戦は一応成功したのだろう。
近藤さんは二ヶ月もの間、屯所にいなかった。それどころか江戸にもおらず、連絡すら疎らだったのだ。
理由は将軍の九州遠征の護衛で、隊の半分を連れてはるか南の地に馳せていた。
つまりは五月五日のその日も、俺達はメールのみで連絡を取り合った。
「帰ったら必ずお祝いするからね」と、受け取ったメールにはクラッカーとケーキの絵文字が無駄に散りばめられていたのを覚えている。
「…なんか、すげえ恥ずかしい」
近藤さんの声に、沈んでいた思考が浮かび上がった。
やや汗ばむ額を撫で、硬そうに見えてその実柔らかな髪をさらさらとすく。
身を隠すように少し斜めを向く体に顔を落とし、無防備な唇に口付けた。
「ん」
近藤さんはキスに弱い。たぶん、口の中にも性感帯があるんだろう。
舌を無尽蔵に動かして口内を舐め回すと、鼻にかかった声で切なく鳴いた。それがたまらなくて、俺はもっともっとと際限のない欲のままに近藤さんを貪る。
「ッは、はぁ、んぅ」
休む間もなくまたキスをした。
そのうち熱い手がこちらの背中に回る。
「ん…んっ、ぅうン」
「は、とろとろだな…」
いやらしく繋がる糸を舐めとれば、近藤さんの目のいろが変わった。
俺の前髪を両側からかきあげて、よく見るように目線を動かす。にやりと笑うと、喉がこくんと鳴った。
「お、俺もう」
「シー」
掠れる声の近藤さんに言って、こっちの額にある手を両手とも取る。何をするのか期待と不安で紅潮する頬に、ちゅっと音を立ててキスをした。
その隙に自分のしていたベルトを取り払い、大した抵抗もない腕を縛る。
はあっと、興奮したようなため息が聞こえた。
「縛られんの、好きだろ?」
「…ん」
今日はとことん素直だ。
素直ついでに、キラキラと濡れる瞳をスカーフで覆う。痛くないように緩く結んだが、頭を振っただけではほどけはしない。
「すげえエロい。写真撮りたい」
「や、写真なんか」
見えている眉が歪んだ。可愛い。鼓動が早まるのを感じる。
胸の上で所在なげに折り畳まれる腕も、黒いベルトに阻まれて動きが制限され、よりこの人の熱を高めているのだろう。
そもそも抵抗しない近藤さんだが、抵抗しないのと抵抗できないのには大きな差がある。
「もう勃ってるぞ。ほんと、エロい体だな」
「お、おまえのせいだろっ」
「ああ」
言って、まだ喚く近藤さんの腹筋を何の前触れもなく撫でた。
ひゃ、と色気のない声でびくつき、何も見えないはずだが頭を上げて俺の名前を呼ぶ。
「トシ、なあ、トシって」
「なんだよ」
「電気まだついてんだろ。消せよ」
「やだね」
俺の声に息を詰まらせる音が聞こえた。
ふ、と笑って丸見えの臍を舌でつつくと、腹筋がかたくなる。すべらかな浅黒の肌が大きく上下し、感じているのだと分かった。
すると上から縛られたままの手が延びてきて、俺の髪をくんっと引っ張る。
「な、なあ」
「ん?」
困ったような声がして近藤さんの方を向けば、腕を上げて目隠しを取っていた。
「やっぱり…目隠し嫌だ」
「どうして」
「だっ、だって、トシの顔、見ながらしたい」
まずいとは思ったが、もう駄目だった。
ゆらゆらと揺れる瞳と視線がかち合った瞬間、頭の上から足の先まで電流のように体を突き抜ける感覚に襲われる。
久々に感じた強烈な欲情に、目眩すらした。
「トシ、おい」
「もういい。もう黙ってろ」
やや乱暴に言って体を下へずらし、緩く勃起しているソレを舌で撫でた。
「あッ、ちょっと」
焦ったような声と共に髪を捕まれたが、構わず吸いつく。
ジュッと派手に音を立て唾液を絡ませれば、すぐに抵抗は止み甘い声が漏れ始めた。
あ、あ、とちいさく悲鳴のように迸るその声に、更にくらくらと煽られて仕方ない。
手も使って完全に勃ち上がるペニスを追い込んでいく。
「や、ゥんっ、トシ、なぁットシ」
「…っは、あんたのここ、すげえひくひくしてる」
「やめ、ろ…ンなっ、恥ずかし、っア!」
イったのかと思うほどに大量の先走りを垂らしている鈴口を抉るようにして舌を動かすと、切なそうに声を上げて鳴く姿がたまらない。
は、と一度息を吐いて上を見る。
俺を凝視している茶色の目は、縁を上気させてしきりに瞬きをしていた。
涙の膜は決壊寸前で、震えているかのように小刻みに歯をカチカチと慣らしている。
「近藤さん…」
思わず呻いていた。
この目だけで頭が沸騰しそうだ。
「ふわ、あ、ぁ」
じゅぷっじゅぽっと卑猥に響く水音も、屯所では聞いたこともないような声も、ぜんぶを聞き逃さないようにしたい。
トシ、と蚊のなくような細い呟きにも、いちいち目で応えてやる。
でなきゃ妙なところで不安がるから、俺も気が気でなかった。
「なぁ、なあ…トシ」
目線を上げる。
腕と腹筋が連動するように痙攣していた。
「もう出ちゃう、なぁ、トシってば」
「出せよ」
「や、だ…」
一端口からペニスを吐き出し、続きは指と手でやる。
血管の浮いた幹とは裏腹に、果実のようにてらりとした先端からはひっきりなしに先走りが漏れていた。
一滴も逃したくなくて、垂れる度に舌を這わせる。
「ンぅ、ッ、ぅう〜っ」
「出せって」
同時に我慢すんなよと言ってみても、拘束されたままの手の平で顔を覆って首を振る近藤さんに、さすがの俺もぴんときた。
この人はこんなガタイをしておきながら、思考回路は誰よりもロマンチックで夢見がちだ。
「一緒にイくか?」
「……、は」
出来るだけやさしい声で言えば、隠れていた瞳が涙をいっぱいに貯めて肯定を示す。
そうとなれば話は早い。俺だって近藤さんを感じたくて、スラックスの中身はどうしようもなく膨れているから。
「い、入れて」
掠れた誘い文句に、なけなしの理性を総動員し否定する。
「ここ、ほぐさねぇと。だからまずはこっちな」
熱い蕾に触れて言うと、きゅっと寄る眉根が可愛い。
息を吐き、近藤さんが何か喋る前にスラックスの前を寛げて泣き濡れるペニスにそっと重ねた。
「うあっ」
「腕、上に上げろ」
胸で折り畳まれている腕を上げさせ、頭の上に追いやる。
可動域の制限された中での動きに少してこずるが、顔が両腕の間から覗くような形に持っていった。
「と、トシ」
興奮からか、掠れて震える呼び名に頷いて、重ねていた中心を手の平で包む。
「あッ」
途端に、体全体でびくっと跳ねた近藤さんが泣くように喘いだ。
元々限界の近かった敏感な肌から一気に汗が吹き出したのか、舐めた乳首は塩辛い。
「近藤さん、きもちいいか」
「んっ、うんっ、いいよ…っ」
「動かすからな」
言うか言わないかの瀬戸際で、俺は腰と手を同時に動かした。
ああ、とたまらない声を上げて近藤さんも腰を揺らし始める。
燃えるように熱い体が愛しい。多分、俺のほうも相当あついはずだ。
「はッ、はぁ、すげ、ぬるぬるだな…」
「あぁあ、ぁあ、きもちい、きもちいい」
目を瞑った近藤さんが、ついにタガが外れたように快感を口にし始めた。
もうこうなったら止まらない。俺も、近藤さんも。
「ふわあッ、はっ、あぁっ」
「たまんねぇ…あんたの匂い…」
首に顔を突っ込んで、ベロベロと舐め回しながら匂いを嗅いだ。
ついでにたくましく浮き出る鎖骨にも甘く噛みついて、その度脈打つペニスに酔う。
「ああ、も、もぉ…」
「イきてぇ?」
「んっぅんっ」
真っ赤になった目でこっちを見ながら、近藤さんはコクコクと何度も頷いた。
俺も小さく頷いて、いっそう激しく手を動かしていく。ぐちゅぐちゅと音が響く中、限界を訴える声も高くなる。
「あ、あぁ、あァ…!」
一瞬、ベルトに縛られた手首が赤くなっているのが見えて、何故か下半身に熱が篭った。
ぶるぶると震えるような感覚に襲われ、目が霞んでいく。
鎖骨に生々しく残る鬱血痕と歯形にも、同じような感覚が沸き起こった。
――この人が俺のものであるという証が、こんなにも心を満たすなんて知らずにいたことが信じられない。
所有のしるしが増えるたび、感情も高ぶっていく。
「ぅあ、トシ、トシぃっ」
「……」
びくびくと痙攣し腹の上に精を放った近藤さんだが、俺は構わず自分の絶頂を追うため手を動かし続けた。
ペニスが焼けるように熱くなり、近藤さんが拒絶するように俺の肩を弱々しく押す。
「や…ッ、だ…ア、ぁ」
その手をベルトごと取り、胸に押し付けて固定した。もう無理だと喚くのを無視して、自由のな方の手でぐしゃぐしゃとペニスを扱く。
イったばかりで力が入らず弛緩した体は、呆気なく二度目の高みに追い詰められていった。
「あぁ、もぉむり、ぃアッ、トシぃっ」
「大丈夫…」
何が大丈夫なのか自分でも分からない。
はあはあと獣のように荒い息遣いで腰を振る自分を、どこか客観的に見ている俺もいた。
その証拠に、体をくねらせてよがる近藤さんの姿はよく見える。
「はっはぁっ、はっ、クソ…イく…」
もっと近藤さんを感じていたいのに、自慰すらロクにままならなかった体はすぐに熱いものをたぎらせた。
ぐらぐらと煮えるような灼熱感に尻の肉が震える。
「ウ、く」
重ねていたものを離し、さっき近藤さんが出した腹の上に同じように射精した。
よすぎて腰が動くのを止められない。
「ッは、はぁっ」
「あ、トシの…痙攣してる」
呆けたような声に瞑っていた目を開けると、近藤さんが片肘をついてこっちを見ている。
腹には二人分の精液がかかり、陰毛を少し濡らしていた。
「エロい…」
「お前の顔がな」
間髪入れず突っ込まれるが、近藤さんは顔を涙で濡らしたままボフンと枕に頭を沈める。
そしてゆっくり手を伸ばし、腹の上の精液をぬるぬると指で掬い上げ笑った。
「ちょ…AVの手作り精液並の量じゃん」
「あんた禁欲でもしてたのか?」
「トシこそ」
表情こそ和んでいるが、近藤さんの手首は俺のベルトで縛られたままだ。
ぎしりと音を立ててベッド上を移動し、顔同士が正面に来るように向かい合う。
――七センチの差は大きい。
「目、真っ赤だな」
「…涙腺ぶっ壊れたのかも」
「いつもだろ。近藤さんの場合」
「いつもは泣いてねぇもん」
「泣いてるよ。きもちいいと涙とまんねぇし、あんた」
「なッ!?」
- 20 -
戻る