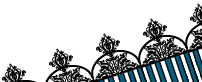「ただいま」
車を走らせること三時間半、車はようやく俺たちを見慣れた屯所に連れてきてくれた。
午後三時四十分を少し過ぎた時間を指している時計も、ともすれば結露してしまいそうなほど湿気が多い。
「おかえり」
近藤さんは暗い顔をして俺を出迎え、書類を整理する手を止めた。
雨は篠付く程度だが、蒸し暑い空気はねっとりと俺たちを包む。
「…お疲れさん。大変だったな」
「ああ。本降りになる前に帰れてよかった」
「天気予報じゃ20%だったのになぁ」
世間話をしながら腰を据え、着替えた着流しの襟を正した俺達の間に妙な沈黙が流れた。
互いに肚は分かっているのに、中々それを吐き出せないズルさに苦笑する。
こういうとき先に口を割るのは近藤さんだが、今日は違う。
時折とことん臆病になるこの人のために、俺が引導を渡してやる。
「線香だけは、上げてやれた」
「そ、か」
「金はまぁ、受け取ってもらえなかったというか、受け取ってもらえたというか」
「?」
老婆のことは言わなかった。きっと混乱するだろうから。
近藤さんはそれ以上何も聞かず、朝泣いたことが照れ臭いのかあまりこちらに目を向けようとしない。
俺はそんな顔へと唐突に手を伸ばし、すべらかな肌に触れた。
「…っ」
驚いたようにハッとして俺を見る近藤さんに、優しく微笑んでやる。
するとすぐに表情が歪んで、大きな黒目の瞳に涙の膜が盛り上がった。
俄に近付いて抱き締めると、逞しい腕が背中に回されて着流しの布をぎゅっと掴む。
「や、やっぱり、ぅ、俺が…っ、行った方がよかったか、な」
「俺でよかったよ。大丈夫」
頭の後ろを摩って宥め、肩にぽすんと乗った重みに耳を寄せれば抱く体が震えた。
少し背中を引っ張ると、素直に離れた顔は涙の濡れている。
両側から頭を挟み、下から覗くように目を見た。
潤む目からぽろっと涙がこぼれるのを親指で掬うと、「子供みてぇ」と笑った。
「夏目くんが愚痴ってたよ。副長が車の中で怖すぎて胃が痛くなったって」
「アイツがンなタマかよ」
「…ありがとう。我が侭聞いてくれて」
「あんたの我が侭聞くのが俺の仕事だしな」
軽口を言い合って笑い合う。
俺は今、この人を救えてるんだろうか。
癒せてるんだろうか。
そうでも思わないと、俺が苦しいからだってことは分かってる。
笑うこの人が背負うものが、少しでも軽くなればと思うのに、結局救っているのは、癒しているのは俺自身なんだ。
それが今は、悔しい。
「あ、そうだ」
こっちが泣きそうになるのを抑えて、俺は持ってきていたあの文を袂から取り出した。
いつの間にかくしゃくしゃになっていたそれを差し出すと、近藤さんは不思議そうに見つめる。
「手紙?」
「ああ。過去の伊東から、今のあんたに宛ててある」
「え!?」
ばっと文を広げ、一心不乱に読み始める近藤さんは、みるみる顔を歪めてさっきの比じゃないくらいにボロボロ泣き始めた。
「うっ、ぅうっ、ふ、ふぐっ」
「ったく…泣きすぎだ」
「だってぇ、こっ、こんなぁ、うわあああ伊東先生ぇぇ」
ついにはサイレンみたいに泣き出した近藤さんの頭を撫でてやる。
何事かと集まって襖越しに困惑する気配に苦笑しつつ、手の中でしわくちゃになる紙を取り上げた。
松永 タツ様
私は明日、江戸へと旅立ちます。
己の力を試すためにも、私の力を必要としている者の為にも、必ず大成してみせます。
あなたがいつか語ってくれた強き剣士に、私はなります。
私ならやれる。絶対やり遂げて見せます。
あなたに誇れるような立派な男子になり、いつの日かここへ帰ってきたときには、一緒に酒を飲みましょう。
絶対に、絶対に、みなに親しまれ、頼りにされ、好かれる人間になります。
見ていてください。
きっと素晴らしい男子になって、あなたの元に帰ってきますから。
だから今は、誰にも黙って旅立つことを許して下さい。
あなたに頂いたたくさんの愛を胸に、私は江戸に向かうのです。
では。さようなら。
伊東鴨太郎
「ごめんなぁ先生…あの時もっと、別の選択をしてれば…もしかしたらあんたは」
「もういいよ。近藤さん。きっとあいつは、最後には思い出したはずだ」
襖の向こうの気配が消える。
文を置き、その頭を抱えた。
「そう思おう。な」
うん、と涙に紛れた近藤さんに、ようやく俺は口付けられた。
◇◇◇
「暑いなぁ」
「だな」
「でっかい月だな」
「ああ」
縁側に腰掛け、俺達は夕涼みをしていた。
虫の声も緩やかな風も、優しく空気に溶けている。
「なぁ、怖い話していい?」
「怖い話?」
近藤さんの方を向けば、怖い話とはいうもののキラキラした目をしていた。
いいぞと肯定して、猪口から酒を舐める。
膝を立て、その上に顎を載せた近藤さんがぽつりと語り始めた。
「伊東先生からの手紙なー」
「うん」
「すっげーボロボロになって、今日見たら触っただけで崩れたんだ」
「ふぅん」
「……驚かないの?」
近藤さんの横目に大して、俺は「驚いてるよ」と返事をする。
ただ、驚くには驚くが、どこか納得している自分もいるのだ。
あのタツという老婆の最後の力をなのだろうか。
「じゃあ俺も怖い話」
「え?」
「幽霊に会った」
「…嘘だ」
じっとりとした目で見られて笑う。不思議と恐怖を感じないのは、あの穏やかな顔と温かい手が理由だろう。
近藤さんの猪口に酒を注いでやりながら、嘘だ嘘だと妙なリズムにのせて歌うのを聴く。
「あんたによろしくってよ」
「幽霊とよろしくなんかしたくない」
「中々美人だったぞ」
浮気者ーと茶化す声に目を細め、夜空を見上げた。
鎮座する月を囲むようにしてちらちら瞬く星が、優しく俺たちを照らしている。
不安定だが、決して消えることはなく。
――ああ、まるで。
「それにしたって、もう幽霊の季節だね」
「幽霊に季節なんかあったのか」
いつだって俺の指標で有り続ける、あんたのようだと。
「ビールの美味い季節でもある」
「いつも言ってんじゃねぇか」
「ハハハ」
きっとこれからも変わらず、俺はあんたに救われて、あんたは俺に愛されればいい。
ふらふらと揺れていいんだ。
(伊東よ。俺はあんたが嫌いだ)
でも、あの手紙を書いた頃のあんたには感謝の言葉を送るよ。
「さーて。もうすぐ虫の大合唱が始まるぞ」
「うるさくて眠れやしねぇよ」
「いいじゃねぇか。風情があって」
今年もようやく、夏が来る。
おわり
全然誕生日に被ってない…ですね。すみません(汗)
リクエスト内容は誕生日に一日だけ近藤さんを独占する、でしたが…あれ?
もう一本のお話にて昇華させられたらいいかなと思います。
それにしたって! 誕生日のリクエストなのに2ヶ月も遅れてしまって、本当にすみません。
リクエストしてくださったフキ様は本当に辛抱強い方だと思います(-.-;)
首をなが〜くして待ってくださったフキ様! 本当にすみませんでした;
よろしければお納め下さいませo(^-^)o
- 19 -
戻る