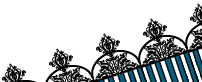きっと子供だましだった。キスとかハグとか、愛してるの言葉とか。
頭が、へんになりそう。こんな俺をみてこいつは気持ち悪くならないかな―――なんてことは、もう考えるスキマさえなかった。
荒い息が降ってくる。俺の足を上げたトシは一度ぶるりと身震いして、うっすら目をあけた。
外は明るく、雲ひとつない。
なのに俺達はこんなところで非生産的な真似をしている。
知る人間はいない。何せここは見慣れた屯所ではなかった。
「…なんだ、もうバテたのか?」
ぐったりしている俺に、言葉とは裏腹に優しく声をかけたトシは微笑む。重い瞼をトシの滑らかな指の背が撫でていくから、もうどうしようかと思った。
自制がきかないんだ。
今までもちろん俺は相手を抱く側だったし、リードだってこっちの役目だった。
なのにどうしてか主導権を明け渡してしまっているトシに色々されるのが、俺は嫌いじゃない。むしろ男のトシに惚れ直してもいた。
でも。
「水いるか」
「うん」
でも、俺にはそれこそ恐怖だった。
俺が今まで積み上げてきたもの、男としての近藤勲が、崩壊していくような気がして。
「ホラ」
「ありがと」
湯のみに並々注がれたミネラルウォーターを俺は一気に飲み干して、襲う眠気と戦う。
多分トシはまだ、満足していないんだろうな。
ほんと、セックスにこぎ着けるまでのこの一ヶ月、生ぬるいマシュマロに包まれてるんじゃないかってくらいの甘い時間をすごした。
その時はまだ俺は俺のままで、恐怖なんか微塵も感じちゃいなくて。
ただなんとなくいつかセックスするのかなと思ってた。
のに。
「なんか、へんだね」
「ん?」
「連れ込み宿って…普通のラブホとかよりなんかこう…お上品っていうか」
眠気をふんだんに含んだ声が、情事の気配にけぶる部屋にぼんやりと響く。
なんだか非現実的で、今俺はなにしてんだろってふと思ってたりする。
「日本建築だもんな。上品てか懐かしいんだろ」
「ああ、かも」
色の抜けきった畳、角の潰れた襖、格子の多い障子。
そういえば昔にみた気がする。
今の屯所とどこが違うんだろうか。
「ねむ…」
「昨日休みだったくせに」
「一日中道場にいたもん」
「アザ出来てるな」
煙草をくわえ火はつけずに呟いたトシは、俺の横腹にくっきりついたアザをつつく。
「あたっ」
「竹刀じゃねぇな。なんでついた?」
出窓の張り出した棚に腕を預け裸のまま呆れた顔をしたトシに「バスケした」と答えたら、もっと呆れられた。
ああ、ほんと嫌んなるくらいお天気だ…なんかもう申し訳なくもなってくる。
――そもそも何で俺達がこんな場所にいるかといえば、情けない話二人して我慢が効かなくなったのだ。
パトカーというストイックな空間の中で久々に二人っきりになったもんだから、もうそっからは怒涛だった。
一応ジャケットは脱いでパトカーに脱ぎ捨て、受付が無人の宿を探し、いやらしい装飾も派手なベッドもない素っ気ないくらいの連れ込み宿に入った。
逆に雰囲気を煽る粗野な部屋で、俺達は敷かれた薄い布団に言葉すらなく倒れたのだ。
「テツのことありがとな」
「…ふん」
「絶対上手くいくと思ったもん。俺の目に狂いはなかったね」
「余計なことしゃべりやがって。あんただって相当だったぞ」
「なんの話だよ」
トシは他にも傷がないか入念に俺の身体を調べて、最後に手を取る。何をするかと思えば、ただ触ったり撫でたりされた。そういえば昔からトシは俺の手をよく触りたがったなぁ。
「トシは昔っから全然変わんないよね…」
「何だそれ、成長してねぇって?」
「んーかもね」
肘を立て布団に寝転んだトシは、手を離すどころか口に(いや鼻に?)持ってって肌にくっつける。
「ひでぇな。あんたのイイところとか全部知ってんのに」
うわ、急にそういうこと言うんだもんな。
口じゃ敵わなくなったとこもあの頃と違う。
トシはにやっと笑って、長い睫毛に縁取られた瞼を閉じた。
ああ、やっぱいい男だよなぁ、こいつ。
「テツはもういいよ。あんたと一緒にいたい」
「そ、そんなこと言うな」
「あんただって思ってたくせに」
う…。見事に見透かされてる。
確かにちょっと寂しいなぁーなんて思ったりしたから。でもトシにべったりなテツにそんな顔できるわけないし。
やきもちとかそういうの、他の奴ら同様素直に表すなんて出来ない。でもトシはそういうとこもちゃんと分かってくれてんだ。
「ヤる?」
ちゅ、と未だ弄っていた手の甲に唇を押し付け、トシは唐突に言う。
やっぱりほら、こいつは敏感に察してくれた。
「…うん」
眠気なんかもう、吹っ飛んだこと。
◇◇◇
「あ、あぁ、ぅあ」
トシの指が尻のすぐ上を擦るように撫でるから、俺はへんな声を抑えられない。
なんだかぞわぞわして、なんというか、小便したくなりそうな感覚というか…とにかくへんなかんじがする。
「トシ、も、そこばっか触んな」
「なんで? イイところだろ」
だからヤなんだっつーの! とは言えず、うぅと呻いていると今度は臍の下あたりを撫でられた。
「ぅわっ」
「まだまだ敏感だな。さすが」
「嬉しくないっ! も、ちょっと、いいからもう!」
慌ててトシの手を掴んだら、もう片方の手が勃起したまんまのソレを直接握る。
いつからこうなったかは知らないけど、トシはことこういうことに関しちゃしつこい方だった。
勘弁してって言ってんのに全然やめてくんないし…。
「あ、も…ぁ」
しつこい動きはやまないまんま、トシは俺のをほにゃららしていく。
息も上がって鼓動も早くなってきて、口からだらだら涎も落ちてくのが恥ずかしいのに。
「イきてぇ?」
「ぅん…」
素直に頷く俺もどうかと思うけど、二回目なのにヤり始めみたいに聞いてくるトシもトシだ。
トシの手の動きに合わせて体も揺れる。視界もぶれて、部屋は明るいはずなのによく見えない。
せりあがる射精の前兆に頭が布団にがくんと落ちて、トシがなんか言ったのもよく聞こえなかった。ああ、やばい、イきそう。
「ぅう、イ、イく」
「ああ」
ぐちゃぐちゃって、派手に音がするくらい扱かれて、なんだかもうどうにかなりそうだった。
さっきトシのを突っ込まれてイったのに、俺はまたこんなことになってる。
それが恥ずかしいのに、そう思えば思うほどきもちよくなった。
「もぉ、も、やだ…早くイかせて」
こんなことだって俺は平気で言っちゃうんだ。あとで猛烈に襲う後悔とか羞恥とか、全部わすれて。
俺だって男なのに、同じ男のトシに弄られてイかされて、気付けばドロドロになるまで一緒にいる。
「近藤さん」
耳元で俺を呼ぶ声がした。けど、搾り上げるみたいに勃起したものを扱かれて、返事も出来なかった。
喉がひゅっと鳴って、呼吸が苦しい。
「近藤さん、すげぇエロい」
「トシ、トシ…」
あ、と声が震えて体温が一気に上がる。
射精の感覚にぶるっとしたあと、すぐに力が抜けて布団に倒れ込んだ。
はぁ、はぁと恥ずかしいくらいに息が上がって、やっぱり羞恥が襲ってくる。
「うぅ、俺だけイくとか」
「顔みれなかった」
「みなくていっつうの…うわっ」
ぐったりしてたら、いきなり背中にキスされて叫んでしまう。
い、今イったばっかなのに! このねちっこいかんじはまたおっ始める気だ!
「あの、ごめん、あとちょっとでいいから休ませてくんない」
「…自分だけイって俺はほったらかしかよ」
「だ、だからちょっと休ませてくれたらまた」
やだね、と不届きな声がして尻をがっしり掴まれて「うひっ」と叫んでしまう。
さっきまで充分すぎるくらい鳴らされて、まだなんだかじっとりしてて気持ち悪いそこに、トシは突然指をいれてきた。
「ちょ、もぉ、トシってば」
「たのむよ…我慢できない」
「ぅ…っ」
おまえのそれは、反則だろ!
◇◇◇
「はっ、あ、ぅうっ」
「わるい、痛かったか?」
短い感覚の呼吸の合間に聞けば首をぶんぶん振るから、剥き出しの背中にキスしてやる。
刀傷の跡をなぞるように舌を這わせると薄い皮膚は余計感じるのか、中がぎゅうと締まるからたまらない。
「んん、んぅ、トシぃ」
「ん?」
「も、無理…無理」
「なにが?」
ああもう、あんた自身何が無理なのか分かってないんだろ。
俺がどうにかなりそうだ。
「な、向き変えよう。顔みせてくれよ」
「やだ…む、無理、ぅあ、う」
「仰向けになった方が楽だろ?」
ぐ、と押し込みながら背中に覆い被さり、肩を持ち上げると驚くほど簡単に起き上がるから、中に入れたままくるりと向きをかえる。
「ぅああっ」
「ほら、足持って」
「や、だ、もう無理っ」
「無理じゃないだろ。きもちいいんだろ」
うーと呻きながらも近藤さんはしっかり足を持って広げた。
膝にちゅぅと派手な音を立ててキスをして、動きを再開する。
「はぁっ、ぁあ、ぅあ」
可愛い。可愛い、ほんとに、声も表情も、もちろん中も、全部俺が変えた。
俺に馴染むように、俺の好みに。
でもまだ足りない。食らうみたいに貪っても、甘い言葉と行動で優しくしても、足りない。
いつでも俺はあんたを欲してんだ。どの一瞬も俺を見ていて欲しい。何をしていても俺を一番に考えていて欲しい。俺を求めて欲しい。
「は、は…はぁ、近藤さん、なかに、出していいか」
「だッ」
がくん、と近藤さんの重たい足が落ちたと思えば、腕が伸びてきて俺の指先を掴んだ。
う、と思わず呻く。
そんな無意識な行動に頭が煮えた。
「ちゃんと…処理する」
たのむよ、中でイきたい。
掠れた小さな声で言えば、近藤さんの頬にさっと赤みが差す。
腕を体の横から少し上へずらし、無防備な喉元に吸い付いた。
「んぁっ」
「背中に、抱きついてていいから」
弱りきった顔をしている近藤さんに言って腕を背中に回してやる。ぎゅっと抱きつかれて、ああ、こうしたかったのかと思う。
ごめんな、気付いてやれなくて。
「イって、トシ…っ」
耳元でそんな言葉が聞こえた。
やばい。殺し文句だろ、それ。
「ぅッ」
呻いて、前屈みになる。ひたすら気持ちよくて、いつの間にか歯を食いしばっている。
「っはぁ、はっ、は」
力が抜けた。ぱたんと近藤さんに覆い被さって高い体温に息を吐く。
背中をさすさすと撫でられ、気持ちよくて離したくなくなる。
中から俺の出したものが溢れるが、気にせず近藤さんを抱き締めた。
「イく?」
「ん…いい…ねむ」
「でもつらくねぇ?」
起き上がりつつ聞くが首をふるから、そのまま横に転がって薄い毛布をかぶる。
近藤さんは早くも目をつむって、ふわぁとあくびをしていた。肘を立て手のひらで頭を支えて、今にも寝そうな近藤さんの顔をみる。
睫毛の先が少しだけ反っていて、泣いたのか涙がついていた。
「すこし寝るか」
「う、ん」
年の瀬も迫ったというのに、本当に俺達は何をやってんだかな。
昼下がりで、仕事中で、連れ込み宿で。
でもなんかもう。
「いつ起きる?」
「…トシが決めて」
幸せすぎてしにそうだ。
あとがき
甘すぎて生クリームを吐きそうです(キモッ
ただただイチャイチャして終わりました。
後悔も反省もしていない←
- 11 -
戻る